
スキスパムハンター・B
(おっ! noteのベルマークに【1】がついたぞ! さっき投稿した小説『バババーバ・バーババ』への ”スキ” かな?)
noteデビューして間もない青年 ウキオは、6畳一間のセンベイ布団に転がしたばかりの我が身を起こし・・・ホクホク顔でスマホをタップした。
(おお! フォロワーじゃない人だ! ボクの小説・・・気に入ってくれたのかな!?)
さっそく、スキをつけてくれた人のプロフィールページにJUMPする。
(プロフィール写真が実写だ・・・なんだかスマートな感じの・・・イケてる感じの人だ・・・フォロワーも多い・・・エッセイが中心なのかな・・・。こんな人にスキされたなんて嬉しいなあ)
――ウキオの表情が少しだけ曇る。
なぜか?
ウキオは少し不安になったのだ。
なぜか?
ウキオの小説を読むようなタイプの人には見えないから、だ。
※その小説は人が出てきて死ぬ。
ウキオの脳裏に、先日の苦い記憶が蘇った。
またあの時のような悲しい気持ちになるのではないか。心の中にこびりついていた感情・・・真っ白なTシャツに一滴垂れたソイソース染みのようなマイナス感情が、ふたたびジワジワと・・・。
だがウキオは真っすぐな、心の優しい青年である。
マイページをチラ見した程度で「この人はこういう人にちがいない」などと決めつけるシツレイな男ではない。わざわざスキをつけてくださる人に対しては、まず何よりも先に「嬉しい」「ありがとう」のキモチが大事。そんな姿勢で日々のnoteライフを楽しんでいた。不安感情をイマジナリー・タンスに突っ込み、気を取り直してスマホを見つめる。
(ボクの作品みたいな小説が好きなのかな・・・他にはどんなスキをしているんだろう・・・ボクも読みたくなる作家さんとか、発見できるかも!?)
ウキオは「マイページの主がどんな記事にスキをつけているかチェックできるページ」を確認した。
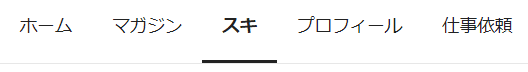
(スゴイ・・・いろんなジャンルに目を通しているんだなあ。・・・あれ? ボクの小説が「スキした一覧」に無いな・・・スキされてまだ15分も経っていないのに・・・また、なのかな・・・またなのかな・・・)
(おかしいな・・・いくらスクロールしてもボクの記事が無い・・・10記事・・・20記事・・・ない・・・30・・・40・・・50・・・60・・・70・・・80・・あった。こんなに下にあるなんて。15分間でこれだけ読んだの?)
【おかしいよなあ? ありえねーって。またなの? ってカンジだよなあ? オメーもか? ってガッカリしちゃうよなあ】
ウキオの顔からみるみる光が失せ、その心はダーク・ウキオに支配されようとしていた。
・・・がっ!
<<ウキオ・・・冷静に。決めつけはよくありません。たくさん読んで、あとでまとめて一気にスキをつけた可能性だってあるでしょう>>
神々しい光を纏ったライト・ウキオが、温かみのある声でウキオに語りかける。
だがダーク・ウキオも黙ってはいない。
【バカか? そんな非効率なことするわけねーだろ? いくつブラウザ開いてんだって話だ。おいウキオ! フヌケに耳を貸さねーでよ、さっさとやっちまおうぜ】
<<待ちなさい・・・SOKUDOKUの可能性もあります・・・>>
ウキオの瞼がピクリと動き、顔に生色が戻る。
(そうだ。”速読” のスキル持ちか! この世にはそういう人もいる。ドラマとかでも見たことがある・・・)
【ハハハッ! 笑わせんじゃねーよ。80記事を15分だぜ? 1記事にどれだけ時間が使えるかわかるかウキオ? ・・・11.25秒だ。ウキオの小説は何文字だっけかなー? え? 15,000文字? アー無理だよねー? ポジティブシンキングもいいかげんにしろって! な?】
<<クッ・・・!>>
【し、か、も、だ。80記事の中にはよぉ・・・「長編記事」だけじゃねえ。「有料記事」がいくつも含まれてるんだぜ? 決済だのしてる間にタイムオーバーよ。実際購入してたらスゲー額だぜ。先日ウキオを悲しませた奴はどのくらいだっけ? 数分で60記事だっけ? それと同じだよ。お、な、じ。ウキオよ。お前もわかってるんだろ? そうだよ。ス・パ・ム。スキスパムだ!】
<<ウキオ・・・! いけません! 闇に飲まれては・・・!>>
「ああ、あ、う、う、うそ・・・」
【・・・そうだ。嘘スキってことだよぉ! スキでもなんでもねースキ! 絨毯爆撃みてーによぉ! カテゴリ別やらピックアップ別によ! 上からポチポチやってるだけなんだよぉ! 機械じみてよぉ! そのお返しにボクチャンの記事も見たりフォローしてくだちゃいってよオォォォォー! ・・・・・・だからウキオ。コイツはお前の小説を読んでねーんだ。はなから読む気もねぇ。やっちまうしかねーのさ】
<<待ち・・な・さい・・・・ブロ・クです・・ブロックすれば精神・・衛生上は・・・>>
【それじゃダメだめだウキオ。ブロックは「事後対処」。新手はどんどん襲ってきやがる。これからもな。そうしてお前は毎回ガッカリするんだ】
「あ、ああ、あ、あ・・・」
ウキオは白目を剥きながらうな垂れ、額を布団にこすりつけた。
涙と涎がいりまじり、スマホの液晶をポツ、ポツと濡らす。
ダーク・ウキオによるウキオ乗っ取りが始まろうとしていた。
意識が遠のき・・・
スパーンッ!
狭い部屋に響き渡るハリテ・サウンド!
・・・そして遅れてやってくる強烈な痛み。ダーク&ライトは除霊されたかのようにスゥっと姿を消した。ウキオは我に返り、ビリビリと痛む頬に手をあてる。ふと眼下のスマホに視線をうつすと―― スマホの中からウキオを睨む老婆と目が合った。
「シャキッとせんかー!!」
「ヒッ・・・」
スマホの最大音量設定をよゆうで上回るボリュームで叱った老婆は、画面の中で腕を組み・・・肩を上下させていた。そんなものを待ち受け画面に設定した覚えはないし、ババアアプリをインストールした記憶もなかった。
「エッ・・・あの・・・すみません」
思わず謝罪するウキオ。
「なにが?」
「エッ?」
「なにがすみませんなの」
老婆がウキオを睨む。
「エ・・・えー、あの、シャキッとしていなく、て?」
「よろしい。胸張っていきな。顔あげて」
「あ、はい・・・」
ウキオはゆっくりと上体を起こし、涙と涎で汚れた画面を寝巻で拭う。
「ちょっちょっちょ!」
スマホから老婆の声。
「薄汚い布切れでゴシゴシやるんじゃないよ! それにちゃんとアンタに向けといてくれないと話せないだろう?」
「あ、はい・・・すみません」
「まぁたすみません、か・・・なんでも謝って」
「はぁ、すみません・・・あ、すみませ、あ」
「フン。・・・ま、いいさ」
老婆は不満げに鼻を鳴らしたが、いざという時に頼りになる教師めいた口調でウキオに語りはじめた。
「まずはじめに言っておく。ウキオ。アンタは余計なことで気を揉まなくていい」
「エッ? アッ、はい・・・余計な・・・?」
「いいかい、ウキオ。アンタはなぜnoteに小説を投稿するんだい」
「え?・・・えーと、書きたいし、読んでほしいし・・・から、です。他の投稿サイトも考えたんですが、noteが自分には合ってるかな、って」
「けっこう。書いてる時はどんな気分だい」
「気分・・・ワクワク、ドキドキ。苦しいときも多いですが・・・楽しいです。他の書き手さんスゴイから・・・負けないぞ、ってゆうか」
「ほいで。noteに投稿したあとは。どうなの」
「あと、ですか?」
「そう言ったろ。耳クソ詰まってんのかい?」
「あ、いえ、すみません。えーと、えー・・・読んでもらえるかなあ、とか、リアクションもらって嬉しいなあ、とか。コメントもらうと、舞い上がっちゃいますね。noteで小説書いてる人たちって、ボクみたいな駆け出しにも優しくて・・・ちょっと発想が普通じゃな・・・あ、いや、ユニークで・・・ボクももっと面白くするぞ! みたいな気持ちになります」
そうだろう、そうだろう、という顔で老婆が繰り返し頷く。
そしておもむろに口を開いた。
「それでいい。そうやって、小説を・・・noteを・・・楽しんでいればいい。それだけでいいのさ。・・・余計なことへの対処はアタシに任せな」
”余計なこと” が何を指すのか。ニブチンのウキオもさすがに気づく。
だが、”アタシに任せな” とは一体どういう意味なのか。ウキオはスマホを両手で包むように握り、画面の向こうの老婆に話しかける。
「任せる・・・って、どういう意味ですか」
「ちょっと行ってくる。待ってな」
「エッ?」
老婆が画面から消えた。
慌ててホーム画面をスライドさせる。いつものアイコンが並んでいる。背景画像のコナン・ザ・グレートと目が合う。若かりしころのシュワルツェネッガー。自分もたくましく・・・困難にも負けず・・・小説家としての道を歩む・・・そう決意したときに設定した彼は、いつもと同じ表情でウキオを見据え剣を構えていた。
「ただいま」
「ウォッ!?」
ウキオは取り落としそうになったスマホをお手玉し、一息ついてから画面を覗き込む。老婆は満足げな顔でチャを啜っていた。
「終わったよ」
「エッ? 終わった?」
「そう」
「なにが・・ですか」
「爆破」
「爆破!?」
「アンタにスキ爆撃した男。洒落たノートパソコンで一心不乱にポチポチカチャカチャやってたからね。パソコンをドカーンと」
「ええぇ・・・」
しばしの沈黙。
老婆は大袈裟に肩をすくめ、手をヒラヒラさせた。
「冗談さ。あたしゃそんな暴力的なことしないよ。ヒッヒッヒ」
「ヒッヒッヒって。・・・ねるねるねるねは・・・?」
「ヒッヒッヒ… 練れば練るほど色が・・・」
しばしの沈黙。
「死にたいのかい?」
「いえ、すみません。で、あの、何をしてきたんですか」
「まず現時点で異常値を吐いてる奴らの大掃除。みんなにいちいちブロックさせるのも忍びないだろう? だから裏世界にご案内」
「裏世界?」
画面の向こうで老婆が頷き、ニタリと笑った。
「そう。”そういう奴” しか集まらない闇の世界。全員で仲良くポチポチしあっているのに誰も相手の記事を読んでいない。虚しい行為が永遠に続く世界さ。知らぬまま楽しく暮らせるようにダミーの自動記事作成アカウントも用意しておいた。本人たちは気づかない・・・読みゃしないんだからヒッヒッヒ」
「コワイ・・・」
「お次は予防と健全化。裏世界コース逝きの切符はまだ渡されていないが、被害をまきちらす奴。その対処」
「対処・・・どうやって・・・」
「ナイショ」
「エッ?」
老婆は画面の中で目を細め、ちょっぴり真剣な顔でどこかを見つめる。
「ちょっと喋りすぎちゃったからね。運営に知られたら修正されちまう。運営は運営でいろいろ手を打ってるから立派なもんさ。スキ然り。フォロー然り。次々にカイゼンしてる。でもね・・・時には・・・アタシみたいな存在が必要なのさ」
「運営?」
「なんでもないよ。ウキオ。アンタはそういうドロドロとした話なんか気にせずに・・・ノビノビと小説を書いてりゃいい」
「は、はあ」
「連載の続き、楽しみにしてるよ。じゃ。ヒッヒッヒ」
肩をポンと叩かれる感触。
ドキリとしたウキオは、首をまわして己の肩を見やる。当然ながらそこに誰かの手は存在せず、部屋の中には自分だけ。
「あの・・・」
スマホに視線を戻すと、老婆は消えていた。
ついさっき引っぱたかれた頬の痛みを思い出し、自撮りモードで顔を確認する。真っ赤な跡。細い指。小さな掌。まるでお婆ちゃんの手のような。
「礼くらい言わせてほしかったな・・・」
呟きながらnoteをリロードすると、ベルマークに【1】がついた。
【完】
いただいた支援は、ワシのやる気アップアイテム、アウトプットのためのインプット、他の人へのサポートなどに活用されます。
