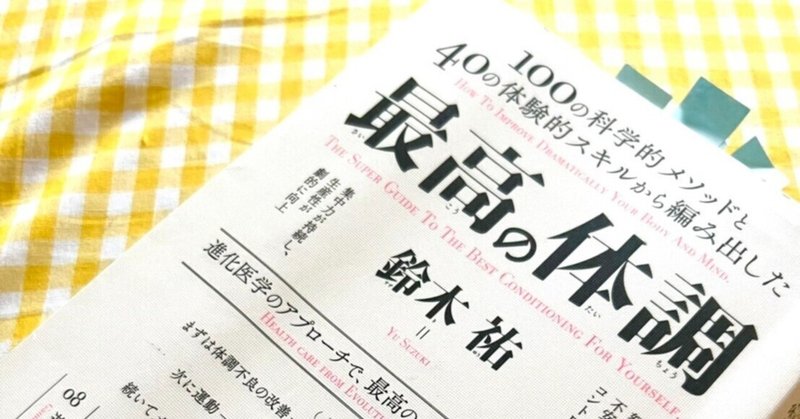
「最高の体調」(良本紹介#5)
ブッダは言う、
「すべての欲望はフィクションだと気づきなさい」
さらにブッダは言う、
「自分という存在すらフィクションだ」と。
===
くーーーーーぅ。
深い。
深くてようやくこの歳にならないと分からなかったけれど、
いや、深すぎて私なんかじゃ、
まだその一部分の理解なのだろうけど、
これがまさに真理だと、
私は命や自己の存在をとらえ始めている。
著者鈴木氏は、
さらにブッダの言葉を引用しつつ言う、
もちろん“いまここ”で行動する主体は存在するのだが、
結局のところ、
私たちは遺伝子を残すために生まれた
宇宙という巨大なシステムの一部でしかない。
「自分」とはあくまで環境とのやりとりのなかに生じる自然現象のひとつであり、なにも変化しない絶対的な自己は存在しえない。
ありもしない自己に執着心をもつからこそ、
不安や迷いが生まれるのだ。
([最高の体調 第7章 死」)
====
本書は、タイトル通り
人間の最高の体調を引き出すための様々なことが記された本だが、
他の健康本と一線を画すのは
本書の大きな軸が「炎症」と「不安」を軸に据えているところだ。
そして「炎症」と「不安」と向き合う中で、
「価値」「死」「遊び」といった視点まで至ることことだ。
現代人の心身の現状を「炎症」「不安」という根本視点から見直し、
論理的に解き、
最後は「死とは何か」まで触れ。
ブッダの悟りの境地まで至るところ。
が、この本の価値をさらに上げる。
自分の存在を無常ととらえ、執着せずに
自分はもちろん大切に、他者をも大切に生きることが、
「炎症」をさげ、健康な状態で、
己の命を他に生かせるということなのだ。
「最高の体調」、
「最高の一冊」です。
以下、気になったところ、メモメモ。
====
【プロローグ】
●かつてないほどのカロリーを摂取している
●デジタルデバイスが近くにあるだけで、人の認知機能は低下する
(2017年テキサス大学の実験)
●パプアニューギニアの2000人のカリル族、うつ病に悩む人はほぼゼロ
【P38~ 炎症編】
●「炎症」とは人の細胞レベルでおこっている家事のようなもの
●長寿の人はみな「炎症レベル」が低い
●「炎症」でわかりやすいのは「風邪」だが、
風邪のように一気に高熱で一気にカタをつけるのではなく、
現代人の「炎症」はもっとわかりにくい形で起こる。
とろ火でジワジワと全身を煮込むような形で進行。
●「体調が悪い」と答えた人ほど、体内の炎症レベルが高い。
「体調が・・」と感じた人はすでに身体が燃え盛っている可能性が大きい。
●慢性炎症は脳の機能にも激しいダメージ。
代表的な例は「うつ病」
●狩猟採集民族キタヴァ族(パプアニューギニア)が脳卒中や動脈硬化にかかるケースはなく、糖尿病の発症率も1%。
●古代人類学者ダニエル・リーバーマン氏提唱 3つのフレームワーク
①多すぎる:古代には少なかったものが、現代では豊富すぎる
・私たちの脳と身体は「低カロリー」にはうまく対応できるが、「高カロリー」を処理するようには設計されていない
・労働時間:コンゴ・フィリピンの狩猟採集民族の労働時間の平均12~19時間/週 P109
毎日数時間ほど食料探しをしたら、あとは家族や友人と踊ったり、親密なコミュニケーション日暮れまで。
②少なすぎる:古代には豊富だったものが、現代では少なすぎる
・少なすぎる代表格「睡眠」
・平均の睡眠時間が1日7~9時間の範囲を逸脱すると体内の炎症マーカーが激増する
・夜中に何度も目が覚めてしまうような場合も、炎症は増える
・ナミビアやタンザニアで94人の狩猟採集民族に活動量計をつけ記録(2015年)
・日暮れから3時間後には必ず眠り、毎朝7時には自然と目を覚ます。
・目覚め夜中に目が覚めるケースはない。みな一晩で完全に体力を戻す。
・そもそも「不眠」「寝不足」のような単語すら存在しない。
・有酸素運動、筋肉を使う運動
・空腹感 等
③新しすぎる:古代には存在していなかったものが、近代になって表れた
・トランス脂肪酸(人体にとって新しすぎるせいで材料として使えず肝臓パニック)
・孤独(孤独を感じた脳も新しすぎる脅威に対して抵抗をはじめ、免疫システムを過剰に働かせた結果、全身は炎につつまれていく)
・デジタルデバイス
・抗生物質・処方薬
・デジタルデバイス 等
【P55~ 不安編】
●「不安」は文明病
●「ぼんやりとした不安」と「はっきりとした不安」
●ぼんやりとした不安が
① 慢性的な不安は記憶力を低下させる
脳の海馬が小さくなる
② 理性的な判断力を奪う
不安感が高まると様々な化学物質の連鎖が起こり、より原始的な脳の働き優勢になる。不安が起きた瞬間に倫理的な判断力を失てしまう。
③ 死期を早める
④ 日常の不安レベルが高い人は心疾患や脳卒中のリスク29%高い(2013)
●ポジティブな感情よりもネガティブな感情の方が強度が高い
・収益や顧客満足度の高いチームは、仕事中にポジティブ発言する割合がネガティブ発言の6倍。これはネガティブ発言1つを打ち消すのに、ポジティブ発言を6回言わなければならないことにもなる(2004)
●「農耕」出現により、現代人への影響が大きいのが「時間間隔の変化」
未来が遠くなった。
狩猟採集の頃は近い未来、近いものへの不安だけだった。
●狩猟採集民族は今現在に神経を集中する。
・行動を決めるのは目の前の獲物であって、またの機会を待つ、長期的な戦略に立って意思決定を下すことはない。
・ピグミー族は徹底的に目の前の「いま」に集中し続けているのです(ロンドン大学)
【P78~ 腸】
●あなたには数年来の大親友がいます。その親友と共同に暮らすようになりました。あなたは友人に住む場所を提供し、その代わりに友人が炊洗濯全部やってくれます。あなたはその友人なしには生きていけません。
しかし、ある日、今まで助けてもらった恩をわすれ友人を自宅から追放。
それでもめげずに戻ってくる友人を、何度も何度も追い出し始める。
↓
ここ数十年、人類は同じような過ちを繰り返している。
↓
「腸内細菌」の話
例:リーキーガット、衛生の発達、抗生物質
●腸内細菌(ビフィズス菌・乳酸菌)の働き
・アミノ酸や食物繊維などを材料にしいてビタミンB群やVKとしった重要な成分を合成。ビタミン欠乏症から免れる。
・栄養の吸収を助ける
・食物繊維を分解してエネルギーにかえる
・脂肪酸を生成して腸壁を守る など
↓
一番大事 「外敵との戦い」兵隊になる。
善玉菌がコロニーを形成し、前線基地を設営。
ここでバクテリアを駆除する武器を創り出し、腸管からの侵入をブロック。
+
腸内細菌は食物繊維から酪酸という脂肪酸を生産。これで有害物質が体内に入るのを防ぐ。
●リーキーガット
・腸の粘膜をつなぐ結着細胞が壊れる→バリア機能が敗れた状態。
腸の細胞に細かな穴が開いている現象。
↓
・腸の穴から未消化の植物やエンドキシン(毒素)等の有害物質が血管に侵入。
・これに免疫システム発動。体内のあらゆるエリアに慢性的な炎症。
↓
・リーキーガット→NO1「疲れやすさ」「アレルギー」など
●衛生の発達
・清潔な暮らしをしいていた西ドイツの方が、東ドイツより花粉症の患者数4倍(1989年)
→衛生状態が悪い保育所に預けられていいた乳幼児の方が微生物にさらされ、免疫システムが鍛えられた
・腸内にすみつく菌
ヤマノミ族50種類、一般的な西洋人数種類
●腸内細菌の食料難=食物繊維料の減少
・厚労省20~27グラム 今の日本人13~17グラム
●抗生物質を使うと腸内細菌が大量死
・たった1回の使用で3分の1死に、半年たってもダメージ回復せず
●抗菌グッズ
・肌に住み着く有益なバクテリアまで殺してしまう
●ケンカ別れした友人に・・
①発酵食品
納豆、キムチ、ぬか漬け、ヨーグルト、ザワークラウト
②プロバイオティクス
ビオスリーHi錠、など (P95参照)
●食物繊維
・野菜とフルーツの接種量を増やす!
・中でも、ゴボウ、寒天、海藻、キノコ類、オクラ、リンゴなどは腸内細菌が好きな水溶性の食物繊維を豊富に含む
・難消化性デキストリン、オオバコ(サイリウムハスク)、イヌリン、レジスタントスターチ
・腸内細菌は加工食品が大の苦手。中でも高脂肪で植物繊維少ないファストフード、精製糖の多い商品(スナック菓子や清涼飲料水)
【P106~ 環境】
●自然とのふれあいにより、確実に人体の副交感神経は活性化する(2016年)
・自然の癒し効果 d=0.71 マッサージ0.57
・自然の中では
「興奮」 喜びや快楽といったポジティブ感情(ドーパミン)
「満足」 「安らぎ」「親切心」といったポジティブ感情(オキシトシン)
「脅威」 「不安」や「脅威」(アドレナリンやコルチゾール) のバランスとれる。
・都市の暮らしでは主に「興奮」と「脅威」
例)吐いても食う。チフスやマラリアの脅威・ゲルマン人の侵攻
・週1回30分でも
・自然の大気には大量の微生物が含まれており、空気中で代謝と増殖を繰り返している。花粉のような微粒子が微生物を運んでいるからだ。大気中の微生物は、わたしたちの呼吸器から体内に入って腸に向かいい、免疫システムに影響を与える
●もともと私たちの脳は見知らぬ人とうまく人間関係をつくれるように設計されていない
(小さな集団の中だけで生きてきたから)
・人の認知リソースは大勢の友人をさばくようにはできていないため、1回につき5人前後としか親密な人間関係を築けない
・友人元々5人+新友人2人投下 2人間引きされる
【P146 ストレス 】
●心臓麻痺の患者は世界で年1700万人。
そのうち25%は激しいストレスによるところ。
・興奮→ACTH、アドレナリンでる→心拍数あがる
→コルチゾール過度の炎症反応で身体がうごかなくなるのを防ぐ
これは猛獣などに対応するための臨戦態勢。そして猛獣が去ると、ACTH,アドレナリン、コルチゾール
でなくなる。
・しかし、慢性的なストレス下では、脈も血圧も上がったまま。心臓にずっと負担をかけてしまう。
●短絡的に終わる急性のストレスをさばくのは得意、
現代の慢性的なストレスに立ち向かうようにはできていない。
●小技:睡眠、ウオーキング(週2-3 12分以上の早歩き)
●リアプレイザル
=ネガティブな感情の再評価
=感情に身を任せるネガティブ感情に支配されるのでなく、
=立ち止まり、冷静になって物事を整理する
「怒っている相手は、こんなこと感じているのかな?」
「イライラする自分は寝不足が大きく影響しているのかもしれない」 など
また、ストレス感じたら「楽しくなってきたぞ!」「面白くなってきたぞ!」と言い聞かせるのも
【P208 死】
●メメント・モリ ~死を想え~
●「すべての欲望はフィクションだと気づきなさい」
●さらにブッダは
「自分という存在すらフィクションだ」
もちろん“いまここ”で行動する主体は存在しますが、
結局のところ、私たちは遺伝子を残すために生まれた巨大なシステムの一部でしかありません。
「自分」とはあくまで環境とのやりとりのなかに生じる自然現象のひとつであり、
なにも変化しない絶対的な自己は存在しえません。
ありもしない事故に執着心をもつからこそ、不安が生まれるのだ。
●「畏敬」の念をもつと体内の炎症レベルが下がる
●畏敬がより大きなものの一部になったかの感覚へ。
過去・現在・未来すべてが含まれた永遠の時間に存在させてくれる。(=自然的超越)
●江戸中期の禅僧・白隠は、晩年に、
「人間死ぬときは死ぬがよい」との境地に達した。
【p282 エピローグ ~まず何をするか?~】
●自然との接触を増やすこと
・ストレスが劇的に下がるのはもちろん、自然の中にいれば大気に含まれる最近が腸内環境にもいい影響をあたえる
●人間関係と食物繊維
●睡眠と運動
●+発酵食品、プロバイオティクス、呼吸法、リアプライザル
+
●「人間は何のために生きているのか?」と学生から質問されたアインシュタイン博士は、
こともなげに答えました。
「他人の役に立つためです。そんなことがわからないんですか?」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
