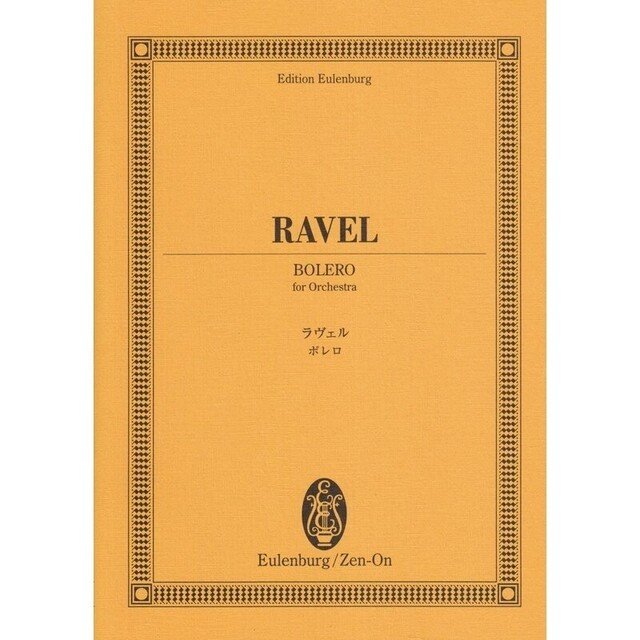
ラヴェル 『ボレロ』
のまにまに DTM Orchestra
00:00 | 00:00
『ボレロ』(仏: Boléro )は、
フランスの作曲家、モーリス・ラヴェルが
1928年に作曲したバレエ曲。
同一のリズムが保持される中で、
2種類のメロディーが繰り返されるという
特徴的な構成を有しており
現代でもバレエの世界に留まらず、
広く愛される音楽の一つである。
2016年5月1日、本国フランスにおいて著作権が消滅した。
この曲は、バレエ演者の
イダ・ルビンシュタインの依頼により、
スペイン人役のためのバレエ曲として制作された。
当初、ラヴェルはイサーク・アルベニスの
ピアノ曲集『イベリア』から6曲をオーケストラ編曲することで
ルビンシュタインと合意していたが、
『イベリア』には既にアルベニスの友人である
エンリケ・フェルナンデス・アルボスの編曲が存在した。
ラヴェルの意図を知ったアルボスは
「望むなら権利を譲りましょう」と打診したが、
ラヴェルはそれを断って一から書き起こすこととした。
作曲は1928年の7月から10月頃にかけて行われた。
同年の夏、アメリカへの演奏旅行から帰ってきたラヴェルは、
海水浴に訪れていたサン=ジャン=ド=リュズの別荘で
友人ギュスターヴ・サマズイユにこの曲の主題をピアノで弾いてみせ、
単一の主題をオーケストレーションを
変更しながら何度も繰り返すアイデアを披露した。
当初は『ファンダンゴ』のタイトルが予定されていたが、
まもなく『ボレロ』に変更された。
ハ長調で、一般的な演奏では、この曲の長さは15分程度である。
この曲は、次のような特徴を持つ。
1・ 最初から最後まで(最後の2小節を除く)
同じリズムが繰り返される。
2・最初から最後まで1つのクレッシェンドのみ
3・メロディもA、B、2つのパターンのみ
これだけを見ると極めて単調なように思われるが、
実際の演奏は非常に豊かな色彩をみせる。
曲は、スネアドラムによる後述のリズムが刻まれる中、
フルートによって始まる。
フルートはAの演奏を終えると
スネアドラムと同じリズムを刻み始め、
代わってクラリネットがAのメロディーを奏でる。
このように、次々と異なった楽器構成により
メロディーが奏でられ、
メロディーもリズムも次第に勢いを増していく。
そして最後には、フルート、ピッコロ、オーボエ、
オーボエ・ダモーレ、コーラングレ、クラリネット、
ファゴット、コントラファゴット、ホルン、
トランペット、ピッコロ・トランペット、
トロンボーン、テューバ、チェレスタ、
ハープ、ヴァイオリン、ヴィオラ、
チェロ、コントラバス、スネアドラム、
バスドラムという大編成で、
フルート単独の時と同じメロディーが奏でられる。
圧倒的な重厚さ(並行3度や5度を組み合わせたりもしている)で
A、Bのメロディーを演奏すると、
曲は初めてA、Bのメロディーを離れた旋律に移り、
音量も最高潮を迎えた直後、
最後の2小節で下降調のコーダで収束し、終焉を迎える。
現代音楽のミニマル・ミュージックに通じる展開である。
『ボレロ』はラヴェルゆかりの
スペインの民族舞踊であるにも関わらず、
自筆スコアの研究では
トライアングルとカスタネットが作曲過程で抹消され、
逆にE♭クラリネットとソプラノ・サクソフォーンが追加されるなど、
そのルビンシュタインの「スペイン人役」という
出自に反して民族色が消された上、
ラヴェルが立ち会った録音は総譜の指示
あるいは舞踊としての『ボレロ』よりテンポが遅いものばかりで、
指揮者のトスカニーニの実演に接したラヴェルは、
そのテンポの速さに激怒し、トスカニーニと口論にまでなったという
(しかし、ラヴェルの弟子のマニュエル・ロザンタールは、
著書『ラヴェル──その素顔と音楽論』のなかで、
この有名な逸話は真実ではないと語っている)。
Wikipediaより
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%AC%E3%83%AD_(%E3%83%A9%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AB)
(2015年06月28日作成)
フランスの作曲家、モーリス・ラヴェルが
1928年に作曲したバレエ曲。
同一のリズムが保持される中で、
2種類のメロディーが繰り返されるという
特徴的な構成を有しており
現代でもバレエの世界に留まらず、
広く愛される音楽の一つである。
2016年5月1日、本国フランスにおいて著作権が消滅した。
この曲は、バレエ演者の
イダ・ルビンシュタインの依頼により、
スペイン人役のためのバレエ曲として制作された。
当初、ラヴェルはイサーク・アルベニスの
ピアノ曲集『イベリア』から6曲をオーケストラ編曲することで
ルビンシュタインと合意していたが、
『イベリア』には既にアルベニスの友人である
エンリケ・フェルナンデス・アルボスの編曲が存在した。
ラヴェルの意図を知ったアルボスは
「望むなら権利を譲りましょう」と打診したが、
ラヴェルはそれを断って一から書き起こすこととした。
作曲は1928年の7月から10月頃にかけて行われた。
同年の夏、アメリカへの演奏旅行から帰ってきたラヴェルは、
海水浴に訪れていたサン=ジャン=ド=リュズの別荘で
友人ギュスターヴ・サマズイユにこの曲の主題をピアノで弾いてみせ、
単一の主題をオーケストレーションを
変更しながら何度も繰り返すアイデアを披露した。
当初は『ファンダンゴ』のタイトルが予定されていたが、
まもなく『ボレロ』に変更された。
ハ長調で、一般的な演奏では、この曲の長さは15分程度である。
この曲は、次のような特徴を持つ。
1・ 最初から最後まで(最後の2小節を除く)
同じリズムが繰り返される。
2・最初から最後まで1つのクレッシェンドのみ
3・メロディもA、B、2つのパターンのみ
これだけを見ると極めて単調なように思われるが、
実際の演奏は非常に豊かな色彩をみせる。
曲は、スネアドラムによる後述のリズムが刻まれる中、
フルートによって始まる。
フルートはAの演奏を終えると
スネアドラムと同じリズムを刻み始め、
代わってクラリネットがAのメロディーを奏でる。
このように、次々と異なった楽器構成により
メロディーが奏でられ、
メロディーもリズムも次第に勢いを増していく。
そして最後には、フルート、ピッコロ、オーボエ、
オーボエ・ダモーレ、コーラングレ、クラリネット、
ファゴット、コントラファゴット、ホルン、
トランペット、ピッコロ・トランペット、
トロンボーン、テューバ、チェレスタ、
ハープ、ヴァイオリン、ヴィオラ、
チェロ、コントラバス、スネアドラム、
バスドラムという大編成で、
フルート単独の時と同じメロディーが奏でられる。
圧倒的な重厚さ(並行3度や5度を組み合わせたりもしている)で
A、Bのメロディーを演奏すると、
曲は初めてA、Bのメロディーを離れた旋律に移り、
音量も最高潮を迎えた直後、
最後の2小節で下降調のコーダで収束し、終焉を迎える。
現代音楽のミニマル・ミュージックに通じる展開である。
『ボレロ』はラヴェルゆかりの
スペインの民族舞踊であるにも関わらず、
自筆スコアの研究では
トライアングルとカスタネットが作曲過程で抹消され、
逆にE♭クラリネットとソプラノ・サクソフォーンが追加されるなど、
そのルビンシュタインの「スペイン人役」という
出自に反して民族色が消された上、
ラヴェルが立ち会った録音は総譜の指示
あるいは舞踊としての『ボレロ』よりテンポが遅いものばかりで、
指揮者のトスカニーニの実演に接したラヴェルは、
そのテンポの速さに激怒し、トスカニーニと口論にまでなったという
(しかし、ラヴェルの弟子のマニュエル・ロザンタールは、
著書『ラヴェル──その素顔と音楽論』のなかで、
この有名な逸話は真実ではないと語っている)。
Wikipediaより
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%AC%E3%83%AD_(%E3%83%A9%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AB)
(2015年06月28日作成)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
