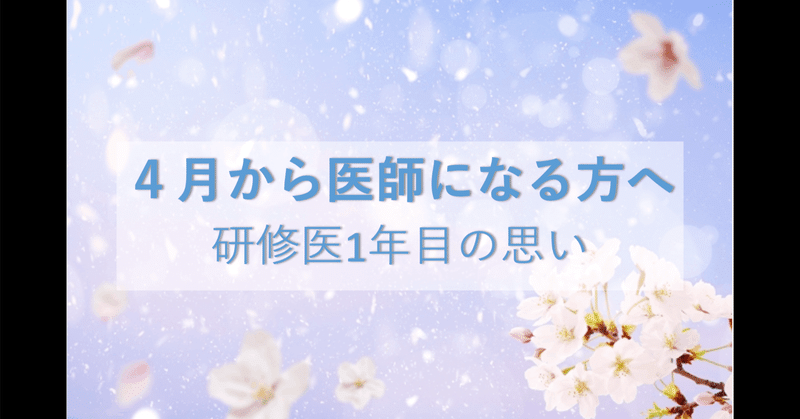
4月から医師になる方へ。研修医1年目の思い。
医師国家試験の合格発表も終わり、いよいよ私もあと1週間後には後輩ができることになりました。時が経つのは早いものです。
1年前の自分の今頃の思いは、
「いよいよ医者になれる!でもとっても不安だあ・・・。
何したらいいんだろう??」
楽しみな反面、いよいよ現場に出るという圧倒的な不安・・・。
そんな時、知り合いの先輩noteユーザーが、新研修医1年目に向けてのアドバイスをnoteにまとめていらっしゃいました。
私はそのnoteを読んでとっても安心しましたし、自信が持てたので、今度は自分がその恩返しをしたいなと思い、このnoteを投稿します。
4月からいよいよ医師デビューされる皆さんへ。
<注意!!>
以下は一個人の感想です。あくまで参考程度に読んでいただけると幸いです。
どんな医学書が必要なの?
医師として働く上でどんな医学書が必要になるんだ??というのは、新研修医にとって毎年気になることの一つだと思います。
そこでこの1年間、私が特によく使っていた10冊を挙げてみます。
・まずはみんなが持っている一冊を持ちたい→「内科レジデントの鉄則」
おそらくほとんどの研修医が持っているであろう一冊です。そのため、この本に載っていることは研修医の共通認識になっています。自分の担当症例や勉強会で学んだことを書き込んで、自分流に育てるのがオススメです。
・鑑別疾患の想起に→「ジェネラリストのための内科外来マニュアル」
前半は患者さんのよくある主訴ごとに挙げるべき鑑別疾患と、診断のために必要な考え方、とるべき問診と身体所見、オーダーすべき検査がまとまっています。後半は高血圧や糖尿病など、common diseaseごとのマネジメントが載っています。内科外来で私がいつも使っている一冊です。
・病棟管理のお供に→「総合内科病棟マニュアル」
病棟業務の基礎(赤本)
病棟での働き方、入院サマリのまとめ方、診療情報提供書の書き方など、研修医が特に知りたい病棟業務の基本について丁寧にまとめられています。病棟デビューの際のお供に有用です。
疾患ごとの管理(青本)
赤本が総論なら、青本は各論。疾患ごとに病歴・身体所見・オーダーすべき検査から、初期対応、入院後マネジメント、退院前アクションプランの流れでまとまっています。
・救急外来のお供に→「京都ERポケットブック」
救急外来での問診ポイント・検査などの総論から、緊急順に赤、黄、緑に重み付けして各症候の対応がフルカラーでまとまっています。ポケットサイズなので、救急外来でとても使いやすいです。
・カルテの書き方の基本が知りたい→「型が身につくカルテの書き方」
カルテの書き方について学ぶならこの一冊。カルテの基本の型が身についていると、患者さんの情報が綺麗にまとまり、自分の思考整理にもチーム医療にも貢献大です。基本的なSOAP形式の日常カルテの書き方から、入院時サマリ、退院時サマリ、外来でのカルテの書き方などまとまっています。早ければ学生から、遅くとも研修医1年目までに読むべき本だと思います。
・手技について流れを確認したい→「診察と手技がみえるvol.2」
採血やルート確保を始め、医師の仕事は様々な手技の連続です。この本は各手技について、ステップごとにカラー写真で、わかりやすく手順を紹介しています。いざ手技をやる前に、この本で手技の流れと注意点をチェックしてから臨むと良いです。
・感染症診療のお供に→「感染症プラチナマニュアル」
言わずと知れた感染症診療のバイブルの一つ。抗菌薬について、起因菌について、各種感染症について、ポケットサイズの中に詳しくまとめられています。抗菌薬や起因菌を、実臨床でパッと確認したい時によく使っています。
・輸液を学ぶ第一歩→「レジデントのためのこれだけ輸液」
研修医の業務で切っても切り離せない関係にあるのが「輸液」です。どんな患者さんで、何を、どのくらいの速度で輸液するのか、国試の勉強だけでは限界があると思います・・・。この本ではとても易しく輸液の使い方が解説されており、重要なところ、初期研修医が最低限習得すべきところに絞って載っているので、初学者にとてもオススメです。
・心電図を学ぶ第一歩→「レジデントのためのこれだけ心電図」
「レジデントのためのこれだけ輸液」と同じシリーズの心電図版。これもまた、重要なところ、初期研修医が最低限習得すべきところに絞って載っている心電図入門書です。緊急性のある心電図はパターン認識で、それ以外は系統的に読めるようになると良いですね。
医学書は紙?電子書籍?
医学書を紙か、電子版か、どっちで買おうか悩む!というのも、例年よくある研修医の悩みです。
私としては、じっくり読みたい本は紙で、現場ですぐ使いたいマニュアルや辞書は電子書籍で、というように使い分けるのがオススメです。
例えるなら、文章そのものを味わう小説は紙で、情報を取り出して使うような実用書は電子書籍で、と使い分けするように。医学書も同じような認識で問題ないと思います。
とはいえ、最初はこれはどっちに当てはまるのかよくわからないと思うので、実際に現場で使いながら自分に合う使い分けを試してみてください^^
勉強法について、EvernoteとGoodNotesはどう使い分ける?
学生から医師になって、アプリを使って学びをまとめている研修医は多いです。
その中でもまとめるためのアプリとして特に人気なのが、EvernoteとGoodnotesだと思います。
そこで、この2つをどう使い分けようか、で私も最初迷いましたし、研修医の間でも同じ迷いを持っている人が多くいました。
1年間働きながら学んでみての私のオススメの学び方として、毎日の症例ベースで気になったポイントを、その都度調べてまとめていくと良いです。
私は病棟で点滴のオーダーはこのようにするという実用的なメモから、この病気の治療効果判定には何を使えば良いのかというクリニカルクエスチョンまで、まずは何でもEvernoteにメモとして放り込んでいました。
そして1日の終わりにEvernoteの清書作業としてまとめることで、記憶に残るようにしていました。
一方で、GoodNotesは手書きしやすいというメリットがあるので、手書きメモを保存するのに使っています。
また、勉強会の資料などGoodNotesに保存すると後でサクサク読めるので、資料データ等はGoodNotesで保存しています。
手書き機能が充実しているため、勉強会の復習もしやすくなりました。
入職前って何をしたらいい?
あと1週間で学生生活が終わり、医師としての日々が始まる!とってもソワソワする日々だと思います。少なくとも私はそうでした。
こんな時、無理して勉強するよりかは、最後の学生生活を満喫するのがオススメです。現場に出て何が必要な知識なのか、わからないまま勉強してもあまりイメージが湧きにくいと思います。その分、家族や友人とゆっくり過ごしたり、趣味に没頭してみたりするといいですよ^^
最後の学生生活、是非是非謳歌してください!
とにかく不安!研修医生活で気をつけるべきことは?
まずは、きちんと食事と睡眠をとることがとても大事です。
夜勤や当直など、今までの生活リズムとは全く異なる世界なので、どうしても生活リズムは崩れがちです。どんなに頑張っていても身体に無理は効きません。
健全な精神は、健全な身体に宿ります。
食事と睡眠が疎かになると、どうしても仕事のパフォーマンスが落ちます。それが大きなミスにつながる可能性だってあります。
食事をとるのがめんどくさい、床に入っても寝付けない、というのはストレスのサインかもしれませんよ。
また、職場のスタッフには敬意を払い、笑顔で挨拶することがとても大事です。
自分がしてもらって嬉しいことを相手にもすると、お互いとても気持ちよく仕事できると思います。笑顔でいるようにすると、相手も働いていて気持ちいいですし、働いていて気持ちいい相手とは、仕事もスムーズに進むものだと思います。
そして、看護師さんに頼まれた仕事は即効でやることをオススメします。
看護師さんに頼まれる仕事は、今まさに現場で必要とされているものが多いからです。医師の指示がないと、看護師さんが動きたくても動けないことは多いものです。看護師さん含め、コメディカルの皆さんの協力無くして医療は決して成り立ちません。リスペクトを大切に。
最後に、研修生活を生き抜くために大切なこと。
医師1年目は、社会人1年目です。
今まで学習者としてだけの存在だった学生時代とは異なり、自分が社会の中で「役割」を持ち、「責任」を負う存在になります。
そして、「生」と「死」に直面することになります。
それは、自分自身が思っている以上にストレスフルかもしれません。
でも、あなたは一人ではありません。
同期が、
先輩が、
指導医が、
あなたの味方が、たくさんいます。
困ったら、身近な人に遠慮なく相談してみましょう。
周りはみんな上手くいっていて、自分だけ躓いているように見える時もあるかもしれません。
でも、周りのみんなも大抵、同じような悩みを抱えているものです。
あなたが得意なことを苦手な同期が、あなたのことも上手くいっていていいなあと思っていることもあるかもしれません。隣の芝生は青く見えるものです。
研修医で、初めて現場に出て、上手くいかないことだらけなのは当たり前です。
手技やら処方やら、大学で学んでこなかったことがいきなり求められるのが現場なのですから。
でも、経験を積み、ひたすら繰り返していく中で、必ず早く、そして上手くなっていきます。
だから、決して焦らず、日々の自分の成長を見つめてみてください。
毎日ちゃんと出勤して、1日に何か一つでも、学んだことがあったなら万々歳。
その日々の成長が、あなたを医師にし、人として成長させ、それが患者さんを救います。
どんな経験でも、無駄になることなんて何一つありません。
私は役に立っているんだ、という自己肯定感が、何よりの拠り所になります。
初期研修のゴールは、「2年間をsurviveする(生き抜く)こと」です。
何よりも自分の体と心の健康を大切にして、
医師という仕事を、自分の人生を、思い切り楽しんでください。
初期研修を1年生き抜いてみての、今の私の思いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
