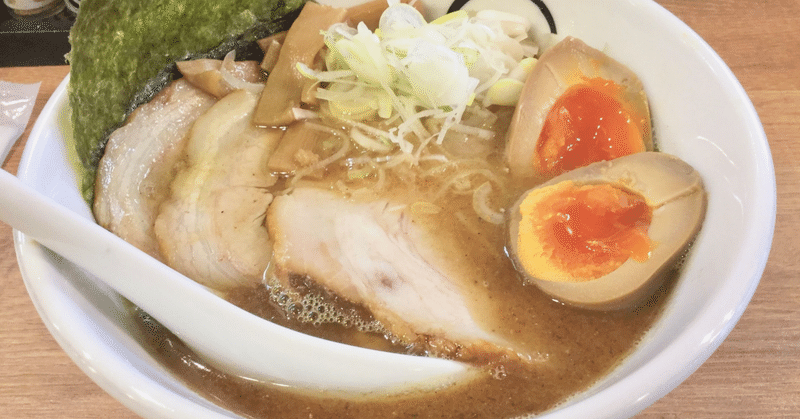
岩波書店『定本漱石全集』注解を校正する155 夏目漱石『明暗』をどう読むか④ 誰もそんなことは教えてくれなかった
見栄っ張りなのか
しかし今彼が自分の前に拡げている書物から吸収しようと力めている知識は、彼の日々の業務上に必要なものではなかった。それにはあまりに専門的で、またあまりに高尚過ぎた。学校の講義から得た知識ですら滅多に実際の役に立った例のない今の勤め向きとはほとんど没交渉と云ってもいいくらいのものであった。彼はただそれを一種の自信力として貯えておきたかった。他の注意を惹く粧飾としても身に着けておきたかった。その困難が今の彼に朧気ながら見えて来た時、彼は彼の己惚れに訊いて見た。
「そう旨くは行かないものかな」
彼は黙って煙草を吹かした。それから急に気がついたように書物を伏せて立ち上った。そうして足早に階子段をまたぎしぎし鳴らして下へ降りた。
リカレント教育やリスキングではなく、学校を出た社会人が仕事の役に立たない専門的な勉強をすること、この問題は高等遊民を巡って何度か論じてきたように思う。実際津田にポアンカレの話を吹き込んだ誰かも学校を出た社会人であり、仕事の役に立たない専門的で高尚な知識を得て、津田を脅かしたわけだ。津田はそんな学び直しに困難を感じている。
それにしても動機が不純だ。学びそのものに熱意があるわけではなく、学んだことを飾りにしたいのだからどうも高等遊民、松本恒三の態度とは異なる。どうもせこい。
この後の展開をざっと理解している立場で読み直すと、あれ、漱石は何故こんな男を書こうとしたのだろうと改めて不思議になるところ。
漱石作品が何かよきもの、真・善・美を求めて書かれ、例えば『坊っちゃん』の「おれ」のような無軌道な者を描いても、その「おれ」の中に何かの真実、何か善なるもの、何か美しいものを見て欲しいと考えていたことは確かなのだ。その点は飽くまで一貫している筈だ。谷崎とは違うのだ。
しかし津田は、例えば田川敬太郎から見れば「灰色の化物」であり、一体何のために生きているのか解らない人間なのではなかろうか。松本恒三には「ふん」と無視されるだろう。長井代助には牛の脳味噌で一杯詰っている頭を持つ人の目に着かない服装をして、乞食の如く、何物をか求めつつ、人の市をうろついて歩く者に見えるのではないか。
この間まで何者かになろうとして金より価値のあるものを目指しかけていた健三を見つめていたので、余計津田にはなにかだらしないものを感じてしまう。
しかし何故だらしないのか、それが解らない。
厭味ったらしい男だ
「おいお延」
彼は襖越しに細君の名を呼びながら、すぐ唐紙を開けて茶の間の入口に立った。すると長火鉢の傍に坐っている彼女の前に、いつの間にか取り拡げられた美くしい帯と着物の色がたちまち彼の眼に映った。暗い玄関から急に明るい電灯の点いた室を覗いた彼の眼にそれが常よりも際立って華麗に見えた時、彼はちょっと立ち留まって細君の顔と派出やかな模様とを等分に見較らべた。
「今時分そんなものを出してどうするんだい」
お延は檜扇模様の丸帯の端を膝の上に載せたまま、遠くから津田を見やった。
「ただ出して見たのよ。あたしこの帯まだ一遍も締めた事がないんですもの」
「それで今度その服装で芝居に出かけようと云うのかね」
津田の言葉には皮肉に伴う或冷やかさがあった。お延は何にも答えずに下を向いた。そうしていつもする通り黒い眉をぴくりと動かして見せた。彼女に特異なこの所作は時として変に津田の心を唆すと共に、時として妙に彼の気持を悪くさせた。彼は黙って縁側へ出て厠の戸を開けた。それからまた二階へ上がろうとした。すると今度は細君の方から彼を呼びとめた。
「あなた、あなた」
同時に彼女は立って来た。そうして彼の前を塞ぐようにして訊いた。
「何か御用なの」
彼の用事は今の彼にとって細君の帯よりも長襦袢よりもむしろ大事なものであった。
「御父さんからまだ手紙は来なかったかね」
「いいえ来ればいつもの通り御机の上に載せておきますわ」
津田はその予期した手紙が机の上に載っていなかったから、わざわざ下りて来たのであった。
岩波はここで「しばや」という芝居の読みに注をつける。それ、前にも出てきているよね?
ここは、「暗い玄関から急に明るい電灯の点いた室を覗いた彼の眼にそれが常よりも際立って華麗に見えた時」が明暗ですねとやらねばならないところだ。まあ、おそらく漱石は意識してそう書いている。しかしこのこと自体はさして深い意味を持たないように思える。こうした明と暗の対比はこの後も何度か現れ、その度にさして深い意味を持たない。
ただここでは、津田が何も思わずに、つまり読者に断りなしに階段を下りて、妻に問われなければ目的を忘れてしまうところだったというところを見なくてはなるまい。つまり階段を降りる時には「そうだ、手紙がないな、確認してみよう」と思っていた筈。そして明るいところで檜扇模様の丸帯を見て、つい用事を忘れてしまった。まだボケる年でもあるまいに、どうも意識がそれからそれへとふらふら動いている。全く信用できない人間だ。ダチョウは相当の馬鹿で、人間が背中に乗ってもそのことをすぐ忘れてしまい、重いとも何とも思わずにそのまま走っていくそうだが、津田もそんなものかもしれない。
そしてお延の方はお延の方で「それで今度その服装で芝居に出かけようと云うのかね」と言われてみるまでおそらく明確にそんなことを計画していたつもりはないが、そう受け止められても仕方のないこと、「いえ私も止しにするわ。芝居よりもあなたの健康の方が大事ですもの」と口では言いながら、どこかで新しい帯を締めて芝居に行きたい気持ちにふんぎりがついていないことを、後で気づかされたのだろう。
漱石はこうしたやり方で、意識とか意思の多層的な構造を指摘していく。
その手紙は何時着いたのか
「郵便函の中を探させましょうか」
「来れば書留だから、郵便函の中へ投げ込んで行くはずはないよ」
「そうね、だけど念のためだから、あたしちょいと見て来るわ」
御延は玄関の障子を開けて沓脱へ下りようとした。
「駄目だよ。書留がそんな中に入ってる訳がないよ」
「でも書留でなくってただのが入ってるかも知れないから、ちょっと待っていらっしゃい」
津田はようやく茶の間へ引き返して、先刻飯を食う時に坐った座蒲団が、まだ火鉢の前に元の通り据えてある上に胡坐をかいた。そうしてそこに燦爛と取り乱された濃い友染模様の色を見守った。
すぐ玄関から取って返したお延の手にははたして一通の書状があった。
「あってよ、一本。ことによると御父さまからかも知れないわ」
こう云いながら彼女は明るい電灯の光に白い封筒を照らした。
「ああ、やっぱりあたしの思った通り、御父さまからよ」
「何だ書留じゃないのか」
津田は手紙を受け取るなり、すぐ封を切って読み下した。しかしそれを読んでしまって、また封筒へ収めるために巻き返した時には、彼の手がただ器械的に動くだけであった。彼は自分の手元も見なければ、またお延の顔も見なかった。ぼんやり細君のよそ行着の荒い御召の縞柄を眺めながら独ごとのように云った。
昔は夜間郵便というものがあったらしい。らしいというのは公的機関の事業でありながら法律等を辿ってみても配達時間等の詳細が解らないからだ。この手紙が昼間着いていたものか、それとも津田が飯を食べている最中に着いたものか判然としない。
もし昼間に着いていたものなら「来ればいつもの通り御机の上に載せておきますわ」と言ったお延がわざわざ津田を迎えに玄関に出ていたにも関わらず、郵便受けの確認を怠っていたということになる。
従ってかりにお延をしっかり者とみるならばこれは津田が飯を食べている最中に着いたものということになるのだろうが、ここがもう一つはっきりしない。
まさか探すまでは「あるともないとも言えない状態だった」とまでは狙ってはいまいが、たかが一通手紙を渡すのに、どうも余計なひと手間がかかっているところだ。
そんなに着物が気になるのか
津田は「そこに燦爛と取り乱された濃い友染模様の色を見守った」「ぼんやり細君のよそ行着の荒い御召の縞柄を眺めながら」と少々くどい。しかしそれも言われてみればの話であり、明確に言語化された津田の感情というものがそこにあったわけではなかろう。
つまり津田はここで「お延の野郎、あんなことを言いながら心の中ではぶつぶつぶつ……」とまで考えていた訳ではなく、それはちょいと帯を出してみたお延の方も同じなのではなかろうか。
つまり明確に言語化されない人間のふるまいが交差する様子が描かれている。あるいは意識の何割かは明確に言語化されるものではないということが書かれている。
親の金をあてにするな
「困るな」
「どうなすったの」
「なに大した事じゃない」
見栄の強い津田は手紙の中に書いてある事を、結婚してまだ間もない細君に話したくなかった。けれどもそれはまた細君に話さなければならない事でもあった。
「今月はいつも通り送金ができないからそっちでどうか都合しておけというんだ。年寄はこれだから困るね。そんならそうともっと早く云ってくれればいいのに、突然金の要る間際になって、こんな事を云って来て……」
「いったいどういう訳なんでしょう」
津田はいったん巻き収めた手紙をまた封筒から出して膝の上で繰り拡げた。
「貸家が二軒先月末に空いちまったんだそうだ。それから塞ってる分からも家賃が入って来ないんだそうだ。そこへ持って来て、庭の手入だの垣根の繕いだので、だいぶ臨時費が嵩んだから今月は送れないって云うんだ」
宗助は役所勤めて弟を大学に通わせる甲斐性もなく、雨漏りのする家で、穴の開いた靴を履いて暮らしていた。津田は三十歳のサラリーマンのようだ。それなのに毎月親から仕送りをして貰っている。
ここで「金の要る間際になって」とは痔瘻の手術代のことだと理解はできるものの、そうした非常事態でない場合に、毎月親から仕送りをして貰っているとはいかにも情けない男なのではなかろうか。
これが時代性の反映かと思えば岩波はむしろ「大正五年当時は好景気のため質屋の金利も下がり……」としている。
大正五年と言えば第一次世界大戦の真っ最中である。後に津田が愚痴をこぼす通り、物価は上がっていたのだろう。それにしても三十にもなって親から毎月仕送りしてもらうというのはどうなのだろう。そんな生き物は恐らく人間だけだ。他の生き物は現金書留が使えないからだ。
この親から仕送りをしてもらうサラリーマンというものが極めて珍しいものなのか、当時は当たり前だったのかという辺りは是非とも説明が欲しいところ。少し調べてみたがなかなかこれという資料が見つからない。
何故ならそれ等の人々はまだ自分で社會に出て稼いで、金を儲けてゐる人々であるが、私と來たら三十にもなつてゐながら未だ母親の脛かじりで、閑潰ぶしのいゝ道樂に小說を書いてゐる、何も知らない幸運な「若隱居」に過ぎなゐからである。
生活の花 長与善郎 著新潮社 1918年
……といった例は見つかるが「親のすねかじり」は大抵書生どまりである。
君たちにはある分だけで生活しようという発想はないのか
津田は平生からお延が自分の父を軽蔑する事を恐れていた。それでいて彼は彼女の前にわが父に対する非難がましい言葉を洩らさなければならなかった。それは本当に彼の感じた通りの言葉であった。同時にお延の批判に対して先手を打つという点で、自分と父の言訳にもなった。
「で今月はどうするの。ただでさえ足りないところへ持って来て、あなたが手術のために一週間も入院なさると、またそっちの方でもいくらかかかるでしょう」
夫の手前老人に対する批評を憚かった細君の話頭は、すぐ実際問題の方へ入って来た。津田の答は用意されていなかった。しばらくして彼は小声で独語のように云った。
「藤井の叔父に金があると、あすこへ行くんだが……」
お延は夫の顔を見つめた。
「もう一遍御父さまのところへ云って上げる訳にゃ行かないの。ついでに病気の事も書いて」
「書いてやれない事もないが、また何とかかとか云って来られると面倒だからね。御父さんに捕まると、そりゃなかなか埒は開かないよ」
「でもほかに当てがなければ仕方なかないの」
「だから書かないとは云わない。こっちの事情が好く向うへ通じるようにする事はするつもりだが、何しろすぐの間には合わないからな」
「そうね」
その時津田は真もにお延の方を見た。そうして思い切ったような口調で云った。
「どうだ御前岡本さんへ行ってちょっと融通して貰って来ないか」
これで何となく解ってきた。この夫婦が親や親せきに頼って生活していて、自分の稼ぎだけで身の丈に合った生活をしないのは、散々周りからたかられまくった『道草』の裏返しだと。健三がけして言わなかったこと、言えなかったこと「君たちにはある分だけで生活しようという発想はないのか」という言葉を、漱石は『明暗』において読者に言わせようとしている。
そう気が付いてみると、ここ。
「郵便函の中を探させましょうか」
これは下女でもいるのかと思わせるところ。いや、実際下女はいるのだが、かなり丁寧に隠されていて、ここまで「させ」の二文字でしか仄めかされていない。当時下女を雇うのは当たり前のことではあったが、それにしてもここまできれいに隠されるとまるで「女中」や「お手伝いさん」がいるのは超お金持ちの家だけで、家電の発達により家事労働が楽になった百年後の読者を騙すために工夫しているかのようだ。
しかし「させ」だけって……。
[付記]
それにしても「させ」は凄いなと思う。ここが読めていないと漱石の凄さは解らない筈。しかし「させ」なんて、翻訳するくらいに読まないと気が付かないんじゃないだろうか。この人の言葉はどれだけ練られていたものかと本当に感心する。イタリア人は本当に理解しているのかな?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
