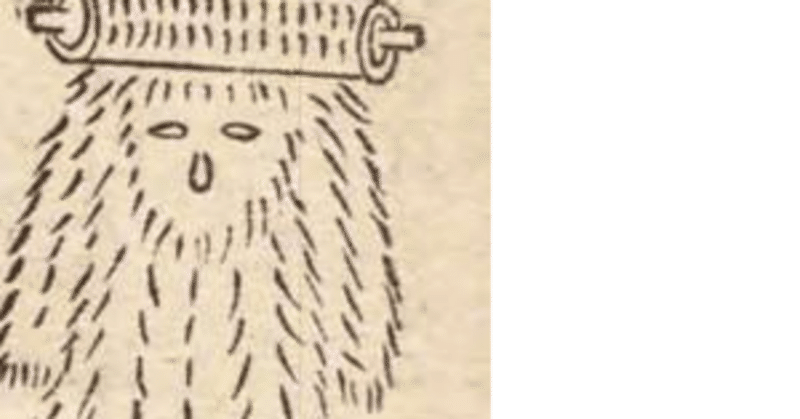
岩波書店『定本漱石全集』注解を校正する91 夏目漱石『行人』をどう読むか③
この『行人』という小説の表の筋はいい加減な使いとしての二郎がお貞の縁談をまとめ、その裏の筋としていい加減な使いとして二郎が直の縁談をまとめたという書かれていない設定があると書いて来た。そこが読めていないと二郎と直が先から知り合いだったという関係性が宙に浮いてしまい、何か真面な事を書いているように『行人』を論じてもネジが一本抜けたようになってしまうと。
お貞の縁談という筋が見えないで勝手に一郎を主人公にして「塵労」に分裂を見出してしまう近代文学1.0の人々は、全員このことを見逃していた。
梅のくだりもそうだろう。そして一郎は既に死んでいるという現在も誰も理解していない。
しかしそればかりではない。
テレパシーか何か
例えばテレパシー、
自分は嫂ほどに頭のできていないお重から、何も得るところのないのを覚さとって、また父や母のいる座敷へ帰ろうとした時、突然妙な話を彼女から聞いた。
その話によると、兄はこの頃テレパシーか何かを真面目に研究しているらしかった。彼はお重を書斎の外に立たしておいて、自分で自分の腕を抓った後あと「お重、今兄さんはここを抓ったが、お前の腕もそこが痛かったろう」と尋ねたり、または室の中で茶碗の茶を自分一人で飲んでおきながら、「お重お前の咽喉は今何か飲む時のようにぐびぐび鳴りやしないか」と聞いたりしたそうである。
「妾説明を聞くまでは、きっと気が変になったんだと思って吃驚りしたわ。兄さんは後で仏蘭西の何とかいう人のやった実験だって教えてくれたのよ。そうしてお前は感受性が鈍いから罹らないんだって云うのよ。妾嬉しかったわ」
「なぜ」
「だってそんなものに罹るのはコレラに罹るより厭だわ妾」
このテレパシーに岩波は、テレパシーの注を付ける。当たり前だ。しかし小説を読むには一つ一つの語の意味を理解するというだけでは足りない。その語の作中での働きを理解していなくてはならない。
この『行人』という小説の中では二度、直と二郎が「テレパシー」とでも解するよりほかにない精神の感応を見せる。ここで一郎が真面目にテレパシーの研究をするのは直の心を知りたいためだが、精神の感応は直と二郎に起こるのだ。「テレパシー」はむしろその前ふりである。
そしてやや先走ると「テレパシー」の代用品として、仲の良い友人に旅行に連れ出してもらい本音を聞き出して報告してもらうという実用的な方法が発見される。離れたところの様子を知るのには昔から手紙という便利な手段があったのだ。
で、『行人』という小説の中では二度、直と二郎が「テレパシー」とでも解するよりほかにない精神の感応を見せるって、どことどこなのか分からない?
実は前にも二度、直と二郎が「テレパシー」とでも解するよりほかにない精神の感応を見せるって書いていたのだが、調べる人はいなかったのだろうか?
調べる気がない?
はい、そうですか。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
