
尼寺や松三本の立ちけらし 夏目漱石の俳句をどう読むか111
尼寺や芥子ほろほろと普門品
解説に「普門品(ふもんぼん)は観音経」とある。
尼寺と芥子の因縁はわからない。
そのまま受け止めれば観音経が読まれているなか芥子がほろほろと散っている尼寺である事よ、という程度の意味か。
芥子は一二メートルの高さにもなる草花なので樹木から花が散るような眺めではあるまい。「ほろほろ」は種子が零れ落ちる様子なのかもしれない。
尼寺や芥子の散り込む日なされ?


芥子は春に「ほろり」と散るものらしい。


弾ける音がするのか?

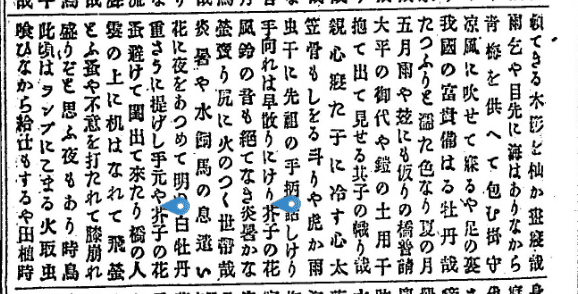
いや、やはり言葉の問題として「散る」のは花だ。実だと「なる」「おつ」「こぼる」であろう。「ほろりほろり」が少し引っかかるが、実は散らないな。
嬰子は殊更散りやすき花なり。風みをもまたず散る花のちらりと鏡にうつりしは誠に雷光石火のごとしと観念して死生一如の甚深微妙を述られたり斯のことく万物を書惜として学ふを不立文字と云へり。
三力||鼻中庵三力||ビチュウアン, サンリキ渋川清右衛門[ほか3名] 1783年

なるほど芥子の花は散りやすきもののようだ。この句は大変力のこもる念力の呪文のような観音経普門品愒の勢いで散りやすき芥子の花が散る尼寺の眺めを詠んだ句と解釈しておこう。
影参差松三本の月夜哉
解説に「参差は長短が不揃いなさま」とある。
長短不ぞろいの影を映して松が三本並んでいる月夜である事よ、という程度の意味か。
私の印象では松というのは横に広がりのあるもので、高さを比べたりしないのになあと不思議だったが、解説に『硝子戸の中』にこの句の回想があるというので見て納得した。
「時」は力であった。去年私が高田の方へ散歩したついでに、何気なくそこを通り過ぎると、私の家は綺麗に取り壊されて、そのあとに新らしい下宿屋が建てられつつあった。その傍には質屋もできていた。質屋の前に疎らな囲かこいをして、その中に庭木が少し植えてあった。三本の松は、見る影もなく枝を刈り込まれて、ほとんど畸形児のようになっていたが、どこか見覚のあるような心持を私に起させた。昔「影参差松三本の月夜かな」と咏ったのは、あるいはこの松の事ではなかったろうかと考えつつ、私はまた家に帰った。
私の生家にも大きな松があり、それはどれが幹だか枝だか区別のつかない、殆ど盆栽のような松だった。漱石の見た松は枝が落とせる程度にわりと幹のしっかり伸びた松だったということだ。
だから影参差なのだ。
ん?
老松参差として枝を交え……とか老松参差として枝を垂れ、というときには松が盛んに横に伸びている表現になるな。
これ、

①互いに入りまじるさま。
②長短不ぞろいなさま
という意味があるとしたら、①ちゃう?

長短不ぞろいの影を映して松が三本並んでいる月夜である事よ、ではなくて、三本の松の枝が入り混じるようにして影を落とす月夜であることよ、なんではなかろうか。
でなければ「三本の松は、見る影もなく枝を刈り込まれて、ほとんど畸形児のようになっていた」とまではいわれまい。
野分して朝鳥早く立ちけらし
野分が吹いた朝鳥たちは早くからどこかへ行ってしまったようだ、という程度のストレートな句かなとまずは思ってみる。

ところで小宮豊隆は「芭蕉のけらし」の中で芭蕉の「けらし」は「けり」+「らし」ではなく、多分に「けり」のニュアンスがあったのではないかと主張している。
この「推量を残すかどうか」という問題に関して言えば、むしろ漱石の句は「けり」+「らし」で推量にしたところが味わいであろう。
この鳥のさえずる音が今朝は聞こえないけれど、野分の音に消されている訳でもなかろうが、鳥たちはどこかでじっと身を潜めているのかもしれないし、旅だったのかもしれない、という推量の曖昧さが面白いではないか。
嘗て夏目漱石は、俳句はレトリクを煮つめて煎じつめたもの、レトリクのエッセンスであると言つた事がある。事實よほどのレトリクの達人でない限り、是ほど切りつめられた詩形の中では、自分の言ひたい事を、自由に又十分に、言つてのける事は出來ないのである。
この句は「聞く」という事実との向き合い方において詠まれた句であり、眺めではないわけだ。しかしどこにも「聞く」とか「聞こえない」とは書かれていない。
だいたい「立ちけらし」は春や秋や噂に使うものだが、そうか「今朝は鳥のさえずりが聞こえない」なら「立ちけらし」かと思ってみると小宮の言っていることが良く解る。
なるほど煎じ詰められている感じがする。まだ明治二十八年なのに。
[附記]
一応今回も「参差」の解釈において岩波の『定本 漱石全集』に再検討を促すような内容になってしまった。
こんなことが毎回続くと本当に死ぬのが恐ろしくなる。
まだ死ねない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

