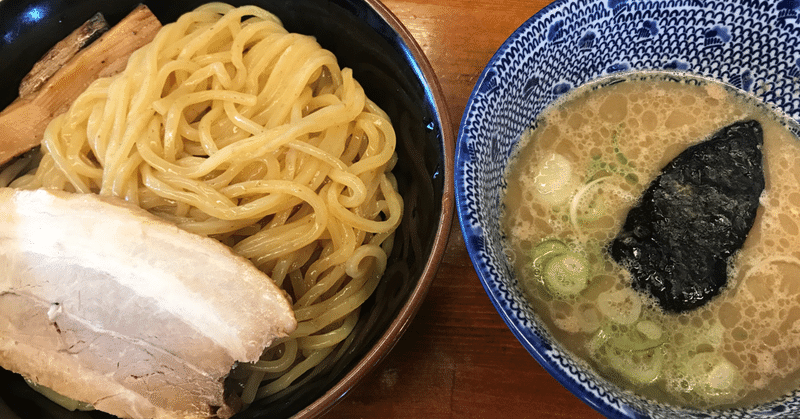
芥川龍之介の『或日の大石内蔵助』をどう読むか この梅の花は柔かい
芥川の得意とするところは「逆張り」あるいは「逆説」である。普通言われていることに対して「実はそうではないのだ」と逆のことを言い出す。これは『鼻』をはじめとしたストーリーそのものに対しても言えることだし、何なら小さなパーツや概念に対しても「違う、違う、そうじゃない」とやってくる。
この『或日の大石内蔵助』ではそのままストーリーと落ちが「逆張り」あるいは「逆説」となる。まず敵討ちで名を上げた大石内蔵助が、江戸中で仇討ちの真似事が流行っている話を聞かされて面白くない。
「手前たちの忠義をお褒め下さるのは難有ありがたいが、手前一人の量見では、お恥しい方が先に立ちます。」
こう云って、一座を眺めながら、
「何故かと申しますと、赤穂一藩に人も多い中で、御覧の通りここに居りまするものは、皆小身者ばかりでございます。もっとも最初は、奥野将監などと申す番頭も、何かと相談にのったものでございますが、中ごろから量見を変え、ついに同盟を脱しましたのは、心外と申すよりほかはございません。そのほか、新藤源四郎、河村伝兵衛、小山源五左衛門などは、原惣右衛門より上席でございますし、佐々小左衛門なども、吉田忠左衛門より身分は上でございますが、皆一挙が近づくにつれて、変心致しました。その中には、手前の親族の者もございます。して見ればお恥しい気のするのも無理はございますまい。」
大石内蔵助は①自分たちは小心者だ、②自分の親族にも変心したものがいる、として謙遜したつもりが話は背盟の徒を罵る方向に進んで行く。
「彼奴等は皆、揃いも揃った人畜生ばかりですな。一人として、武士の風上にも置けるような奴は居りません。」
「さようさ。それも高田群兵衛などになると、畜生より劣っていますて。」
忠左衛門は、眉をあげて、賛同を求めるように、堀部弥兵衛を見た。慷慨家の弥兵衛は、もとより黙っていない。
「引き上げの朝、彼奴に遇あった時には、唾を吐きかけても飽き足らぬと思いました。何しろのめのめと我々の前へ面つらをさらした上に、御本望を遂げられ、大慶の至りなどと云うのですからな。」
「高田も高田じゃが、小山田庄左衛門などもしようのないたわけ者じゃ。」
間瀬久太夫が、誰に云うともなくこう云うと、原惣右衛門や小野寺十内も、やはり口を斉しくして、背盟の徒を罵りはじめた。寡黙な間喜兵衛でさえ、口こそきかないが、白髪頭をうなずかせて、一同の意見に賛同の意を表した事は、度々ある。
大石内蔵助には自分たちが忠義の士と持ち上げられることも、また背盟の徒が犬畜生とされることにも不快である。「我々と彼等との差は、存外大きなものではない」とさえ考えている。しかし大石内蔵助は黙った。先ほどは反論したのが謙遜と取られてあらぬ話の流れとなった。だから黙っていたのが今度はまた謙遜と取られて話は大石内蔵助が世間を欺くためにわざと遊び惚けていたことに向けられていく。
伝右衛門は、こう云う前置きをして、それから、内蔵助が濫行を尽した一年前の逸聞を、長々としゃべり出した。高尾や愛宕の紅葉狩も、佯狂の彼には、どのくらいつらかった事であろう。島原や祇園の花見の宴も、苦肉の計に耽っている彼には、苦しかったのに相違ない。……
「承れば、その頃京都では、大石かるくて張抜石などと申す唄も、流行はやりました由を聞き及びました。それほどまでに、天下を欺き了せるのは、よくよくの事でなければ出来ますまい。先頃天野弥左衛門様が、沈勇だと御賞美になったのも、至極道理な事でございます。」
反論しても謙遜ととられ、黙っていても謙遜ととられ、褒められたくもないのに褒められどうしである。仕方がないので「いや、それほど何も、大した事ではございません。」としぶしぶ答えてみれば、やはり褒められる。
「あの通り真面目な顔をしている内蔵助が、当時は里げしきと申す唄を作った事もございました。それがまた、中々評判で、廓中どこでもうたわなかった所は、なかったくらいでございます。そこへ当時の内蔵助の風俗が、墨染の法衣姿で、あの祇園の桜がちる中を、浮さま浮さまとそやされながら、酔って歩くと云うのでございましょう。里げしきの唄が流行はやったり、内蔵助の濫行も名高くなったりしたのは、少しも無理はございません。何しろ夕霧と云い、浮橋と云い、島原や撞木町の名高い太夫たちでも、内蔵助と云えば、下にも置かぬように扱うと云う騒ぎでございましたから。」
こうなるとまた謙遜をするわけにもいかなくなる。しかし考えていたことはこんなことである。
内蔵助は、こう云う十内の話を、殆ど侮蔑されたような心もちで、苦々しく聞いていた。と同時にまた、昔の放埓の記憶を、思い出すともなく思い出した。それは、彼にとっては、不思議なほど色彩の鮮かな記憶である。彼はその思い出の中に、長蝋燭の光を見、伽羅の油の匂を嗅ぎ、加賀節の三味線の音を聞いた。いや、今十内が云った里げしきの「さすが涙のばらばら袖に、こぼれて袖に、露のよすがのうきつとめ」と云う文句さえ、春宮の中からぬけ出したような、夕霧や浮橋のなまめかしい姿と共に、歴々と心中に浮んで来た。如何に彼は、この記憶の中に出没するあらゆる放埓の生活を、思い切って受用した事であろう。そうしてまた、如何に彼は、その放埓の生活の中に、復讐の挙を全然忘却した駘蕩たる瞬間を、味った事であろう。彼は己を欺いて、この事実を否定するには、余りに正直な人間であった。勿論この事実が不道徳なものだなどと云う事も、人間性に明な彼にとって、夢想さえ出来ない所である。従って、彼の放埓のすべてを、彼の忠義を尽す手段として激賞されるのは、不快であると共に、うしろめたい。
大石内蔵助は天下を欺くために遊んだのではなく、時には敵討ちのことなど忘れて楽しんでいたのだ。これが逆説①。そして人間にはそういうところがあるもので「我々と彼等との差は、存外大きなものではない」、忠義の士であれ背盟の徒であれ、その人間の中にはそう単純でもないものがあるのだというのが逆説②。
大石内蔵助は「心の底へしみ透って来る寂しさ」を覚える。
面白そうな話というものは単純に作られたもので逆説②の複雑さに堪えられない。大石内蔵助は「青空に象嵌をしたような、堅く冷たい花を仰」ぐ。いったこの世のどこに堅い梅の花など存在するものだろうか。そのように見えることが逆説③。
逆説①②に気が付いていた人は、逆説③の遊びに気が付いただろうか。「青空に象嵌をしたような」とは作り物めいたという様子である。梅の花は作り物めいて見えた。しかしこうとも言えようか。「堅く冷たい花」とは大石内蔵助が見たままである。この梅の花が本当は柔かいなどとどのようにして確かめられようか。歌舞伎の中の大石内蔵助も象嵌である。「堅く冷たい花」である。
かんがりと ほのぼのと
道理こそ たしかに
似より おなじような
今日はこの三つの言葉だけ覚えて帰ってください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
