
曼殊沙華雀蛤とは凡夫なり 夏目漱石の俳句をどう読むか112
曼殊沙華あつけらかんと道の端
解説に一茶に
女郎花あつけらかんと立ちにけり
という類似句があることが記されている。




なんだかなあという感じである。

多数決だと「立てりけり」だろうか。「立ちにけり」はこの一例だけ。どうする岩波さん?
そのままでいいの?
直した方がよくない?
少なくとも併記だよね。

この句は例の『漱石俳句研究』でも大真面目に議論されている。三人とも「あつけらかん」は漱石が独自に取り出したものとみているようで、一茶の類似句には言及しない。

鑑賞としてはそれでいいと思う。一茶の句が先にあったとして、そこに関連はないように思える。勿論これが子規の句であれば問題である。
対比して関連を論じねばなるまい。
ただしこの漱石の句の場合、まさに「あつけらかん」としてここに詠まれているので、そのまま「あつけらかん」と眺めればよいのではないかと思える。


寅彦は「あつけらかん」に哀れ、孤独を感じ、東洋城は「ぽかん」と見ている。私もどちらかと言えば東洋城よりの「ぽかん」の印象だ。小宮が「場面」として「先生が入る」という立場ながら、東洋城は「入らない」という見立てで、これに関しては私は小宮寄りの考えである。
立てりけりではなく道の端なので見るものと見られる者の位置関係が出来ている。つまり場面があり、漱石は曼殊沙華を見下ろしている。よくもまあ何でもないような顔をしてけばけばしい花弁を逆巻くものだなあ、君は煉獄杏寿郎か、と漱石も「ぽかん」、曼殊沙華も「ぽかん」としている絵が面白いではないか。
一茶の句だと一茶の位置はない。これは「道の端」で場面が出来ている句だ。
史官啓す雀蛤とはなりにけり
解説に「雀蛤となるは寒露の節の第二候」とある。二十四節気七十二候のうち第二候は「菊花開」ではなかろうか。
と思えばこれは日本の場合。中国では寒露が「鴻雁来賓」「雀入大水為蛤」「菊有黄華」に分けられるようだ。
晩秋に雀が群れて海浜で騒ぐことから、雀が蛤になるという俗信が古くから中国にあり、「雀、海に入って蛤となる」という言葉が生まれた。
これでは全然句の意味が伝わらないのではなかろうか。まず「雀蛤とはなりにけり」は中国の二十四節気七十二候の「雀入大水為蛤」由来ではなく、中国の歴史書「国語」の「晋語九」由来のもので「雀入干海為蛤」由来、だからこそ「史官啓す」(歴史書を編纂する官吏が申し上げます)なのではなかろうか。
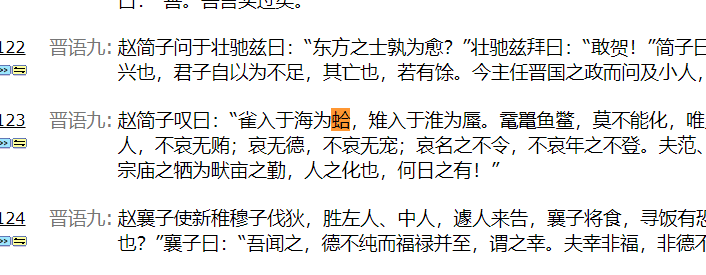



俳句や和歌の季題となっている「雀蛤になる」という言葉の元をたどれば俗諺ではなく歴史書なんだよな、というのが漱石の句の大意で、それに対して解説は「国語」という歴史書を無視する形になっているので、言ってみれば「ない」滑稽を無理に作り出している形になってしまっている。
漱石としてはたまたま「国語」(全二十一巻そのものでないにせよ、その抜粋か少なくとも「国語」に言及した本)を読んでいて、「へえ、こんなところが起源なのか」と感心したのだろう。
このニュアンスが解説からはまるで伝わらない。「国語」を読んでいないことが問題ではない。自分の知っていることを書いてしまって解釈を歪めてしまっていることが問題なのだ。
勿論誰しも自分が知っていることしか書けない。
しかしそれだけでは意味が解らないから調べる。まさかこの記事も何も調べないで書いたとは誰も思わないだろう。
もう一度句を見てほしい。
史官啓す雀蛤とはなりにけり
この句の意味が「寒露の節の第二候」で理解できますかということだ。全然つながらない。「国語」でつながる。つながるところまで調べないかね?
これ、あたりまえのことじゃないですかね?
岩波書店さん、マジで頑張って。
岩波教養主義はどこへ行ったの?
これじゃあ全然ダメだからね。
行く年や仏ももとは凡夫なり
解説に、
『平家物語』「祇王」にみえる今様の一節に「仏も昔は凡夫なり……」とある。

この解説も惜しい。
行く年や仏ももとは凡夫なり
この句の意味としてはむしろ「我らも終には仏なり」、つまり一休和尚の、
正月や冥途の旅の一里塚
という感覚がないと前後が上手く繋がらないのではなかろうか。
それとも、
今年は自分は凡夫だったけど、仏様だって昔は凡夫だったんだから、来年こそは頑張って偉くなってみせるぞ、という意味に解したのであろうか。
まあ、そういう解釈が絶対にありえないとは言わないが、『平家物語』からそこまで前向きな感情が取り出せるものだろうか。
いずれにせよ、そのくらい前向きならもう少し頑張ってもらいたい。
未来は変えることが出来る。
[余談]
今回も解説にあやをつけてしまった。
しかし仕方ない。
間違いは間違い。
宇宙全体が駄目になっているような気がする。
とても個人的なレベルの話ではない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

