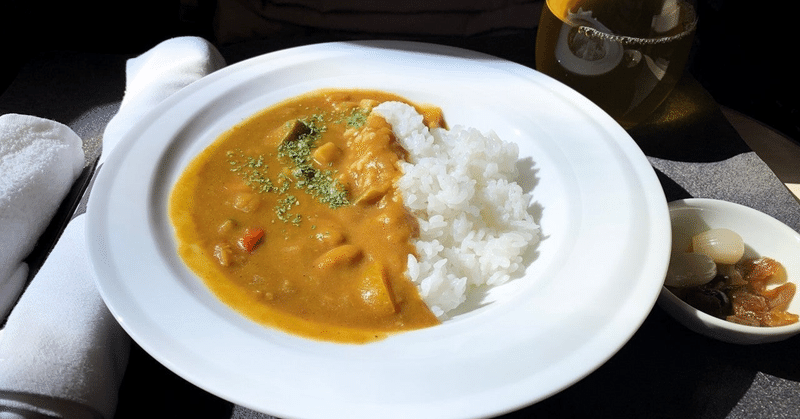
岩波書店『定本漱石全集』注解を校正する146 夏目漱石『道草』をどう読むか22 誰かが嘘をついている
島田一人でもう沢山なところへ
健三も細君も御常の書いた手紙の傾向をよく覚えていた。彼女とはさして縁故のない人ですら、親切に毎月いくらかずつの送金をしてくれるのに、小さい時分あれほど世話になって置きながら、今更知らん顔をしていられた義理でもあるまいといった風の筆意が、一頁ごとに見透かされた。
その時彼はこの手紙を東京にいる兄の許に送った。勤先へこんなものを度々寄こされては迷惑するから、少し気を付けるように先方へ注意してくれと頼んだ。兄からはすぐ返事が来た。もともと養家先を離縁になって、他家へ嫁に行った以上は他人である、その上健三はその養家さえ既に出てしまった後なのだから、今になって直接本人へ文通などされては困るという理由を持ち出して、先方を承知させたから安心しろと、その返事には書いてあった。
御常の手紙はその後ふっつり来なくなった。健三は安心した。しかしどこかに心持の悪い所があった。彼は御常の世話を受けた昔を忘れる訳に行かなかった。同時に彼女を忌み嫌う念は昔の通り変らなかった。要するに彼の御常に対する態度は、彼の島田に対する態度と同じ事であった。そうして島田に対するよりも一層嫌悪の念が劇しかった。
「島田一人でもう沢山なところへ、また新らしくそんな女が遣って来られちゃ困るな」
健三は腹の中でこう思った。
ここにおいてなかなか読み切れなかった例の手紙の趣旨は結局「金をくれ」というものだったことが明らかになる。実際ありとあらゆる、いや、99パーセントのメッセージは「金をくれ」に尽きる。「金をくれ」「買ってくれ」それ以外のメッセージはごくわずかだ。
この『道草』という作品は一面において健三が寄ってたかって金をせびられる話だ。
現時点ではまだ姉の御夏が小遣いの値上げを要求しただけだが、門司の叔父の「儲け話」が既に控えている。さあ、次は誰が来るのかと考えさせるところだ。
經濟上の苦境に陥いって来た
夫の過去について、それほど知識のない細君の腹の中はなおの事であった。細君の同情は今その生家の方にばかり注がれていた。もとかなりの地位にあった彼女の父は、久しく浪人生活を続けた結果、漸々経済上の苦境に陥いって来たのである。
と言っているそばから妻の父の苦境が出てきた。どうも父の財産は長太郎が使い果たしてもうない。元養父がややこしいことを言ってきている。門司の叔父もややこしいことを言って来そうだ。突然御常が来るかもしれない。そこに妻の父がきたらこれはさすがに無下にも出来まいが、何しろ金が足りないというので忙しいのに仕事を増やしたばっかりだ。夜の帰りも遅い。
段々負荷がかかってきた。
己は駄目だ
彼はその青年に仏蘭西のある学者が唱え出した記憶に関する新説を話した。
人が溺れかかったり、または絶壁から落ちようとする間際に、よく自分の過去全体を一瞬間の記憶として、その頭に描き出す事があるという事実に、この哲学者は一種の解釈を下したのである。
「人間は平生彼らの未来ばかり望んで生きているのに、その未来が咄嗟に起ったある危険のために突然塞がれて、もう己は駄目だと事が極まると、急に眼を転じて過去を振り向くから、そこで凡ての過去の経験が一度に意識に上るのだというんだね。その説によると」
青年は健三の紹介を面白そうに聴いた。けれども事状を一向知らない彼は、それを健三の身の上に引き直して見る事が出来なかった。健三も一刹那にわが全部の過去を思い出すような危険な境遇に置かれたものとして今の自分を考えるほどの馬鹿でもなかった。
岩波はこの「記憶に関する新説」に注解をつけて、それがベルクソンの『物質と記憶』にあらわされた説だとした上で、漱石蔵書目録に『物質と記憶』はなく「作中で健三がベルクソンについて詳しく知っていることは、作品に設定された時間からは不自然なことである」とする。
いや、漱石蔵書目録にないのだから、「不自然」ではなく「不可能」なのではなかろうか。
そもそも岩波は「現実世界とは異なる時間に支配されているのが作品の世界である」と規定していた筈である。つまり漱石は何でもありの世界を書いているので現実的にはあり得ない「存在しないテキストの引用」が可能なのだ。
これは一人漱石だけが操るレトリックではない。元少年Aはダフネ君に一度だけ見せ、ダフネ君が即座に丸暗記し、ワープロで打ち込み、印刷して、事件の証拠として警察に提出した長文の詩「ちょう役十三年」を『絶歌』でそのまま引用してしまった。
そんなことはありえないのではないか、とは誰一人言わない。馬鹿々々しい話だが、そういうことはたまに起こるのだ。
あの辺も昔と違って大分だいぶ変りましたね
「この間比田の所をちょっと訪ねて見ました」
島田の言葉遣はこの前と同じように鄭重であった。しかし彼が何で比田の家へ足を運んだのか、その点になると、彼は全く知らん顔をして澄ましていた。彼の口ぶりはまるで無沙汰見舞かたがたそっちへ用のあったついでに立ち寄った人の如くであった。
「あの辺も昔と違って大分だいぶ変りましたね」
健三は自分の前に坐っている人の真面目さの程度を疑ぐった。果してこの男が彼の復籍を比田まで頼み込んだのだろうか、また比田が自分たちと相談の結果通り、断然それを拒絶したのだろうか、健三はその明白な事実さえ疑わずにはいられなかった。
今目の前で起こったように映像で流された事件でさえ、犯人が誰なのか解らないということがある。例えば9.11。調べてみれば調べてみるだけ解らない話だ。あるいは地下鉄サリン事件。これもおかしなところが多い事件だ。テレビはケネディ暗殺事件祖から安倍元首相殺害事件までおかしな映像を流し続けてきた。
二発目の時、安倍元首相は一発目で何があったかと時計回り反対方向で後ろを振り返っている。その角度は90度以内。山上の位置からは頸部前方に当たらない。この単純な事実に、さらにどのような科学的な検証、証拠が必要とおっしゃるのでしょうか。 https://t.co/E1m0eqg77t
— 孫崎 享 (@magosaki_ukeru) April 15, 2023
健三も「あの辺も昔と違って大分だいぶ変りましたね」と「この間比田の所をちょっと訪ねて見ました」には面食らっただろう。それではまるで「用というほどの用があったわけでもありませんが久々に」が省かれて「この間比田の所をちょっと訪ねて見ました」のようであり、「しばらくあそこらへは行っていなかったもので行ってみると」が省かれて「あの辺も昔と違って大分だいぶ変りましたね」と言っているかのようである。これは四十六章なのだ。
つまり、二十七章の
「一体どうしたんです。島田がこちらへでも突然伺ったんですか」
「いやわざわざ御呼び立て申して置いて、つい自分の勝手ばかり喋舌って済みません。――じゃ長さん私から健ちゃんに一応その顛末を御話しする事にしようか」
「ええどうぞ」
話しは意外にも単純であった。――ある日島田が突然比田の所へ来た。自分も年を取って頼りにするものがいないので心細いという理由の下に、昔し通り島田姓に復帰してもらいたいからどうぞ健三にそう取り次いでくれと頼んだ。比田もその要求の突飛なのに驚ろいて最初は拒絶した。しかし何といっても動かないので、ともかくも彼の希望だけは健三に通じようと受合った。――ただこれだけなのである。
「少し変ですねえ」
健三にはどう考えても変としか思われなかった。
この比田の話が俄然怪しくなってくる。袴を返しに来た長太郎からは既にこの間の相談通り島田の要求を断った旨を聞いている。それが三十六章。つまりいまさら島田がぶらりと久々に比田を訪ねましてねといえる筈がないのだ。仮に比田の言うことが正しければ、島田が適当なことを言っていることになる。しかし二十七章からこの四十六章の間に健三の曖昧で不確かな「過去」が挟まれていることから、いかにも時空が歪んでしまったような感じがする。
もう大分久しく会わないには違ない
島田は相手に頓着なくただ世間話を進めて行った。健三の方では無論自分から進んで不愉快な問題に触れる必要を認めないので、ただ老人の迹に跟いて引っ張られて行くだけであった。すると何時の間にか島田の言葉遣が崩れて来た。しまいに彼は健三の姉を呼び捨てにし始めた。
「御夏も年を取ったね。尤ももう大分久しく会わないには違ないが。昔はあれでなかなか勝気な女で、能く私に喰くって掛ったり何なんかしたものさ。その代り元々兄弟同様の間柄だから、いくら喧嘩をしたって、仲の直るのもまた早いには早いが。何しろ困ると助けてくれって能く泣き付いて来るんで、私ゃ可哀想だからその度にいくらかずつ都合して遣ったよ」
島田のいう事は、姉が蔭で聴いていたらさぞ怒るだろうと思うように横柄であった。それから手前勝手な立場からばかり見た歪んだ事実を他に押し付けようとする邪気に充ちていた。
それにしても「歪んだ事実」とは何だろう。あるいは「歪んでいない事実」というものがどうやったら見つけられるだろうか。「岸田首相の襲撃を捉えたカメラは事前に事件を知っているようで茶番だ」は誤り。といった日本ファクトチェックセンターが確認した事実が「歪んでいない事実」なのだろうか。日本ファクトチェックセンターは
カメラワークは経験に裏打ちされたもので、報道のプロの撮影手法としては一般的。「段取りを知っていた茶番」というのは根拠がなく、実際の現場の状況も総合して誤りと判定した。
と結論付けているが、逆に映像は一般人の背中に邪魔されているのでポジション取りが出来ていないことが解る。報道のプロがポジション取りが出来ていないことの検証はされていないようだ。つまりその映像だけからは「段取りを知っていた」かどうかは判断できないが、逆にその映像のみで「茶番でない」とまでは言い切れない。何故か報道のプロがポジション取りが出来ていない位置から経験に裏打ちされた撮影技法を見せた?
そう言うところは調べないで、「茶番」までを打ち消したい願望が見えるところがこの組織の怪しいところだ。
健三が島田に見た邪気もそういうものであろう。
「こちらへはその後まるで来ないんですか」
「ああこの二、三年はまるっきり来ないよ」
「その前は?」
「その前はね、ちょくちょくってほどでもないが、それでも時々は来たのさ。それがまた可笑しいんだよ。来ると何時でも十一時頃でね。鰻飯かなにか食べさせないと決して帰らないんだからね。三度の御まんまを一ひとかたけでも好いいから他の家で食べようっていうのがつまりあの人の腹なんだよ。そのくせ服装なんかかなりなものを着ているんだがね。……」
七章と姉の言葉「この二、三年はまるっきり来ないよ」と四十六章の島田の「もう大分久しく会わないには違ない」はやはり絶妙に食い違う。何しろ島田は今の御夏と子供時分の御夏を比べているかのようだ。これでは「この二、三年はまるっきり来ないよ」とはならない。誰かが嘘を言っている。
しかし健三は明確には姉を疑うことができない。ここまで食い違う話をしている島田を疑うことで逃げようとしている。
法印か何ぞのように
島田は妙に鼻の下の長い男であった。その上往来などで物を見るときは必ず口を開けていた。だからちょっと馬鹿のようであった。けれども善良な馬鹿としては決して誰の眼にも映ずる男ではなかった。落ち込んだ彼の眼はその底で常に反対の何物かを語っていた。眉はむしろ険しかった。狭くて高い彼の額の上にある髪は、若い時分から左右に分けられた例がなかった。法印か何ぞのように常に後へ撫で付けられていた。
彼はふと健三の眼を見た。そうして相手の腹を読んだ。一旦横風の昔に返った彼の言葉遣がまた何時の間にか現在の鄭寧さに立ち戻って来た。健三に対して過去の己に返ろう返ろうとする試みを遂に断念してしまった。
岩波はこの「法印」に注解をつけて「この髪形をしているために、帽子をかぶらない習慣であったと思われる」としている。坊主なら頭巾の方が良かろうが、坊主でないなら帽子を被らない理由にはならない。根拠のないところからの思い込みによる主張である。
なぜ日本ファクトチェックセンターはこの点を指摘しないのだろうか。それはおそらく「この髪形をしているために、帽子をかぶらない習慣であったと思われる」という岩上の見解が現政権にとって危険なものではないからだろう。
問題の取り上げ方から立場というものが見えてくることもある。
[余談]
「永遠と話を聞かされたよ」??
— 明鏡国語辞典 (@MeikyoKokugo) April 18, 2023
『明鏡国語辞典 第三版』「永遠」の[注意]欄で解説しています。 #明鏡 pic.twitter.com/uts6iwcheM
永久に、なら使えそう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
