
芥川龍之介の『玄鶴山房』をどう読むか③ 昼間寝ているのか
時代や歴史や人生などというものは年寄りの特権的なもので、若い時はいつも目の前の現実しかなかった。振り返る時間もなかった。今もそうしてできるだけ目の前を見て生きようとしているが、つい時代や歴史や人生を突き付けられてしまう瞬間がある。
芥川の『玄鶴山房』もそうした作品だ。前回は「文化竈」に引っかかったがよく読むとその前に「文化村」が出て来ていた。

今、「文化」のつく言葉というと「文化包丁」と「文化シャツター」くらいしか残っていないが、大正末期から昭和初期にかけて、新しいものには何でもかんでも「文化」がつけられていた。
谷崎潤一郎が『痴人の愛』を連載しはじめるのが大正十三年。文化村には文化住宅が建ち、文化的な生活を始めていた。
佃煮には「文化煮」というものまであった。
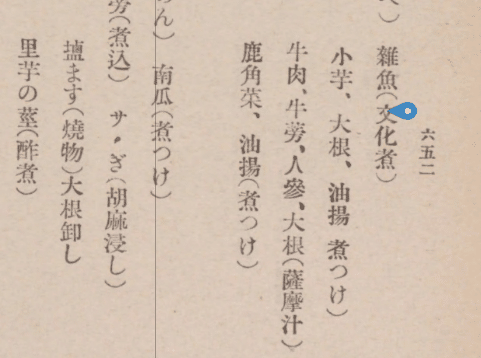
これはつまりいつの時代にも「あたらしいもの」が現れて人気になり、廃れてしまうという歴史である。人は誰しもその人生に於いてどこかの歴史に属して、その時代の「ふるいもの」と「あたらしいもの」の間で生きるしかない。今 X では黒人奴隷と酒とたばこが「あたらしいもの」で、一週間もするとみんな忘れてしまうと思う。それが繰り返されるのが人生で、いつのまにかリミットが来る。箸袋に名前が書かれていたことなんか忘れてしまう。人生なんてむなしいものだ。
「玄鶴山房」の夜は静かだった。朝早く家を出る武夫は勿論、重吉夫婦も大抵は十時には床に就くことにしていた。その後でもまだ起きているのは九時前後から夜伽をする看護婦の甲野ばかりだった。甲野は玄鶴の枕もとに赤あかと火の起った火鉢を抱え、居睡りもせずに坐っていた。玄鶴は、――玄鶴も時々は目を醒ましていた。が、湯たんぽが冷えたとか、湿布が乾いたとか云う以外に殆ど口を利いたことはなかった。こう云う「離れ」にも聞えて来るものは植え込みの竹の戦ぎだけだった。甲野は薄ら寒い静かさの中にじっと玄鶴を見守ったまま、いろいろのことを考えていた。この一家の人々の心もちや彼女自身の行く末などを。………
驚いた。
驚かないと駄目だとかそういう話ではない。
私は驚いた。
看護婦が夜伽をするのかと思えば、主格が看護婦の甲野に転じている。これは芥川作品の中でも極めて珍しいやり口ではないか。そして思わず出かかって躊躇した言葉が「今更、死ぬ間際になって……」。
まさに今この私自身が「今更、死ぬ間際になって……」日々noteを更新しながら、投げ銭以外に何を期待しているのかと考えてしまう。「今更、死ぬ間際になって……」とは言いながら、それでもまだこの時の芥川程差し迫った死というものを意識している訳でもないが、それでも「なんでもできる」ほどの時間のない中で、日々noteを更新していることは紛れもない事実なのである。

ではその瞬間瞬間に「甲野は……考えていた」などというトリッキーな神技を編み出しているかと言えば、さすがにそこまでの事は出来ていない。何か意味のあることを書いている筈だとは思うが、人によってはこれを意地悪なただの間違い探しだと捉えてしまうかもしれないなと思う。
それにしても看護婦目線か。まるで「家政婦は見た」的発想ではないか。いや、そのアイデアそのものは既にシェイクスピアにある。あることはあるが、なかなかできる細工ではない。
やってみれば分かる。大抵は小手先の悪ふざけに見えてしまう。漱石は下女目線では語らなかった。谷崎は……谷崎にもそういう作品は……ちょっと思い当たらない。太宰治は? 三島由紀夫は? いや、誰ならあるのだ?
筒井康隆と丸山健二にはあるかもしれない。しかしそういうことではないのだ。重吉が寝た後、甲野が起きていて、自然に主格がスイッチするのは『明暗』の作法だろうというのだ。しかし妻ではなく、看護婦という、家族に於いては傍観者に視線を預け、なんなら彼女自身の生末を考えさせようとするその巧みな設定に唖然としているのだ。
こんなことを芥川のほかに誰がやった?
しかも「今更、死ぬ間際になって……」。あほちゃうかと思う。なんでもつとはやくやらへんねんと。それはもちろん誰にでも思いつくことではない。彼にしかできなかったこと、と言ってもよいのではないか。このアイデアそのものは明日書かれる新人の小説に即応用可能だが、それだけを真似てもほとんど意味はなかろう。
何故なら『玄鶴山房』はこの後看護婦の事を忘れさせてしまう怒涛の展開を見せるからだ。しかしそれがどんな展開なのか、まだ誰も知らない。
何故ならまだ書いていないからだ。
[余談]
昔の人は十時に寐るのか。テレビはないものな。ネットもないし。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
