
春の雨彼岸桜は木魚哉 夏目漱石の俳句をどう読むか109
春の雨あるは順礼古手買

この同じ本で例の「朱鞘」の句は正岡子規の句だと認識されているので、やはり岩波書店が間違っているんじゃないかな。
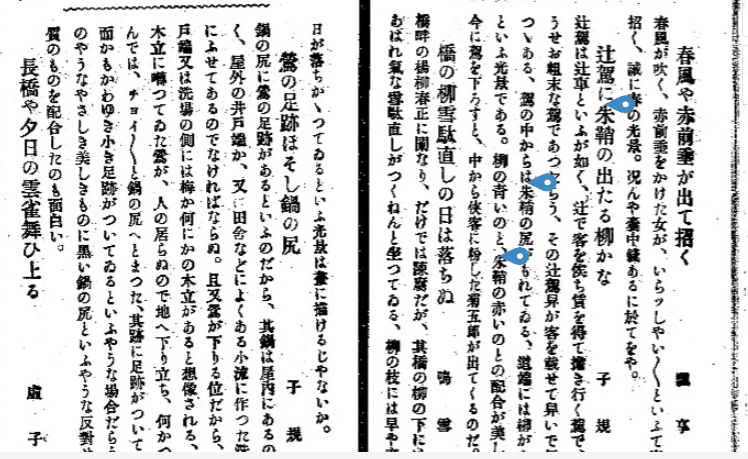
解釈はまあ鼠骨の書いている通り、春の雨で家にこもっていたら順礼と古手買がやってくる……。

いやいや、これは順礼、古手買、節季候に化けて、家々を覗いているんじゃないの、探偵しているんじゃないのと、漱石の被害妄想、監視されている妄想が出てきた句なのではないか。
よくよく考えてみれば雨の中の古手買って、古着が雨に濡れて大変だろう。要するになんやかんやと理屈をつけて家を覗きに来る奴がいるぞという意味で「順礼古手買」なのではないか。
一般的には『坊っちゃん』で初めて確認されるとされていた漱石の被害妄想、監視されている妄想が明治二十八年に既に出ていたとなると、これはまたこれで新説になるんじゃない?
なんか昨日から驚くことばかりだな。
尼寺や彼岸桜は散りやすき
彼岸桜が格別に散りやすきものとは思わねど、尼寺に来てみれば訪ね来る人を待ちかねて散ってしまうような、そんなはかなさがしみじみ感じられるということなのであろう。
いやいやソメイヨシノに比べると彼岸桜は小さく地味で開花は早い。ただそのように事実のみを述べたのではなく、尼寺の何とも言えぬ世を捨てた感じというものを彼岸桜に移してみたのであろう。
この句が明治二十八年四月の句であるとするなら「尼寺に行け」と言っているようにも思えなくもない。(さすがにそこまではあれか。)
叩かれて昼の蚊を吐く木魚哉
この句には
たゝかれて蚊を吐昼の木魚哉 東柳
たゝかれて蚊を吐く昼の木魚哉
という類似句があることが既に解説で指摘されている。こういう具合に「朱鞘」の句にも経緯の説明が必要だろう。

叩かれて昼の蚊の出る木魚かな

1896年は明治二十九年。この時点で読み人知らずの類似句はあったわけだ。
叩かれて呑んだ蚊を吐く木魚哉

昼の蚊を叩き出したる木魚かな

叩かれて呑まれた蚊を吐く木魚かな
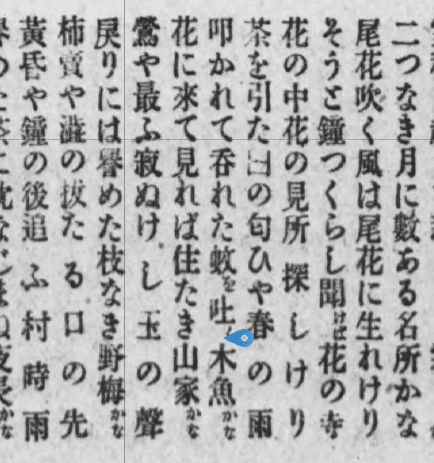
呑んだ蚊を叩かれて吐く木魚かな

たゝかれて口から蚊吐く木魚かな

こうして散々こすり倒されて、伝言ゲームのようになっている。但し、「昼の蚊を吐く」とした漱石の句が一番整っている感じがする。
ただし解釈としては小宮豊隆が「理知の働きで作られた句」と言い、松根東洋城が「意外に蚊の出たという軽い滑稽味を感じる」と評し、寺田寅彦は「滑稽味は感じない」と反論する。「非常に鮮明な実感があつて」「寧ろ真面目な、さびしみのあるもので」というのに対してやはり小宮は滑稽を見る。……と案外意見が分かれるところのようだ。

私の印象では本来蚊の活動時間は昼なので、昼の蚊は遠慮がないという感じがある。日光は嫌いで薄暗いじめじめしたところを好むが夜行性ではない。


となると木魚にいたのは休憩中だったということで、それが追い出されるのであるから、蚊にしてみれば迷惑な話で、やはり滑稽と取りたい。
馬子歌や小夜の中山さみだるゝ
この句は、西行の
年たけてまた越ゆべしと思いきや命なりけり小夜の中山
……の小夜の中山に掛川の日坂馬子歌が聞こえる中、五月雨てさみしい様子が詠まれている。
日坂馬子歌がこのままのものであったとしたら、なんか辛いことあったの? と聞きたくなる。
まあこんなに声は張らないだろうけど、雨の中本当に日坂馬子歌が歌われていたら、なかなか薄気味悪いというか、そういう感じがしてしまうのは、あくまでも現代的な感覚なのだろうか。
なんにしても、
馬の息山吹散つて馬士も無し
で、吹き飛ばされた馬子が戻ってきてよかった。
[余談]
岩波書店への問い合わせの件、結果が出たら報告するね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

