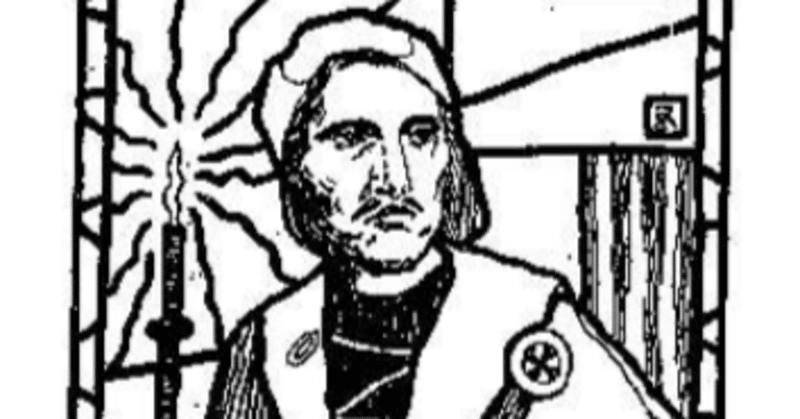
『倫敦塔』について①
何度読み返してみても『倫敦塔』は不思議な話です。書いてあることは解るけれども、何が書いてあるのかは解らない、ロジックが利かない、そういう話に思えます。つまりこれまでの私自身の理屈でいえば「それでは読んだことにはならない」作品なのです。例えば、
二十世紀の倫敦がわが心の裏から次第に消え去ると同時に眼前の塔影が幻のごとき過去の歴史を吾が脳裏に描き出して来る。朝起きて啜る渋茶に立つ煙りの寝足らぬ夢の尾を曳くように感ぜらるる。しばらくすると向う岸から長い手を出して余を引張るかと怪しまれて来た。今まで佇立して身動きもしなかった余は急に川を渡って塔に行きたくなった。長い手はなおなお強く余を引く。余はたちまち歩を移して塔橋を渡り懸けた。長い手はぐいぐい牽く。塔橋を渡ってからは一目散に塔門まで馳せ着けた。見る間に三万坪に余る過去の一大磁石は現世に浮游するこの小鉄屑を吸収しおわった。門を入って振り返ったとき、
憂いの国に行かんとするものはこの門を潜れ。
永劫の呵責に遭わんとするものはこの門をくぐれ。
迷惑の人と伍せんとするものはこの門をくぐれ。
正義は高き主を動かし、神威は、最上智は、最初愛は、われを作る。
我が前に物ものなしただ無窮あり我は無窮に忍ぶものなり。
この門を過ぎんとするものはいっさいの望みを捨てよ。
という句がどこぞで刻んではないかと思った。余はこの時すでに常態を失っている。
……と、あたかも旅行記、エッセイかと見まがうように始まった物語は、急に常態を失った「余」という信頼できない話者と付き合わされる幻想小説になります。つまり基本的には全部の出来事が現実ではないのですが、実際全部の出来事が現実ではない、として読むことはなかなか難しいのです。人は仮構の中にもどこか現実世界の合理性を求めていて、仮構の前提となるあり得ない設定を受け入れてしまった後は、その残りの部分では現実世界と変わりない合理的な世界の成り立ちを希望してしまうものではないでしょうか。ないでしょうかと云いながら、これは私個人の感覚なのですが。ところがこの『倫敦塔』という小説は、あたかも阿片中毒者の白日夢のように、幻想を畳みかけるのです。しかも『夢十夜』のように考えさせることを放棄させるような形ではなく、理屈を完全には放棄していないのでさらにややこしいのです。この『倫敦塔』は並外れて厄介な作品だと思います。
この一作に関しては、ダミアン・フラナガンの着想もけして奇抜ではないと思われるほどです。
小供は女を見上げて「鴉が、鴉が」と珍らしそうに云う。それから「鴉が寒そうだから、麺麭をやりたい」とねだる。女は静かに「あの鴉は何にもたべたがっていやしません」と云う。小供は「なぜ」と聞く。女は長い睫の奥に漾ようているような眼で鴉を見詰めながら「あの鴉は五羽います」といったぎり小供の問には答えない。何か独りで考えているかと思わるるくらい澄ましている。余はこの女とこの鴉の間に何か不思議の因縁でもありはせぬかと疑った。彼は鴉の気分をわが事のごとくに云い、三羽しか見えぬ鴉を五羽いると断言する。あやしき女を見捨てて余は独りボーシャン塔に入る。(夏目漱石『倫敦塔』)
この「あやしき女」と小供の会話は常識的には会話になっていません。言葉は交わしていますが、意味としてはすれ違っているからです。「彼は鴉の気分をわが事のごとくに云い、三羽しか見えぬ鴉を五羽いると断言する」と「余」は冷静に指摘しているようでもありますが、その「余」もまた「この女とこの鴉の間に何か不思議の因縁でもありはせぬかと疑った」と少々真面でないことを考えています。まあ「常態を失っている」のならばそうなっても可笑しくはないのですが、読み手として混乱するのは、「常態を失っている」話者がなまじっか理屈を持ってこようとするからなのです。理屈を完全に放棄して、つまり自分が見聞きする不思議な出来事をそのまま語ってくれればそれは、ああ不思議だな、で片付けられるのですが、理屈を言い出すとややこしいことになります。「余」は、意味としてはすれ違っている会話にオカルト的な根拠を求めようとしています。これが「鴉は五羽いました」なら「今見えている三羽は今しがた二羽の鴉を食べてしまったところなので今は食欲がありません」という理屈にもなるのでしょうが、「あの鴉は五羽います」では見えない二羽の鴉が見えている「あやしき女」が鴉の感情をも見えているというただただオカルトチックな話になってしまいます。
この鴉については、
無我夢中に宿に着いて、主人に今日は塔を見物して来たと話したら、主人が鴉が五羽いたでしょうと云う。おやこの主人もあの女の親類かなと内心大いに驚ろくと主人は笑いながら「あれは奉納の鴉です。昔しからあすこに飼っているので、一羽でも数が不足すると、すぐあとをこしらえます、それだからあの鴉はいつでも五羽に限っています」と手もなく説明するので、余の空想の一半は倫敦塔を見たその日のうちに打ち壊されてしまった。(夏目漱石『倫敦塔』)
……と宿の主人がまるで合理的な種明かしをした如く書かれていますが、
①「あやしき女」が鴉の気分をわが事のごとくに云い
②「あやしき女」が三羽しか見えぬ鴉を五羽いると断言する
……と云う謎に関しては全く解決していないわけです。つまり言葉の上では「手もなく説明」されているようでありながら、何にも説明されていないのです。何も説明されていないのに「余」は納得してしまっています。むしろ、
③いつでも五羽いる筈の鴉が二羽不足していたのは何故
……と云う謎が加わります。そしてむしろ「今見えている三羽は今しがた二羽の鴉を食べてしまったところなので今は食欲がありません」という打ち捨てた筈の理屈が再び浮かび上がってきます。「一羽でも数が不足すると」という主人の言葉が気になります。「一羽でも数が不足すると」とはどういう状況なのでしょうか。不足する、とはまさに鴉の死を意味していないでしょうか。そしてさらに「いつでも五羽に限っている」としたら、
④「余」が鴉は三羽しかいないと思ったのは何故なのか
……と云う謎が加わります。無論全部の不整合を「余が常態を失っているから」と片付けて片付けられないことはない筈なのですが、どこかでこの『倫敦塔』は現実の合理性と接点を持ちたがっているのですね。だから困るのです。
どのみち「あやしき女」は怪しいのです。いえ、一番怪しいのは「余」です。
余が想像の糸をここまでたぐって来た時、室内の冷気が一度に背の毛穴から身の内に吹き込むような感じがして覚えずぞっとした。そう思って見ると何だか壁が湿っぽい。指先で撫でて見るとぬらりと露にすべる。指先を見ると真赤だ。壁の隅からぽたりぽたりと露の珠が垂れる。床の上を見るとその滴したたりの痕が鮮やかな紅の紋を不規則に連つらねる。十六世紀の血がにじみ出したと思う。壁の奥の方から唸り声さえ聞える。唸り声がだんだんと近くなるとそれが夜を洩るる凄い歌と変化する。ここは地面の下に通ずる穴倉でその内には人が二人いる。鬼の国から吹き上げる風が石の壁の破れ目を通って小ささやかなカンテラを煽るからたださえ暗い室の天井も四隅も煤色いろの油煙で渦巻いて動いているように見える。幽かに聞えた歌の音は窖中にいる一人の声に相違ない。歌の主は腕を高くまくって、大きな斧を轆轤の砥石にかけて一生懸命に磨いでいる。その傍には一挺の斧が抛げ出してあるが、風の具合でその白い刃はがぴかりぴかりと光る事がある。他の一人は腕組をしたまま立って砥の転るのを見ている。髯の中から顔が出ていてその半面をカンテラが照らす。照らされた部分が泥だらけの人参のような色に見える。「こう毎日のように舟から送って来ては、首斬り役も繁昌だのう」と髯がいう。「そうさ、斧を磨ぐだけでも骨が折れるわ」と歌の主が答える。これは背の低い眼の凹んだ煤色の男である。「昨日は美しいのをやったなあ」と髯が惜しそうにいう。「いや顔は美しいが頸の骨は馬鹿に堅い女だった。御蔭でこの通り刃が一分ばかりかけた」とやけに轆轤を転ばす、シュシュシュと鳴る間から火花がピチピチと出る。磨ぎ手は声を張り揚げて歌い出す。
切れぬはずだよ女の頸は恋の恨みで刃が折れる。(夏目漱石『倫敦塔』)
ここにあるのは「余」の幻覚と幻聴と妄想でしょう。何しろ十六世紀のことですから、到底現実ではありません。そう思ってみると、の一言で、意識は想像・幻想の世界に完全に入り込みます。この想像・幻想が一旦途切れたところにまた、「あやしき女」が現れるのです。これは二十世紀のことなので、現実のような感じがしてしまうわけです。現実の世界に「あやしき女」が現れたように錯覚してしまうのです。
ふと気がついて見ると傍に先刻鴉に麺麭をやりたいと云った男の子が立っている。例の怪しい女ももとのごとくついている。男の子が壁を見て「あそこに犬がかいてある」と驚いたように云う。女は例のごとく過去の権化と云うべきほどの屹っとした口調で「犬ではありません。左りが熊、右が獅子でこれはダッドレー家の紋章です」と答える。実のところ余も犬か豚だと思っていたのであるから、今この女の説明を聞いてますます不思議な女だと思う。そう云えば今ダッドレーと云ったときその言葉の内に何となく力が籠って、あたかも己れの家名でも名乗ったごとくに感ぜらるる。余は息を凝して両人を注視する。女はなお説明をつづける。「この紋章を刻んだ人はジョン・ダッドレーです」あたかもジョンは自分の兄弟のごとき語調である。「ジョンには四人の兄弟があって、その兄弟が、熊と獅子の周囲に刻みつけられてある草花でちゃんと分ります」見るとなるほど四通りの花だか葉だかが油絵の枠のように熊と獅子を取り巻いて彫ってある。「ここにあるのは Acorns でこれは Ambrose の事です。こちらにあるのが Rose で Robert を代表するのです。下の方に忍冬が描かいてありましょう。忍冬は Honeysuckle だから Henry に当るのです。左りの上に塊っているのが Geranium でこれは G……」と云ったぎり黙っている。見ると珊瑚のような唇が電気でも懸けたかと思われるまでにぶるぶると顫えている。蝮が鼠に向ったときの舌の先のごとくだ。しばらくすると女はこの紋章の下に書きつけてある題辞を朗らかに誦した。
Yow that the beasts do wel behold and se,
May deme with ease wherefore here made they be
Withe borders wherein ……………………………………
4 brothers' names who list to serche the grovnd.
(夏目漱石『倫敦塔』)
なるほど不思議な女です。しかしこの話も宿の主人には全く不思議でない話にされてしまいます。
余はまた主人に壁の題辞の事を話すと、主人は無造作に「ええあの落書きですか、つまらない事をしたもんで、せっかく奇麗な所を台なしにしてしまいましたねえ、なに罪人の落書だなんて当てになったもんじゃありません、贋もだいぶありまさあね」と澄したものである。余は最後に美しい婦人に逢った事とその婦人が我々の知らない事やとうてい読めない字句をすらすら読んだ事などを不思議そうに話し出すと、主人は大に軽蔑した口調で「そりゃ当り前でさあ、皆んなあすこへ行く時にゃ案内記を読んで出掛けるんでさあ、そのくらいの事を知ってたって何も驚くにゃあたらないでしょう、何すこぶる別嬪だって?――倫敦にゃだいぶ別嬪がいますよ、少し気をつけないと険呑ですぜ」ととんだ所へ火の手が揚がる。これで余の空想の後半がまた打ち壊わされた。主人は二十世紀の倫敦人である。(夏目漱石『倫敦塔』)
ここですね。不思議だね、変だね、という話にしません。そんなことは何の不思議もないのだよと理屈を言います。一応は理屈ですが、案内記を読んで出掛けたとして、「見ると珊瑚のような唇が電気でも懸けたかと思われるまでにぶるぶると顫えている。蝮が鼠に向ったときの舌の先のごとくだ」という女の様子はまさに今、題辞をその眼で見ているかのようではないでしょうか。ジョン・ダッドレーは大逆罪の罪で倫敦塔で処刑されました。「あやしき女」はあたかもジョン・ダッドレーの縁故者のようです。しかし十六世紀の血を生々しく我が手に見たのは「余」なのです。案内記は持たず一枚の地図だけを頼りに倫敦塔を訪ねた「余」はどういうわけか十六世紀の首斬り役の姿を見て、声を聞くわけですよね。これはどうも真面ではありません。本当に真面ではない人の特徴は明らかに真面ではないのに、自分ではそのことを一切気にしないのです。「余」も「あやしき女」のふるまいを不思議がりますが、自分の手が血で赤く染まったことを不思議がりもせず、また宿の主人にも話さないのです。
このやり口で、何が何だか分からなくなります。つまり漱石先生は完全にいっちゃっているようでありながら、三層の仮構を組み立て、その中で冷静に登場人物を動かしている訳です。一層目は宿の主人のレベル、二層目は怪しき女のレベル、三層目は十六世紀の首切り役のレベル。「余」は直接十六世紀の首切り役の会話を聞き、怪しき女の不思議なふるまいに戸惑い、宿の主人の話で現実に引き戻されます。しかし宿の主人の現実は、今にも底が抜けそうなあやふやな現実です。こうなると、読んでいる私は、四層目の確かな現実が欲しくなります。『夢十夜』は三層目の仮構です。『永日小品』は一層目の仮構です。これらが組み合わされると、こんなにも話が分からなくなるのかと感心するのが『倫敦塔』という小説です。
この小説には作者による解題ととれる説明書きも加えられています。
この篇は事実らしく書き流してあるが、実のところ過半想像的の文字であるから、見る人はその心で読まれん事を希望する、塔の歴史に関して時々戯曲的に面白そうな事柄を撰んで綴り込んで見たが、甘く行かんので所々不自然の痕迹が見えるのはやむをえない。そのうちエリザベス(エドワード四世の妃)が幽閉中の二王子に逢いに来る場と、二王子を殺した刺客の述懐の場は沙翁の歴史劇リチャード三世のうちにもある。沙翁はクラレンス公爵の塔中で殺さるる場を写すには正筆を用い、王子を絞殺する模様をあらわすには仄筆を使って、刺客の語を藉り裏面からその様子を描出している。かつてこの劇を読んだとき、そこを大おおいに面白く感じた事があるから、今その趣向をそのまま用いて見た。しかし対話の内容周囲の光景等は無論余の空想から捏出したもので沙翁とは何らの関係もない。それから断頭吏の歌をうたって斧を磨ぐところについて一言しておくが、この趣向は全くエーンズウォースの「倫敦塔」と云う小説から来たもので、余はこれに対して些少の創意をも要求する権利はない。エーンズウォースには斧の刃のこぼれたのをソルスベリ伯爵夫人を斬る時の出来事のように叙してある。余がこの書を読んだとき断頭場に用うる斧の刃のこぼれたのを首斬り役が磨いでいる景色などはわずかに一二頁に足らぬところではあるが非常に面白いと感じた。のみならず磨ぎながら乱暴な歌を平気でうたっていると云う事が、同じく十五六分の所作ではあるが、全篇を活動せしむるに足るほどの戯曲的出来事だと深く興味を覚えたので、今その趣向そのままを蹈襲したのである。但し歌の意味も文句も、二吏の対話も、暗窖の光景もいっさい趣向以外の事は余の空想から成ったものである。ついでだからエーンズウォースが獄門役に歌わせた歌を紹介して置く。(夏目漱石『倫敦塔』)
普通解題を読めば「ああ、そういうことか」と納得するものですが、この漱石の説明を読むと、なるほどと思いつつ、だからといってこうなる? とむしろ疑問が増えていくような気がします。「見る間に三万坪に余る過去の一大磁石は現世に浮游するこの小鉄屑を吸収しおわった」ってどんな映像になりますかね?
久しぶりに青天を見て、やれ嬉しやと思うまもなく、目がくらんで物の色さえ定かには眸中に写らぬ先に、白き斧の刃はがひらりと三尺の空を切る。流れる血は生きているうちからすでに冷めたかったであろう。烏が一疋下りている。翼をすくめて黒い嘴をとがらせて人を見る。百年碧血の恨みが凝って化鳥の姿となって長くこの不吉な地を守るような心地がする。(夏目漱石『倫敦塔』)
この場面、件の鴉の数のくだりの前に据えられています。「流れる血は生きているうちからすでに冷めたかったであろう」とは、断首の恐怖のために血も凍えていただろうと読むことはできます。その程度の抽象性に戸惑っている訳ではないのです。しかしそれなら「目がくらんで物の色さえ定かには眸中に写らぬ先に」ではなかろうと思うわけです。では、何故「流れる血は生きているうちからすでに冷めたかったであろう」?
それに「百年碧血の恨みが凝って化鳥の姿となって長くこの不吉な地を守るような心地がする」ってどんな心地ですかね?
解ります?
あまりにも解らないので、今回は何かずばっという答えのない、疑問だけの話に留めます。続きは、いずれ。
The axe was sharp, and heavy as lead,
As it touched the neck, off went the head!
Whir―whir―whir―whir!
Queen Anne laid her white throat upon the block,
Quietly waiting the fatal shock;
The axe it severed it right in twain,
And so quick―so true―that she felt no pain.
Whir―whir―whir―whir!
Salisbury's countess, she would not die
As a proud dame should―decorously.
Lifting my axe, I split her skull,
And the edge since then has been notched and dull.
Whir―whir―whir―whir!
Queen Catherine Howard gave me a fee, ―
A chain of gold―to die easily:
And her costly present she did not rue,
For I touched her head, and away it flew!
Whir―whir―whir―whir!
斧は鋭く、鉛のように重かった。
首に当たると、首が取れた!
ワーワー ワーワー ワーワー!
アン女王はその白い喉をブロックの上に置いた。
致命的な衝撃を静かに待った
斧はそれを真っ二つに切り裂いた。
彼女は痛みを感じなかった
ワーワー、ワーワー、ワーワー!
ソールズベリーの伯爵夫人は 死なないだろう
誇り高き貴婦人の尊厳ある死だ
私は斧を振り上げ 彼女の頭蓋骨を割った
それ以来、刃は刻まれ、鈍くなった。
ワーワー ワーワー ワーワー!
キャサリン・ハワード女王は私に報酬を与えた
金の鎖だ簡単に死ねると
その高価な贈り物を、彼女は後悔しなかった。
彼女の頭に触れたら、飛んでいってしまったからだ
ウィーウィーウィーウィーウィーウィー!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
