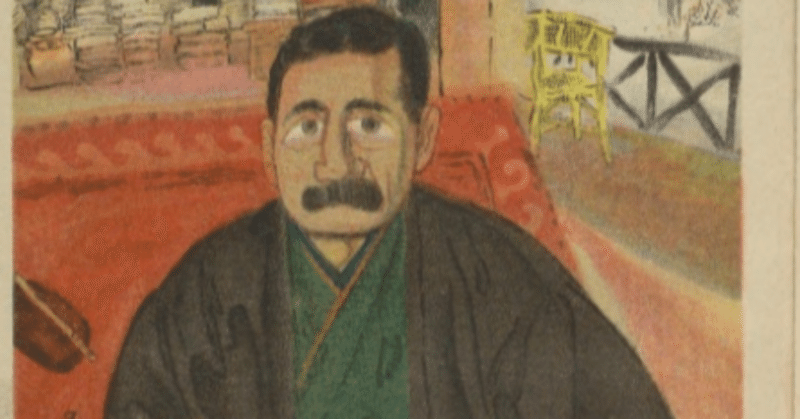
石原千秋の『三四郎』に関する読みの水準について② 大変立派だ
『三四郎』の「終わり」に当たる第十三章が三四郎視点から全知視点に変換されるのは、おそらく帰省中に三四郎に読者には言えない秘密が出来たからだろう。それは、お光との祝言でなければ、婚約だろうか。三四郎の死角で美禰󠄀子が生き、読者の死角でおそらく御光が生きたのだ。それが、『三四郎』の終わりの意味である。
例えば夏目漱石の『こころ』の主人公「私」の母が「お光」であることを思ってみると、『野分』において「生徒を煽動して白井道也を追い出した教師」が描かれることによって『坊っちゃん』の山嵐が実は生徒を煽動していたのではないかという疑問がわいてくるのと同じような意味で、『それから』において平岡の勤めていた銀行で帳簿に穴をあけた「関」が、『こころ』においては「私」の妹の婿として現れることで遺産相続ではもめそうな予感がするし、また『明暗』においては清子を巡って関とはひと悶着ありそうな気がしなくもないものである。
ここで石原が指摘するような「読者には言えない秘密」「読者の死角」というものは物語の構造上確かに設けられていると言って良いように思える。
無論「それは、お光との祝言でなければ、婚約だろうか。」という疑問文で書かれた指摘はやや行き過ぎている感はあるものの、羽織まで贈られていることは確かなので、里に帰れば間を詰められる程度のことはあったと考えてしかるべきところではあろう。
すると広田さんが、
「君はどうです」と聞いた。
「私は……」
「まだ早いですね。今から細君を持っちゃたいへんだ」
「国の者は勧めますが」
「国のだれが」
「母です」
「おっかさんのいうとおり持つ気になりますか」
「なかなかなりません」
ただ祝言や婚約があったとすれば、持ち帰ったものが暗さだけであることがやや物足りない。大学一年で婚約というのもいささか焦りすぎにも思える。
「佐々木に買ってもらうつもりだそうだ」と広田先生が言った。
「ぼくより」と言いかけて、見ると、三四郎はむずかしい顔をして腰掛けにもたれている。与次郎は黙ってしまった。
ここでの三四郎の態度は、まだ美禰󠄀子に未練があるというよりはまさに失恋直後のような落ち込みようだ。
要するに、国から母を呼び寄せて、美しい細君を迎えて、そうして身を学問にゆだねるにこしたことはない。
しかし「お光さん」の上位変換モジュールである「名古屋の女」のさらに上位変換モジュールを逃して、国に引き戻されることは、このふりに対して落ちになっているので、けして悪いバランスではない。
ここは「祝言や婚約」はともかく、読者の死角において三四郎をさらにげんなりさせるような、実家でのお光さんの圧力まではあったと考えてよいだろう。「迷羊、迷羊」が示す通り、三四郎はまだ迷える位置にいて引き返せるのではないかと私は考える。
しかしこの考えも石原千秋の指摘があって考えたことなので、読者の死角を指摘した石原千秋は大変立派だと賞賛すべきであろう。
[余談]
それにしても三四郎のよし子に対する何とも言えない思慕のようなものはどう整理されるべきなのであろううか。『三四郎』の謎はまだまだ解けない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

