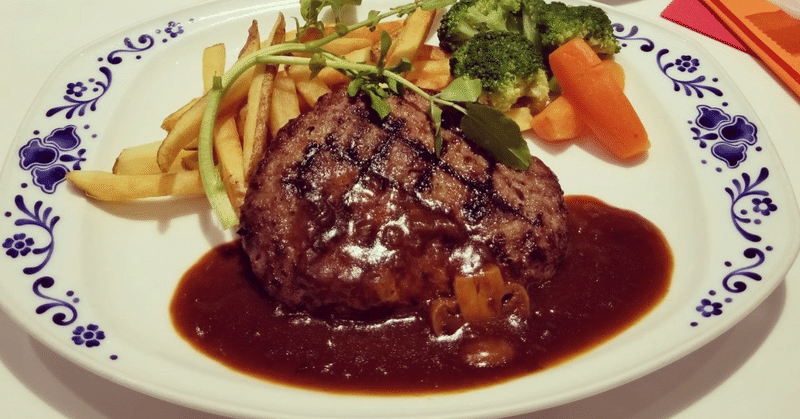
『彼岸過迄』を読む 4346 田川敬太郎は童貞なのか?
田口の門前には車が二台待っていた。玄関にも靴と下駄が一足ずつあった。彼はこの間と違って日本間の方へ案内された。そこは十畳ほどの広い座敷で、長い床に大きな懸物が二幅掛かっていた。湯呑のような深い茶碗に、書生が番茶を一杯汲くんで出した。桐を刳った手焙りも同じ書生の手で運ばれた。柔かい座蒲団も同じ男が勧めてくれただけで、女はいっさい出て来なかった。敬太郎は広い室の真中に畏まって、主人の足音の近づくのを窮屈に待った。ところがその主人は用談が果てないと見えて、いつまで待ってもなかなか現われなかった。敬太郎はやむを得ず茶色になった古そうな懸物の価額を想像したり、手焙の縁を撫で廻したり、あるいは袴の膝へきちりと両手を乗せて一人改たまって見たりした。すべて自分の周囲まわりがあまり綺麗いに調っているだけに、居心地が新らし過ぎて彼は容易に落ちつけなかったのである。しまいに違棚の上にある画帖らしい物を取りおろしてみようかと思ったが、その立派な表紙が、これは装飾だから手を触れちゃいけないと断るように光るので、彼はついに手を出しかねた。(夏目漱石『彼岸過迄』)
田川敬太郎は童貞なのだろうか。三四郎はどうも童貞のように思える。『坊っちゃん』の「おれ」もまだ女を知らなさそうだ。と、突然こんなことを言い出すのは、
この『彼岸過迄』という小説がモラトリアム小説であると同時に、田川敬太郎を中心に見た時には若者の生きづらさを描いた青春小説にも思えるからだ。そしてさらに須永市蔵の偏屈な千代子への思いを確かめると、これが童貞小説にも見えて來るから困ったものだ。
童貞小説とはなかなか厄介なもので、庄司薫の『赤頭巾ちゃん気をつけて』では主人公の薫君が、白衣の下は裸の美人の女医に「好きです」と告白したり、『白鳥の歌なんか聞こえない』ではおさなじみの一条由美ちゃんに抱きつきながらジーンズの中に射精してしまったりもする。総じて若い男というものは始終そっちのことで頭がいっぱいで、巧く心のバランスが取れていないものなのだ。だから童貞小説ではリアルになれば成る程、ところどころでアンバランスな精神の動きが現れる。
この記事で書いた赤ん坊連れの女に対する田川敬太郎の「おかしな」感覚も、これを童貞小説と見ることで少しは得心できる。また、
この記事に書いた須永市蔵の嫉妬のあまり重い文鎮を相手の脳天の骨の底まで打ち込むような感情の激しさも少しは理解できるような気がする。私もまだ小学校七年生で童貞なので、童貞の頭の可笑しいところがよく分かるのだ。兎に角理屈ではなくアンバランスなものがある。
たとえばこの「女はいっさい出て来なかった」という表現の内にも、田川敬太郎の童貞性といったものが現れているかもしれない。「いっさい」とはなんだ。無駄に残念がってはいまいか。職業の斡旋依頼と引き換えに頼まれた用事の報告に他人の家に上がって、「女はいっさい出て来なかった」とはどんな感覚かと言えば、新入社員が入社当日集団で健康診断に連れていかれる時に引率の総務課の女子社員の胸を見てしまうとか、看護師さんの「ちくっとしますよ」に惚れるとか、そんな感覚だろうか。
田口要作が接遇を男に任せたのは、「千代子を出せない」という事情からだろうが、そんな事情を知る筈もない田川敬太郎の「女はいっさい出て来なかった」はやはりおかしい。
ただ本当に田川敬太郎は童貞なのだろうか。
敬太郎が須永から「君もこの頃はだいぶ落ちついて来たようだ」と評されても、彼は「少し真面目になったかね」とおとなしく受けるし、彼が須永に「君はますます偏窟に傾くじゃないか」と調戯からかっても、須永は「どうも自分ながら厭になる事がある」と快よく己の弱点を承認するだけであった。(夏目漱石『彼岸過迄』)
このような会話の裏にあるもの。そして、昨日書いた記事の、
二日酔いとだけ書かれて、飲酒の場面が書かれないという漱石の記述法などから考えて、
「何です今頃楊枝なぞを銜え込んで、冗談じゃない。そう云やあ昨夕あなたの部屋に電気が点いていないようでしたね」と云った。
「電気は宵の口から煌々と点いていたさ。僕はあなたと違って品行方正だから、夜遊びなんか滅多にした事はありませんよ」
「全くだ。あなたは堅いからね。羨ましいくらい堅いんだから」
敬太郎は少し羞痒ったいような気がした。(夏目漱石『彼岸過迄』)
これは冗談は冗談だとして、その裏返しもあるからこそ「敬太郎は少し羞痒ったいような気がした」のではなかろうか。つまり田川敬太郎もYOASOBIくらいは経験があるのではないかと、今日の時点では考えている。昨日はまだ考えていなかった。漱石もいちいち言わないまでも「女は妊娠ばかりしていて困る」というくらいしていたわけで、健康な成人男子が何もなくて落ち着いていたらそれは病気だ。いや病気の正岡子規だって、女も男も知っていた。漱石の断片にも「肛門 プレートニツクラツブの条と連結す」というものがある。
彼は須永のように地面家作の所有主でない代りに、国に少し田地を有っていた。固より大した穀高になるというほどのものでもないが、俵がいくらというきまった金に毎年替えられるので、二十や三十の下宿代に窮する身分ではなかった。その上女親の甘いのにつけ込んで、自分で自分の身を喰うような臨時費を請求した事も今までに一度や二度ではなかった。(夏目漱石『彼岸過迄』)
この「自分で自分の身を喰うような臨時費」とは何かと考えてみるとどうも怪しい。単なる飲み食いの金ではなさそうだ。「自分で自分の身を喰う」が抽象的すぎる。いや具体的使用されるケースとしては「蛸配」のことで蛸が自分で自分の足を食べることから、企業等が利益が出ていないのに配当することを言う。株の世界では。では他にどんな意味があるかと言えばこれが解らない。ただ抽象的であるということは、具体的には書けないことなのではなかろうか。
出すのか出るのか出さされるのかわからないが、それでも金をとられることを「自分で自分の身を喰う」と表現したのではなかろうか。こっちばかり活動してお腹が空いて寿司を食いたくなるのに金迄とられるから「自分で自分の身を喰う」と表現したのではなかろうか。
それで約一時間ほど須永と話す間にも、敬太郎は位地とか衣食とかいう苦しい問題を自分と進んで持ち出しておきながら、やっぱり先刻見た後姿の女の事が気に掛って、肝心の世渡りの方には口先ほど真面目になれなかった。一度下座敷で若々しい女の笑い声が聞えた時などは、誰か御客が来ているようだねと尋ねて見ようかしらんと考えたくらいである。ところがその考えている時間が、すでに自然をぶち壊す道具になって、せっかくの問が間外れになろうとしたので、とうとう口へ出さずにやめてしまった。(夏目漱石『彼岸過迄』)
漱石はこのように助平心を強調しつつ、やはり三四郎よりは不純な性格を田川敬太郎に与えているように見える。いつどこで誰ととは書かれないにしても、田川敬太郎には三四郎よりは少しは経験があるようだ。それは「自分で自分の身を喰うような臨時費」のお蔭で得たものであり、その結果として「君もこの頃はだいぶ落ちついて来たようだ」と評されるようになったのではないか。
これは絶対そうだという話ではないし「自分で自分の身を喰うような臨時費」の意味はさっぱり分からないという話でも無い。これを辛抱強く続けて行かなくては『彼岸過迄』を読んだとは永遠に云えないよ、という話である。
[余談]
「なぜそんな所に黒子なんぞができたんでしょう」
「何も近頃になって急にできやしまいし、生れた時からあるんだ」
「だけどさ。見っともなかなくって、そんな所とこにあって」
「いくら見っともなくっても仕方がないよ。生れつきだから」
「早く大学へ行って取って貰うといいわ」(夏目漱石『彼岸過迄』)


このイケメンは昭和天皇である。上の写真では右眉の上に大きな黒子のようなものが見える。下の写真にはない。というより、黒子のある写真は見たことがない。ということは、昔から黒子は手術で取るべきものだったのだろうか。
この辺りの感覚も時代によって異なるのかもしれない。
黒子があっても十分イケメンなのに。
(その夢世界では)覚醒時の自分と全く違う人になっている夢を見たのにそれでも覚めてから(自分が見た夢として)思い出せるとすれば、それは独在性の矛が貫いたことになるのでは?という話をしました。しかしそういう場合には、たとえ実際に見ても(超越論的な盾に遮られて)思い出せないのでは?と。 https://t.co/yeAVxZBzoF
— 永井均『独在性の矛は超越論的構成の盾を貫きうるか』発売中 (@hitoshinagai1) October 21, 2022
「差別は自己価値の底上げを本質としています。自分の価値に自信がない人間が、他人の価値を引きずりおろし、価値のない人間として見下すことで、自分のほうが上だ、自分のほうが価値がある、と思いたがっているのです。」(山竹伸二『ひとはなぜ「認められたい」のか』ちくま新書、P234) pic.twitter.com/Cvvc7y1u3J
— 本ノ猪 (@honnoinosisi555) October 20, 2022
これでええんか?
— 和丸号 (大塚和之) (@kazumarugou) October 20, 2022
女子4×400mリレー決勝
優勝した中国湖南省チーム pic.twitter.com/XjueyTfDba
東京駅の京葉線ホームが遠い!
— 一目置かれる雑学 (@trivia_hour) October 21, 2022
っていう人は、有楽町駅で降りて、
一度改札出てから
京葉線ホームに向かうと近いですよ。
なんとこれはJR公認で、有楽町駅で
「京葉線に乗るから一度出してくれ」
と頼むと、小さな券を貰えます。
それを京葉線ホーム近くの改札で
出せば入れるという裏ワザ!
ちなみに東京駅に残されてる原敬・浜口雄幸両首相の暗殺現場がこれ。 pic.twitter.com/evgPnkUXh5
— コロ介(転生したらからくりロボットだった件) (@korosukebenary) October 18, 2022
Amazonで使い捨て用のイヤホンを1000円で買ったらこんな紙入ってた....
— ざわ (@kobepackopener) October 21, 2022
レビューが高いのにはこんなからくりあったのか!!! pic.twitter.com/gMBt0O82pu
30歳以上の引きこもりの
— からくり堂 (@kallakuli) October 19, 2022
半数以上が30歳以上 pic.twitter.com/Kd32ghcopv
コレに尽きます! pic.twitter.com/UVY0L8gkbU
— からくり堂 (@kallakuli) October 20, 2022
え、まさか『メリロート事件』をご存知ないんですか?メリロートを摂取した女性が肝障害で次々に入院し、厚生労働省が警告してますよ。メリロートサプリ中の有効成分『クマリン』の使用は米国では禁止済。日本のリンパ浮腫診療ガイドラインも「使わないように推奨」。サプリで浮腫改善とはいきません。 https://t.co/Mag0i2dyKT pic.twitter.com/6AQyel2Nnu
— やさひふ|皮膚科専門医|医学博士|Lumedia編集長 (@S96405539) October 19, 2022
ANA の飛行機予約サイト、アプリから日本語で購入するより、ブラウザで英語で購入する時の方が 25% も安いのはなんでなんだぜ… 1ドル150円でも7000円以上安い。 pic.twitter.com/EmMqlR5pGn
— 西嶋 悠貴 (@yuki24ja) October 18, 2022
600人超えちゃいましたね
— 秋篠宮悠仁 (@ishiguro1496sai) October 21, 2022
さすがは僕です☺️
みなさん本当にありがとうございます
ふへへへへ
ふほほほほ
ぐひひひひ
あはっあはっあはっ
ふへっ
ふひひっ
ふへへへー pic.twitter.com/SIjfkDKADD
なんか勉強になるわ。キノコでも、干ししいたけやドライポルチーニは、グアニル酸、生マッシュルームはグルタミン酸。
— Donald Chu Chu (@donaldchuchu) October 17, 2022
生ハムは肉でもグルタミン酸で、イノシン酸じゃない。 pic.twitter.com/OSIQ2OuvOz
撮りためたマツコの知らない世界見てる
— 月(つき)@10/10パノラマ (@tsuki_sushisuki) October 20, 2022
ほんと勉強になるわ pic.twitter.com/jRgq0pQRgs
勉強になるわね pic.twitter.com/yp693hfLPB
— むかぴ@舞鶴 (@mukapiii_AZLN) October 21, 2022
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
