
染くさい芭蕉破れて蘭の香や 夏目漱石の俳句をどう読むか23
蘭の香や門を出づれば日の御旗
解説にこの句を子規に送った九月二十三日は秋季皇霊祭とある。この句は三十二句まとめて送った中の最初の句なので、これもおそらく実景ではない。芥川の元日の句のようにあらかじめ詠まれたものであろう。




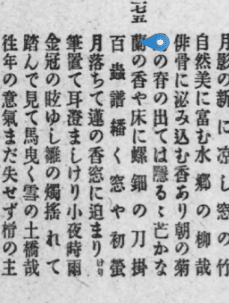

蘭の香や蝶の翅にたきものす 芭蕉






どうも気のせいか「蘭の香や」の句には開いた取り合わせが目立つような気がする。それは勿論「蘭の香や」とまで詠んで「いい香りだった」と読むわけにはいかないことは解る。
しかし、
蘭の香や落胤の君詩に敏し
って何?
蘭の香や温故知新の机
って何?
そもそも「蘭」とは何なのか。「春蘭秋菊 倶に廃す可からず」ということわざがある。ここは菊の香ではいけないのか。
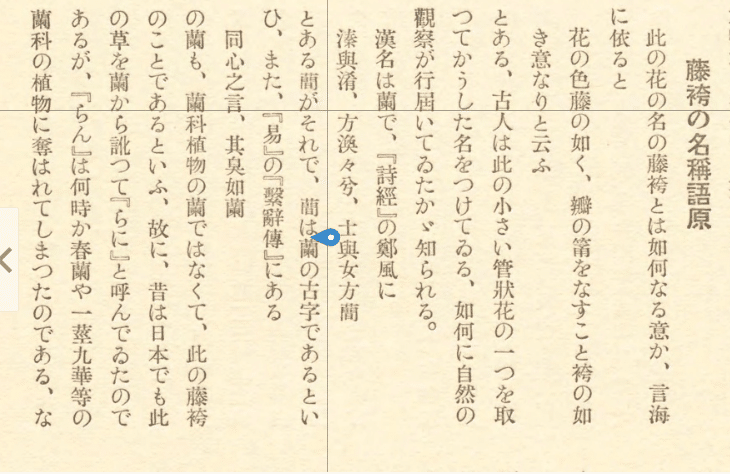

蘭の香にはなひ待らん星の妻 其風
何か皇室と蘭の間に因縁はないものかと小一時間調べたが何も見つからなかった。この句は解釈を保留とする。全く何もないのにこんなことになるのかなと思う。思うが何も出てこない。
さらにこの蘭は藤袴ではないかという疑問は消えない。この疑問はいつか答えが出るものであろうか。
芭蕉破れて塀破れて旗翩々たり
この句は、
蘭の香や門を出づれば日の御旗
この句との対比において、何か「庶民の暮らしは貧しいのに日の御旗は呑気に翻っているよ」という、典型的な貧乏人のポストのようなものに見えなくもない。


芭蕉破れて塀破れて旗翩々たり
芭蕉破れてからの塀破れては、例によって無関係。たまたまながら、
時雨けり走入りけり晴れにけり
という惟然の句の形式に三分の二までは当てはまる。それでいて芭蕉破れてからの塀破れてが無関係なので既に滑稽なところに、旗翩々たりと床屋の政治談議みたいな批判性が付いて来る。これはまあ好みの問題ではあるが、言ってやった感が鼻についてどうかと思わせる句だ。
朝寒に樒売り来る男かな
解説に樒は枝を仏前に備えるものとある。それにしても朝寒は晩秋の季語なので九月二十三日に送った句としてはかなり早い。
朝貌や垣根に捨てし黍のから
解説は去来の「明月や椽取りまはす黍の虚」という句を紹介している。この句にちなんだと言いたげだ。しかし高桑闌更の、
朝露や垣根に捨てし薬殻 闌更

こちらの方が類似していないだろうか。この闌更の句は有名でこそないが、例によって子規がきちんと書き写して整理しているので、子規経由で漱石にもこの句が伝わっていた可能性が高い。去来の句も当然意識してはいただろうが、闌更の句も無関係とは思えない。
そしていずれの句も意味不明である。
朝貌や垣根に捨てし黍のから
朝貌や、はまずいいとして、垣根に捨てし黍のからが解らない。垣根に朝顔がつるを伸ばしているので、その栄養になればということで黍のからを撒いたのか。それにしては「捨てし」の投げやりな感じが引っかかる。
あえて言えば、
朝露や垣根に捨てし薬殻
この句に意味は考えずにただ音だけ似せたのかと思える所。いわゆる地口の作法で詠んだ句とも思えなくもないところ。この句も解釈は保留とする。
柳ちる紺屋の門の小川かな
この句は、
柳散り棄屑流るる小川かな 子規
と関係があるのだろうか。
根岸と日暮里との頃を流れてをる小川を音無川といつてをつた。秋から冬になるとそこで百姓が大根や葱)洗つてをるのをよく見掛けたことがある。
子規句解
高浜虚子 著創元社 1946年
麥綠菜黃の中を流るゝ小川かな

そしてこの句とは関係があるのかないのか。
山燒の火屑流るゝ小川かな 紫萍
この句とは関係はなさそうだ。
野分して蛇の流るゝ小川かな 枯木
この句も関係なさそうだが、例の泥亀の句と趣が似ているな。
二三寸菖蒲芽を出す春の水
斯ういふやうな「紺屋の門」とか「菖蒲芽を出す」と云ふやうなところに目を着けて作つた方が間違ひがない、後に慣れて來ると廣いものが自然出來るやうになる。
俳句階梯
沼波瓊音 著東亜堂 1908年
とあるので単なる俳句のレッスンのようにもとれ、
此處は紺屋か紺屋の門か藍の臭する染めくさい
と言われるので、藍=愛の仄めかしのようにもとれ、なんとも解釈に迷う。今日は調子が悪い。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
