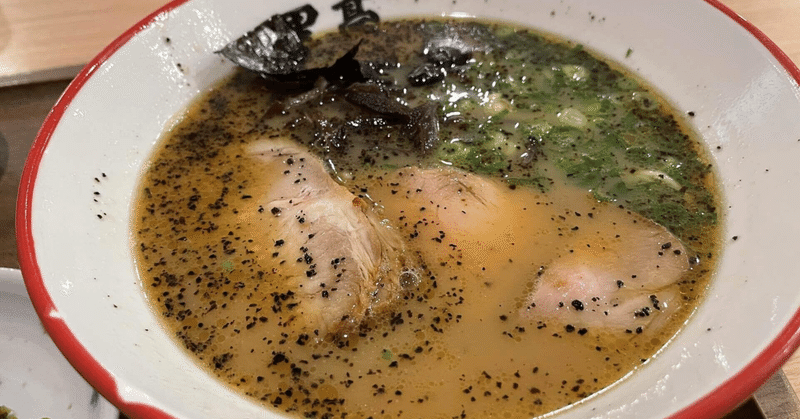
芥川龍之介の『開化の良人』をどう読むか① コキュ旦那と神風連
何故『南瓜』の題名は『開化の殺人』ではなく『南瓜』なのか。それは『南瓜』がおそらく維新以降の出来事、殺人事件を描いていながら、書かれていること、つまり殺人に至る経緯や殺し方そのものは旧弊なのか新時代なのか解らない話だからである。ハムレットと脇差の衝突が『南瓜』の魅力なのだろう。その緞帳芝居のような一幕劇は「開化もの」とは呼ばれることがなかった。
しかしおそらく「開化もの」のキーになるのは『南瓜』であり、『南瓜』を無視して語られた『開化の良人』論にはほぼ意味がない。「開化もの」と呼ばれている作品群の中でも「開化」の意味は明確に異なる。『南瓜』はその中心にあり、『開化の良人』において「開化」は旧弊の対義語として用いられており、現在に続く新時代の方向性を示しており、『開化の殺人』において「開化」は明治初期という狭い時代区分の意味しか持たない。
あの色の白い、細面の、長い髪をまん中から割った三浦は、こう云う月の出を眺めながら、急に長い息を吐くと、さびしい微笑を帯びた声で、『君は昔、神風連が命を賭として争ったのも子供の夢だとけなした事がある。じゃ君の眼から見れば、僕の結婚生活なども――』私『そうだ。やはり子供の夢だったかも知れない。が、今日我々の目標にしている開化も、百年の後になって見たら、やはり同じ子供の夢だろうじゃないか。……』」
1969年に書かれた三島由紀夫の『奔馬』を1927年に死んだ芥川龍之介は読んでいない。では三島由紀夫は芥川龍之介の『開化の良人』を読んだだろうかとふと考えてみる。いや、ふとではないな。『開化の良人』に「神風連」の文字を見れば、やはり誰しも三島由紀夫の『奔馬』を思い出さないわけにはいかないだろう。『奔馬』は、一言で言えば神風連が子供の夢であることを百も承知の上でテロリストになろうとする男の話、のようにも読めるからだ。主人公・飯沼勲を見守る弁護士の名は本多。『開化の良人』のお喋り野郎と同じ苗字である。そして『豊饒の海』全体の主脇役である。つまり三島由紀夫は『開化の良人』を読んでいないか、読み切れてはいなかったのだろう。そうでなければ本多を『豊饒の海』の軸に据えることは無かったはずだ。
「その証拠は彼が私と二人で、ある日どこかの芝居でやっている神風連の狂言を見に行った時の話です。たしか大野鉄平の自害の場の幕がしまった後だったと思いますが、彼は突然私の方をふり向くと、『君は彼等に同情が出来るか。』と、真面目な顔をして問いかけました。私は元よりの洋行帰りの一人として、すべて旧弊じみたものが大嫌いだった頃ですから、『いや一向同情は出来ない。廃刀令が出たからと云って、一揆を起すような連中は、自滅する方が当然だと思っている。』と、至極冷淡な返事をしますと、彼は不服そうに首を振って、『それは彼等の主張は間違っていたかもしれない。しかし彼等がその主張に殉じた態度は、同情以上に価すると思う。』と、云うのです。そこで私がもう一度、『じゃ君は彼等のように、明治の世の中を神代の昔に返そうと云う子供じみた夢のために、二つとない命を捨てても惜しくないと思うのか。』と、笑いながら反問しましたが、彼はやはり真面目な調子で、『たとい子供じみた夢にしても、信ずる所に殉ずるのだから、僕はそれで本望だ。』と、思い切ったように答えました。
この『たとい子供じみた夢にしても、信ずる所に殉ずるのだから、僕はそれで本望だ。』という三浦の言葉は、まるで三島由紀夫がそのまま引き取ったように思える。あるいは芥川は平岡公威がやがてそんなことを言い出す事を知っていたのではなかろうか。帰太虚、城山の西郷さん、増上慢の死に狂いと言って三島由紀夫は死に向かった。「信ずる所に殉ずる」としか言い訳の出来ない死を選んだ。一説には檄で拡声器を用いなかったのは電気を嫌う神風連を模したと言われる。
それにしても『南瓜』の奈良茂は何故脇差などを指していたのだろうか。あるいはこれは江戸時代かと読み直すと「新聞」や「ハムレット」が出て來る。吉原は新吉原だろう。やはりこれはどうも明治の話だ。
「見やあがれ。己だつて出たらめばかりは云やしねえ。」――南瓜はさう云つて、脇差を抛り出したさうだがね。返り血もかかつたんだらうが、チヨツキが緋天絨鴦なので、それがさほど目に立たない。人を殺したつて、殺さなくつたつて、見た所はやつぱりちんちくりんの、由兵衛奴にフロツクを着た、あの南瓜の市兵衛が、それでもそこにゐた連中にや、別人のやうに見えたんだらう。
三島事件の後、楯の会を玩具の兵隊と笑っていた右翼は「本物だったのか」と反省し、東大全共闘は「三島先生の死を悼む」と立て看板を出した。左翼は過激化し、警察力が強化された。「兎に角これで見ても、何でも冗談だと思ふのは危険だよ。笑つて云つたつて、云はなくつたつて、真面目な事はやつぱり真面目な事にちがひないからね」と『南瓜』に書いてあったのに、それを誰一人読んでいなかった証拠である。
それにしても芥川の悪いのは神風連が命を賭して争ったことと結婚生活、そして今日我々の目標にしている開化のいずれにも小さな矛盾が隠れていることを『奔馬』の五十年前に指摘してしまっていることだ。三島由紀夫は得意げに「神風連小史」のような記録は小さな矛盾が省かれてこそ成立するものだと語る。そんなことは当たり前だと『奔馬』の五十年前に芥川は書いているのだ。
神風連の乱に密告者がいたことはほぼ確かであろう。神風連の乱でさえ単なる純粋な若者たちの已むに已まれぬ已むに已まれぬ決起などではあり得ないのだ。

三島由紀夫は神風連の純粋を信じてはいない。しかしまさか神風連を浮気者の妻と重ねることは考えなかっただろう。この神風連を浮気者の妻と重ねるという途轍もないところが『開化の良人』の最大の魅力といってよいだろう。あるいは夫婦生活に殉じる話に旧弊な神風連を持ち出すところが芥川の魅力だ。
そして『開化の良人』の面白さを三島由紀夫の『奔馬』が増幅させていることも間違いなかろう。
飯沼勲は仲間から疑われることを恐れ、自棄ばちのようなテロ事件の末、さして意味の無い死を選ぶ。この『奔馬』を三島の死に重ねた中曽根康弘に三島由紀夫の小さな矛盾が見えていたのかどうか、私には解らない。
ただ私にわかるのは『開化の良人』が誰にも読まれていないということだけだ。『たとい子供じみた夢にしても、信ずる所に殉ずるのだから、僕はそれで本望だ。』と芥川が書いてから百四年経った。『開化の良人』はまだ珍しくもない。開化の威風はまだ続いていて、信ずる所に殉ずる者たちは開化の細君と暮らしている。そうでないものもいる。子供の夢は続いている。
百年の後から眺めれば、確かに「愛(アムウル)のある結婚」はむしろ旧弊だがそんなものもどこかにはあるのだろうと思う。ただ神風連はもういない。みんなスマホをいじっている。電気無しでは暮らせない。夏周の遺制あるなりと言える支那人がいなくなった。
日本より世界の方が変わった。
[余談]
三浦の妻は従弟を純粋に愛していた訳ではなかった。その事実は「思いもよらないほかの男から妻へ宛てた艶書」によって証拠立てられたものだ。冤罪の可能性がないではない。
芥川龍之介氏の『開化の良人』(中外)は描寫論上から見てちよつと面白い問題になる。と云ふのは、決して多元的にはなつてゐないけれども、一元的仲介者が少くとも一一つ重なつてゐる。
岩野の説明はこう続く。
・三浦夫人は三浦と本多子爵に見られている。
・三浦は本多子爵に見られている。
・本多子爵は「私」にだけ見られている。
岩野はこれを重貫的一元描写の一種と云いたいらしい。
うーん、そういうことではなくて。
明日ちゃんと説明する。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
