
いぜんと読んでね 芥川龍之介の『枯野抄』をどう読むか①
大正七年の作である。偽書『花屋日記』を粉本としていることから、既にいくつかの誤りも指摘されている。しかし見事な文章である。どんな文章?
元禄七年十月十二日の午後である。一しきり赤々と朝焼けた空は、又昨日のやうに時雨れるかと、大阪商人の寝起の眼を、遠い瓦屋根の向うに誘つたが、幸ひ葉をふるつた柳の梢を、煙らせる程の雨もなく、やがて曇りながらもうす明い、もの静な冬の昼になつた。立ちならんだ町家の間を、流れるともなく流れる川の水さへ、今日はぼんやりと光沢を消して、その水に浮く葱の屑も、気のせゐか青い色が冷たくない。まして岸を行く往来の人々は、丸頭巾をかぶつたのも、革足袋をはいたのも、皆凩の吹く世の中を忘れたやうに、うつそりとして歩いて行く。暖簾の色、車の行きかひ、人形芝居の遠い三味線の音――すべてがうす明い、もの静な冬の昼を、橋の擬宝珠に置く町の埃も、動かさない位、ひつそりと守つてゐる……
脳の血管に詰まったゴミのようなものが剥がれ落ちて流れていくような感じさえする。着飾った美文とは違う。言葉の連なりが心地よく揺らぐ。元禄七年という遠い昔を目の前に展開させて、グーグルストリートビューの人形をつまんで地面に落としたようにして一回転させてみる。無駄に視覚化することなく説明は説明で済ます。この塩梅が絶妙である。ぼんやり、うつそり、ひつそりとした光景にはカチコチの視覚化は合わない。何しろこれは遠い昔の画なのだ。
この時、御堂前南久太郎町、花屋仁左衛門の裏座敷では、当時俳諧の大宗匠と仰がれた芭蕉庵松尾桃青が、四方から集つて来た門下の人人に介抱されながら、五十一歳を一期として、「埋火のあたたまりの冷むるが如く、」静に息を引きとらうとしてゐた。時刻は凡そ、申の中刻にも近からうか。
このあたりの設定そのものは『花屋日記』から借りたままである。しかしどうにもこの作品には解らないところがある。そう長くはない作品なので、ざっと一読してから確認してもらいたい。
解らないというのは、ここだ。
その時羽根楊子の白い先を、将にその唇へ当てようとしてゐた惟然坊は、急に死別の悲しさとは縁のない、或る恐怖に襲はれ始めた。それは師匠の次に死ぬものは、この自分ではあるまいかと云ふ、殆ど無理由に近い恐怖である。が、無理由であればあるだけに、一度この恐怖に襲はれ出すと、我慢にも抵抗のしやうがない。元来彼は死と云ふと、病的に驚悸する種類の人間で、昔からよく自分の死ぬ事を考へると、風流の行脚をしてゐる時でも、総身に汗の流れるやうな不気味な恐しさを経験した。従つて又、自分以外の人間が、死んだと云ふ事を耳にすると、まあ自分が死ぬのではなくつてよかつたと、安心したやうな心もちになる。と同時に又、もし自分が死ぬのだつたらどうだらうと、反対の不安をも感じる事がある。これはやはり芭蕉の場合も例外には洩れないで、始めまだ彼の臨終がこれ程切迫してゐない中は、――障子に冬晴の日がさして、園女の贈つた水仙が、清らかな匂を流すやうになると、一同師匠の枕もとに集つて、病間を慰める句作などをした時分は、さう云ふ明暗二通りの心もちの間を、その時次第で徘徊してゐた。
書かれていることは解るが、何故惟然にこうした心境を与えたのかが判然としない。(※ちなみに「惟然」は「ゐねん」とルビがふられているも「ゐぜん」と読むのが正しいようである。)惟然は『花屋日記』においてさえ、そういうタイプの男ではないのだ。

前夜正秀と二人にて一つの蒲團をひつ張りて被りしに彼方へ引きこなたへ引きこなたへ引きて終夜寢入らさりければはてはしらじらと夜明けるにぞ其事を互ひに笑ひあひて
ひつ張りて蒲団に寒きわらひ哉 惟然
おもひよる夜伽もしたし冬籠 正秀
一坐是をきゝていづれもどつと笑ひければ師も笑ひたまへり
※「引張てふとんぞ寒き笑ひ声」とも伝わる。
これが十一日のこと。要するに正秀と一つの蒲団を引っ張り合いして寒かったよと、子供のようにじゃれてみんなを笑わせている。『花屋日記』においてはこの時点ではまだ芭蕉も笑えたという設定であり、どうにも惟然は賑やかしキャラである。また例の、「丈草出かされたり」のところの五句の吟詠は惟然が自ら買って出て行っている。何か飄然としたところが見えて、明るい。
その『花屋日記』の惟然のイメージと、芥川が『枯野抄』で惟然に与えた心境とがどうもそぐわないもののように思えるのだ。惟然の句は、全体としては軽く、どこかいい加減で、さすがは女房子供を捨てて出家した奴だという感じのするものが多い。
きりぎりすさあとらまへたはあとんた
のらくらとただのらくらとやれよ春
梅の花赤いは赤い赤いはの
長いぞや曾根の松風寒いぞや
凉まうか星崎とやらさてどこじや
水さつと鳥はふはふはふうはふは
しかも「無理由」で片づけられてはいるが、例えば芭蕉より四歳年下の惟然が今更死に対して「総身に汗の流れるやうな不気味な恐しさ」を感じるというのはなかなか特異な心境なのではなかろうか。
確認してみよう。
末期の水は其角から順に芭蕉の唇に刷毛で塗られた。
其角は死期の師匠の不気味な姿に嫌悪を覚えた。これくらいの逆張りは解らないでもない。芥川は其角の案外芭蕉に染まらないところを見ていたのであろう。芭蕉にはなやかなること其角に及ばず、と言わしめた其角は芭蕉の死後たちまち洒落風に転じた。
冬柳枯れて名ばかり残りけり 其角
芭蕉を悼む句としてはあまりにもクールなこの「名ばかり残りけり」という詠みようはまさに「死期の師匠の不気味な姿に嫌悪を覚えた」と解釈されてもおかしくはないものである。

次に末期の水を取らせるのは、芭蕉の最も恵實な信奉者であったと言われる去来である。
手伝いの周旋やら調度類の買入れやらの世話を一人で背負っていた去来は自分の満足と、その満足に対する自己批評とによる悔恨との不思議に錯雑した心もちを味はう。これは非常にリアルな解釈であろう。
親の介護は半年くらいでちょうどよかった、と話していたおばさんがいた。これ以上長いと続いたかどうかわからないし、半年でも介護したら親孝行したなと納得できるから悔いはないと。これは本当に正直な心の声だと納得できる。
しかしだからこそ単なる逆張りならば惟然に与えられた心境は去来に与えられた方が面白かったのではあるまいか。
たけの子や畠隣に悪太郎 去来

三番目は丈艸である。丈艸は突然笑い声のような慟哭を発した正秀の誇張あるいは「慟哭を抑制すべき意志力の欠乏に対して、多少不快を感じ」つつも自ら嗚咽してしまう。これも非常にリアル。
実は丈艸こそが死後も芭蕉に寄り添っていたのではないかとも思える節もあり、やはり単なる逆張りなら惟然に与えられた心境は丈艸が引き受けても良かったと言える。
うづくまる 薬缶の下のさむさ哉 丈艸
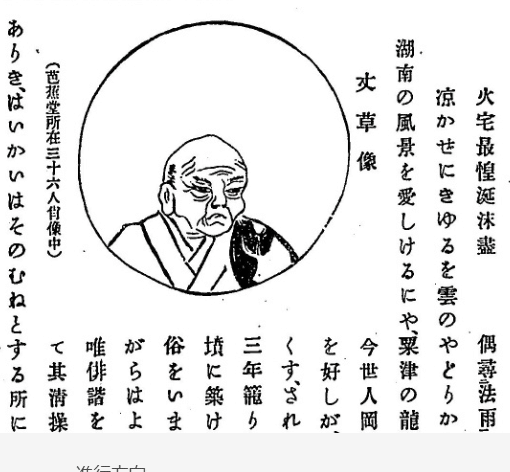
次の支考は「他門への名聞、門弟たちの利害、或は又自分一身の興味打算――皆直接垂死の師匠とは、関係のない事ばかり」考えて師匠の死を観察していた。三十一もの俳号を持ち、六十冊もの本の編者となる支考を芥川は皮肉屋と見ている。(支考を皮肉屋とする見立てはちらほらみられる。といいつつ俳句をやっていて皮肉屋でないものなどいるのかしら?)
この支考に対する書きようも解らないではない。ありきたりの悲しみなどないのだ。正秀の笑い声のような慟哭がいかに純粋なものであろうと、それは文学的には誇張なのだ。そんな朝鮮の葬式のようなものは嘘なのだ。そんなことを漱石の葬式の受付を手伝った芥川は言いたいのであろう。ちなみにこの支考について内田露庵は「蕉門に一個の怪物あり」と評しており、表現は異なるものの兎に角多才でかつ大胆というような評価が散見される。
叱られて次の間にたつ寒さかな 支考

そして惟然の番となる。弟子としてのありきたりでない師の死に対する心境が出尽くしたわけもなく、やはりこうして順に確認していくと惟然の処で急に解らなくなるのである。これが解るという人はやはり知ったかぶりなのではなかろうか。
私には解らない。
作品としては惟然の後は端折っているので、芥川が其角から支考までをふりとして、惟然のところで「解らなくさせている」という形式であることはまた確かなのだ。支考まではなんとなく解るでしょ、で、ほら、惟然の心境が解る? 解らないよね? という構成なのだということは解る。
ここをやはり漱石と芥川の関係に引き寄せて考えてしまおうという人があるかもしれないが、私にはさすがにそれは迂闊だと思える。もう一度惟然の句を眺めてもらいたい。惟然は芥川ではない。そして自らの死を意識するのに大正七年は早すぎる。
彼は芭蕉と旅行して、夜木枕が痛くて眠れなかつた。この時惟然は帶を解き之を枕に卷きつけて寢た。芭蕉は彼を見て『惟然は頭の奢りに家を失へりや』と笑つたさうである。この帶を解いて無造作に寢る彼の態度に面白い詩趣が漂つてゐる。そこが彼の本領だ。
『惟然坊はあだ口をのみ噺出して一生眞の俳諧といふもの一句もなし。蕉門の內に入つて世上の人を迷はす大賊なり。これは『俳諧問答』中の許六の言葉だ。然りこんな評言に惟然は風馬牛であらう。
蕉門俳人論
野口米次郎 著第一書房 1926年
性磊落飄逸にして、奇行甚だ多く傳つてゐる。
野田別天楼 開題||安井小洒 校蕉門珍書百種刊行会 1926年
惟然はその人物の飄逸なのと共に、句風の一種特異な事を以て知られて居る。
潁原退蔵 著大八洲出版 1946年
惟然はどうも風狂の人だ。「師匠の次に死ぬものは、事によると自分かも知れない」とは一番考えないタイプの人間だ。「そこを敢えてあべこべにしたんだよ」では説明にはならない。敢えてには意味がない。
と疑問だけおいて今日は終わろう。つづきはまた明日。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
