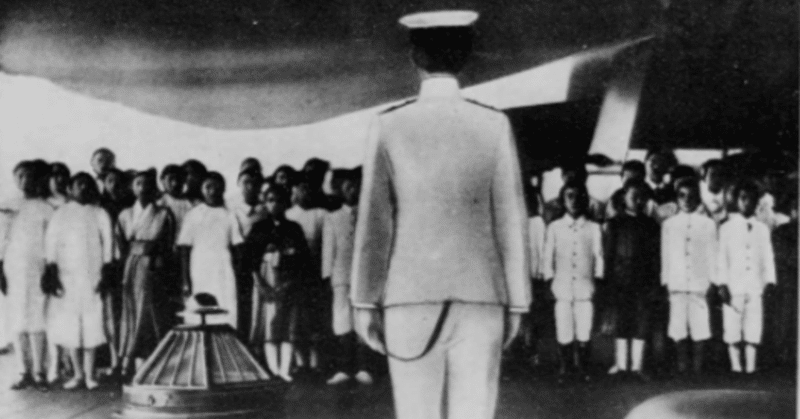
石原千秋の『こころ』の読みの水準について① そう単純な話ではない
原因はそこではない
『こころ』の「先生」は、血のつながった叔父に裏切られて人間不信となり、それで下宿先の「奥さん」や「お嬢さん」(後に妻となる静)をも信頼できなくなった。この道筋はよく理解できる。
厳密にいうと、これは誤りですね。
私と叔父の間に他たの親戚のものがはいりました。その親戚のものも私はまるで信用していませんでした。信用しないばかりでなく、むしろ敵視していました。私は叔父が私を欺いたと覚ると共に、他のものも必ず自分を欺くに違いないと思い詰めました。父があれだけ賞め抜いていた叔父ですらこうだから、他のものはというのが私の論理でした。
ここから「先生」は「血のつながった叔父に裏切られて人間不信となり」というロジックが生まれてきたものと思われますが、この後「先生」は旧友に土地の処分を依頼し、その代金を受け取っているのです。人間不信ではそういうことはできません。
「私の気分は国を立つ時すでに厭世的になっていました。他は頼りにならないものだという観念が、その時骨の中まで染み込んでしまったように思われたのです。私は私の敵視する叔父だの叔母だの、その他の親戚だのを、あたかも人類の代表者のごとく考え出しました。汽車へ乗ってさえ隣のものの様子を、それとなく注意し始めました。たまに向うから話し掛けられでもすると、なおの事警戒を加えたくなりました。私の心は沈鬱でした。鉛を呑んだように重苦しくなる事が時々ありました。それでいて私の神経は、今いったごとくに鋭く尖ってしまったのです。
それでも「先生」は「血のつながった叔父に裏切られて人間不信となり」と言いたくなるような心情が吐露されています。ここでは人類とまで言われていますので、旧友だけが唯一の例外で、残りの全ての人間は信用していないのではないかと考えたくもなります。
ところがどうも、
私は金に対して人類を疑ったけれども、愛に対しては、まだ人類を疑わなかったのです。だから他から見ると変なものでも、また自分で考えてみて、矛盾したものでも、私の胸のなかでは平気で両立していたのです。
とあるので少なくとも「それで下宿先の「奥さん」や「お嬢さん」(後に妻となる静)をも信頼できなくなった」というわけではない、ということが解りますね。
どうも「血のつながった叔父に裏切られて人間不信となり」とだけでは片づけられない二段階の心の変化があるわけです。下宿に迎えられた「先生」は次第に心を開きます。
私の心が静まると共に、私は段々家族のものと接近して来ました。奥さんともお嬢さんとも笑談をいうようになりました。茶を入れたからといって向うの室へ呼ばれる日もありました。また私の方で菓子を買って来て、二人をこっちへ招いたりする晩もありました。私は急に交際の区域が殖えたように感じました。それがために大切な勉強の時間を潰される事も何度となくありました。不思議にも、その妨害が私には一向邪魔にならなかったのです。奥さんはもとより閑人でした。お嬢さんは学校へ行く上に、花だの琴だのを習っているんだから、定めて忙しかろうと思うと、それがまた案外なもので、いくらでも時間に余裕をもっているように見えました。それで三人は顔さえ見るといっしょに集まって、世間話をしながら遊んだのです。
この時点では人間不信ではありませんね。そして「先生」は一番胸につかえていた問題を奥さんに話します。
私は郷里の事について余り多くを語らなかったのです。ことに今度の事件については何もいわなかったのです。私はそれを念頭に浮べてさえすでに一種の不愉快を感じました。私はなるべく奥さんの方の話だけを聞こうと力めました。ところがそれでは向うが承知しません。何かに付けて、私の国元の事情を知りたがるのです。私はとうとう何もかも話してしまいました。私は二度と国へは帰らない。帰っても何にもない、あるのはただ父と母の墓ばかりだと告げた時、奥さんは大変感動したらしい様子を見せました。お嬢さんは泣きました。私は話して好い事をしたと思いました。私は嬉しかったのです。
私のすべてを聞いた奥さんは、はたして自分の直覚が的中したといわないばかりの顔をし出しました。それからは私を自分の親戚に当る若いものか何かを取り扱うように待遇するのです。私は腹も立ちませんでした。むしろ愉快に感じたくらいです。ところがそのうちに私の猜疑心がまた起って来ました。
もし「奥さん」と「お嬢さん」を信用していなければ、叔父に騙された話などできない筈です。「奥さん」が舌打ちして、「気づいていたんですか」と返して来たらぞっとしますよね。
しかしこの後です。この後猜疑心が起こります。
私が奥さんを疑り始めたのは、ごく些細な事からでした。しかしその些細な事を重ねて行くうちに、疑惑は段々と根を張って来ます。私はどういう拍子かふと奥さんが、叔父と同じような意味で、お嬢さんを私に接近させようと力めるのではないかと考え出したのです。すると今まで親切に見えた人が、急に狡猾な策略家として私の眼に映じて来たのです。私は苦々しい唇を噛みました。
こうして向けられた疑惑はまだ「奥さん」に対するもので、「お嬢さん」には向いていませんでした。「お嬢さん」が信用できなくなるのは真砂町事件の後のことです。
こうした一つ一つの段取りを確認しながら読んでいくことが大切ですね。
女性蔑視でもない
改めて確認するが、血のつながった叔父に裏切られて人間不信となったから「奥さん」や「お嬢さん」をも信用できなくなったというなら、一応筋は通っている。しかし〈血のつながった叔父に裏切られて人間不信となったから、女は愚だと思った〉では筋が通らない。「先生」にこの屈折を強いているのは、明らかに「女はミステリー」とか「女は謎」という女性蔑視の感情だ。
この女は愚、の後に続くのがこの文章である。
それほど女を見縊っていた私が、またどうしてもお嬢さんを見縊る事ができなかったのです。私の理屈はその人の前に全く用を為さないほど動きませんでした。私はその人に対して、ほとんど信仰に近い愛をもっていたのです。私が宗教だけに用いるこの言葉を、若い女に応用するのを見て、あなたは変に思うかも知れませんが、私は今でも固く信じているのです。本当の愛は宗教心とそう違ったものでないという事を固く信じているのです。私はお嬢さんの顔を見るたびに、自分が美しくなるような心持がしました。お嬢さんの事を考えると、気高い気分がすぐ自分に乗り移って来るように思いました。もし愛という不可思議なものに両端があって、その高い端には神聖な感じが働いて、低い端には性欲が動いているとすれば、私の愛はたしかにその高い極点を捕まえたものです。私はもとより人間として肉を離れる事のできない身体でした。けれどもお嬢さんを見る私の眼や、お嬢さんを考える私の心は、全く肉の臭を帯びていませんでした。
私は母に対して反感を抱いだくと共に、子に対して恋愛の度を増して行ったのですから、三人の関係は、下宿した始めよりは段々複雑になって来ました。
少なくとも「お嬢さん」に対しては信仰に近い愛を持っているので蔑視はありませんね。
そして別にここでは「ミステリー」や「謎」を感じているわけでもないので「「先生」にこの屈折を強いているのは、明らかに「女はミステリー」とか「女は謎」という女性蔑視の感情だ。」では筋が通らないわけです。
それが女性蔑視かどうかは別として「女はミステリー」とか「女は謎」というものが現れてくるのはやはり真砂町事件の前後のことで、ここで石原が疑問に感じている「女は愚」という解釈はたちまち別の解釈に置き換えられています。
そのうち私はあるひょっとした機会から、今まで奥さんを誤解していたのではなかろうかという気になりました。奥さんの私に対する矛盾した態度が、どっちも偽りではないのだろうと考え直して来たのです。その上、それが互い違いに奥さんの心を支配するのでなくって、いつでも両方が同時に奥さんの胸に存在しているのだと思うようになったのです。つまり奥さんができるだけお嬢さんを私に接近させようとしていながら、同時に私に警戒を加えているのは矛盾のようだけれども、その警戒を加える時に、片方の態度を忘れるのでも翻すのでも何でもなく、やはり依然として二人を接近させたがっていたのだと観察したのです。ただ自分が正当と認める程度以上に、二人が密着するのを忌むのだと解釈したのです。お嬢さんに対して、肉の方面から近づく念の萌さなかった私は、その時入らぬ心配だと思いました。しかし奥さんを悪く思う気はそれからなくなりました。
このように整理されて女の愚は消えていきます。
奥さんは滅多に外出した事がありませんでした。たまに宅を留守にする時でも、お嬢さんと私を二人ぎり残して行くような事はなかったのです。それがまた偶然なのか、故意なのか、私には解らないのです。
この「解らない」も同時に解決されているので一旦ここで「女はミステリー」ではなくなりますね。
それからよくよく考えれば「女はミステリー」になる真砂町事件に関しても、Kが、
・金もないのに足下の悪い中何の用事で出かけたのか
このことだけをきっちり説明していたら謎にも何にもならなかったわけで、女ばかりに責任を押し付けるわけにもいいきませんね。
また「女はミステリー」とは言いながら『明暗』における清子などそもそも謎のないところに無理に謎を押し付けられているようなところがないとも言えませんし、『道草』の健三の腹違いの姉など無教養なのに随分ミステリーを仕掛けてきますので、あまり大ざっぱに括らないで作品ごとに細かく見ていくことが必要でしょうね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

