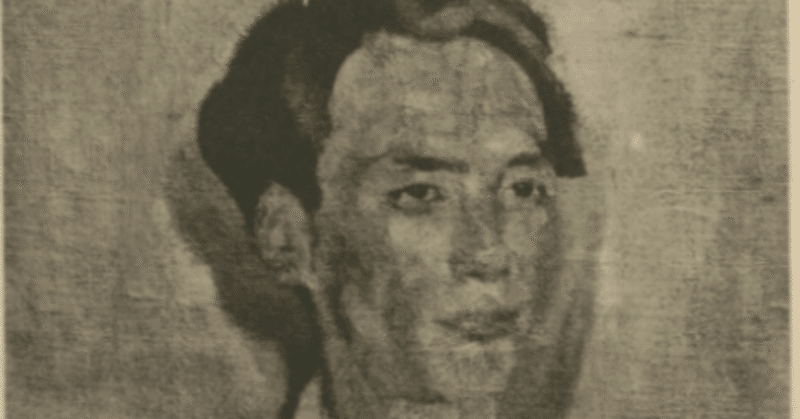
芥川龍之介の『玄鶴山房』をどう読むか① 保吉ではないんだ
たまたまなのか何なのか芥川龍之介の『玄鶴山房』に関して私はこれまでまともな記事を一つも書いてこなかった。
うっかり?
そうかもしれないし、そうではないかもしれない。
いずれにせよ、書いておこう。
………それは小ぢんまりと出来上った、奥床しい門構えの家だった。尤もこの界隈にはこう云う家も珍しくはなかった。が、「玄鶴山房」の額や塀越しに見える庭木などはどの家よりも数奇を凝らしていた。
この家の主人、堀越玄鶴は画家としても多少は知られていた。しかし資産を作ったのはゴム印の特許を受けた為だった。或はゴム印の特許を受けてから地所の売買をした為だった。現に彼が持っていた郊外の或地面などは生姜さえ碌に出来ないらしかった。けれども今はもう赤瓦の家や青瓦の家の立ち並んだ所謂「文化村」に変っていた。………
しかし「玄鶴山房」は兎に角小ぢんまりと出来上った、奥床しい門構えの家だった。殊に近頃は見越しの松に雪よけの縄がかかったり、玄関の前に敷いた枯れ松葉に藪柑子の実が赤らんだり、一層風流に見えるのだった。のみならずこの家のある横町も殆ど人通りと云うものはなかった。豆腐屋さえそこを通る時には荷を大通りへおろしたなり、喇叭を吹いて通るだけだった。
「玄鶴山房――玄鶴と云うのは何だろう?」
たまたまこの家の前を通りかかった、髪の毛の長い画学生は細長い絵の具箱を小脇にしたまま、同じ金鈕の制服を着たもう一人の画学生にこう言ったりした。
「何だかな、まさか厳格と云う洒落でもあるまい。」
彼等は二人とも笑いながら、気軽にこの家の前を通って行った。そのあとには唯凍て切った道に彼等のどちらかが捨てて行った「ゴルデン・バット」の吸い殻が一本、かすかに青い一すじの煙を細ぼそと立てているばかりだった。………
中央公論昭和二年一、二月号に発表される『玄鶴山房』は前年の十二月頭には書き始められていて本人の自覚としては「陰鬱極まる力作」ということらしい。この時期複数の作品が並行して書かれていた可能性があることから「陰鬱極まる力作」とは寧ろ『歯車』のほうではないかと私は考えているが、証拠と言うほどのものはない。作品の長さ的には『玄鶴山房』よりも『歯車』の方が長いし、仕掛けの手数も多い。『玄鶴山房』が力作と呼べるほどのものかどうかは……。
十二月十六日高野敬録宛書簡に「二月号におまはし下さるまじくや」とあるのが『玄鶴山房』であるとした場合、
小説かけたりや、僕は今二つ片付け三つ目を書いてゐる。捗どらず。痔猛烈に再発、昨夜呻吟して眠られず。小穴の妹危篤。多事、々々、々々。
という記述と、
僕ハ陰鬱極マル力作ヲ書イテヰル。出来上ルカドウカワカラン。
この記述の平仄が合わない。十二月五日に書き始めた原稿は十二日には書き終わっている筈だ。高野敬録は中央公論の編集者。遅れたのは『玄鶴山房』。『玄鶴山房』は陰鬱極まるという作品でも無し。何なら一、二月に発表される陰鬱極まる作品は……これといってない。
となるとやはり『歯車』か『或阿呆の一生』が少しずつ書きはじめられていたと考えるのが自然ではかろうか。



これらの写真は昭和三年七月、芥川の命日の記念に百五十部限定で刷られた「おもかげ」という小冊子から採ったものである。玄鶴山房のどこかにはこの澄江堂の投影があることくらいは確かであろう。芥川は絵も達者で、風流な趣味を持っていた。この家も随分数寄に仕上がりつつあり、自慢だった。
ところで「堀越玄鶴は画家としても多少は知られていた」としながら「たまたまこの家の前を通りかかった、髪の毛の長い画学生」たちが玄鶴を知らないのはいきなりの自嘲だろうか。
芥川は勿論かなりの有名人で人気作家であったわけだが「ゴム印の特許」や「地所の売買」で資産をなしてゐたわけではない。原稿料と印税でなんとか暮らしていた。資産家とは呼べないと思う。これもまた自嘲であろうか。
そもそも玄鶴とは? 老いた鶴、黒い鶴、二千年生きてくたびれた鶴である。『鶴は病みき』を思えばこれもまた自嘲に見えなくもないが、さすがにそれはなかろうか。
あまり先走っては何だがここで画学生らが捨てる「ゴルデン・バット」は安物の煙草で、最後に出てくる「敷島」が高級煙草であることとシンメトリーをなしていることはまだ誰も知らない。
ただ彼は、枕許に近い土間の上に、昨夜発見しなかったものを見出した。いや、それは発見はしたのであろうがつい気がつかなかったのであろう。それは見慣れない莨の吸すい殻がらだった。――その莨は「敷島!」
杜は「ゴールデンバット」ばかり吸っていた。敷島は絶対に吸わなかった。お千も吸わない。
灰皿には、バットの吸い殻が、まるで焼跡の棒杭みたいに乱雑にうず高く積み重なって、まだその吸い殻からは盛んに煙がたちのぼっていました。そしてその吸い殻の中には敷島の吸い殻が五六本まじっていました。平素バットばかりしか吸わない人だったので、敷島の吸い殻があるのは不思議だと私は一目見たときに思いました。
漱石、芥川、谷崎らは平素「敷島」を吸っていた。従って「敷島」が高級というより今でいうメビウスのような普通のもので、「ゴルデン・バット」は「新生」のようなものか。
藪柑子の実が赤らんだり、とあることから「凍て切った道」とあるにもかかわらず季節は晩秋、から初冬にかけての設定かと思う。書簡では十二月五日に室生犀星にあてて、
僕ハ陰鬱極マル力作ヲ書イテヰル。出来上ルカドウカワカラン。
このように書いているから大体この時期のことかなと思うばかりである。するとヤブコウジの実が少し遅くなる。「枯れ松葉に藪柑子の実が赤らんだり」の「らんだり」が少しの時間の経過を含んだ表現と見做していいかもしれない。
タマユラニ消ユル煙草ノ煙ニモvita brevisヲ思ヒヲル我ハ
vita brevisは「人生は短し」という意味だそうだ。

我鬼先生、既にお疲れの時期で、

こんな両班みたいな可愛らしい子供だったのが、
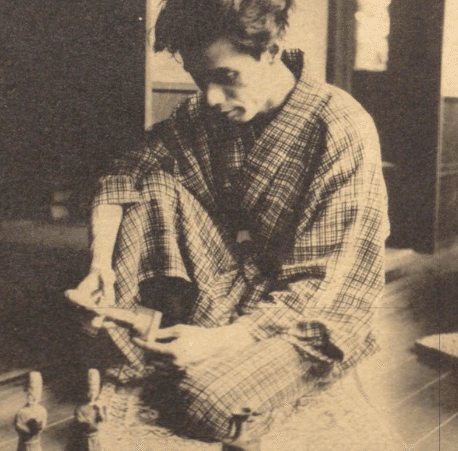
このくらいお疲れだった。

重吉は玄鶴の婿になる前から或銀行へ勤めていた。従って家に帰って来るのはいつも電灯のともる頃だった。彼はこの数日以来、門の内へはいるが早いか、忽ち妙な臭気を感じた。それは老人には珍しい肺結核の床に就いている玄鶴の息の匂だった。が、勿論家の外にはそんな匂の出る筈はなかった。冬の外套の腋の下に折鞄を抱えた重吉は玄関前の踏み石を歩きながら、こういう彼の神経を怪まない訣には行かなかった。
なるほど玄鶴は肺結核にかかった老人らしい。vita brevisだ。しかしそんなことはみんな一緒なんだよ。人生なんてあっという間。

夏目漱石の『彼岸過迄』において田川敬太郎が小川町の停留所での探偵を命じられた時刻が午後四時から午後五時の間のこと。この時刻が役人や会社員の当時(明治四十五年頃)の通常の帰宅時間に当たる。大正三年の『各種事務員就職案内』でも「午后四時迄」とされていて変わりはない。
例へば銀行員の勤務時間は八時間位にしか過ぎないが、紡績會社員たどは十時間乃至十二時間も續いて勤務しなければならない。だから、よほど身體が丈夫でないと困る。
剣持鋭 著国民書院 1916年
この銀行員の勤務時間が「従って家に帰って来るのはいつも電灯のともる頃だった」と書かれているから当たり前に一時間は伸びていて、外の職業と比べても少しは長くなっていたのであろう。重吉は堀越重吉になったことを銀行に届け出て名札も名刺も作り変えてもらったのだろうか。なかなか大変なことだ。
折鞄とは抱鞄の一種で、ストラップで閉じるかばん、医者も銀行員も用いた。「抱えて」とあるからまだ手提げ式ではなかったのだろう。大正十年ごろからは手提げ式が流行るのでやや時代遅れの感じだ。踏み石は敷石で「歩きながら」とあるので沓脱石ではなかろう。
帽子とステッキはどうだったのか。
それはまだ誰にも解らない。
何故ならここまでしか読んでいないからだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

