
ゆらゆらゆれる 芥川龍之介の『影』をどう読むか②
芥川はこの頃他人の女房とセックスがしたかったのではないか、と書いたところで昨日はいったん終わりにした。
つい勢いで書きすぎると何か見落としをしてしまいそうなので、少し時間を置いた。
インターネットを通じていろんな人の書いているものを読んでいくと、本人は相当自信をもっていて、自分のことを教養のある読書家だと任じている風な人が、ものすごく初歩的な勘違いをしていて驚く。しかしそれは商業出版された本でも同じで、そういう凡ミスは基本的にみなよく確認していないから起こることだ。
急ぎすぎてはいけない。「曰牡丹」なんて書いている人もいるけれど、これは「白牡丹」だ。

この人だけが残念なのではない。私の本を買わない人は、皆夏目漱石作品を誤解したまま死んでいく。悲惨なことだ。
本当にちょっとしたことが肝心だ。例えば『影』の読みは何か。単に「かげ」でよいのかとか、あれこれ考えながら読まなくてはならない。そうでないと「芥川はこの頃他人の女房とセックスがしたかったのではないか」とは書けない。書いてはいけない。
鎌倉。
下り終列車の笛が、星月夜の空に上った時、改札口を出た陳彩は、たった一人跡に残って、二つ折の鞄を抱えたまま、寂しい構内を眺めまわした。すると電燈の薄暗い壁側のベンチに坐っていた、背の高い背広の男が一人、太い籐の杖を引きずりながら、のそのそ陳の側へ歩み寄った。そうして闊達に鳥打帽を脱ぐと、声だけは低く挨拶をした。
「陳さんですか? 私は吉井です。」
陳はほとんど無表情に、じろりと相手の顔を眺めた。
「今日は御苦労でした。」
「先ほど電話をかけましたが、――」
「その後何もなかったですか?」
陳の語気には、相手の言葉を弾き除けるような力があった。

「こんにちはごくらうでした」?

「けふはごくらうでした」?



青空文庫の定本は筑摩書房のものらしい。しかしいくらなんでもこれは「けふ」であろう。芥川の生原稿を持っている人は、ぜひこの点を確認してもらいたい。
さてさてここでまず気になるのは、吉井に鳥打帽を被らせている点だ。鳥打帽など珍しくもなかろうが、房子の発言と結び付けられて、やはりこの吉井という探偵はじかに窓から部屋の中を覗いて顔を見られたのかと思わされるところ。それにしても随分と迂闊な探偵がいたものだ。
そしてもう一つ引っかかる。この吉井という男は足が悪いのだろうか。「太い籐の杖を引きずりながら、のそのそ陳の側へ歩み寄った」とはどういうことなのか。「杖を引きずり」とは文字通りの意味なのか。何故「のそのそ」なのか。足が悪ければ見張りはできても備考には向いていない。長谷で見た「若い人」と吉井は別人なのではないかという気がしてくる。
なぜなら陳の吉井に対する第一印象は「背の高い背広の男」だ。一方房子の印象は「若い人」。房子の身長がよほど高くない限り、二十歳そこそこの房子が吉井を「若い人」として認識するであろうか。あるいは陳の身長がよほど低くない限り、房子がまず「若い人」と見做すような男に対して「背の高い背広の男」と認識するものであろうか。
なんということのないただのズレのようでありながら、実はここにも小さな『薮の中』がある。スクランブル交差点は渋谷の駅前だけにあるのではない。

実は代々木公園に向かう上り坂にあるこの交差点もスクランブル交差点だ。こういうところを面白いと思わないでただ『薮の中』だけ面白がる人というのは、本当の意味で芥川作品を読めているとは言えないだろう。
「何もありません。奥さんは医者が帰ってしまうと、日暮までは婆やを相手に、何か話して御出ででした。それから御湯や御食事をすませて、十時頃までは蓄音機を御聞きになっていたようです。」
「客は一人も来なかったですか?」
「ええ、一人も。」
「君が監視をやめたのは?」
「十一時二十分です。」
吉井の返答もてきぱきしていた。
「その後終列車まで汽車はないですね。」
「ありません。上りも、下りも。」
「いや、難有う。帰ったら里見君に、よろしく云ってくれ給え。」
陳は麦藁帽の庇へ手をやると、吉井が鳥打帽を脱ぐのには眼もかけず、砂利を敷いた構外へ大股に歩み出した。その容子が余り無遠慮すぎたせいか、吉井は陳の後姿を見送ったなり、ちょいと両肩を聳やかせた。が、すぐまた気にも止めないように、軽快な口笛を鳴らしながら、停車場前の宿屋の方へ、太い籐の杖を引きずって行った。

「ことば」?
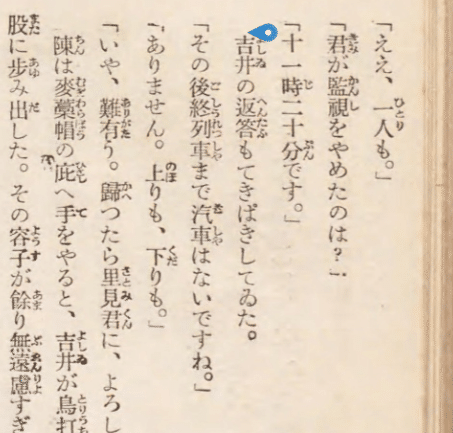
さてこれはどちらであろうか。「へんたふ」が自然ではあるが、むしろ「返答」とだけ書いてあるものを「ことば」と読ませるものであろうか。そう考えると「けふ」ではなく「こんにち」なのかもしれないと思えてくる。まさにサスペンス。ゆらゆら揺れる。
麦藁帽子も突然出てきて少しは驚かせる。三人称の語りなのに、語り手は陳の服装を描写していなかった。とっても、まあ、あいみょんの歌にあるようなつばの広いものではなかろうが、紳士が麦藁帽子をかぶり、鎌倉の駅前が砂利道であるという時代性が、現在の読み手にしてみればおやと思わせる所か。
むしろ芥川自身の意図としては、汽車がないのに吉井の帰りはどうするのだ、まさか探偵風情がこの時代に自動車か、と思わせる為に「帰ったら里見君に、よろしく云ってくれ給え」と言わせておいて、吉井は鎌倉に宿をとっていて帰らないというちぐはぐさまでだろう。
昼間から見張っていたのだから、深夜のチェックインの予約はどんな具合にしていたのかとか、そもそも「今日は御苦労でした。」と言っているが家を空けたのはこの日だけではないのに探偵をつけたのはこの日だけなのかとか、本当は陳が「帰ったら里見君に、よろしく云ってくれ給え」とあまり相手のことを気遣わない性格なので、そもそも連泊ではないのかと、そのあたりのところまではぎりぎり意識の中にあったかもしれない。
何しろ陳の性格の悪さ、横柄さというものは強調しようとしているところは間違いない。
そして『浅草公園』で見られたようなカメラワークが幽かにここにもあることに驚く。
陳は麦藁帽の庇へ手をやると、吉井が鳥打帽を脱ぐのには眼もかけず、砂利を敷いた構外へ大股に歩み出した。その容子が余り無遠慮すぎたせいか、吉井は陳の後姿を見送ったなり、ちょいと両肩を聳やかせた。が、すぐまた気にも止めないように、軽快な口笛を鳴らしながら、停車場前の宿屋の方へ、太い籐の杖を引きずって行った。
カメラは陳の背中を映し、主人公をほったらかしにして吉井についていく。まるで遊びなれた女が、そんなことくらいなんでもないわとキスするように芥川はすんなり主人公を置き去りにしている。やはり『影』が映画的小説なのだとはっきり分かったところで今日はここまで。
[余談]
なし。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
