
芥川龍之介の『アグニの神』を読む 日本の神は役に立たない
婆さんは三百弗の小切手を見ると、急に愛想がよくなりました。
「こんなに沢山頂いては、反って御気の毒ですね。――そうして一体又あなたは、何を占ってくれろとおっしゃるんです?」
「私が見て貰いたいのは、――」
亜米利加人は煙草を啣えたなり、狡猾そうな微笑を浮べました。
「一体日米戦争はいつあるかということなんだ。それさえちゃんとわかっていれば、我々商人は忽ちの内に、大金儲けが出来るからね」
「じゃ明日いらっしゃい。それまでに占って置いて上げますから」
「そうか。じゃ間違いのないように、――」
印度人の婆さんは、得意そうに胸を反らせました。
これは大正十年の作である。「日米戦争」という文字は明治四十年には書籍の中に現れていた。日露戦争後、貧しくなった日本から食い詰め者が世界中に移民する中で、世界との摩擦が広まっていった。
學童排斥問題より次で我移民拒絕となり、在米邦人の迫害となり、日米戰爭の噂さへ起るに至つた。今尙ほ米國では相當の地位にあるものが我國に對して不穩の言を爲すものがある。
この当時小説の中には「日米戦争必至論」まで現れる。1910年には「一時日米戰爭は流行語たるか如き觀ありたり」とまで言われ、翌年には「歐洲の或批評家は日米戰爭の場合に起るべき問題を論じ米國は最初二年間連敗ずるも其後機運一轉し終局の勝利を占むべしと云へり」(『国防海軍論』川島清治郎 著嵩山房 1911年)などと、いかにももっともらしいことまで言われるようになった。

これは日本国内の漠然とした不安から起こったものではない。日米開戦論にはむしろ米国側からの日本脅威論、ある意味黄禍論の一種という側面がある。
近來は漸くその鋒先を收めたやうであるが、果して全く止めたのであるか、或は休戰してゐるのが、兎に角熱心に日米戰爭を說き廻つたのである。それが近來有名なるホーマーリーの『日米戰爭論』である。それからまた『日露再戰』といふのが、英人ハリソンの手に依つて出來た。
この大隈重信の言うところの『日米戰爭論』は1911年に日本語訳が出ている。第一次世界大戦が1914年に始まると、日米戦争は途端に単なる風説ではなくなる。
日米戰爭の遲遠は歐洲戰爭の結果に由りて決する、そして日米戰争の動機は支問那題から爆發すといふは蓋し好事者の流言に外ならない。
第一次世界大戦は1918年(大正七年)11月11日に終結する。
即ち英國は當然日米戰爭に引入れられる、但し何れに味方するかは將來の祕密である。
大正十年において「一体日米戦争はいつあるかということなんだ」などという会話は決して突飛なものでもなんでもなく、また非現実的なものでも無かったはずだ。ただし小説『アグニの神』は突飛な話だ。支那の上海のある町に住む印度人の婆さんは、香港の日本領事の娘、妙子を攫い、その妙子にアグニの神を降ろして予言を行っていた。
そこに遠藤という日本人が押し入り、ピストルで老婆を脅して妙子を救い出そうとするが、老婆の妖術で追い返されてしまう。
妙子は眠ったふりをして偽の予言を行い、老婆に自分を解放させるように仕向ける計画を立てる。その知らせを受けた遠藤はドアの外から様子をうかがう。
「日本の神々様、どうか私が睡らないように、御守りなすって下さいまし。その代り私はもう一度、たとい一目でもお父さんの御顔を見ることが出来たなら、すぐに死んでもよろしゅうございます。日本の神々様、どうかお婆さんを欺せるように、御力を御貸し下さいまし」
ここで妙子は日本の神々様に祈る。しかしアグニの神は降りてきて、妙子は眠ってしまう。偽の予言で老婆を騙す筈が、失敗したと思いきや、妙子は荒々しい男の声で語り始める。
「いや、おれはお前の願いなぞは聞かない。お前はおれの言いつけに背いて、いつも悪事ばかり働いて来た。おれはもう今夜限り、お前を見捨てようと思っている。いや、その上に悪事の罰を下してやろうと思っている」
婆さんは呆気にとられたのでしょう。暫くは何とも答えずに、喘ぐような声ばかり立てていました。が、妙子は婆さんに頓着せず、おごそかに話し続けるのです。
「お前は憐れな父親の手から、この女の子を盗んで来た。もし命が惜しかったら、明日とも言わず今夜の内に、早速この女の子を返すが好い」
ここでいくつもの疑問が湧く。
・何故今なのか。これまでは黙認してきたのは何故か。
・日本の神々様は把になってもアグニの神にかなわないのか。それとも日本の神々様の代わりにアグニの神が妙子の願いを聞き届けたのか。
・現人神は何をしているのか。
・何故「憐れな父親の手から」なのか。妙子の母親はこの世にいないのか。
・妙子には何の罪もないのか。
「遠藤サン。コノ家ノオ婆サンハ、恐シイ魔法使デス。時々真夜中ニ私ノ体ヘ、『アグニ』トイウ印度ノ神ヲ乗リ移ラセマス。私ハソノ神ガ乗リ移ッテイル間中、死ンダヨウニナッテイルノデス。デスカラドンナ事ガ起ルカ知リマセンガ、何デモオ婆サンノ話デハ、『アグニ』ノ神ガ私ノ口ヲ借リテ、イロイロ予言ヲスルノダソウデス。今夜モ十二時ニハオ婆サンガ又『アグニ』ノ神ヲ乗リ移ラセマス。イツモダト私ハ知ラズ知ラズ、気ガ遠クナッテシマウノデスガ、今夜ハソウナラナイ内ニ、ワザト魔法ニカカッタ真似ヲシマス。ソウシテ私ヲオ父様ノ所ヘ返サナイト『アグニ』ノ神ガオ婆サンノ命ヲトルト言ッテヤリマス。オ婆サンハ何ヨリモ『アグニ』ノ神ガ怖イノデスカラ、ソレヲ聞ケバキット私ヲ返スダロウト思イマス。ドウカ明日あしたノ朝モウ一度、オ婆サンノ所ヘ来テ下サイ。コノ計略ノ外ニハオ婆サンノ手カラ、逃ゲ出スミチハアリマセン。サヨウナラ」
確かに母親とか両親とは書かれていない。
・そもそも婆さんの悪事とは何か。仮に予言をそのまま伝えたとしたら、それは悪事なのか。
・婆さんの妖術はアグニの神とは関係ないのか。
・そもそも何故香港の日本領事の娘を上海の印度人の婆さんが攫うのか。
・何故アグニの神が上海まで出張してくるのか。
・アグニの神は日米開戦の時期をアメリカ人に教えることを悪事と見做していまいか。アグニの神は戦争で儲けようとする商売人を批判してはいまいか。
・何故印度人の婆さんが悪者なのか。イギリス領インド帝国に何か恨みでもあるのか。
・何故印度人の婆さんは上海でもカレーを手づかみで食べるのか。印度人の婆さんは独身なのか。サリーを着ているのか。
・それにしても何故わざわざ日本人の妙子がアグニの神との媒介として選ばれたのか。
・彼らは何語で会話をしているのか。アグニの神は何語を話すのか。
そんな疑問を置き去りにして、婆さんは自分で自分の胸をナイフで刺して死んでしまう
遠藤はもう一度、部屋の中を見廻しました。机の上にはさっきの通り、魔法の書物が開いてある、――その下へ仰向きに倒れているのは、あの印度人の婆さんです。婆さんは意外にも自分の胸へ、自分のナイフを突き立てたまま、血だまりの中に死んでいました。
「お婆さんはどうして?」
「死んでいます」
妙子は遠藤を見上げながら、美しい眉をひそめました。
「私、ちっとも知らなかったわ。お婆さんは遠藤さんが――あなたが殺してしまったの?」
遠藤は婆さんの屍骸から、妙子の顔へ眼をやりました。今夜の計略が失敗したことが、――しかしその為に婆さんも死ねば、妙子も無事に取り返せたことが、――運命の力の不思議なことが、やっと遠藤にもわかったのは、この瞬間だったのです。
「私が殺したのじゃありません。あの婆さんを殺したのは今夜ここへ来たアグニの神です」
遠藤は妙子を抱えたまま、おごそかにこう囁きました。
これで日米戦争の件はうやむやになった。アグニの神はそうした重大事を教えるべきではないと考えたのか。……しかしアグニの神など存在しないとしたら、印度人の婆さんを殺したのは妙子だろう。妙子は「女の子」と形容されるが年齢や体格には触れられない。妖術さえ使われなければ、妙子が勝てない相手ではなかったのかもしれない。いや、そもそもアグニの神など存在しないだろう。日本の神々様が存在しないように。あるいは日本の神々様がまるで役に立たないように。
もしもアグニの神が役に立ったのなら、老婆は焼き殺されていただろう。アグニの神は火の神である。
[余談]
芥川と話をしてゐると、きまつて、「死ぬ話をしようや、」に話をもつてゆく。さういふ芥川はいつも「僕の女房は自分には過ぎた者だ。」と言つて涙を湛へてゐた。「女房も僕のやうに、過去に過失を持つてゐてくれる女であれば、また、今日に、或は先きにいつてでも過失を犯してくれるやうな人間であつてさへくれるのなら、どれほど僕の氣持は救はれるか」と掻き口説いてゐた。
芥川の遺書のなかには、〔一、もし集を出すことあらば、原稿は小生所持のものによられたし。二、又「妖婆」(「アグニの神」に改鑄したれば、)「死後」(妻の爲に)の二篇は除かれたし。〕といふ字句があつた。
仮にこの証言をストレートに受け取れば、印度人の婆さんが芥川龍之介の奥さん、芥川文という妙な図式が出来上がる。
ここで、そうか、なるほど、とはならない。
いかにもピンとこない。
もしかしたら奥さんだけにはばれてしまうコードが隠れているのかもしれないが、作品として見た時、一般読者に対しては、妖婆を作者の妻と仄めかすことには失敗していると考えてよいだろう。
作者が生前單行本にすることを肯んじなかつたものは澤山あるが、相當の長さのものでは、「妖婆」と「邪宗門」と此「偸盜」との三つであらう。
佐々木茂索も「出来そくなひだから」という本人の弁を疑いつつ、この問題を解いてはいない。
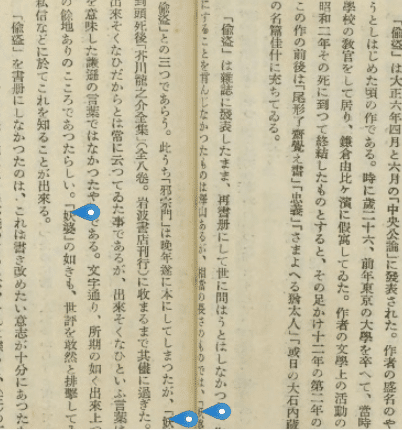
すごー😂😂 pic.twitter.com/OBQ2v9wCs2
— マッチヤン (@QrmhPb4rtA6JxTH) October 24, 2022
妖術だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
