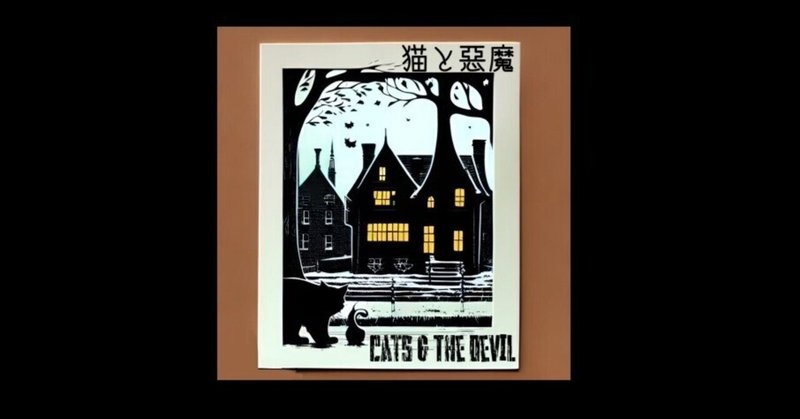
「猫と悪魔」 実話怪談 (note創作大賞2023・ミステリー小説部門応募作品)
あらすじ
時は平成。舞台は海外。語り部である私(Kitsune-Kaidan)の実話怪談。
数々の霊体験の中でも最も謎に包まれた身の毛もよだつ悪魔(デビル)との出会い。悪魔とはいったいどのような存在なのか。悪魔が私に伝えたかったこととは?
きっと答えは一つではない。読み手によって異なる解釈があるこの怪談話。挿絵と共にお楽しみ下さい。
はじめに
この怪談は、私が初めて悪魔(デビル)と出くわした実体験の話です。驚きを誘う大どんでん返しのオチはないですが、怪奇な出来事の中には、実話怪談特有の謎めいた不可解さが漂っています。じわじわと忍び寄る恐怖が背筋をぞくぞくさせる話です。
この怪談は、怪談の中でも一風変わった、シェイプシフターのジャンルに属するのではないかと思います。シェイプシフターというのは、その名の通り、さまざまな姿や形に変身する「妖怪」などのことを指します。その正体は実に不可思議で、幽霊や動物、爬虫類、魂、宇宙人、地底人、はたまたダークワールドに至るまで、さまざまなものが含まれると言われています。人々を怯えさせる存在として、古くから世界中で恐れられてきたのだろうと思います。
日本において、狐や狸といったシェイプシフターは広く知られている存在です。昔から、信じられない不可思議なできごとに巻き込まれた際には、「狐につままれた」という言葉が使われてきました。葉っぱを頭に乗せて変身する狸の姿がよく描かれており、誰しもがそのような物語を一度は読んだことがあるのではないでしょうか。
そして、我々を恐怖に包み込む素材として、黄昏時、逢魔時(おうまがとき)、丑三つ時といった闇の刻の存在が不可欠です。太陽が沈み、辺りが暗闇に包まれると、これまで見慣れた世界とはまるで異なる場所に独り置き去りにされたかのような、言い表せない孤独感に取り憑かれます。今まで話していた相手の正体は果たして何者なのだろうか?そんな疑心暗鬼の念さえ生まれてくるかもしれません。
私が実際に海外で体験したこの怪談は、まさにシェイプシフターたちの繰り広げる物語の中に、いつの間にか巻き込まれてしまったような感覚を味わった体験談です。この怪談をこうして人に語るのは、今回が初めての試みです。
前置きはこのくらいにして、さっそく不思議な世界へとご案内しましょう。

日常
当時、私はオーストラリアのシドニーに住んでいた。慣れない海外生活には苦労がつきものだが、それでも私は日々の仕事や勉強に追われ、忙しい日々を送っていた。
(せっかくシングルになったんだから、海外らしいことをしたいな!)
少し前までうまくいっていなかった恋人との関係に、やっと終止符をうつことができた私は、その解放感からひとりで気ままに旅に出たいという衝動にかられていた。
仕事や勉強、さらに恋に疲れ果てた私は、非日常的な癒しを求めていた。しかし、友人をわざわざ呼び出して自分のネガティブな感情を吐露する気分でもなかった。もともと一人でいることが好きな私は、地元のビーチで静かに立ち尽くし、楽しそうにサーフィンをする人々や、おしゃれなカフェで愛を語り合うカップルたちをぼんやりと眺めていた。
(今ごろ日本はあったかいんだろうなー)
日本とは真逆の季節であるオーストラリアは、ちょうど秋から冬に変わる寒い時期だった。
「よくこんな寒いのにサーフィンなんかできるな」
と言って、私は身震いをしながら肩をすくめてビーチを後にした。
特に行くあてもなかったので、ダウンタウンでウィンドウショッピングを楽しんだり、古着屋で掘り出し物を探したり、本屋で立ち読みをしたり、カフェのテラス席でブラックティーを飲みながら、さっきの本屋で見つけたかわいらしい黒猫の無料のポストカードに、母に送るメッセージを思いつきで書き綴っていた。
(黒猫か…)
私はどちらかと言えば犬派だ。母も犬が好きだ。なのに、なぜ黒猫のポストカードを選んだのか、自分でもよくわからなかった。本屋のレジの横にあった広告用のポストカードの黒猫と目が合った気がしたのだ。なんの広告だったのかは記憶にない。確かホテルかなにかの広告だったような気がする。それがいったいどんなホテルを宣伝していたのか、私にははっきりとは思い出せない。
「ハロー」
道端を歩くアボリジニ風の男性が私に声をかけてきた。
「ハロー」
私は彼に向かって挨拶を返した。
「タバコあるかい?」
「ごめんなさい。タバコないです」
このようなやり取りは、日常の風景の一部である。
カフェを出た私は、手に持っていた黒猫のポストカードを郵便ポストに投函し、もう少しぶらぶらすることにした。

バスツアー
そんな時、私は偶然にもコミュニティーセンターで目にした「タスマニア島一周の旅」というパンフレットに不思議な魅力を感じた。オーストラリアといえば、ケアンズの「グレート・バリア・リーフ」や、かつてエアーズロックと呼ばれていた「ウルル」といった有名な観光スポットが数多く存在する。そのような観光地へと向かう、大きな荷物を背負い、旅を楽しむバックパッカーの姿もよく見かける。
そんな中、私はなぜかタスマニア島への旅に心を奪われ、迷わずに参加申し込みをすませたのだ。「ウルル」への憧れがあったにも関わらず、なぜかタスマニア島への魅力に引き寄せられたのは不思議だった。
「なんで、タスマニアなの?」
友人からの連絡で、いつものプールバーに集まることになったので、私はその場にやってきた。友人に予想通りの質問を投げかけられた時、私がなぜタスマニア島を選んだのかをあれこれ考え込んだ。しかし、タスマニアはそれなりに有名な観光スポットのある島である。
友人は、くわえタバコをしながら、巧みにビリヤードの白い手球を6番の的球に命中させた。
先住民であるアボリジニの方々が約3万年以上も前から住んでいたルトルウィタ島は、1803年以降植民地化が進み、イギリスの刑務所が設立されるなど、悲しい歴史を背負っている。その背景からか、タスマニア島にはお化けの噂や怪談が数多く伝えられており、ゴーストツアーや刑務所ツアーが人気を集めている。私が参加するバスツアーにも夜のゴーストツアーが含まれていた。私は正直言って、肝試しや心霊スポット巡りのようなものは苦手だ。しかし、それがツアーの一環として組み込まれている以上、どうしようもないと、その時は軽く考えていた。
北海道よりも小さなタスマニア州の自然に恵まれた名所を、約1週間かけてバスで巡る旅の終着点は、州都のホバートとなっていた。ホバートといえば、あの有名なジブリ映画「魔女の宅急便」の主人公のキキが住み込みで働くかわいいパン屋さんのモデルとなったと言われるパン屋がある、かわいらしい町だ。そのパン屋の前には、まるでキキのような服装をした女性が立っていたという記憶が私には残っている。偶然にもタスマニア出身の友人が帰省中だったので、バスツアー終了後にホバートの町で彼女と合流を計画した。
「ほらね!タスマニア島でも楽しいことがけっこうあるんだから」
私は自身を納得させるかのようにつぶやいて、タスマニア島の魅力を見出すことに没頭していた。そうするうちに、あっという間に出発の日がやってきた。

私は家のオーナーでもあるシェアメイトに、しばらく留守にすることを告げた。彼女はとっても気さくで明るい女性で、私は彼女を信頼していた。彼女の愛犬は私にとっても癒しの存在だった。彼女は家で小さなカフェを経営していて、私はその建物の一室を借りて暮らしていた。カフェの店員たちもとても親切で、私に温かく接してくれた。そのため、私が出発する際には、異変が起きるとは思いもしなかった。
シドニーから飛行機であっという間にタスマニアに到着し、私が参加するツアーの小さな白いバスが停車しているのが目に入った。
さっそくバスに乗り込むと、私以外には7〜8人ほどの人々が、狭いバスの中でひしめき合っていた。私は明るく挨拶をしながら、空いている一番前の席に座った。
バスの運転手は陽気な女性で、その存在にほっと胸をなでおろした。私は人混みや団体行動が苦手なので、少人数のバスツアーは心地よかった。ツアー参加者もみんなフレンドリーで、和やかな雰囲気で旅がスタートした。
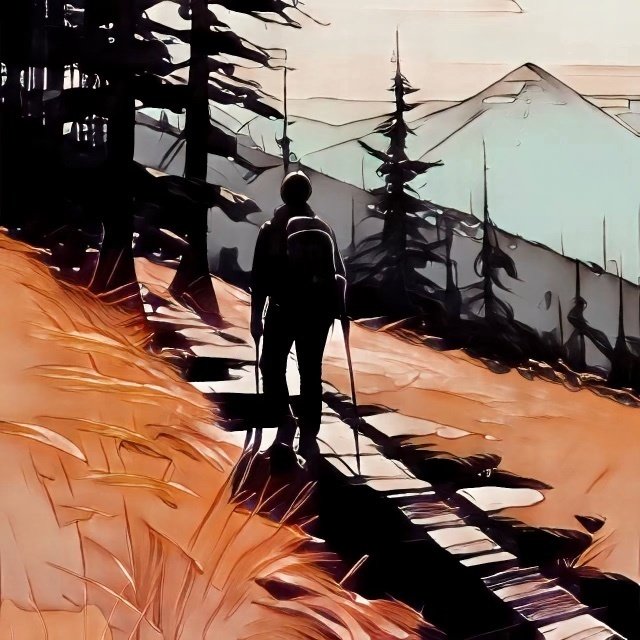
ゴーストツアー
ハイキングやビーチでのんびり過ごし、美しい景色に酔いしれ、星を眺めたり、動物と触れ合いながら、歴史を感じる旅が順調に進んでいった。
例のゴーストツアーは夜に出発することになっており、心霊スポットとして有名な場所を巡るツアーだった。ツアーガイドは、植民地時代の過酷な生活を送りながら亡くなった人々の残した思いや恨みが幽霊となって現れるという話を冷静に語っていた。怖いと同時に興味深いものだった。
(ゴーストツアーというより、夜の観光みたいだな)
私は寒さと眠気によるかすかな疲労感を感じていた。
ちょうどガイドが、幽霊が目撃されるとされる建物について話している最中、私の右後ろに何者かの気配を感じた。気温が低い寒さとは異なる、冷たい空気が私を包み込むような感覚に陥った。
少しだけ首を動かし、後をふり返らずに目だけを後ろにやると、そこには昔の西洋風の服装をした一家が立っているのがちらっと見えた。見たくないと思っているのに、首が勝手に動いてしまう。そして、私は思わず完全にふり返り、その家族の姿をしっかりと見てしまったのだ。
背の高いハンサムな男性は木綿の白いシャツを着て、薄いカーキ色のパンツとブーツをはいていた。きれいな女性は長いスカートを身にまとい、子どもが1人いた。もしかするともう1人子どもがいたような気がしたが、はっきりと覚えていない。ただ、全員が無表情だったことは鮮明に覚えている。ゴーストツアーをしている私たちの団体の方をじっと見つめていた。
(えっ?)
ドッキリを仕込んでいるなんて、ずいぶん手の込んだツアーだなと私は思った。そう思おうとしたのかもしれない。
「あっ、そういうことか…」
私は日頃から幽霊を見ることには慣れているのでそうつぶやいたが、特に驚きはなかった。ただ、その家族の姿はまるで俳優の仕込みのように美しく、一瞬間違えるほどだった。しかし、よく考えてみると色あいが薄く、全く動かずにただ立っている様子から、彼らは生きている人間ではないことを再認識した。
いったいどれくらいの時間が経過しているのだろうか…。
バスツアーに参加していた男性が私の様子に気づいたようで、話しかけてきた。私は黙って、静かにその家族の幽霊がいる方向を指さした。しかし、男性には特に何も見えなかったようで、彼は他のツアー参加者の元に戻っていった。私はツアーの進行を妨げたくなかったので、この秘密を誰にも伝えずに心にしまった。
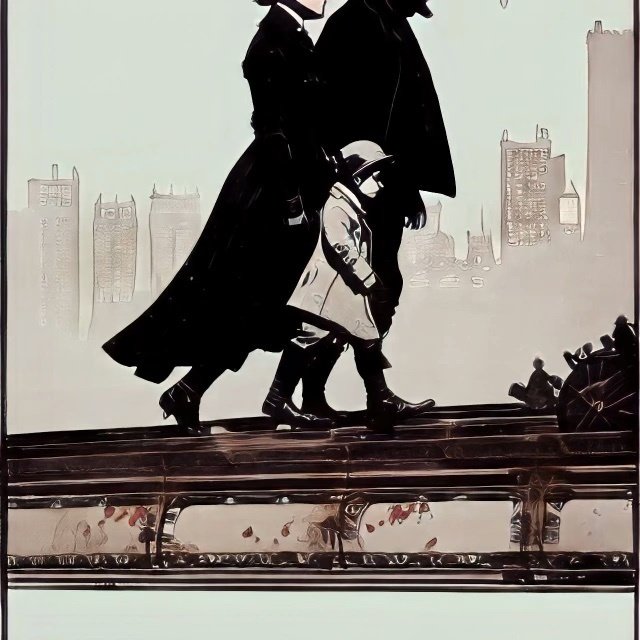
次の瞬間、その家族の幽霊はスッと消えてしまった。子供の幽霊が最後まで私を見つめているのがうっすらと記憶に残っている。その子は、丸いボールのような物を手に持っていたような気がした。何も言葉を発しなかったが、私の注意を引こうとしているような感覚があった。なんとも言えない切なさが、私の心に残った。彼らは決して攻撃的な存在ではなかったので、私はただ彼らを島の歴史の一部として受け入れることにした。ゴーストツアーはその後、何事もなく静かに終了した。

タスマニアデビル
話は変わるが、このツアーでは多くの野生動物と直接触れ合うことができるのが特徴だった。その点については賛否両論あるが、当時はコアラ、カンガルー、ワラビー、ウォンバット、カモノハシ、ハリモグラ、タスマニアデビルなどと触れ合ったり、近くで見ることができた。
特にタスマニアデビルは非常に興味深い動物だ。彼らは黒い体に白いラインが入り、赤い耳を持つ小さなオオカミかクマのような不思議な外見をしている。しかし、そのかわいらしい外見とは裏腹に、鋭い牙を持つ肉食動物だ。観光客の方を見て怯えているように見えたが、餌を与える係の若い男性にはなついているようだった。小さな体で必死に係員の後をついて歩いている姿がかわいらしかった。そのかわいらしい顔が餌を食べる時に口を大きく開けると、鋭い牙がのぞいた。係員が防御手袋をはめて渡す生肉に、タスマニアデビルは荒々しく食らいついた。そこから野生の凄さを感じ取った。
タスマニアデビルの最も特徴的な点はその鳴き声だ。タスマニアデビルの名前の由来には複数の説があるが、イギリスの入植者が「暗闇で聞いたタスマニアデビルの鳴き声がまさに悪魔(デビル)の声のようであった」と考えた説や、「暗闇で目や耳が赤く光って見えたため、悪魔に取り憑かれているのではないか」と考えられた説があるという。
(タスマニアデビルはなんてかわいいんだろう)
動物好きの私は、その時はまったくと言っていいほど、後に起こる出来事に気づくことなく、のん気に動物たちとふれあっていた。

運転手
陽気なバスの運転手が別の運転手に交代するまでは、何の問題もなくツアーは順調に進んでいった。
(次の運転手さんもいい人だったらいいな…)
しかし、そう思ったのも束の間、次の運転手は環境問題に熱心に取り組んでいるらしく、ことあるごとに人間の愚かさを語る少し風変わりな運転手だった。地球温暖化や自然破壊の問題についてただ熱心なだけではなく、怒りを抱えているような様子だった。私は自然保護の重要性は理解していたし、関心もあった。しかし、バスツアーに参加したのは彼と自然問題について議論するためではないので、どこか息苦しさを感じた。
彼は年齢に比べて若作りをしているように見えたが、実際にはかなり歳を重ねているように感じられた。汚れた分厚いセーターを着て、ぼろぼろのカーキのパンツとブーツをはいていた。背が低く、話しかけてくる時にかなり近づいてくるので、それが私に恐怖を感じさせた。
私はあまり彼と関わらないようにしていたが、まるでテレパシーで通じたかのように、彼の矛先は私に向けられた。
「日本人はなんで森林を伐採して箸を作るんだ?」
などと、事あるごとにきれいな景色を楽しむ私に挑戦してくる運転手に対し、初めのうちは、
「私は洗って使える箸を使っていますよ」
などと、答えていた。しかし、運転手の攻撃がおさまらないので、他のツアー参加者が私を助けてくれた。
「彼女が木を伐採して箸を作ってるわけじゃないでしょ」
そう言って助けてくれた女性は、美しく魅力的なイギリス人だった。運転手は彼女には弱いようで、やっと攻撃がおさまった。
さらに、かなり過酷なハイキングの末、見事なビーチに辿り着いた私たちは、喜びに満ちて思わず砂に触ったり、石を手に取ったり、海辺を楽しんでいた。しかし、運転手が突然、凄まじい勢いで駆け寄り、私に向かって叫んだ。
「今、石に触っただろう?全てのものは自然にあるべきなんだ。絶対に触ったり動かしたりするな。元に戻せ!」
私は恐怖に襲われ、言葉もなく手に握っていた石を砂の上に落とした。驚いたツアー参加者たちが駆け寄って、私を助けてくれた。
「なぜ、彼女ばかりを攻撃するの?」
ある参加者の女性が運転手に問いかけた。
「まったく、なぜ、日本人は木を切り倒して箸を作るんだ!」
彼はブツブツと同じことを繰り返し、向こうへ行ってしまった。
残された私たちは、互いに目を合わせ、黙って頷くしかなかった。
しかしながら、運転手の環境問題に関する話はバスの中でもおさまることはなかった。ツアー参加者たちは旅の疲れとともに無言の時間が増えていった。
窓の外の景色は徐々に薄暗くなっていった。わずかに残る薄いピンク色の夕日が、空にかすかな希望を残していたが、それさえも黒い闇に打ち消されるように、漆黒の闇が迫ってきた。まるで私たちの乗るバスを追いかけるかのように、夜があっという間に訪れた。
運転手は道路で車にはねられたワラビーの死骸を見つけるたびにバスを停車させ、外に出てそれを抱きしめ、涙を流しながら埋葬したり、草むらに運んだりした。私たちは黙ってその様子を見守るしかなかった。みんなは今日の宿に早く到着したいと心の中で切望していた。運転手が何度も車を停めるため、あたりは完全に暗くなってしまった。空腹と疲労で私たちはぐったりしていた。すると、
「今日はもう遅いから店は閉まっている。夕食はあきらめたほうがいい」
と、運転手が私たちに向かって言い出したのだ。
(あんなに何度もバスを停車するからでは…?)
と、誰しもが思ったが、口を開く者はいなかった。静寂がバス内を支配し、全員黙って宿に到着するのを待つしかなかった。
他にすることもなく、真っ暗な窓の外を眺めながら、自分の人生について考えることにした。その頃の私は、仕事のペースをわずかに緩め、勉強に力を注いでいた。ただし、学んだことを実際の仕事にどれほど活かせるか不安を感じていた。このまま海外での生活を続けるためには、さらなる努力が必要だと感じていた。
(あぁ、このままタイムスリップできたらいいのに)
その頃の私は不安や疲労感に満ちており、少し投げやりな気持ちになっていたのかもしれない。
「くそっ!」
運転手が何度も叫んでいた。勤務時間がおしてイライラしているのだろう。

宿の女性と猫
そして、やっと宿に着いた時はすでに夜の10時を過ぎていたと思う。運転手はさっさと宿に姿を消し、残された私たちは荷物を持ってバスから降りた。
辺りは暗闇に包まれていて、黒い木々が生い茂っていた。静寂が漂い、本当にこんな場所に宿が存在するのかと疑いたくなるほどの静けさが広がっていた。重たいバックパックを背負うと、まるでビーチの石が詰まっているのではないかと思うほどの重みが感じられた。みんなは黙って宿へ向かう暗い小道をゆっくりと歩いていた。私はみんなの後ろからついて行った。街頭も何もない小道だった。
ようやくたどり着いたその日の宿は、まるでお化け屋敷のような、ハロウィンのようなおどろおどろしい雰囲気をただよわせていた。周囲が暗くて見えにくく、自分がおとぎ話の中に迷い込んだような錯覚に襲われた。

門をくぐると、ほうきを持って、髪の長い厚化粧をした目の大きな中年の女性が出迎えてくれた。私はこんな場所に人が立っているとは予想していなかったので、驚いて一瞬凍りついた。
「こんばんは」
私はその女性に挨拶したが、彼女は口角をあげてにっこりと微笑むだけで、言葉を交わすことはなかった。大きな口が印象的だった。
さらに奥へと足を踏み入れても、薄暗さが残り、視界はぼんやりとしか広がらなかった。私は疲れ果てていたため、何も考える余裕もなく、ただみんなの後ろについて進むことしかできなかった。

同時に、猫が床を歩く姿に目を奪われているうちに、その女性はどこかに消えてしまった。不思議なことに、その後再びその女性と出会うことはなかった。思い返してみると、他のツアー参加者はその女性に挨拶をしていなかった。おそらくみんなにはその女性の姿が見えていなかったのではないか…。とにかく一言も口にしない彼女がとても魅力的でもあり、不気味でもあった。
(ハロウィンの仮装なのかな…?)
そう思い込もうとしたのだが、季節はハロウィンの時期とは関係のない冬だった。最後尾の私は、その女性の気配を背中に感じながら、ぞろぞろと進むみんなの後について前に進んで行った。やわらかなカーブを描くその薄暗いエントランスを抜けると、ようやく先に灯りが見えてきた。

部屋と鍵
「いらっしゃい」
フロント受付の中年の男性が対応してくれた。
「今日は混んでいるので別のツアーの宿泊客と相部屋ですから、あしからず。」
愛想のない中年男性は、無愛想に私たち一行に部屋の鍵を手渡した。ツアー参加者たちと同様に、よく見かける赤いプラスチック製のキーホルダーの鍵をぽんっと渡された。共同部屋なので、特に鍵を確認する必要もなく、ポケットにそれをねじ込んだ。私はみんなの後について部屋番号を探した。ツアーの参加者たちは、
「5番。5番と」
と、言いながら、暗い外廊下のような通路を歩き部屋を探した。
(この宿にはいったい何部屋あるのだろうか…)
迷路のような複雑な形状をした宿のように感じた。外廊下には冷たい風が吹き抜けていた。大げさかもしれないが、このまま永遠に部屋に辿り着けないのではないかと思えるほど、暗くて寒くて、疲れ果てて、お腹もすいていた。
ようやく5番の部屋の前にたどり着いたツアー参加者の女性がくるっとふり返り、最後尾を歩いていた私に対して、
「あなたは何番?」
と、聞いてきた。
「えっと、私は…」
そう言って、私はさっきもらった赤いキーホルダーをポケットから取り出し、書かれている部屋番号をはじめて確認した。
「えっと、6番って書いてある」
「あれ?じゃあ、あなた、私たちとは別の部屋なの?」
と彼女は言って、私を不思議そうに見つめた。2人でしばらく顔を見合わせた。
「でも、フロントの人は同じ部屋って言ってたよね?」
と私は言った。

そんなやりとりの中、私たちは思わず目を奪われる光景に出くわした。どちらともなく同時に5番の隣の6番の部屋を見ようとしたが、私たちは無言で固まった。
なぜなら、2人が同時にのぞいたその先には崖が広がっていたのだ。
ヒューッ。
風の音が響き渡った。
暗い外廊下が続くその宿は、フロントに近い部屋から1番、2番…と順番に番号がふられている。そして、5番の角部屋で廊下が終わり、そこから先には何もなかった。
つまり、6番の部屋など存在しないのだ。
2人で再度その先を確認したが、何度見てもただの断崖絶壁が広がっているだけだった。崖と宿の間には生垣のような木々が生い茂り、ちょっとした塀のようになっていた。暗闇の中にも見えるその先の景色は崖と海。うっすらと海の音が聞こえてくる。
不気味な感覚が私たちを包み込み、一瞬、時間が静止したような気がした。しかし、とりあえず鍵を使うことなく5番の部屋に他の参加者たちと一緒に入り、荷物を置くことにした。納得のいかない思いと疑問が胸の中に漂って、モヤモヤと広がっていた。
「私は下がいい!」
ツアー参加者たちが大声で叫びながら、騒然としていた。
さっそく、2段ベッドの下段の獲得交渉が始まった。別のツアーの宿泊客が到着する前に、私たちは全員で下段を確保した。
誰しもが子供の頃、おそらく2段ベッドの上段を奪い合った経験があるだろう。子供の頃はハシゴを使って上段に登ることが、まるで特別な世界へと昇っていくような感覚を抱かせ、喜びを感じていた。私の2段ベッドは通常の高さよりも低い位置に設定されていた。いとこや友人の家に泊まりにいくときは、通常の2段ベッドに泊まることがあり、それがますます上段に登ることを楽しみにさせてくれた。上段にいると、下段の世界が遠く、暗く、闇の世界のように感じられた。いつから下段の方が魅力的だと感じるようになってしまったのだろうか…。

荷物を置いた後、遅い夕食をとるためにキッチンに向かった。再び、薄暗い廊下をみんなでぞろぞろと進みながら、キッチンを探した。
(本当に迷路のような構造だな…)
運転手は食べ物がないと覚悟したほうがいいと言っていたが、ラッキーなことに手軽なカップヌードルのような食品を手に入れることができた。キッチンスペースでそれぞれ軽食の準備をした。私はサンドウィッチを手に持ち、ハーブティーを飲むためにお湯をわかした。お湯がわくのを待っている間、ツアー参加者たちが軽食を用意する様子ををぼーっと眺めていた。その一方で、鍵のことをぼんやりと考えていた。
(なんで私の鍵だけ6番だったんだろう…)
ピィー。
やかんの音が響き、私は我に返った。
疲れ果てた私たちはそれぞれ軽い夕食をとりながら、古びて広々としたリビング・ダイニングのような部屋で少し談笑した。
ツアー参加者たちは世界各国から集まっていた。フランス、イギリス、ニュージーランド、インドネシアと、私の記憶ではそのような国々出身だったと思う。特にインドネシアの家族は、自国の文化についてユーモアたっぷりに話してくれた。私はアジア共通のあるある話で盛り上がった。疲れ切っていた身体が一瞬緩んだ気がした。
みんな、運転手の話題に触れることはなかった。実際、ここにきてから一度も運転手の姿を見てないことに気がついた。
(そんなことはどうでもいい…)
私は頭を横にふって強く否定した。そして、軽くシャワーを浴びる準備をしようと思い、一度部屋に戻った。
再び、あの薄暗い外廊下を歩いて、5番の部屋に向かった。
(それにしても、寒いな…)
「ん…?」
ふと、誰かの視線を感じるような気がした。
薄暗い外廊下には私以外には誰もいなかった。5番の部屋の前に着いた時、やはり6番の部屋が気になった。5番の角部屋の端から、向こう側をもう一度見るために身を乗り出して覗いた。外壁が果てしなく続いており、その隣には生垣のような塀が延々と続いているだけだった。そして、海の音がかすかに聞こえてくる。外壁と生垣の隙間は細すぎて、人が通れるようなスペースではなかった。
(あれ…?)
また、誰かの気配や視線を感じるような気がした。
(やっぱり、誰もいない)

2段ベッド
「アタシ、上段は絶対イヤ!」
そう大声で叫んで、私の荷物を勝手に持ちあげ、2段ベッドの上に乱暴に放り投げる女性の姿が目に入った。
「それ、私の荷物。私が先に下段に置いたんだけど」
と言うと、ものすごい剣幕でにらみつけて、
「たった今、アタシが下段で寝ることを決めたの。何か問題でもある?」
と、喧嘩ごしに言い返してきた。
当時の私は、わりと自分の意見をはっきりと述べるタイプだった。ところが、その無礼な女性の背後には、宿泊客たちがもめごとをさけたいという明白な表情や心配そうな顔が見えたので、
「問題なし!」
と言って、2段ベッドの上に置かれたバックパックから、シャンプーや石鹸などを取り出すと、私はシャワーを浴びるためにシャワー室に向かった。
「あー、イライラする。ああいう人嫌い」
自分が口に出して言っていることに気がついた。そして、こんなに疲れて眠たい日に喧嘩などしなくてよかったと胸を撫で下ろした。心配そうな人たちの顔を見なければ、言い合いに発展していたかと思うとゾッとした。
(ん…?)
「なんだ、猫か…」
さっきとは別の猫が歩いている。

フロント
まだイライラがおさまらない私は、ブツブツと独り言をつぶやきながら、シャワーの前に鍵を交換するためにフロントに向かった。そこには先ほどの無愛想な中年男性が1人で座っていた。
「あのー、すいませんが、ちょっと鍵が間違っていたみたいなんですよ。これは6番の鍵だと思うんですが、5番の間違いじゃないかと…」
と、私は言った。
「えー?どれどれ」
と、面倒くさそうに言いながら、私の手から赤い『6番』と書かれた鍵をもぎ取り、確認していた。ところが、突然、彼の態度が一変した。
「たっ、大変失礼しました。申し訳ございませんでした。こんなことがあってはならないことです」
と言って、平謝りをしながら、フロントデスクの机の引き出しに手荒くその赤い『6番』の鍵を投げ入れ、ばんっと力強く引き出しを閉めた。そして、すばやく壁から『5番』と書かれた青い鍵をとって私に渡しながらもう一度、
「本当に失礼しました」
と言った。
「6番の部屋を探したんですが、5番の隣に部屋はなかったんです」
私は場の雰囲気を和ませるために笑みを浮かべながら言葉を投げかけたが、フロントの男性は明らかに困惑した様子で、ただ謝罪の言葉を繰り返すばかりで問題解決には至らなかった。フロントの奥の部屋からもれるテレビの音が私の耳に届いた。普段の私なら、もしかしたら訳を聞いたかもしれない。しかし、その日の私は不可思議なことには首を突っ込まないという自然な防御が働いたのだろう。私はあきらめてシャワー室に向かうことにした。
(なんだったんだろ…?スタッフが悪ふざけで6番の鍵を作ったのかな…)
私は何か不可思議な感覚を察知した瞬間、それ以上掘り下げることは避けるようにしている。もともと好奇心旺盛な私は、見てはいけないもの、聞いてはいけないこと、知ってはいけないことを知りたいという欲求を抑えるのが難しい子供であった。しかし、成長するにつれて、知らない方がいいことがあるということも少しずつ理解してきたのかもしれない。それが大人になるということなのか、それとも単に人間としての経験によるものなのか、はっきりとはわからない。ただ、自分にしか見えていないものや聞こえないものという存在については、いまだに混乱を抱えることが多い。身の危険を感じるザワザワとした感覚が襲ってくる時は、身を守る本能が第一に働くようになった。その時も、深く追求することを避け、ただその事実を受け流すことにした。
また、猫が歩いていた。

シャワー室の恐怖
ぴちょん、ぴちょん。
シャワー室に着いた時、水滴がしたたる音が聞こえた。しかし、そこには誰の姿もなかった。
「よかったー。誰もいない!」
このような宿では、朝にシャワーの争奪戦が勃発することがある。私は当時、髪がとても長かったため、朝に髪を乾かすのは面倒だし、シャワーを奪い合うことも避けたかった。だから、こういった場合は夜にシャワーをすませることにしていた。あのベッド争奪の様子を見る限り、朝のシャワーも争奪戦が激しそうだと思われた。
(うん…?)
なんとなく気配がする…。
「あれ?やっぱり誰かいるのかな?」
ぴちょん、ぴちょん。
何度も確認しても、やはりそこには私以外誰もいなかった。だが、常に誰かに見られているような気配が漂っていた。
シャワーを浴び、隣にある洗面台で髪を乾かしていると、たびたび誰かがシャワー室に入っていく気配がした。しかし、何度確認しても私は1人だった。鏡越しに見ても、背後を振り返って見ても、やはり私はただ一人だった。
すると、足音が響き、シャワー室のドアが閉まる音がしたが、シャワーの音は聞こえず、ただ水滴が静かに落ちる音だけがシーンと静まり返ったシャワー室に響いていた。背筋がゾクっとした。
その時、宿に到着した時に出会ったハロウィンの仮装のような中年女性の顔が思い浮かんだ。
ぴちょん、ぴちょん。
「あの人、いったい誰なんだろう?」
ぴちょん、ぴちょん。
その瞬間、また、背筋がゾクっとした。
ぴちょん、ぴちょん。
「まっ、いっか」
私は強気で乗り切るため、一心に髪をドライヤーで乾かし続けた。こんな時に限って、自分の長い髪の毛を見ると少し自分のことをうとましく思う。急いでいる時には、なぜか髪の毛がなかなか乾かないように感じる。むしろ、乾かせば乾かすほど髪がどんどん濡れていくのではないかという幻想が生まれる。
(中途半端に乾かすと、明日必ずボサボサになるんだよな…)
ぴちょん、ぴちょん。
完璧主義とは言わないが、朝の忙しい時間にボサボサの髪を整えるのは面倒くさいだけだ。ただし、この不気味さに耐えるよりも、明日のボサボサの髪の方がまだマシだと思える自分がいた。
ぴちょん、ぴちょん。
(もう、いいや…)
その時、私がそんなことを考えている最中も、どこからともなく何者かの足音が響いてくる。何者かがシャワー室に入っていく気配を感じたが、不思議なことに一向にシャワーの音が聞こえてこない。
ぴちょん、ぴちょん。

ダイニングルーム
荷物を急いでまとめ、シャワー室から飛び出した時、廊下の角を曲がって誰かがこちらに向かってくる気配を感じた。宿泊客がいるのだなと思うだけで、少しは心が安らいだ。しかし、どういうわけか誰も角を曲がって現れない。私は右側から誰も出てこないことに不思議さを感じながら、左に進んだ。
あまり鮮明には覚えていないが、確かに小柄なアジア人の女性が歩いてくるような気がしたのだ。しかし、実際に彼女がいたのかどうか、それすらも思い出せない。ただ、強烈な恐怖が私を襲ったことだけは確かだ。
(まただ!)
その時、私の脳裏にあのハロウィンの仮装のような中年女性の顔が浮かんだ。相変わらず、かすかな笑みを浮かべている。よく考えて見ると、口元は笑っているが、大きな目は笑っていないように思えた。
逃げるように部屋に戻ると、例の下段のベッドを横取りした女性のグループと私のツアー参加者たちが楽しそうに談笑していた。私は軽く会話に参加したが、彼女たちの中には差別的な発言が多く、心地よい雰囲気ではなかった。
「アンタの発音はイギリスなまりの英語だよね」
「そっちはニュージーランドなまりだよ」
「アンタはどう考えでも日本なまりの英語。○▼※△☆▲※◎★●」
「あははは!」
一応話に加わったことを後悔した。この会話のどこが面白いのか、私には理解できなかった。爆笑している女子たちの声がカビ臭くて古い壁に反射して響いていた。私は上手に愛想笑いができているのか、自信が持てなかった。
そこで、1人でダイニングに向かうことにした。また、薄暗い外廊下をぬって一人、ダイニングの方へと向かった。
(冷え込んできたな…)
オーストラリアといえば、ハワイや沖縄などの夏の暖かなイメージを持つ人が多いのかもしれない。実際、私もその一人だ。日本から初めてやってきた時は真冬の季節だった。こんなに寒いとは予想していなかったので、薄手のジャケットしか持ってこなかったことを後悔していたが、それが懐かしい思い出として心に残っている。
(もうすぐ、約一年か…)
真夏のオーストラリアは気分も開放的になり、笑顔が絶えないような気がする。夏のイベントやマーケットなど、屋外で楽しむイベントが多く、心も踊る。しかし、冬は雪が降る地域はほとんどないものの、気温が急激に下がる。ただし、雪国のようにしっかりとした暖房設備を備えた家は少なく、底冷えがするような寒さが辛い。簡易的な温風機が一般的で、寒さに敏感な私は常に厚着してをして寒さをしのいでいた。この宿には温風機がないようだ。
その時、猫が目の前をひょいと横切った。
(いったい何匹の猫がいるんだろう…?)
私は猫が好きだが、猫アレルギーを持っているために触ることができない。本当は人懐っこい猫ならば撫でてあげたいのだが、残念ながらそれができない。ただ、この宿の猫たちは特にフレンドリーではないようだ。むしろ、猫たちは自立心を持った存在のように感じられる。宿泊客に寄り添ってくるような態度も見せない。もしかしたら、私が猫アレルギーであることを察知しているのかもしれない。

ダイニングにはまだツアーの男性参加者が集まって談笑しており、彼らと少し話を交わした後、別のツアー参加者としてやってきた日本人とも出会い、少し会話を楽しんだ。女子軍団の寝室での会話に参加するよりも、こちらでの会話の方が少しだけマシだった。
「こんばんは」
私は日本人の男性に挨拶をした。
「えっ、日本人だったんすか?」
彼は驚いた様子で尋ねてきた。
「アジア系のこっちの人かと思いました。英語をどうやって勉強したんすか?」
彼はオーストラリアの有名な観光地をバックパッカーとして巡っている最中のようだった。ケアンズにはたくさんの日本人がいるから、英語を話さなくても平気だと教えてくれた。でも、せっかくお金をかけて海外にきているのだから、そろそろ日本人とばかり連んでいないで、もう少し本格的に英語の勉強がしたいと思っているそうだ。海外にいると、普段では出会えなかったり話せなかったりする人々と出会える面白さがあるように思う。「一期一会」という言葉を意識するようになったのは、こうしたできごとがきっかけのように感じる。
リビング・ダイニングになっているその空間は異常に広くて、湿気が漂い、カビ臭く、暗く、じめじめとした感じがあり、また肌寒い雰囲気も漂っていた。それゆえ、あまり心地よい場所ではなく、どこか落ち着かない印象を受けた。その場所には、年季の入ったアンティーク調の暖炉が備えられていた。しかし、その暖炉は単なるインテリアの一部となっており、実際に火が灯ることはなかった。
その広い空間に各ツアーの宿泊客が思い思いに過ごしている。火が灯らない暖炉の前のソファーに座って、ボードゲームを楽しむ人たちが目に入った。
(この暗くて長い夜を、今までどれだけの人々が、あの暖炉の前に座って過ごしてきたんだろう…)
壁際に古めかしいアンティーク調の椅子が何脚か無造作に置かれている。私は椅子を見ると、実際に誰も座っていないはずなのに、過去に誰かが座り続けてきたであろう残像のようなエネルギーを時折感じることがある。そしてその日も、誰も座っていないはずのアンティークの椅子に、なぜか誰かが座っているような気がした。
床には、かつて高級品であったであろうペルシャ絨毯のような柄の赤いカーペットが広がっていた。ところが、その絨毯の上には宿泊者たちがお腹を満たすための現代風の安っぽいテーブルが無造作に置かれており、宿泊者たちが土足で絨毯を踏みつけるので、埃っぽくて薄汚れている様子がうかがえた。
寂しい気配の中に埋もれて、埃をかぶった誰にも見向きもされることのないアンティークの小物が静かに存在していた。私はアンティークに興味があり、骨董品屋を訪れることも好きだ。海外の田舎町には、日本から買い付けに訪れるバイヤーが見れば飛び上がって喜ぶであろう、貴重なデットストックやレアな品々が、信じられないほど安値でごちゃ混ぜにに売られている古道具屋や古着屋が時おり存在する。私自身は買い付けをするわけではないが、そうした場所を散策するのは楽しい。
しかし、そのリビング・ダイニングに置かれたアンティークたちをじっくりと眺める気分にはなれなかった。先ほどアンティークを見て歩くのが好きだと言ったが、例外がある。どんなに魅力的な骨董品であっても、絶対に触りたくないものもある。誰も座っていないのに誰かが座っているような感覚を与える椅子と同様、小物にも過去の所有者の感情やエネルギーのようなものを強く感じすぎて、恐怖心がわいてくることも少なくない。一方、自分の好みでもないはずなのに、黒猫のポストカードのようなものになぜか手が伸びてしまうこともある。物に宿る不思議な力を感じるのは私だけではないはずだ。
(こんなに寒いのに、なんで暖炉を使わないんだろう…)
私は寒いのでしぶしぶ女子軍団のいる部屋に戻ることにした。
また例のごとく、薄暗い外廊下を一人で静かに歩いていた。
突然、またあのハロウィンの仮装のような中年女性の顔が脳裏に浮かんだ。しかし、彼女はもはや微笑むことはなかった。無表情で、何かを思案しているような印象を受けた。

悪魔現る
部屋に戻ると、なんと電気は消され、真っ暗だった。明日も早いし疲れているので、みんな早く寝る準備をしているようだった。あまりにも真っ暗で、どこに何があるかを把握するまでには少し時間がかかった。私は突き当たりにある自分の2段ベッドの位置を把握し、手を伸ばしてハシゴをつかんだ。
ギシ、ギシ、ギシ…。
私はハシゴを使って2段ベッドの上に登った。
(2段ベッドに登るなんていつぶりだろう…)
しばらくの間、眠りにつくことができなかった。幼い頃、弟と2段ベッドで遊んだ懐かしい思い出が浮かんでは消え、頭の中にはあてもなく彷徨う思考が広がっていた。
幼い頃、両親が少し風変わりなL字型の2段ベッドを用意してくれた。その時、弟がなぜか下段を選びたがった。私はこだわりの強い弟が、当然上段を選ぶだろうと思っていた。だから、上段交渉の方法考えていたのだが、彼が下段を望むと知った瞬間、拍子抜けしたのを覚えている。普段から何事も譲る姿勢を取っていた私だが、2段ベットに関してはどうしても上段が欲しかった。上段をもらって嬉しいはずなのに、なぜか喜びに包まれることができなかった。
それと似たようなことがその後もう一度訪れた。中学生の頃、おのおのが子供部屋を選ぶ時がやってきた。私は絶対に角部屋で、2つの窓がある部屋を手に入れたかった。弟も同じように思うだろうと思っていた。どのように交渉すればいいのかを考えていると、弟は好きな方を選んでいいと言ってきた。結局、その時も私が思い通りに好きな方の部屋を選ぶことができた。その後、弟は原因不明の病気にかかってしまった。
(きっと私が窓が2つある風通しのいい部屋を選んでしまったからかな…)
角部屋を選んだ自分に罪悪感を感じていた。
再び2段ベッドの話に戻るが、弟は「お化けごっこ」と名付けてよく私を下段からからかってきた。私が上段で本を読んだり、うとうとしていると、
「ワン、ワン、ワン」
下段から犬の鳴き声が聞こえてくる。弟が犬の真似をしているのだ。私はなぜかそれが非常に怖くて嫌だった。弟は私が怖がるのを見るのが楽しいらしく、いつも予期せぬ瞬間に私を驚かせてきた。
「ワン、ワン、ワン」
子供にしか理解できない独特の世界だ。今となっては、なぜあんなに恐怖を感じていたのか理解できないが、とにかく上段にいると下の闇の世界から守られているような魔法の場所のように感じていた。
ギシ、ギシ、ギシ…。
弟は時折、お土産を持って上段に登ってくることがあった。そのお土産とは彼のお気に入りの絵本やぬいぐるみだった。
(上段に登ってきた弟を、そのまま上段で守っていれば、下段の闇の世界にひきずりこまれた彼は病魔に襲われることはなかったのかもしれない…)
そんな考えがふと浮かんだ。
すると、下段のベッドから轟音のようなイビキが響き渡ってきた。
「ガゴー、ガゴーッ」
(あの人、すごいイビキ…)
そう思ったのも束の間、私も長旅と奇妙な運転手との出来事によって疲労が蓄積されていたのか、知らぬ間に深い眠りに落ちてしまった。ただ、壁の向こうからはまだ宿泊者たちが談笑する声が聞こえてくるような気がした。
(あの人たち、まだ寝ないのかな…)
そう思ったのを最後に眠りについた。
どのくらいたった頃だろう。
「うーん、うーん」
誰かがものすごく低い声でうなされているのが聞こえてきた。すぐに下段の女性の声だとわかった。彼女の声は苦しげで、まるで首をしめられているかのようだった。暗闇に包まれた部屋では何も見えず、私は心配になった。すると突然、
ギシ、ギシ、ギシ…。
ふと、何者かがハシゴを登ってくる音が耳に響いた。闇に包まれた空間で、私は目を凝らしてハシゴのかかった自分の足元の方に視線を向けた。
ギシ、ギシ、ギシ…。

ひょこっと姿を現したのは、黒くてしなやかな体を持ち、キリッとした眼が光り、口元にニヤッと笑いを浮かべる何者かだった。まるで全身タイツをまとったような姿をしており、私は驚きのあまり、その存在と目があったまま身動きが取れなくなってしまった。猫のような小さな耳としなやかなしっぽが特徴であり、まるでアメリカのコミックに登場するようなスタイリッシュなキャラクターのように見えた。
「え?またハロウィンの仮装?」
一瞬そう思おうとしたが、その種のダマシは通用しないことは一目瞭然だった。
その細身の明らかに悪魔のような存在が、ヒョイっと私のベッドに飛び乗り、近づいてきた。
(なんて軽やかな動き!)
私は驚きを通り越して感心してしまった。その存在はあまりにも美しく、男性か女性かというよりも、ジェンダーレスな印象を与えた。悪魔は2段ベッドの上で身をかがめていたため、はっきりとしたサイズはわからなかったが、小柄で私よりも背が低いように思えた。その得体の知れない存在がなぜ私の前に現れたのか、全く想像がつかず、ただ見惚れていた。
相変わらずうなされている下段の女性をちらりと見やった後、悪魔は私にニヤッと笑いかけた。その瞬間、悪魔が下段の女性を苦しめているのだと理解した。悪魔は一言も発さず、ジェスチャーだけで私に話しかけてきた。
その姿が実にチャーミングで、私はついこの悪魔の虜になりそうな感覚に陥った。しかし、私の内なる防御力のようなものが同時に「気をつけろ!」と警告しているのも感じた。心を奪われてしまうと危険だという一つの思いが、自分の魂をかろうじて自分の体の中にとどめているような感覚があった。

スッと人差し指を伸ばし、まるでマジックでも披露するかのように壁を指差した。何の変哲もないカビ臭い古びた宿の殺風景な壁が、私の顔のすぐ横にそびえたっていた。私は相変わらず悪魔の魅力に呆然としながら、美しい指先が指す方向を見つめていた。
すると、突然壁に丸い穴が開いたかのように見え、壁が透けて光景が浮かび上がった。さっきまで私が居た、あの広いリビング・ダイニングだ。眠る直前まで聞こえてきたツアーの男性参加者の談笑する姿は、その場には存在しなかった。暖かそうな暖炉の前で、昔の格好をした人々が楽しそうに談笑しているのが見えた。まるでゴーストツアーで見た幽霊の家族のような服装だった。
彼らが何を話しているのか、なぜそこに座って楽しそうに談笑しているのか、そしてなぜさっきまで火が灯っていなかった暖炉に突如として暖かな炎がゆらいでいるのだろうか。私は目の前に広がるその光景に困惑していた。かすかに英語らしき言葉が聞こえてくるような気がした。
そして、同時にフロントの無愛想な男性の顔が、今見えている光景の右上に浮かんだ。しかしながら、彼はその壁の向こうの光景の人々の中にはいないことが明白だった。フロントの男性は下を向きながら、引き出しから何かを取り出して見ている様子だった。彼の手の中に握られたものは、あの赤い6番の鍵のように見えた。
私は金縛りにはあっていなかったが、その光景に圧倒されて体が硬直したままだった。しばらくの間、その過去の人々の光景を見つめていたが、ゆっくりと目を悪魔の方に戻した。悪魔はなんとも言い難い悲しげで哀愁ただよう表情で、その光景を見つめていた。そう、まるで何かを懐かしむように…。そして、再び私を見るやいなや、サッと身をひるがえし、去って行った。

私はしばらくの間、固まったまま呆然としていた。
(今のは、いったいなんだったんだろう…)
普段は深入りしないようにしていた不可思議な出来事について、その時ばかりは考えずにはいられなかった。私は横になったまま再び眠ることもできず、さまざまな思いが頭を巡った。
(あの壁の向こうで談笑していた人たちは、この土地の住人だったのかな?)
(もしかして、6番の部屋は彼らの部屋だったのかな?)
(悪魔はなんであんなに寂しそうな表情をしていたんだろう…)
(あのフロントの男性、いったい何を隠しているんだろう…)
そんなことを考えながら、気がつけば眠りに落ちていたのだった。

朝と猫
目が覚めると、朝の光が室内に差し込んでいた。私は凍えそうな体を暖かいお風呂で解きほぐしているかのような感覚に包まれた。寒い日の優しい朝日に救われるような気分だった。暗闇も悪魔も、朝日の光に隠れてしまったのだろうか。昨夜限りの相部屋の人たちはすでに出発してしまったのだろう、そのことに気づいた。
「私の下の人、かなりうなされていたけど、だいじょうぶだったのかな?」
私はツアー参加者にそう尋ねてみたのだが、
「さあ…。あたし達が起きた時にはもうみんないなかったよ」
「とくに何にも聞こえなかったけど…」
誰も気づいていない様子で、下段の女性の安否を確かめる手段は私にはなかった。あんなに大きな声でうなされていたのに、誰にも聞こえなかったというのは信じがたい。あの悪魔のことを口に出すことはできなかった。もし他の人に話してしまったら、何か不吉なことが起こりそうな予感がしたのだ。特に悪魔に口止めされたわけではないが、それを口に出すべきではないという強い直感があった。
さあ、朝のシャワー争奪戦の時間が訪れた。私はシャワーを使わないため、優雅に洗面台の前で歯をみがいていた。朝のシャワー室は夜と比べ明るく、少しだけ気分が軽くなった。ツアー参加者のきれいなイギリス人の女性が私の隣に立ち、今日の予定などについて会話をしながらそれぞれ準備を整えていた時だった。
(うん?)
2人同時に強い視線を感じて、同時に上を見上げた。

すると、そこにはたくさんの猫たちが集まり、天窓にびっしりはりついてこちらを見ていた。およそ5〜6匹以上はいたと思う。彼らの目はまるで何もかも知りつくした証人のような眼差して、瞬きもせずにじっとこちらを凝視している。私は息をのんだ。
「きゃーっ」
イギリス人女性は驚きの声をあげたが、お互いに猫たちの存在に触れず、さっきまで話していた旅の話題を続けた。猫たちは相変わらず、じっとこちらを見つめているのを感じた。私もドキッとしたが、昨夜、誰かが見ている気配を感じたことが、今の猫たちの様子を見てなんとなく理解できたような気がした。
その瞬間、再び昨晩出会ったハロウィン風の女性の姿が脳裏に浮かんだが、私はイギリス人女性にそのことは言わなかった。あの印象深いハロウィン風の中年女性の正体が、実は猫だったのではないかと思うのは、私だけなのだろうか…。
The End

おわりに
冒頭でもお伝えしました通り、この怪談には劇的な結末はありません。ただし、タスマニアの入植者の過酷な暮らし、土地を奪われた先住民のアボリジニや野生動物たち、そして刑務所の囚人たちなど…。さまざまな人や動物たちの歴史がこの小さな島に刻まれています。その中には私たちが解明できない不思議な出来事も多く存在するのかもしれません。
不思議な空間に足を踏み入れる時、いつも次元が異なる別の空間に迷い込んでしまったかのような感覚がします。全ての歯車が噛み合った時、きっと私たちは非日常の空間に迷い込んでしまうのではないでしょうか。
それにしても、私にとって印象深いのは、あの悪魔との出会いでした。悪魔は不思議で怖い存在でありながら、私に対して友好的でした。もし私が言い合いをして下段のベッドを奪っていたら、私がうなされる側になっていたのでしょうか…。また、あのハロウィン風の中年女性も気になる存在です。彼女の正体が猫である可能性も考えられますし、悪魔と彼女には何か関連があるのかもしれません。以来、ハロウィンの仮装を見るたびに、私は何とも言えない気持ちになるのです。
「シェイプシフター」という一言で簡単に片付けられるものではないのかもしれません。この体験には「人怖」という領域も関わっているように思えてなりません。同じ人間としてこの次元に存在しているにも関わらず、時折人格が変わったかのように怒りを露わにしたり、醜い部分をさらけ出すこともあります。もしかすると、本人自身もなぜそんな行動をするのかについて気づいていないのかもしれません。果たして私たちが見えていると信じているこの次元だけが、実際に存在しているものなのでしょうか。
バスツアーは無事にその宿を出発し、途中で奇妙な運転手さんから普通の運転手さんに交代し、無事に最終目的地のホバートの町に到着しました。ツアー参加者と別れを告げ、待ち合わせしていた友人が私を迎えに来てくれました。彼女はさっそく私を連れて刑務所ツアーへと車を出発させたのでした。そして刑務所でも、また不可思議な体験が私を待ち受けていたのです…。
私がタスマニアからシドニーに帰宅すると…。いつもしっぽをふって私を喜んで迎えてくれるはずのかわいい犬が、姿を見せません。首を傾げながら、私は部屋の前に立ち、ドアを開けました。なんと、私の部屋はもぬけの空。すべてのものが運び出された後だったのです。私は何が起こったのか瞬時に理解できず、部屋の前で鍵を持ったまま立ち尽くしました。カフェの店員が慌てて駆け寄ってきて、謝罪の言葉と共にこう言いました。
「本当にごめんなさい。あなたの部屋はもうないの」
「はっ?」
私は混乱しすぎで状況をすぐに受け入れることができませんでした。
「とにかく、ごめんなさい。あなたの荷物は別のアパートに全部運び出したの。大変だったのよ。色々あってね…。私たちももう時期クビよ」
この話はまた別の怪談へとつながりますので、今回はここまでにしておきましょう。
「みなさんは、この怪談をどんな風に解釈しますか?」
Kitsune-Kaidan

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
