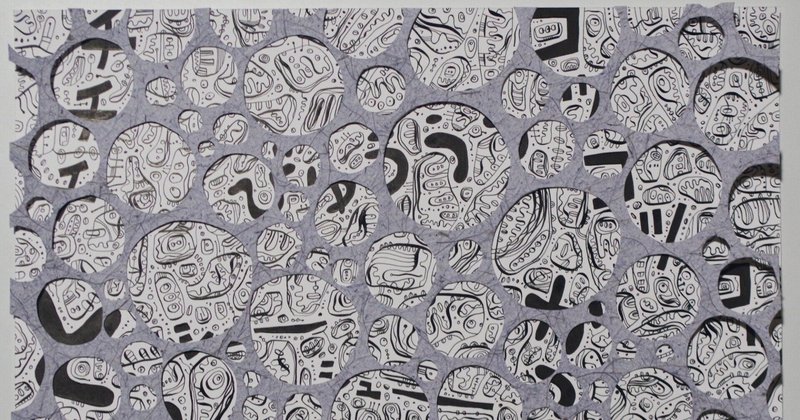
お求めなのが速度であれば。
「書くだけなら、書けます」
職場で、文字を書く機会を与えてもらったとき「できる?」と聞かれると、このように答えてしまう。その回数も二度、三度と重なってきた。もう少しわかりやすく、このざっくりとした程度が伝わらないものかと思う。
例えば、企画書を書くだけなら書ける。まず現状を確認した上で、このまま先に進んだ場合のイメージを描く。そこに足したいものや足りないもの、摩耗していくものや、工数が減らせそうなものを探して書く。今、何に困っているのか、そもそも困っているのか。その一つを勘で選んで書く。それだけなら、大して難しいことではない。
しかし、その企画が取り上げるに値するか、検討に値するか、実行に値するかはまた別の話である。現状は日々移り変わり、仮組みした土台を固めながら先へと進まなくてはならない。一度基準を決めても、実行の段になって基準を守れないことはザラにある。そういった企画は、そもそも練り上げの段階で粗があると見て良い。関わる人がスムーズに動きやすい形ではなく、理想の状態へと一足飛びに行くよう無理な動作を組み込んだために歪みが生まれるのだ。
それを避けるためには、企画の品質を上げなくてはいけない。例えば、大して問題ではない状況を既知の問題として取り扱っていないか。起きている問題への解決策として、問いと解という対応が取れているか。何より、今現状に至るまでにはどのような要素が絡み合っていたかを書き表せるか。いくつもの基準を設けて、考え事をフィルターに通す。そうして残ったものの中から更に「他人に選ばれたもの」だけが生き残る。
良いものではなく、選ばれたものが生き残るのだ。そこにいる関係者たちが「これならやっても良い」と手に取ったものが選ばれる。それは一番好みなものを選ぶ楽しみもあるし、悪いものの中で一番マシなものを選ぶ感覚に近いだろう。とにかく、良いと思ったものが必ずしも採用されるわけではない。また、客観的に全てのデータが最有力を示していたとしても選ばれるとは限らないのだ。
そうした土台の上でだが「一旦、書面にまとめてほしい」というオーダーに対しては、これらの工程を浅く踏んで提出することがある。これが、書くだけの状態である。少なくとももう一歩、精査する余地を残した前提であったり、もう二つ解決策を出して差をみるということもない。目標も、現状から逆算したもののうち一番印象に残ったものにパッと飛びついている。それが最も解決すべきポイントである根拠が浅い。
相手の求める文章であるかが、文字の世界においてはかなり大切だ。そのうえで、ただ書くだけなら書けるのである。要点を漏らしていないか、細部に間違いがないかを確かめる手順を省略して、まず文字としてそれらしいものを早く作る。砂をかき集めて山を作り「ひとまずこれくらいの量でどうでしょうか」とさじ加減の確認をするのだ。そのあとで、密度や素材を変える。場合によってはもう一度作り直したほうが早い。しかし、一度枠を作ってしまえば、その枠組み内に収めるのが上手い人に仕事を回せる。もしくは「ここの表現が違う」と指を差して教えてもらうこともできる。
とにかく枠を組むだけなら、大抵簡単に終わる。むしろ私の場合は枠の中に収めることのほうが難しい。文字数も「千文字以上」のほうが「千文字以下」より楽だ。千文字以上なら、書き上げてから更に足すことができる。それに、千文字を超えていると分かれば書き上がってから見直さずともノルマはクリアできる。
しかし、千文字以内は文字数以下に収まっているかきちんと確認しなくてはならない。また、大体九百文字くらいのニアピンを狙わねばならないため、書きながら考えることが多いのだ。
ともあれ、書くだけなら書ける。それはエッセイも同じである。質より量というわけではないが、量の質感を確認することが必要な場面もあるのだ。ここまでだいたい、千文字と半分。スクロールしたときの長さで、二千文字まで来ているかは感覚でつかめる。
オーダーメイドに仕立て上げるのは難しいが、ザッと文字を並べてそれらしく整列させるのが特技だ。内容や誤字脱字のチェックは苦手項目なので、ソフトに一度任せたり一日寝かせてみたりする。書くときの私と読むときの私はできるだけ距離が空いている方がいい。修正した後にも、また時間を開けて読むことだ。書き上げたものが、適切な形で相手に届く体裁をたもっているかを確認するには一度寝てから読むか人に読んでもらうほうが良い。
特にエッセイは、投稿してから誤字を修正することも多々ある。ともあれそれでも、書くだけなら書けるのだ。
ここまで読んでいただいてありがとうございました。 感想なども、お待ちしています。SNSでシェアしていただけると、大変嬉しいです。
