
掛軸 十六幅目から二十幅目
十六幅目 圓同大虚無欠無餘
圓なること大虚に同じ、欠ること無く餘ること無し。
太虚は大空・宇宙を意味します。
円は宇宙と同じで欠ける事なく、余ることも無い。
欠けると言うことは、必要としている。
余ると言うことは、必要としていない。
そのどちらもない。
必要という考えすらない。
それが宇宙であり、円である。
という深い解釈もあります。
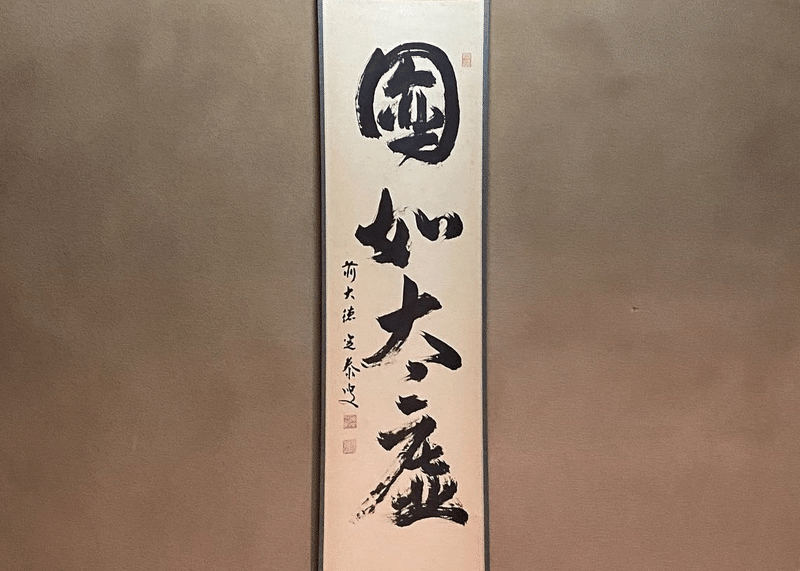
「圓同大虚無欠無餘」
十七幅目 竹上下節清風起
1年の節目に門松で竹を飾り、上半期下半期の節目には七夕で竹を飾ります。
日本の風習に竹は必要不可欠ですが、少しずつ文化離れが進み、竹の節目も知らない方々がいるそうです。
竹を知らなければ、清風も感じられないですが、それを伝えるのが文化かも知れません。これを節目に知って頂きたいですね。

「竹上下節清風起」
十八幅目 唯吾知足
龍安寺にある蹲が有名で、四文字のそれぞれにある「口」を重ねたデザインになっています。
知足とは足るを知ること。自分の身分をわきまえて、それ以上の事を求めないこと。満足すること。
唯吾知足
私は、満ち足りていることだけをしっている。
不満を感じず満ち足りた心を持つことが大切だということです。

「唯吾知足」
十九幅目 諸悪莫作衆善奉行
軸を見ると難しく感じるかも知れませんが、
悪いことはするな、良い事をせよ。
という意味です。わかりやすいと思います。
内容も3才ぐらいの小さな子でもわかります。ですが、その通りできるのか…80才を超えた翁でも難しいかも知れません…
善いことをする、悪いことをしない、それが仏教の極意であることは皆知っているが、そのとおりできる人は稀である。
南方録に、こんなエピソードがあります。
利休は茶の湯の極意を聞かれ
「夏はいかにも涼しいように、冬はいかにも暖くなるように、炭は湯の沸くように茶は服の良きように、これが秘伝のすべてです。」
と答えました。
聞いたものは
「それは誰もが解っていることです」
と返します。
利休は
「それならば、その心得が出来た茶を見せて下さい。客にまいり、あなたの弟子になります。」
と返しました。
そこに笑嶺和尚がいまして
「利休が言ったことはもっともである。『諸悪莫作 衆善奉行』と鳥窠和尚が答えられたことと同じである。」
と言いました。
どうぞ、今日も、涼しさのあるお茶を。

「諸悪莫作衆善奉行」
二十幅目 本来無一物
本来、何もない。
空っぽである。
物に囚われてはいけない。
欲もいらない。
五欲という言葉があります。
色・声・香・味・触の五境。
それを感じる五感。
この五つが引き起こす欲望を五欲といいます。
欲はいらないでしょうが、
五境・五感は必要では?
必要という感覚は欲ですね。

「本来無一物」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
