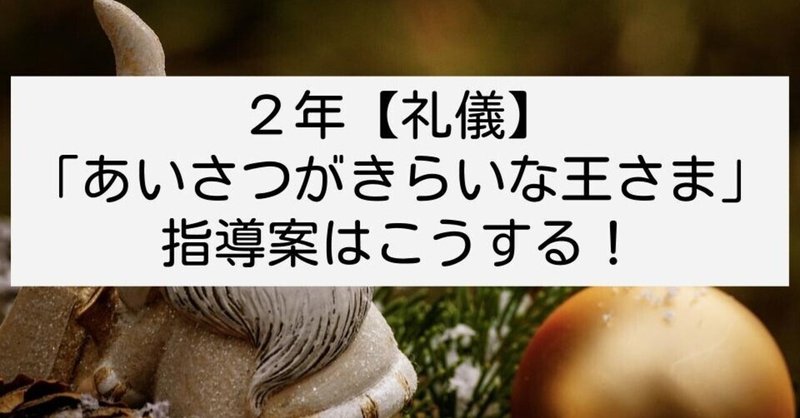
2年「あいさつがきらいな王さま」【礼儀】の指導案はこうする!
こんにちは。
今日は『2年「あいさつがきらいな王さま」【礼儀】の指導案はこうする!』
このテーマで教材解説をします。
今日は道徳の「礼儀」です。
低学年の教材を取り上げます。
日本には、「道」とつくものが多くあります。
柔道、剣道、華道、茶道、合気道など。
これらは、型を重んじています。
型から入り、型に心を込める。
心や本質を知ってから始めるのではないのです。
礼儀も同じです。
心を込めても、動作に表れないと相手には伝わりません。
まずは型(動作)から入り、心がその後で込められていくのです。
ここを押えた上で、授業をしてくださいね。
では、解説です!
1 教材について
2 内容項目と教材
3 導入
4 発問
5 まとめ
順番に解説します。
1 教材について
B 主として人との関わりに関すること
「礼儀」
1・2年の目標・・・・気持ちのよい挨拶、言葉遣い、動作などに心がけて、明るく接すること
2年生「あいさつがきらいな王さま」(日本文教出版)
あらすじ
王様はいろんな人にあいさつをされるので、うるさいという理由で、国中であいさつを禁止しました。
うっかりあいさつをしてしまったパン屋さんや子どもがろうやに入れられてしまいました。
暗くてさびしい国になって、王様も暗い気持ちになっていきました。
ある日、歌声が聞こえてきたので、王様が行ってみると、ろうやの中から聞こえてくる声でした。
「おはよう、おはよう。」
それはとても楽しそうな声でした。
何日か経って、王様はばったり会った家来に「やあ、おはよう。」とあいさつをうっかりしてしまいました。王様は、あいさつをしたおかげで暗い気持ちがいっぺんにふっとんだことに驚きました。
「そうか、あいさつはこんなに気持ちのいいことだったんだ。」
王様は自分が間違っていたことを謝り、あいさつ禁止もやめました。
この国は、あいさつがとびかって、ずっとずっと笑い声のあふれる楽しい国になりました。
2 内容項目と教材
①実は難関教材
シンプルに見えて、実は難しい教材です。
なぜなら、あいさつのない世界を子どもたちは体験したことがないからです。
学校では「あいさつをしましょう」と指導されるので、あいさつをすることが当たり前になっています。
子どもたちが過ごしている今の生活は間違いなく、「あいさつのある世界」なのです。
『いや、あいさつをしない子もいます!』
こう思うかもしれません。
しかし、「あいさつをしない子」に気付くということは、
『あいさつをすることが当たり前の世界になっている』ということです。
あいさつをしない子自身も、しないことを指導されたり、友達からあいさつをされることで、
あいさつを意識するということは、「あいさつのある世界」に生きている一人で間違いないのです。
問題は、「あいさつのない世界」をどのように認識させるかです。
この点をどう扱うかが、この教材の難しさになります。
「あいさつのない世界」を体験させようと思うと、一時的にでも「あいさつ禁止」のルールを作ってやってみる必要がありますが、日中に数時間禁止しても意味がないでしょう。
子どもたちがあいさつを一番するタイミングは「朝」だからです。
「おはよう。」を言ってはいけないことが、どれだけ苦しいかを体験できなければ、この教材の本質の部分を味わうことができません。
また、学年全体や学校全体で「あいさつ禁止」の世界を試してみることも、現実的ではないでしょう。
②解決策
では、この教材はどのように扱えばいいのでしょうか。
こうなると、「想像する」しかありません。
あいさつをしない、あいさつを禁止されている世界を想像するようにします。
子どもの経験の手がかりとして、「あいさつをしなくて気まずい思いをした経験」を話し合います。
誰でも、次のような経験はあることでしょう。
・あいさつをするタイミングを逃して、ずっと気まずいままだった。
・あいさつをしたけど、返してくれなくて悲しい気持ちになった。
など、あいさつについてのマイナスな経験について、話し合います。
そして、そのことがずっと続く世界のことを想像します。
あいさつは、相手がいるから成り立ちます。
あいさつができないということは、相手との関係を成り立たせないということです。
あいさつをしないと・・・・
・相手の存在を認めていないことと同じ。
・相手のことを思いやっていないことと同じ。
・自分には関わってほしくないというメッセージを発していることと同じ。
低学年の「礼儀」は、「親切、思いやり」と質的には似ているので、
相手のことを考えることが礼儀、という理解で進めていいです。
つまり、「あいさつのない世界」は、相手のことを尊重しないし、自分のことしか考えない。
思いやりのある人は悪い人と認定される、そんな世界なのです。
ギスギスして、暗い気持ちになって当然ですよね。
それを、「あいさつをしなくて気まずかった経験」から広げて、想像させることで展開していきましょう。
③王様の変化を考える
展開のアイディアとして、王様の心の変化を考える活動があります。
最初の王様は、言ってみたら充分な「あいさつ」に囲まれている生活だったのです。
周りはきちんとあいさつをする人だらけだし、王様にきちんとあいさつをしようとした。
それを王様は、「うるさい」と思うだけで、「気持ちいい」とは思わなかったのです。
しかし、あいさつを禁止して、「あいさつのない世界」にしてみることで、
あいさつの重要さに気付いたのです。
そして、再びあいさつのある国になって、楽しい国になりました。
このときのあいさつの数は、最初よりも増えたのでしょうか?
あいさつが増えたから、楽しい国になった?
あいさつの量は増えてはいない?
あいさつの量が変わっていないとすれば、変わったものはなんでしょうか。
1つは、王様の心です。
あいさつで人とつながろうとする気持ちが王様に芽生えたので、
王様自身が「楽しい国だ」と思えるようになったのでしょう。
また、王様のように、これまであいさつを「うるさい!」と思っていた人もいるかもしれません。
その人も、王様と同じように「あいさつはいいものだ。」と思ったことでしょう。
最初と最後の王様の変化を考えてみる活動も、有効ですね!
3 導入
T:教師 C:子ども
ここから先は
¥ 1,000
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
