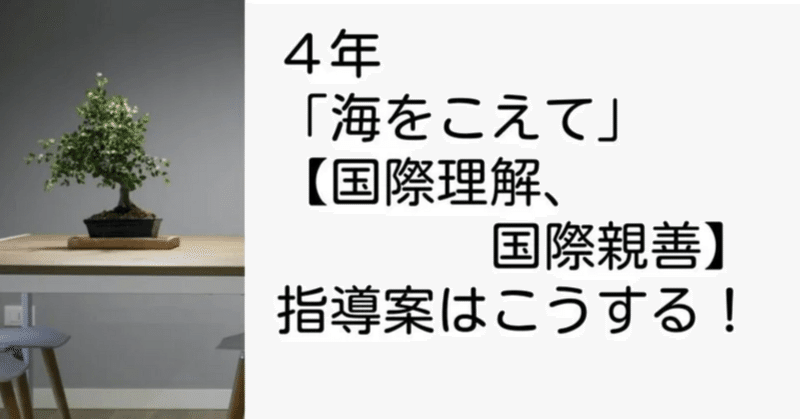
4年『海をこえて』【国際理解、国際親善】の指導案はこうする!
こんにちは。
今日は『4年「海をこえて」【国際理解、国際親善】の指導案はこうする!』
このテーマで教材解説をします。
今日の話題は国際理解です。
昔に比べて、外国の情報を
気軽に知ることができる時代になりました。
国境がなくなってきていると
言えるかもしれません。
では、海外のことを知るために
大切な心とはなんでしょうか。
いっしょに考えていきましょう!
では、解説です!
1 教材について
2 内容項目と教材
3 導入
4 発問
5 まとめ
順番に解説します。
1 教材について
C 主として集団や社会との関わりに関すること
「国際理解、国際親善」
3・4年の目標・・・・他国の人々や文化に親しみ、関心をもつこと。
4年生「海をこえて」(日本文教出版)
あらすじ
フランスでガーデニングを勉強しているアリス。盆栽を勉強するために日本にやってきた。
盆栽の講習会では様々なことを教わった。
・4年に1度『世界盆栽大会』が開かれること。
・盆栽は、1本の10年先の美しさを考えながら剪定すること。
・とても長い時間の作業であること。
講習が終わって先生が話しかけてきた。
「フランスのお庭も本当にすばらしいですね。色とりどりの花と緑の美しさは、まるで絵に描いたようです。日本の盆栽とはまた違った美しさがあるように思います。」
「そうなんです。左右が鏡にうつしたようにつり合っていて、スケールがとても大きいんです。」
なんだか今日、盆栽美術館に来てほんとうによかったと思いました。
ガーデニングのすばらしさを世界中に広めていこう。そして、「盆栽の心」が世界に広がりますように。
2 内容項目と教材
国際理解、国際親善の結論は2つです。
①国同士の関係は、人同士の関係と同じ
②国が違っても、幸せを求める気持ちは同じ
この2つを押さえておけば、まず授業の芯がぶれることはありません。
今回は特に、②にスポットが当たった教材です。
アリスさんは、日本に盆栽を学びに来て、たくさんのことを知りました。
また、盆栽だけでなく盆栽を教える先生のお話にも感銘を受けたのです。
盆栽からは、
・キラキラと輝いて見える。
・長い時間の中で生きてきた大きな自然が、ギュッと1本の木につめこまれている。
・四季の美しさを小さな盆栽で表現している。
アリスさんは盆栽でたくさんのことを感じました。
また、先生からフランスのガーデニングについて、「色とりどりで花と緑が美しいこと」を褒められました。
日本の盆栽とはまた違うよさを見出してくれている、先生の心の広さに心を打たれたのです。
盆栽は確かに素晴らしい。
フランスのガーデニングも素晴らしい。
でも、どちらがいいというものではなく「どちらもいい」のです。
互いの国で、これまでにたくさんの人が関わってきた歴史が、盆栽やガーデニングに詰まっているのです。
つまり、盆栽やガーデニングは、その国の文化そのものであり、互いの文化を尊重し合うことは、「互いの国を大事にしていること」につながるのです。
さらに視点を増やします。
アリスさんは、なぜ日本に来ようと思ったのでしょうか。
「盆栽の勉強をしたいから」という理由ですが、ただ「勉強したい」という理由だけで海外に行くのです。
それはもう、よっぽどの探究心があるからにちがいありません。
では、ここで考えたいことは、「アリスさんは、盆栽のどんなところに魅力を感じて、日本にやってきたのだろう。」ということです。
さいたま市の盆栽美術館を見学する場所に選んだことも、偶然ではないはずです。
盆栽は、アリスさんのどんな心をひきつけたのでしょうか。
子どもたちと考えてみたいですね。
今回の教材の目的は「フランスにもガーデニングという素晴らしい文化がある」ではありません。アリスさんやフランスという比較の事象を出すことで、『日本には盆栽という海外に誇る文化がある』ことを認識するためです。
また、盆栽のよさを認識する過程で、フランスのガーデニングもよさがある、という点を押さえることもポイントです。
すでに書きましたが、盆栽もフランスのガーデニングも、どちらがいいというわけではなく「どちらもいい」のです。
決して、「盆栽よりガーデニングのほうがいい」「盆栽のほうがガーデニングより素晴らしい」といった優劣をつける流れにならないように注意しましょう。
3 導入
T:教師 C:子ども
ここから先は
¥ 1,000
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
