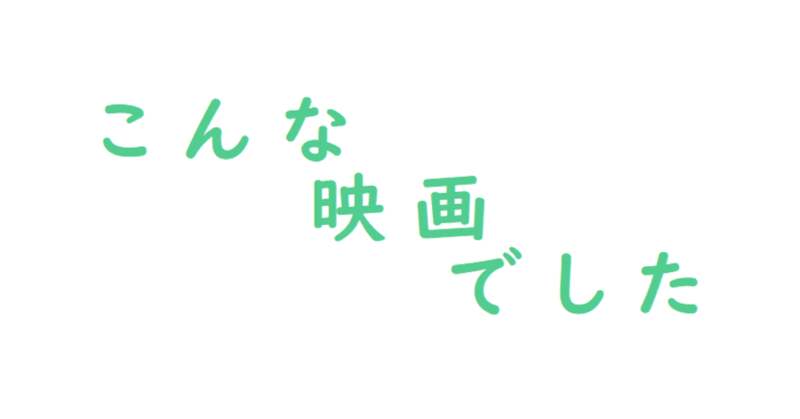
【こんな映画でした】197.[サーミの血]
2017年10月24日 (火曜) [サーミの血](2016年 SAMEBLOD SAMI BLOOD 108分 スウェーデン/ノルウェー/デンマーク)
最近は神戸は元町にある「シネリーブル神戸」でよく観ている。ここでかなり前に、この映画のチラシも入手していた。ただあまりに前過ぎてすっかり忘れていた。ところが芥川賞作家である目取真俊氏のブログをたまたま見たところ、神戸に来た折にこの映画を観たことが書かれてあった。ということで早速調べてみると、かろうじてまだ一日一回の上映があり、急いで行ってきた次第。家に帰って探したら、この映画のチラシを発見。私も一応チェックしていたようだ、観るべき映画あるいは観たい映画の一つとして。
*
アマンダ・シェーネル監督作品。さて映画はショッキングであった。すっかり忘れていた。すっかりこのようなテーマというか、問題が歴史に存在していたことを忘れていた。退職後、もう体系的に勉強してないせいだろう。
サーミ同様の問題は、世界中に存在してきているはずなのだ。そして日本なら東北・北海道のアイヌ、そして沖縄で同様のことを和人たちは、間違いなくやってきたのだ。
地理の授業で、世界の少数民族としてラップ人の名前くらいは知っていたが、その実態として差別を受け、迫害を受けていたことにまでは思い至らなかった。スウェーデン語の強制は、日本語の強制であり、母語を使うと体罰というのも同じ。人権も民主主義もない時代だったのかと。帰って見てみると描かれているのは1930年代のスウェーデンであった。
(「ラップ人」という呼称は蔑称とされ、今は使用されないとのこと。ただ映画の中では1930年代のことであるので、主人公に「あんたたちにもラップ人の血が混じっている」と言わせている。)
映画は、今はもう年老いた元教師で姉である主人公が、故郷で亡くなった妹の葬儀に行くシーンから始まる。なぜ彼女がそんな気むずかしい顔をしたままなのか。その理由がこのあと1930年代に遡ってたどられていくことになる。
考えてみると人類学や民族学というのは、ある意味酷い学問だ。学問のためと称して、少数民族の人たちを研究対象としてのみ扱う。従って非人間的なことを平気でしてしまう。そんな屈辱的なシーンがこの映画の中にもあった。
そしてさらに、彼らを差別し見下すのだから、呆れる。ヒューマニズムというのは、一体いつ頃から出てくるのだろうかと思った。なぜ謂われなく差別されなければならないのか。その理不尽さは差別された者でなければ、ついに理解できないことだろう。私も分かっているとは言えても、本当にそうかと問われたら自信がない。
*
2020年 2月17日 (月曜) [サーミの血](2016年 SAMEBLOD SAMI BLOOD 108分 スウェーデン/ノルウェー/デンマーク)
二回目。何度観てもやはり良い映画だ。しんどく辛いが、見終わった後にある種の幸福観を感じられる。良い映画のもたらしてくれる恩恵だ。
それにしても中身は、辛い。自分の帰属する場所・人間関係から離脱して生きていくことの大変さは、想像を絶する。近しい人たち、なかでも母親と妹とも訣別していくわけだ。その時の、それでもそうしなければ自分がなくなってしまうとのエレ・マリャ(女優レーネ・セシリア・スパルロク、撮影当時18歳くらいか)の決意と実行力は凄い。
オープニングシーンは、その彼女の何十年後かの姿(78歳と書いてあるのもあった)を描く(マイ=ドリス・リンピ、撮影当時73歳くらい)。息子とその娘の三人で車で向かう先とその目的が、まもなく分かる。妹の葬儀の参列だったのだ。しかし教会での人々のエレを見る目は冷たい。花を棺に備えることなく立ち去る。そして息子たちとは別れて、一人ホテルへ。
ホテルの食堂で、夕暮れの窓の外を眺めやるシーンから、一挙に若い頃の回想シーンへ。エレは妹のニェンナと一緒である。まもなく二人で寄宿学校へ。そこはラップ人、いやこの言い方は差別用語であり、彼らはサーミと自称する。支配者であるスウェーデン人からしたら、彼らは差別されるべき「ラップ人」なのだ。
映画の中でも露骨に、彼女たちに差別の言葉と態度を投げかけてくる。それに耐えているエレの顔は凜々しい。しかし他のみんなは下を向いてその場をそそくさと立ち去る。汚いとか臭いとか。信じられない偏見である。これも教育の成果であろう。
なおこの姉妹を演じた女優二人は、現実に本当の姉妹であったようだ。
ラストシーンは再び現在に戻り、エレは教会に行き、棺桶の蓋を開け、ニェンナの顔を見る。そして「赦して」、と。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
