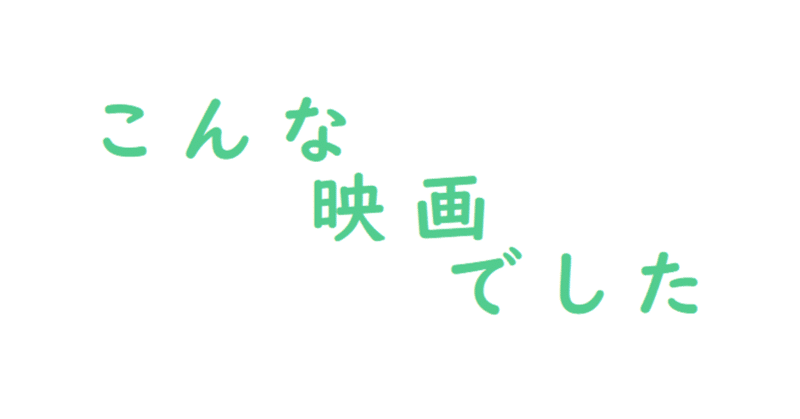
【こんな映画でした】403.[断崖]
2023年 1月 3日 (火曜) [断崖](1941年 SUSPICION アメリカ 99分)
アルフレッド・ヒッチコック監督作品。主役ジョニーをケーリー・グラント(撮影当時37歳)を殺人犯にできないという製作者側の意向により、ヒッチコックにとっては不満の残る作品となっているようだ。私も観て、これは駄作とはいわないまでも、この結末のように改変してしまったら失敗作といってもいいかと思う。最初から積み重ねてきたジョニーというかケーリー・グラントの演技を最終的に裏切るような決着になっている。
妻リナ役をジョーン・フォンテイン(撮影当時23歳)。世間を知らない良家のお嬢さん役。だから簡単にジョニーの計略に嵌められてしまい、結婚に。原題通り疑惑を募らせていき、ジョニーの親友のビーキーも何者かに殺され、次には自分が保険金目当てで殺されると推測するにいたる。
ところが映画では、車の助手席にリナを乗せ、断崖絶壁の際を猛スピードで走り、その助手席のドアを解錠し、リナを突き落とそうとするが。車は停まり、二人は仲直りをして家に戻ることにして映画は終わる。――これは一体何なんだ、と思わずガックリくる終わり方なのだ。
*
これはどうもつろくしない、おかしいと思って早速トリュフォーの『映画術』の該当箇所を読んだ。やはり、そうだったのだ。ヒッチコックは原作の小説とも、この公開された映画の結末とも違うものを考えていたとのことなのだ。
ヒッチコック 『断崖』の結末は、じつに気にいらないんだよ(P.129)
で、どのような構想を持っていたか。まずジョニーがコップに入れたミルクを彼女の部屋に階下から持って上がってくるシーンは、この映画でもカットされていない。つまりそれだけ魅力的なサスペンスフルなシーンなのである。そのミルクが薄暗い階段を上がってくるジョニーの手の上で(お盆を使っている)光っているのだ。これはトリックを使っているとヒッチコックは明かしている。これを見せられたらリナならずとも、これは毒入りであると察知できる。それまでに「証拠の残らない毒」の話を出ている。
にもかかわらずリナはそれを飲まなかった。まったく口にしてない状況が次に映し出されるのだ。これはハシゴを外された感がある。もうこの先は、ヒッチコックの構想とは違うものになっていたわけだ。
ではどうしたかったのか。簡単に言えば母親宛の遺書を書き、その手紙の投函をジョニーに依頼し、彼女はミルクを飲んで死ぬ。ジョニーが殺人犯人であるともちろん知っての上で。彼女の死でフェイドアウトし、ラストシーンはフェイドインでジョニーを映し出し、彼が口笛を吹きながら街のポストに投函するところでフェイドアウト。The End となる。これがヒッチコックの考えた結末だったそうだ([嘆きのテレーズ]を思い出させる)。
*
アメリカ映画のスター主義は、スターは絶対に悪人・悪役にならないということ。殺人犯人に仕立てることは不可能なのだ。ずいぶんと狭量だとは思うが、アメリカの映画会社は芸術作品を作っているわけではなく、あくまでもビジネスだからだろう。
ということでヒッチコックの弁を聞いてホッとしたが、映画としての本作はヒッチコックの名作の一つに数えたくない、私は。折角ケーリー・グラントがどうしようもない狡い男・誠意も誠実さの欠片もない嫌な男を上手く演じてきているのに、最後の最後で妻にとっては愛すべき良い人でした、となっては観てる方はひっくり返ってしまうのだ。そういう意味ではケーリー・グラントのためにも、この結末というかストーリー展開は良くなかったと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
