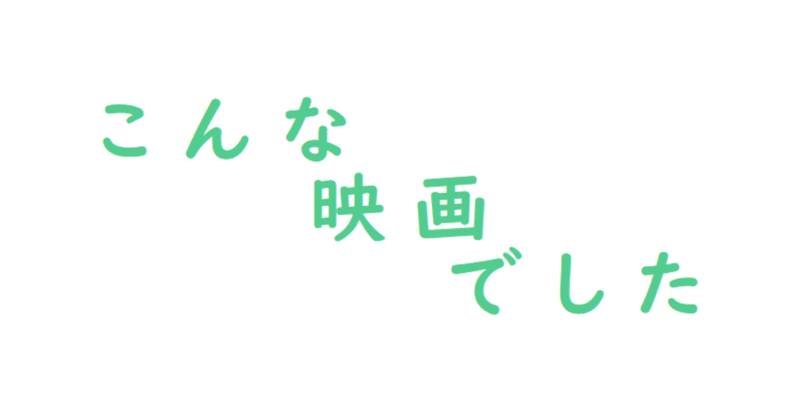
【こんな映画でした】43.[帰らざる夜明け]
2022年 3月14日 (月曜) [帰らざる夜明け](1971年 LA VEUVE COUDERC フランス 89分)
最初はたしか九州へ旅行中、小倉かで1973年 2月 4日に[エルビス・オン・ツアー](1972年 ELVIS ON TOUR アメリカ 93分)と併映で観たのだと思う。
フィリップ・サルドの音楽が鳴り出した途端、私はすぐに思い出した。いや、思い出さされた。これは知っている、と。調べてみると彼の映画音楽は他にも[子熊物語][個人生活][これからの人生][テス][ポネット][湖のランスロ]の計7本も観ている(聴いている)のが分かった。1945年生まれだから存命だろう。
ピエール・グラニエ=ドフェール監督作品。かつて[個人生活]を観ている。「LA VEUVE」は「未亡人」の意味らしい。アラン・ドロンは撮影当時35歳。未亡人はシモーヌ・シニョレ、撮影当時50歳。舞台は「フランス 1934年6月」とテロップが出ることで分かる。
綺麗な田園風景を俯瞰で、つまりヘリコプターで撮影しながらのオープニングシーンである。俯瞰から田舎道を走るバスをとらえ、寄っていく。やがてバスは停まり、一人の女性が降りてくる。これがシモーヌ・シニョレ扮する「未亡人クーデルク」(これが原題)。彼女の手荷物(といっても30キロもあるもの。やがてそれが孵卵器であることが分かる)の、包装をしてある新聞紙には「ファシストの脅威を一掃せよ/ドゥメルグ挙国一致内閣/パリで流血騒動」の文字が見られる。時代背景であろう。
*
ラストシーンはかの[明日に向かって撃て](1970)や[俺たちに明日はない](1967)のような劇的なものに勝るとも劣らない映像となっている。男は家から飛び出していき撃たれる。スローモーションで飛び上がる様が描写される。女は家の中で流れ弾を受け、息絶える。なかなかの名場面・名シーンである。
ラストのカットは、アラン・ドロンの死顔のアップをまずはそのままカラーで、そしてやがてモノクロにして、テロップが。そこには「1922年物理学者エティエンヌ・ラビーニュの息子ジャン・ラビーニュは、パーティーで2人の高官を射殺した。彼は裁判官に動機を問われ、 "ウンザリしたから" と答えた」、と。実在のモデルがあったのかもしれない。
このように最後になぜ彼が逃げていたのかが明かされる。その生い立ちについてはクーデルクとの会話の中で少しは分かるようになっている。あまり幸せなものではなかったようだ。家族の愛情に飢えていたようだ。それがクーデルクとの出会いで、一瞬とはいえ満たされることになる。ただそれが命取りになったことは否めない。
田舎の人たちの偏狭さは目に余るものがある。そんな中でオッタヴィア・ピッコロ扮する若い娘フェリシーが清涼剤ともいえる。もっとも彼女が、ジャンの部屋に忍び込んで身分証明書を盗み、それが警察に届けられて偽物と分かり、射殺(逮捕ではない)されることにつながるのだが。
あと気になったのは、ここでもユダヤ人差別が出てくること。ジャンを捕まえる応援と称して元軍人たちも大挙してやって来る。その時に捕まえるのは「ユダヤ人か、ユーゴか」と言っているのだ。この頃の政治状況を知らなければ分からないことなのだろう。お隣ドイツではそろそろナチスが台頭しつつある頃なので、フランスでもそれに共鳴する人たちがいたということかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
