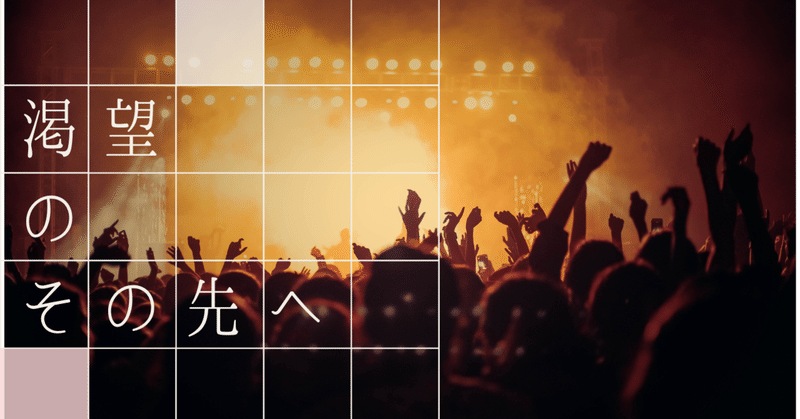
渇望のその先へ
『不要不急の外出を控えていただくよう要請を……』
『今週末の不要不急のイベントは軒並み中止となり……』
『特にですね、不要不急と見なされる行事はやめていただいて……』
不要不急、不要不急、不要不急。
ある時から壊れたレコードプレイヤーのごとくにおおやけを名乗る人々から唱えられるその文言は、まるで呪いの言葉のように世間に広がっていった。錦の御旗のようにその言葉が掲げられれば、こちらとしては黙らざるを得ない。うっすらと広がっていくその言葉は、目には見えないがこちらの首元を真綿で絞めるようにじわじわと圧迫してくる。その呪文さえ唱えていればまるで正義の側にでもいるかのように。
感染が広がる中で人の集まる場所が次々に閉じられていき、それはライブハウスも例外じゃなかった。
僕がファンとして追いかけているバンドのニューアルバムをひっさげての全国ツアーも、ご多分に漏れず各会場が軒並み中止となってしまった。
こっちは駄目なのにあれはいいのかよ、と思うことは正直なところ何度もあった。誰かと誰かの都合や思惑がこんなにもあからさまにぶつかり合ってしまうような出来事を目の当たりにして、僕は戸惑うことしか出来なかった。
誰かを恨んでも仕方がない。誰が悪いわけじゃないんだ。そう思おうと努力はしたけれど、次々に舞い込んでくる公演キャンセルの通知に心が押しつぶされそうになる。お金は戻ってくるけれど、落ち込んだ心はそう簡単には取り戻せそうにない。
無くなって初めて気づく事がある、なんてありふれた言葉だけど、今まで当たり前に出来ていたこと、目の前にあったものがある日突然跡形もなく無くなってしまうという事がこんなにも辛いものだったということを骨の髄まで思い知らされた。
僕は今までどれだけライブに救われていたんだろう。
思い返してみれば明日への気力を奮い立たせてくれたのはいつもライブの熱気だった。
不要不急なものか。
だってこれがなければ生きている意味がない。
僕らはただ生きるためだけに生きているんじゃない。
危機に瀕したライブハウスやアーティストに対して僕らが出来ることはとても少なかったけれど、それでも出来るだけの事はやった。ライブハウスが主催するクラウドファンディングへの支援や、アーティストのグッズの購入、手探りの中で行われた配信ライブでの投げ銭も行った。この病の蔓延する世の中を、どろりとした酷く粘性の高い液体を掻き分けるように必死になって僕らはなんとか息をしていた。ついに息が出来なくなった事例もたくさん見てきた。
春に予定され、急遽中止になっていたバンドの全国ツアーの再開が伝えられたのは、夏を通り過ぎて秋になってからだった。
完全に元通りの公演となったわけではもちろん無くて、一度に入れる人数を減らした上で観客の間隔は開けて声援も禁止、当然マスクは着用して入場前には検温をするというすっかり定着した新しい習慣に則っての開催だった。
事前の混乱を予想して以前よりも早めに設定された開場時間に合わせて会場のライブハウスを訪れると、入場待ちの列は普段よりも人数は少なく、間隔を空けて形成されていた。チケットの番号を確認して列に並ぶ。徐々に進んでいく列に従って移動し、ライブハウスの入り口に到達すると、あらかじめスマホにインストールしておいたCOCOAの画面と入場チケットをもぎりの係員に提示する。係員は僕の額に赤外線式の体温計を向けてスイッチを押し、表示された体温を確認すると、僕を中へと促した。
入り口で手指を消毒してから硬貨を支払い、ドリンク引き換え用のコインをもらうと会場後方のドリンクコーナーでビールを注文。渡された缶ビールの冷たさを感じながら会場前方まで足を進める。足元には一定間隔でマークが配置されていて、公演中はそこから動かないようにとあらかじめ指示されていた。
距離は離れているし、声も出せない。観客同士の間隔を空けるために入場できる人数も少なくなっている。それでも僕を含めた観客が生み出した熱気はいつもと変わらずに会場の内側を埋め尽くしていた。徐々に人も増えて熱気の密度も上がっていく。久々のこの感じ。どうにも熱くなってくる体をクールダウンさせるように冷たい缶ビールを頬に当てた。
会場の暗転とともにメンバーがステージに現れる。僕らはありったけの思いを込めて、手が痛くなるほどに全力で拍手を送る。
まずは一発目、ツアータイトルと同名のアルバムのイントロ曲からのスタートだった。思わず漏れ出しそうになる声を必死にこらえて代わりに両手を振り上げる。そこから続けざまに3曲、これまでの鬱憤を晴らすかのような力強いメンバーの演奏とボーカルのシャウトが会場の熱気に負けない勢いで響き渡った。
いきなりの全力疾走で一気に汗だくになった彼らを会場の照明が照らし出す。久しぶりに目の前に現れたメンバーは皆一様に満面の笑みを浮かべている。普段はクールに振る舞っている彼らが今日に限っては感情を剥き出しにして僕らと向き合っていた。
「久しぶり!今日は集まってくれてありがとう!」
ボーカルのMCにオーディエンスは精一杯の拍手を送る。
ステージ上の彼らが誰よりも一番この日を待ち望んでいただろう。子供のようにはしゃぐ彼らの様子を見てこちらも嬉しくなってくる。僕は思い出したように手に持ったビール缶のプルトップを押しあげる。
「あ、やば、泣いちゃうかも」
そう隣で呟く知らない女の子の目にはすでに大粒の涙が光っていた。ちょっと大げさだな、なんて思いながら僕もビールを一口。気持ちよく喉を通っていきながら体に染み渡っていくビールが、思った以上に僕が渇いていたことを教えてくれた。
……ああ、そうだ、そうだよ。これなんだ。この感じだ。
僕に必要だったのは、僕が必要としていたのは、この感じなんだよ。
渇いていたのは体だけじゃなくて、心もだったんだ。
ひび割れた心に染み渡っていくように、僕は缶ビールを喉に流し込む。
気がつけば、僕は泣きながらビールを飲んでいた。

感極まっているのは僕だけじゃない。ここにいる皆がそうだった。
まだまだとても勝ったなんて言える状況じゃない。戦況は一進一退、むしろ状況は僕らに不利で、油断すればあっさりと窮地に追い込まれてしまう。これからも敵がどこかも分からない、どうすれば勝てるのかも教えてもらえない、歪な戦いは続くのだろう。
それでも一歩、やっとの思いで僕らは一歩を踏み出した。
勝利の美酒とは言えないけれど、僕らは再びここで、この場所でビールを飲んでいる。口に広がる爽やかなホップの苦みがこんなにも懐かしい。
これを味わうためならば、何度だって歯を食いしばって立ち向かってやる。
MCを終えたボーカルが後ろを振り向き小さく頷くと、ドラムがカウントを始める。再び会場が暗くなり、ギターのフレーズがかき鳴らされる。
僕は残ったビールを勢いよく飲み干すと、空缶を力強く握って潰して、それから大きく腕を振り上げた。
高く、高く。
更なる活動のためにサポートをお願いします。 より楽しんでいただける物が書けるようになるため、頂いたサポートは書籍費に充てさせていただきます。
