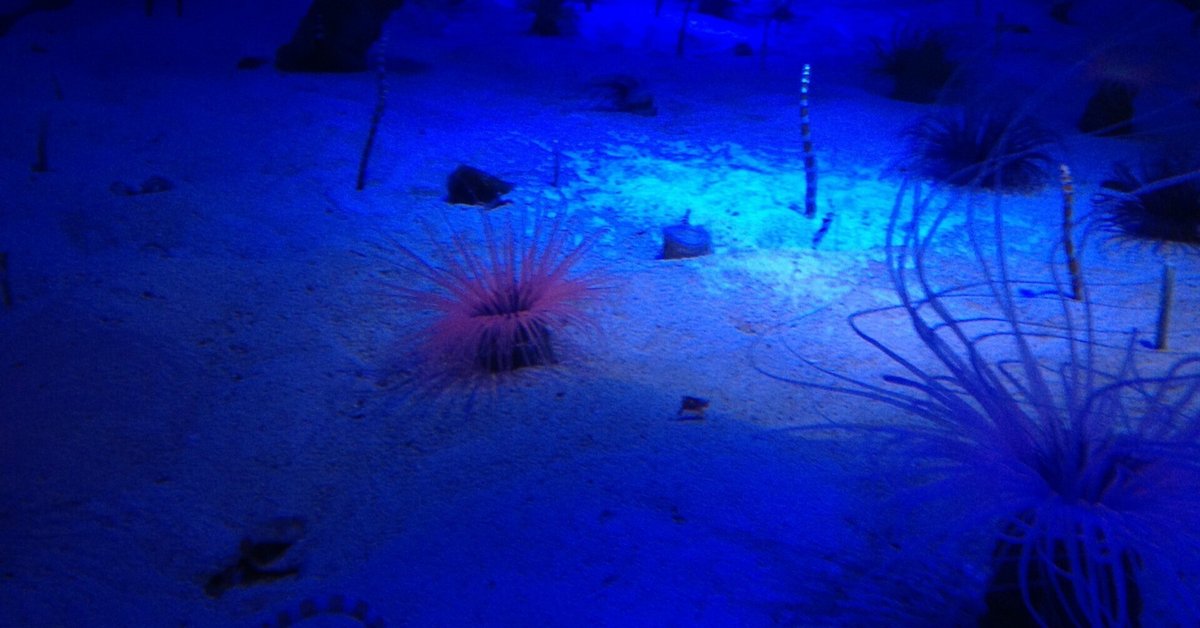
聖なる夜に花は揺蕩う 第5話 円と十字「全10話」
【あらすじ】
12月10日(金)、週刊誌『FINDERー』の事件記者・桐生、北村とカメラマンの岡島は秩父湖に来ていた。彼らは切断された遺体を発見する。きっかけは、今朝『FINDER』編集部に送られてきた手紙だった。いままでに5人殺害し、そのうちの1人を湖に沈めたという内容で、詳細な地図と免許証も同封されていた。手紙には、犯人の署名として円と十字の印が記されていた。円と十字の印を手掛かりに、桐生たちは残る4件の事件へと導かれていく。
12月15日水曜日
桐生は北村と羽田発午前八時半の飛行機に乗り、長崎空港に着いたのは十時半だった。そこからタクシーに乗り、二人は岩戸神社へ向かっていた。すでに正午を回っている。
「岩戸神社はパワースポットみたいですね。地元の人たちには『岩戸さん』の愛称で親しまれてるって、ネットに書き込みがありました」
桐生はタクシーの窓から見える樹林帯に視線を向けた。水曜は『FINDER』編集部の公休日だが、じっとしてはいられない。白石夏希の母親から話を聞くことが第一優先だ。
なぜ夏希は失踪したのか。彼女はなぜ、十字の入ったビー玉を握りしめていたのか。
「お客さんたち、どっから来たと?」
運転手がミラー越しに桐生たちに視線を向けていた。旅行鞄などは持ってないが、地元の者とは様子が違う。そんな空気を感じとっているようだ。
「東京です。運転手さんは、十一年前、洞窟の神社で殺人事件があったのをご存知ですか」
北村が問いかけた。
「ああ、あん事件は酷かったね。殺されたんは地元のもんやったかな。まだ犯人は捕まっとらんのや」
タクシーは坂を上り続けている。もしバスで来ていれば、バス停から一時間歩くことになっていた。この坂道を一時間歩くのはきつい。犯人はどうやって現場へ行ったのだろう。
車は細い道を進み、立て札の前で停車した。樹林帯への入口で、数メートル先に細い丸太で作られた鳥居が見える。
「こん先ん駐車場で休憩しとぅけん、帰りもよかったら乗っていってくれん」
運転手は浅黒い顔に皺を刻み、人のよさそうな笑みを浮かべた。
「それはありがたい。一時間もかからずに戻れると思いますよ」
二人はタクシーから降りた。鬱蒼と茂る木々の間を、冷たい風が吹き抜けていく。
「この辺りの木は、杉と檜らしい。神社に祀られる神は、高い木を伝って降りてくると信じられてる。だから神社の周りに高木を植えるって何かで読んだよ」
「でも、北村さんは神も悪魔も信じてないですよね?」
「絶対の神なんてものは信じてないよ。でも自然界に精霊がいることは否定しない。神社に来れば、ちゃんとお祈りもするよ」
北村は両腕を伸ばし、深呼吸した。
鳥居は聖域への入口といわれている。高木の鳥居を抜けると、苔に覆われた石の鳥居が見えた。奥に階段が続いている。
ところどころ風化して欠けていた。上り切ると小さな神楽殿があった。その奥に、黒々とした岩肌が見える。近づくと、間口が十五メートルほどの洞窟があった。祠には奉納と書かれた紫の布が掛けられ、両側にいくつもの石灯籠が置かれている。
「神秘的ですね。ネットの記事には、岩永姫命をお祀りしていると書かれていました。岩永姫は『岩のように長く続く命』を神格化した神様で、一般的には『岩の神』や『寿命長久の神』とされているようです。あの、手水舎はないみたいだから、この水で手と口を清めてください」
「へぇ、桐生君て、そういうことに詳しいの?」
「いえ、僕も北村さんと一緒です。神様を信じてるかと訊かれたら答えられないけど、不思議な力を否定することはできないって。清められるものは清めておきたいっていうか」
桐生は鞄からミネラルウォーターのボトルを取り出し、北村の両手に掛けた。
「とくに俺たちみたいな仕事をしてたら、清めることは大事だな」
北村は口も清め、祠の前に立った。北村と並んで手を合わせ、事件解決とスクープ獲得を祈願した。
右奥にも洞窟が二つあり、祭壇には水と榊が供えられていた。周囲には大きな石がいくつもあり、十二月だと思えないほど草が生い茂っている。白石真人はここで犯人に襲われたのだろうか。
桐生は屹立した木々を見上げ、スマートフォンで何枚か写真を撮った。
岩戸神社から二十分ほど下ったところに、白石夏希の実家はあった。道幅は広く、辺りは収穫を終えた畑に囲まれている。畑のなかにぽつぽつと民家が建っていた。運転手に礼を言い、二人は通り沿いに建つ二階建ての家へ向かった。玄関前に車庫があり、白のセダンが駐まっていた。
北村がチャイムを鳴らすと女性の声で応答があり、ドアが開いた。
「遠かところ、よう来てくれたね」
細面で色白の女性が桐生を見る。涼やかな目元が白石夏希とよく似ている。
「きょうは、お時間を割いていただき、ありがとうございます」
北村は名刺と羽田空港で買った最中を差し出し、頭を下げた。
「娘んために時間ば使うてもろうとぅとは、うちんほうばい。お土産までいただいて、申しわけなかとです」
白石夏希の母親は優しい笑みを浮かべ、二人をなかへ招き入れた。玄関を入ってすぐ突き当たりが居間だった。十畳ほどの広さがあり、ガラス戸の向こうに庭が見える。卓袱台のそばで三毛猫が微睡んでいた。わずかに目を開け、二人を見るなり俊敏に部屋から飛び出していった。
卓袱台の上にはA4サイズのクリアファイルが載っており、そのすぐ隣にはガラスの卓上ツリーが飾られていた。オーナメントの天使やトナカイが、天井から吊るされたペンダントライトの光をきらきらと反射している。
「そりゃ、十一年前ん事件ん記事ばスクラップしたもんや。よかったら見よってくれん。いま、お茶ば淹れますけん」
白石夏希の母親は桐生たちに座布団を勧め、入ってきたドアとは違う引き戸から出ていった。
卓袱台の前に北村と隣り合って座り、桐生はファイルの表紙を開いた。当時の新聞記事が黒い台紙に貼り付けられ、ホルダーに収められている。
記事は航空写真入りで、洞窟前の敷地にはシートが掛けられていた。草むらの周辺には捜査員が写っている。通報があったのは八月二十九日の午後五時半だと、台紙に白いペンで書き込まれていた。
母親は湯呑みと切り分けたロールケーキの皿を盆に載せて戻ってきた。皿には小さめのフォークが添えられている。
「ケーキば買うてきたんばい。あん子は蜜柑の入ったロールケーキが大好物なんや。クリスマスにはまだ早かばってん、どうぞ召し上がってくれん」
母親は桐生の向かいに座り、ケーキの皿と湯呑みを二人の前に置いた。三毛猫は母親の膝の上に載り、安心した様子でうずくまった。
「真人さんは、ずっとこちらに住んでいたんですか」
北村はロールケーキの皿を引き寄せ、フォークを刺した。一口分を口に入れ、頬を緩めた。うまそうに食べる北村を見て、母親も嬉しそうだ。桐生もロールケーキを一切れ食べた。スポンジの生地はしっとりとして、生クリームと蜜柑の甘さが口のなかに広がった。
「真人さんは、学生ん頃は東京ん農業大学へ行ったとばってん、卒業後は長崎に戻って実家ん畑ば手伝うとった。主人は、夏希がまだ幼か頃に病死しましんしゃい。うちが仕事ん日はよう面倒ば見てもろうた。うちゃ長かこと看護師ばしとぅ。夏希は小学生で夏休みやったけん、事件があった日も真人さんが夏希ん面倒ば見てくれとった」
母親は三毛猫の背中を撫でながら、記憶を辿るように首を左に傾けた。
「真人さんは子供好きだったんですね。結婚はされてたんですか」
桐生の言葉に、母親は首を振った。
「東京におった頃には恋人もおったげなばってん、こっちに帰ってきてからは一人やったね。縁談は何度かあったとばってん、どれもご縁がなかったみたい」
「十一年前の事件の日、夏希さんが手に握っていたビー玉のことは覚えていますか」
北村は手帳に書き付けた円と十字の印を母親に見せた。母親は手帳を見つめたまま、大きくうなずいた。
「あん子は、あんビー玉ば誰からもろうたんかはうちにもゆわんじゃった。ばってん、今年ん正月に帰ってきたときに、少しだけ教えてくれよらした。こん印ば大切に持っとりゃ、また会えるったいって」
「……また……会える……ですか。それって、いったい……」
「夏希さんは、記憶を封印していたんじゃなかったのかもしれない。全部ちゃんと覚えてて、そのことを誰にも話さなかったとしてら、そこから導き出される答えは、一つしかない」
北村は緊迫した表情で唇を噛み締めている。
――夏希がもう一度会いたかったのは、犯人ではないのか。
「お母さんは、その言葉の意味を問いただしましたか」
「あん子ば助けて来れた人がくれたんじゃろうと思うとうと。そん人が通報してくれたばい、きっと」
その可能性はある。だが、もう一つ別の可能性もある。忌まわしい想像は黒い冷気となり、一気に全身に広がった。
それは、夏希は十一年前に真人を殺した殺人者との再会を自分から求めていたのではないか、というものだ。だから歌を歌い、あの印をアイコンにしたのではないか。
そしてついに奴を呼び寄せた。『名もなき殺人者』を。
12月16日木曜日
桐生は編集部に戻ったあとも考えていた。通報者がビー玉をくれたのなら、秘密にする必要はない。白石真人を殺した犯人が夏希にあげたと考えるのが自然ではないだろうか。
犯人について証言しない理由について、ある仮説が浮かんでいた。夏希は白石真人に虐待を受けていたのではないか。その現場にでくわした人物が、夏希を助けるために真人を殺したのかもしれない。
だが、不可解なのは真人が絞殺されていることである。真人を突き飛ばし、誤って殺したのではない。そこには明確な殺意がある。
椅子にもたれ、手帳を開いた。
今年の一月には、夏希は『名もなき殺人者』と再会できると思っていたのだろうか。奴から連絡が来たのだとしたら、ブログのコメント欄かメッセージ機能を使ってやりとりがあったのかもしれない。
円と十字の印は警察も調べているはずだ。夏希の失踪事件にも辿り着いているかもしれない。そのうち警察が『名もなき殺人者』を逮捕してくれる。
そう考えても、桐生の体に充満した黒い冷気は薄れていかなかった。遠くで誰かが歌っている。メネラウスは迷宮に迷い込み、いまも彷徨っている。青い煌めきはもう戻らない。
奪ったのは『名もなき殺人者』ではないのか。夏希は奴と二度と会うべきではなかった。奴に正義はない。闇を貪る猛獣だ。
「桐生君、また失踪者が見つかったよ」
北村に話しかけられ、顔を上げた。
「円と十字の印が残されていたんですか」
「ああ。今日発売された『FINDER』であの印を見て、連絡してきてくれたんだ。娘さんが失踪してるらしい。これから出られるかい?」
「もちろんです」
席を立とうとしたところへ、岡島がやってきた。
「いま、少しだけいいですか」
「やあ、先週は助かったよ。岡島君のおかげで、すごい写真が撮れたからね」
北村は笑顔で答えた。グラビア班に所属する岡島は、芸能人や作家のスナップから事件現場の撮影までこなしている。そのため編集部で顔を合わせることは少ない。
「来週の特集号に使う写真、どれがいいですか。テーマは失踪した女性たちだと聞いてますけど」
岡島はタブレットの画面を切り替え、北村に差し出した。桐生も画面を覗き込む。モノクロの画像が十枚ほど並んでいる。
北村は画像をタップして、一枚ずつ見ていく。交差点を行き交う車や工事現場、人のいない公園の写真などの街の写真が続く。
横で見ていた桐生は、十枚目まできて視線が吸い寄せられた。白い空に蝶が舞っている。辺りには木が茂り、蝶を見上げるようにシャッターが切られていた。
「その写真は南米で撮ったんです。画面ではわからないと思いますが、翅が驚くほどの鮮やかな青で、まるで発光してるように煌めいていました。モルフォ蝶だと思います。アマゾンのジャングルに生息し、二十九種類にも及ぶそうです」
「……メネラウスという蝶も、モルフォ蝶の仲間だよね」
北村は白石夏希が作詞した曲のタイトルを口にした。
「よくご存知ですね。ほかにもアキレスとかアドニスなど、響きも詩的ですね。なかでもレテノールモルフォはとくに美しいといわれていて、闇から朝焼けのブルーに変わるグラデーションを持ち合わせているらしい。この写真の蝶は、レテノールじゃないですね。メネラウスかアドニスかな」
岡島は視線を落とし、蝶の画像を見つめている。
「じゃあ、この写真でお願いするよ」
白い空を舞う蝶の画像に、失踪した白石夏希が重なる。自分から『名もなき殺人者』に会いに行ったなどとは思いたくない。無事でいてほしい。自由を求めて彷徨いながら、いつか探し求めていた答えを見つけてほしい。簡単に見つからなくても、生きていれば鍵を拾うことはできる。その鍵で開く扉が、どこかにかならずあるはずだ。
「この写真が気に入ってもらえて、俺も嬉しいです。あと、これ、明日からなんですけど」
岡島は人懐こい笑顔を浮かべた。濃紺の別珍のジャケットに手を突っ込み、取り出したDMを桐生と北村に渡した。表面に『報道写真展』と記されている。会期は明日から一週間で、場所は銀座の画廊だ。
「よかったら来てください」
「明日、かならず行くよ。二人で」
北村の横で桐生もうなずいた。
「よかった。六時からレセプションパーティーがあるんです。ワインも用意してるんで、二人ともその頃に来てください。お待ちしてます」
岡島はタブレットを片手に立ち上がり、軽やかな足取りで自分の席へ戻っていった。
連絡をくれた人物とは、川崎で待ち合わせているという。
まだ昼前だが、川崎駅構内にあるカフェはそれなりに人が入っていた。店員に待ち合わせだと伝えると、窓際のテーブル席に案内された。
周囲を見回し、一人でケーキとお茶を楽しんでいる女性が多いのに気づいた。手元には本や手帳を置き、スーツ姿でうつむく様子はいかにも仕事ができそうだ。一日仕事を頑張る自分へのご褒美といったところか。
隣に座る北村は、さっそくタブレットにログインしていた。
できる女性たちに囲まれ、この場でもっとも浮いているのは自分たちだろうと桐生が思っていると、男が店に入ってきた。小柄で中肉中背の男は四十代前半くらいだろうか。頭髪には白いものが混じっている。
男は店員に案内され桐生たちの席まで来ると、清澄茂と名乗った。交換した名刺にはシステムエンジニアと記されている。北村が店員にコーヒーを三つ頼み、清澄と向き合った。取材に応じてくれたことに礼を言うと、清澄は困惑した表情を浮かべた。
「今朝、通勤途中に『FINDER』を読んでいたら、あの手紙が載っていて驚きました。まだ仕事があるんですが、早めのランチを摂ることにして抜けてきました。あなたがたは、秩父湖の遺体を発見されたんですよね」
目尻の下がった小さな目には不安の色が映っている。
「あの手紙が編集部に送られてきたので、確かめに行ったんです。そこで遺体を見つけました。お嬢さんが失踪されたのはいつごろですか」
北村は手帳を開き、清澄に質問していく。
「今年の八月です。樹里亜は大学二年生で、夏休みだったので毎日のように出かけていました。でも、八月の終わりに、あの子は家に戻らなかった」
八月と聞き、桐生は顔を上げた。白石真人が殺されたのも八月の終わりだった。
「八月の何日ですか」
「二十九日です。行き先も告げずに出て行ったきり戻ってこないんです。警察にも行きましたが、調べてくれているようには思えません」
清澄は運ばれてきたコーヒーに視線を落とした。桐生は日付を書きつけながら、日にちの符合に心臓の鼓動が早まるのを感じていた。
――白石真人が殺された日に、清澄樹里亜が失踪した。それは単なる偶然なのか。
「円と十字の印は、どこに残されていたんですか」
「樹里亜のパソコン・デスクの上です。アクリルの透明な球のなかに、青い針金で作ったようなリングが十字に重ねられています。掲載されていた手紙の印のように」
「その置物に気づいたのは、いつ頃ですか」
「樹里亜が失踪したあとです。メモや日記に手掛かりがあるかもしれないと思い、机の周りや引き出しを見てみました。そのときに、見慣れない置き物があること気づきました。あの子の机の周りには、ほかにもガラスの瓶や天使のオルゴールが並べられていましたけど、ちょっと違和感を覚えました。あの子らしくないっていうか……」
「持ち物にはその人の個性がでますからね。その置き物は、誰かが樹里亜さんにあげたものかもしれません。恋人がいたとか、誰かに会いにいった可能性はありますか」
北村はペンを走らせながら訊いた。
「……付き合っていた男はいました。パソコンに保存されていた写真とFacebookを調べたところ、高校の同級生だとわかりました。先日、その男に会いにいったんです。でも、樹里亜が失踪する少し前に別れたようです。嘘かもしれませんが、それ以上問い詰めることはできませんでした」
清澄は薄いグレーのスーツに紺のトレンチコートを羽織ったまま、苦しそうにワイシャツの第一ボタンを外した。ネクタイはしていない。
「その男性の名前と住所、教えていただけますか。私たちで、その男性からもう一度話を聞いてきますよ」
北村の提案に、清澄は目を瞬いた。
「そうしていただけるなら、これもお渡しします。いつも持ち歩いて、時間を見つけては調べていたんです」
清澄は鞄からA4サイズのファイルを取り出し、テーブルに置いた。なかを開くとワープロ文字で文が綴られ、ところどころに写真が貼られていた。
「こちらが樹里亜さんですか」
桐生は一ページ目に貼られた写真に視線を落とした。目鼻立ちのくっきりとした若い女性が写っている。父親には似ていない。襟元にリボンの付いた赤いブラウスを着て、まっすぐこちらを見つめている。
「その写真は大学の入学式の日に自分で撮って、Facebookに載せていました。文章は樹里亜のパソコンにあった日記をプリントアウトしてきました。男の電話番号と住所は、最後のページに入れてあります」
清澄はファイルの最後のページを開き、桐生たちに見せた。横浜の住所の下に堀内暁生と書かれている。
「樹里亜と堀内は、三年ほど交際していたようです」
「何が原因で別れたのか、堀内さんに訊かれましたか」
北村は住所をスマートフォンに打ち込み、清澄を見る。清澄は砂糖を二杯入れ、ティースプーンでかき混ぜている。
「性格の不一致とかなんとか言ってましたよ。でも、樹里亜の同級生から聞いた話では、堀内の浮気が原因らしいです。樹里亜に別れを切り出され、未練のある堀内が何かしたんじゃないかって、そればっかり考えてしまって……」
清澄は顔を歪め、自分の考えを打ち消すように首を振った。
何かわかったら連絡すると約束し、清澄と別れた。北村を見ると、さっそく電話を架けていた。
「堀内さんと連絡が取れたよ。横浜駅にある焼肉店でバイトしてるらしい。お店で何か注文してくれるなら、取材に応じてもいいってさ」
「その堀内が、『名もなき殺人者』の可能性はあると思いますか」
「そうだったら、事件解決だよ。とにかくその店へ行ってランチしよう」
北村は改札へ歩き始めた。
店は横浜駅の通り沿いにあった。
ガラスドアを引き開け、なかへ入る。照明は暗めで、入口の壁にはF五十号サイズの写真が飾られていた。銀縁の額に収められた写真は、黒い背景に浮かび上がる深紅のダリアだ。いくつもの花びらにはかすかに水滴が付いている。
広い店内にはテーブル席と座敷があり、どの席も壁で仕切られていた。正午を回ったところだが、平日だからか空いている。一人で食事している女性とパソコンを開いて仕事をしている男性がいるだけだ。
ドア付近にいた店員が二人に声を掛けてきた。
「堀内さんはいらっしゃいますか」
「俺が堀内です。もしかして、お二人は『FINDER』の記者さんたちですか」
堀内は二人に満面の笑みを向けた。ガタイがよく、肩まである茶色の髪に黒いタオルを巻いている。耳には銀色のピアスが光り、左右で違ったデザインになっていた。右の天使は微笑んでいるが、左は不気味な髑髏で、こちらを睨みつけている。
北村が名刺を差し出すと、堀内はホッとした様子で歩き出した。
「よかった。おっかない人が来たらどうしようかと思ってたとこです」
堀内は笑顔のまま、桐生たちを座敷へ案内した。スタッド付きの黒いブーツがコツコツと床を鳴らす。オレンジ色の間接照明に照らされた通路を進み、引き戸を開けた。なかは個室で、四畳ほどの座敷になっている。
桐生は上がり框でスニーカーを脱ぎ、テーブルの手前に座った。掘り炬燵になっている。
奥に座った北村はメニューを一瞥し、Aランチを注文した。牛カルビと塩タンにライス、サラダとコーヒーが付いてくる。桐生はBランチの熟成豚のロースとやみつきハラミにした。
「お二人は樹里亜のことを知りたいんですよね? 店長には話通してあるんで、このあと質問に答えますね」
堀内は持っていた伝票に素早くオーダーを書き込み、テーブルのコンロに火を点けて座敷から出ていった。
「堀内君には、後ろ暗いところなんてないみたいだね。俺たちにも感じいいし」
「落ち着きすぎですよ。もう別れてるといっても、三年も付き合ってた彼女が失踪してるんですよ。それなのにちっとも心配してないなんて、逆に怪しいと思います」
桐生は目を眇めた。
「西岐さんは、もっと瀬田さんのことを心配してたよな。遺体の身元も報道されてるから、西岐さんは相当なショックを受けてるだろうな。桐生君と璃子ちゃんは、月曜日にも西岐さんに会いに行ったんだろ?」
「ええ、でも留守でした。もしかしたら事件のショックで、どこかを彷徨ってるのかもしれませんね」
現実逃避のために、どこかのホテルにでも篭っているのかもしれない。
「西岐さんは西岐さんで怪しいけどね。卯月君が見た車は、西岐さんのかもしれないからね。痴情の縺れで殺してしまって、警察の目を欺くために連続殺人犯を騙ってる可能性だってあるよ」
『名もなき殺人者』に関係した取材内容は、デスクを含め特集班で共有していた。
北村は清澄のファィルをテーブルに広げると、タブレットのカメラで撮り始めた。数枚撮り終えたあと、ファィルを桐生に見せてくれた。
樹里亜が特大苺パフェを手に持ち、微笑んでいる。この時の樹里亜は黒髪のボブカットで、サイドの髪を金色のピンで留めていた。写真の横に丸みのある文字でパフェの感想が書かれている。
瀬田絢子とも白石夏希とも似ていない。『名もなき殺人者』はどうやってこの三人を選んだのだろう。
桐生が考えていると、堀内が戻ってきた。そつのない動作でおしぼりを手渡し、ランチセットを二人の前に置いた。牛カルビは赤みにほどよくサシが入っている。桐生の豚ロースは厚みがあり、ハラミの横には輪切りの玉ねぎが載っていた。サラダはベビーリーフの上にスライスされた赤と黄色のパプリカが散らされている。
「きみは、いつごろまで樹里亜さんとお付き合いしてたの?」
北村はおしぼりで手を拭いながら切り出した。
「今年の二月に別れました。彼女、もともと被害妄想気味で、気分の浮き沈みが激しかったですね。ちょっと嫌なことがあると何度も電話を架けてきて、真夜中に会いに来いとか強要してきたり。既読スルーするとLINEが何十通も届いてゾッとしました。疲れたってのが本音です」
「樹里亜さんは、きみのことが大好きだったんだろう。堀内君、モテるでしょ? だから心配されてたんじゃない?」
北村は“浮気を疑われていたのでは?”とは訊かなかった。取材対象への言葉遣いには気をつけなければならない。熱くなった網に肉を載せていく。
「いや、あっちが恋愛にのめり込むタイプだったんですよ。一種の依存症って奴かな」
「だから堀内さんから別れを告げたのか」
桐生はサラダをフォークで突き刺しながら、堀内に視線を向けた。堀内のピアスが揺れている。不気味な髑髏のほうだ。
「深みに嵌まる前に別れたほうが、お互いのためだったんですよ。俺は自由になりたかった。記者さんならわかるでしょ?」
堀内の言葉に桐生は首を傾げた。この男が樹里亜に対して不誠実だったことはわかる。トングで北村の塩タンと自分のやみつきハラミをひっくり返す。
「樹里亜さんは、どうして失踪したんだと思う?」
北村は赤いパプリカを口に放り込み、コーヒーで流し込んでいる。舌は火傷しないのだろうか。
「樹里亜はよく俺に『自殺してやる』って言ってました。闇に魅入られているっていうのかな。どうしてあんなにきれいなのに、破滅的になっちゃうんでしょうね。失踪したって聞いて、自殺を決意したのかと思いましたよ。でも、そのうちに戻ってくるんじゃないですか。いざ死ぬってなったら、さすがにビビるっしょ」
堀内から別れを切り出された樹里亜は、堀内を責めたのではないか。堀内の関心を引くために樹里亜は失踪した。そう、堀内は思っているかもしれない。
桐生は口を歪め、やみつきハラミにかぶりついた。
堀内から聞いた話が真実なら、清澄樹里亜には自殺願望があったことになる。自宅で清澄のファィルを確かめたが、張り詰めた空気などは感じられなかった。希死念慮を窺わせるものもない。
お気に入りの服のコーディネートはフェミニン系で、休日は渋谷にあるレストラン・『パフューム』でトロピカルパフェを食べていた。ごく普通の女子大生としか思えない。
ためしに『パフューム』で検索すると、渋谷の公園通りにあるとわかった。帰りに寄ってみようと思っているうちに、麻布十番駅に着いた。北村は白石夏希が通っていたボイストレーナーに会ってくるといい、途中で別れていた。
地下道を通って地上に出ると、急に雨が降り出した。走れば十分もかからない。コートのフードをかぶり歩き始めたが、編集部に着く頃には土砂降りになっていた。ドアを開けると璃子が駆け寄ってきた。
「西岐さんの本、取り寄せて読んでみたのよ。そしたら、これ」
璃子は手にしていた西岐の著書『人生を遊ぶ』を開き、差し出した。桐生はナイロンコートの水滴をフェイスタオルで拭きながら、開かれたページに視線を向けた。見開きはカラー写真で、西岐が黒い車にもたれかかるようにして笑っていた。車体のフロントグリルに写るエンブレムはアウディだ。
「瀬田さんが乗り込んだのは、西岐さんのアウディでほぼ決まりね。これから西岐さんの自宅へ行って、瀬田さんと会っていたことを確かめましょう」
璃子はコート掛けからライトブルーのレインコートを掴んだ。
「電話を架けといたほうがいいんじゃない?」
桐生は本を璃子に返し、スマートフォンを取り出した。電話を架ける前に、コーヒーを一杯飲む時間が欲しかった。
「何度も架けたわ。でも架け直してくれないから、取材を拒否してるのかも。本当に留守なら、管理人に聞いてみましょう」
璃子は桐生が返事をする前にドアを開けた。
雪が谷大塚駅を出たところで雷が鳴った。雨脚は弱まらず、黒く濡れたアスファルトを激しく打ち付けている。傘に雨が当たる音が耳に響いた。人通りは少ない。
桐生たちの横を、時折タクシーが走り抜けていった。璃子は水溜まりを器用によけながら足早に進んでいく。十分後には赤茶色のマンションに辿り着いた。土砂降りでも体内方位磁石に支障はないらしい。
桐生の髪は湿気のせいで二倍に膨張していた。エントランスで傘を閉じ、桐生はほっとした。
「さっき、北村さんと一緒に清澄さんに会ってきたよ。娘さんが今年の八月二十九日に失踪してる。机の上に、十字の印が入ったビー玉があったんだよ。夏希さんが持ってたものと同じだろうね」
「じゃあ、瀬田さんの事件を合わせて三件が繋がったのね。もし、犯人が西岐さんなら、前代未聞の一大スクープになるわ」
璃子は毅然とした表情で集合ポストに近づき、眉を寄せた。四〇三号室のポスト投函口からチラシがはみ出している。
「西岐さん、本当に留守かもしれないわね」
「とりあえず、部屋へ行ってみよう。部屋に篭ってるだけかもしれないし」
エレベーターのボタンを押すと、すぐに扉が開いた。なかへ乗り込み、四階を押す。
「本当は失踪した女性たちが無事であってほしいのよ。もし犯人が彼女たちを殺さずに監禁しているなら、助け出してあげたい」
「うん。竹本君は夏希さんが生きてるって信じてるしね。十一年前に夏希さんに何があったのかわからないけど、もし自分から犯人に会いに行ったんなら、犯人との間に信頼関係があったのかもしれない。そんな相手を、犯人も殺せないんじゃないかな」
桐生は鞄からフェイスタオルを取り出し、コートの水滴を拭いた。璃子は水滴が気にならないらしく、エレベーターの表示モニターを見つめている。
「『メネラウスの迷宮』の詩、何かに似てると思ってたの。きのう思い出したんだけど、ウィリアム・ブレイクの『無心のまえぶれ』って知ってる?」
璃子は赤い傘を左手に持ち替えた。傘があった右側に小さな水溜りができている。
「ブレイクの絵なら見たことがあるよ。ダンテの『神曲』の挿絵として使われていたよね。タイトルは『聖物売買の教皇』だったかな」
今年の二月、著名な彫刻家の自宅を訪ね、『神曲』の挿絵を見せてもらう機会があった。絵の中央には大きな円筒が描かれ、男が頭から円筒の穴に落ちていこうとしていた。
男の両足首は炎に焼かれていた。そのすぐそばには、子供を抱きかかえた男がしゃがみこみ、円筒から突き出た足を見つめている。解説には、しゃがみこんでいる男はウェルギリウスで、抱きかかえられているのはダンテだと書かれていた。
「ブレイクは画家でもあるけど、詩も有名よ。幻覚を見ていたともいわれたブレイクの詩は、多くの芸術家にインスピレーションを与えたらしいわ。桐生君も、ぜひ読んでみて。きっと夏希さんは、ブレイクの詩が好きだったんだと思うわ」
エレベーターのドアが開いた。水溜まりを残して外へ出る。通路にも水が溜まり、排水溝へ流れ込んでいた。
「こんな大雨の日に、アウトドアを楽しめるはずないよ。西岐さん、部屋にいるんじゃない?」
桐生は四〇三号室のチャイムを鳴らしてみた。だが、応答はない。
「管理人さんを訪ねてみる?」
桐生の問い掛けに、璃子は「ちょっと電話を架けてみましょう」とスマートフォンを取り出した。しばらくすると、ドアの向こうから電話の着信音が聞こえてきた。
「西岐さん、いるみたいね」
璃子はドアノブに手をかけた。ドアが開く。傘をドアの横に立て掛け、二人はなかへ入った。
「西岐さん、『FINDER』です。お話を伺いたいんですが」
桐生は呼び掛けながら、玄関を見回した。飾り棚の上に置かれたスマートフォンが鳴り続けている。
間接照明は点いたままで、正面の壁に飾られた青い抽象画が下から照らされていた。靴は一足も出ていない。つねにシューズボックスにしまうのだろう。あるいは煙草でも買いに出掛けたのか。
前回通された仕事部屋を覗くが、誰もいなかった。部屋は片付いている。ガラステーブルの上には飲みかけのコーヒーカップ一つ載ってない。電気は点いているのに、不自然なほど人の痕跡が感じられない。
――すぐに立ち去るべきだ。
高校時代の数学教師は、「何よりも直感に従え」と教えてくれた。胸の奥で何かがざわめいている。この感覚は以前にもあった。あのときも桐生は直感に従わなかったが、後悔はしていない。見つけること。そして何かを見つけたら声を上げる。それが自分たちの仕事だと信じていた。
桐生は廊下へ引き返し、手前の部屋のドアを開けた。六畳ほどの部屋に棚があり、大きめのバックパックや釣竿、ライフジャケット、何に使うのかよくわからない色とりどりの紐などが整然と並べられていた。
「西岐さん、きれい好きね。展示が趣味とか」
璃子が後ろから部屋を覗き込んだ。飾られた釣竿はよく磨かれている。璃子を残し、桐生は廊下へ出た。どこかで換気扇が回っている。前方のドアの向こうは洗面所だろう。
ドアを開けようとして、手を止めた。突き当りの部屋から、かすかに音楽が聞こえてくる。
「西岐さん、いらっしゃるんですよね?」
突き当たりの部屋に近づきながら、西岐に呼び掛けた。昨夜は徹夜し、まだ寝ているのかもしれない。目覚ましの曲が流れているのだろうか。
ノブに手を掛け、ドアを開いた。
十畳ほどの寝室で、ダブルベッドが置かれていた。ベッドの向こうはガラス戸になっていて、カーテンは開いている。激しい雨がガラス戸に無数の筋を作りながら流れていた。
壁際に黒のローチェストがあり、上に黒いステレオスピーカーが置かれていた。曲はそのスピーカーから流れている。繊細で鋭角なギターにハイヴォイスが重なった。
中央の黒いパネルに青い文字で曲名が表示されているが、小さくて読み取れない。だが、桐生はその曲がU2の『Where The Streets Have No Name』だと知っていた。音は響き合い、増殖していく。
白いシーツの上に横たわるものは、異常だった。両腕を頭上に伸ばし、顔は天井を向いているが目は閉じている。服は身につけていない。浅黒い肌に汚れはなく、みずみずしいとさえいえるほどだ。だが死んでいる。体が奇妙に捻れているだけではない。遺体は真っ二つに切断され、左胸に円と十字の印が刻まれていた。それは西岐亮司だった。
警察に通報後、わずか四分で制服警官が到着した。そのあとは機捜の刑事や田園調布西署の刑事たちが次々と臨場し、現場は騒然となった。
桐生と璃子は刑事たちに同じ話を繰り返した。璃子は真っ青な顔で、ずっとハンカチで口元を押さえていた。桐生も璃子と変わらないほど蒼白だったに違いない。
二時間後、田園調布西署へ移動し、二人は別々に調書作りに協力した。刑事課室で年配の刑事が淹れてくれた薄いコーヒーを飲みながら、桐生は自問自答を繰り返していた。
――なぜ、犯人は遺体を切断したのか。
シーツには、ほとんど血痕が付いていなかった。詳しい死因は司法解剖を待たなければならないが、頭部に損傷があったことから、死因は鈍器で殴られたことによる脳挫傷ではないか。
切断はバスルームで行われたことがわかっている。遺体の皮膚がきれいだったのは、切断後にシャワーで洗ったからだろう。
まともな感覚で考えれば、犯人は犯行後、一刻も早く現場を去りたいはずだ。だが、この犯人は違う。殺人現場を自分の作品のように演出していた。
西岐を殺害したのは『名もなき殺人者』だ。あの手紙に書かれたことが事実だとすると、今回の殺人で六人が殺されたことになる。
これは、警察への挑戦だ。遺体を切断することで残虐性を倍加し、歴史に自分の名前を刻もうとしている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
