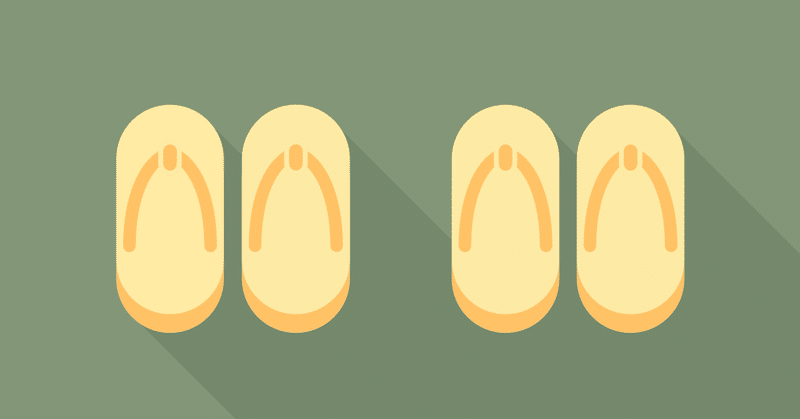
コントラバス売り
「たのもう、たのもう」
武術太極拳連盟東京都へじま区支部の門は、建物が建設されたときからこれまで、延べ689回たたかれてきた。本日新たに「690~693回目の叩き」を行ったのは、瓜田小甚(うりたこはなはだ)という青年だった。日本列島にぎりぎり含まれるが、地図上ではなく索引にしか名前が載っていないほど小さな島で生まれ育った彼は、クラウドファンディングで募ったお金で都内進出を果たしたというわけだった。残った金はすべてディアゴスティーニに消えた。今日明日の飯にも困っていて、消費者金融、区役所生活科と行き先を迷った挙句ここへ来た。門下生となればあわよくば、寝食を恵んでもらえるのではと考えたのだった。もちろん月謝という概念を知らないわけではなかったが、クリスマスムード一色の都内のイルミネーションや、年の瀬のたのしげでにぎやかな空気感が、「まあどうにか煙に巻けるだろ」という彼持ち前の軽薄なポジティブシンキングに拍車をかけたのであった。
「君、入門希望者?」
扉を内側から開いたのは小人のようなおじいさんであった。一見すると虚弱なハゲにしか見えない普通の壮年なのだが、ゆっくりとした動作の中にはどこか品がある。体の芯がはっきりととおっていて、歩いてもまったく揺るがない体幹が、明らかな達人であることを裏付けていた。小甚の直感が、この人にウソは通じないと告げた。
「僕はこの街にコントラバスを売りに来たのです。」
小甚は静かに狂っていた。しかし、それをまた良しとして受け入れることで、言動は人間の範疇を少し超える程度で済んでいた。自分の父親や母親のことを見て、「自分は常人だ」と思い込むことこそが人を狂わせる最大の原因となることを、小甚は理解していた。
「しかし、それには体力も財力もコントラバスも足りない。この場所の一角で、弦だけでもいいので作らせてくれないか。」
かなり無理は承知だった。関係者でも入門希望者でもないものが急にきて、あらゆるステップをすべて放棄して武道場の一角で弦楽器を作らせてくれと伝えてくるのだ。起きていることとしては、天変地異とほとんど変わらない。
にもかかわらず、老人はあっはっはっはと笑い出した。
「ご老体、認知に異常が?」
「いや、すまん。何言っているか本当にわからないので笑ってしまった。」
「入りなさい。ともかく君には必要なものがあるだろう。今日、この扉をたたいた時に、君が支払った勇気とユーモアの分くらいは、助けになろう。」
「使えるジジイだ。月謝の話だけはしないからな。」
二人は英検準二級の面接問題の話などをしながら、会館の廊下を進んでいった。
こんにちは、サポートエリアです。 サポートエリアを見てくれてありがとうございます。 見てくれて嬉しいです。 サポートエリアでした。
