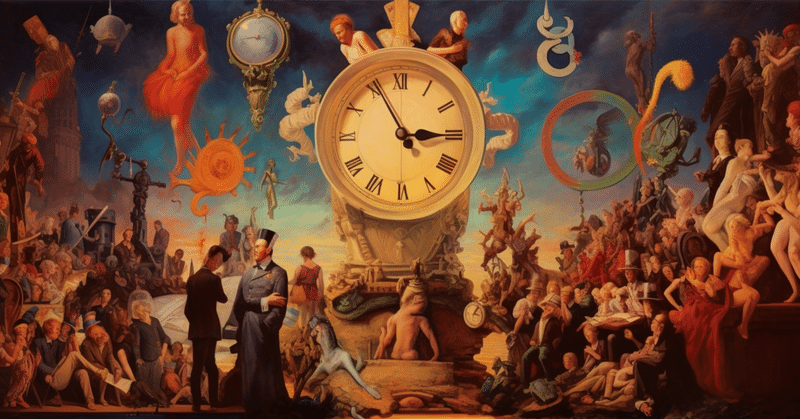
レゴ🄬シリアスプレイ🄬メソッドとシュルレアリスム
シュルレアリズムに関心をもち、それをテーマとして調べている学生から相談があった。ゼミの時間を使って、シュルレアリスムの考え方に沿ったワークを実施してみたいという。
シュルレアリスムの手法に沿って作られた作品を鑑賞することについてはいろいろと語られているものの、自分でシュルレアリスムの考え方を使って何かを作ってみるのは面白い。
その学生をはじめとする、これまで参加したゼミのメンバーは何度も(延べ50時間以上)レゴ🄬シリアスプレイ🄬メソッドを使ったワークを体験している。そのワークの中で、レゴ🄬ブロックを使ってシュルレアリスムを自分たちで体験することができるのではないかと考えたという。
面白い取り組みだと感じたので、許可して実際に行ってみた。主な手順は以下の通りである。以下の手順では基礎演習は除いている。
(1)ブロックから手に任せてモデルを作ってみる(作業 8分)。
(2)作ったモデルを自分のこととして読み解いて話してみる(相互に作品への質問もする)。
(3)モデルを見ながら、紙に心に浮かぶ言葉、フレーズ、文をひたすら書き出していく(作業 5分)
(4)書き出した「言葉、フレーズ、文」が「現在の自分にかかかること・最近のエピソードについて、どこまで表現できているか」について分析し、つながりを可視化する(→その結果を共有して意見交換する)

作品は作品作りで行い、その後に作品を見ながら改めて文章を書くという体験は新鮮だった。
何を作っているのかも考えずに作ったモデルには、後付けで見ていると、自分のことが比較的強く関連して出ていた。この点は、何回体験しても面白い。
ブロックを山積みの中から取り出すとき、それをくっつけるときに何らかの手掛かりや判断をしているのだが、そのときに自分の記憶のなかにある何かが判断の材料に使われるのであろう。参加者の中には、最近の休みに行った場所や読んだマンガを想起させる表現があると言って驚いていた。頭の中では、ぐるぐると記憶の断片が沈み切らないまま漂っているのかもしれない。
また、そのモデルを見ながらなんとなく書きだした文章は自分のことが多かった。これはワークの中で一度自分のこととして意味づけしたために、より明確に文章に出やすくなったと思う。
文章の中盤から書いていた「文・フレーズ・文章」は、モデルの表現から離れ、モデルを中心とした情景描写に文章が移っていった。より具体的にはモデルからの視点で見える風景のワードが書かれていった。
これを後から見直して、自分のこととして見てみると、自分の抱えている悩み(対人関係が苦手なこと)が表れていると感じた。
モデルから文章へという転換は面白い。モデルを説明的に記録するのではなく、モデルを見ながら心に浮かぶことを書くほうが、モデルの記録として優れている部分があるのではないかとも感じるほどであった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
