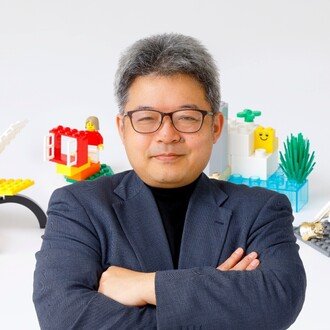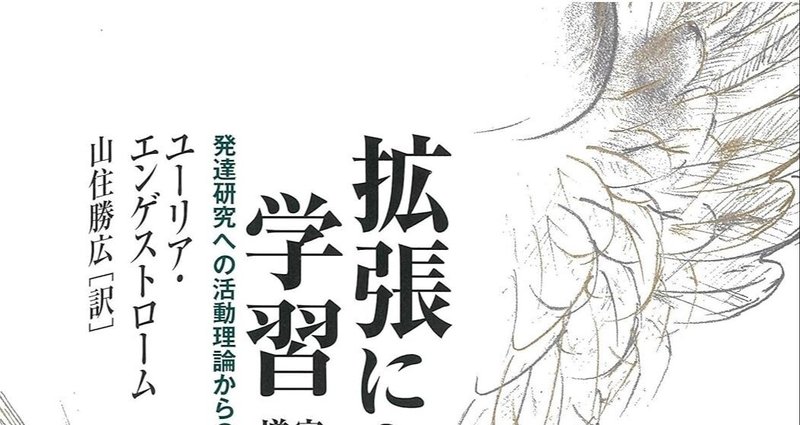
ユーリア・エンゲストロームの活動理論に基づく『拡張する学習 完訳増補版』について簡単に内容を紹介しながら、レゴ🄬シリアスプレイ🄬メソッドとの関連を考えていきます。
- 運営しているクリエイター
記事一覧
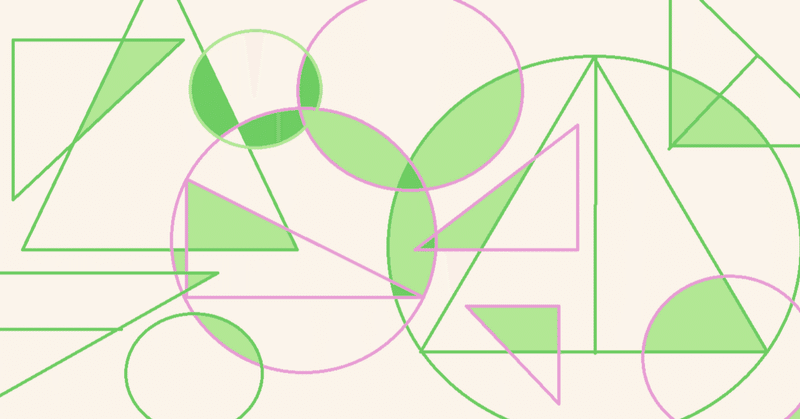
『拡張による学習』をレゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドの文脈で読む(4)第2章 人間の学習の歴史的形態としての学習活動とその出現(前半) p.67~
本書の第2章は100ページ以上あるため、前半と後半に分けてみていきたい。 章のタイトルは「人間の学習の歴史的形態としての学習活動とその出現」となっている。学習ではなく「学習活動」としているのが一つ目のポイントで、前半では人間の「活動」というものの大きな枠組みが示される。 もう一つのポイントは、人間の学習活動は時間と共に進展するという意味で歴史的であり、一般的な構造に基づきながらも領域ごとに異なる進化を遂げるという意味で文化的であるという点である。これは本章の後半で主に