
【アマテラス誕生の謎】高天原は阿波にあった!
お元気様です。
歴史沼チャンネルのきーです。
四国・阿波には、日本の正史が隠そうとしている古代史の謎がたくさん存在することはご存じでしょうか?
日本神話や日本の成り立ちの歴史は、九州・出雲・奈良大和を中心にして語られています。
ですが九州や出雲・奈良大和を日本の成り立ち・神話の舞台として語るには、あまりにも辻褄が合わないことが多いです。
たとえば、邪馬台国に位置や、神武東征の謎、高天原や天磐船の話など、いまだに解明されていない謎がたくさんあります。
しかし近年、この謎を解く遺跡や伝承が四国や阿波に集まっていることが注目されています。
なので今回は、『高天原は阿波にあった!』というテーマでご紹介します。
YouTube動画で見たい方はこちらです💁♀️
高天原とは?
最初に高天原とは...ということを簡単に説明しておきましょう。
高天原とは、日本神話のなかで天照大神をはじめ多くの神々が住んでいたとされる天上の世界で天照大神が統治していた世界です。
ギリシャ神話に例えればオリンポス山、北欧神話に例えればアスガルドのような場所が高天原です。
日本神話について書かれている『古事記』の上巻には、高天原での神々のエピソードや出雲国の大国主のエピソードを中心に記されています。
国生み神話

高天原や天照大神のお話をするには、天照大神が誕生する前までのお話をしなくてはなりません。
天照大神の生みの親である、イザナミとイザナギの2柱の神様のお話である国生み神話から話を始めましょう。
国生み神話とは、国作りを命じられたイザナギ・イザナミが下界の海をのでかき混ぜると、この矛先より滴り落ちる潮が積もり重なってという島が出来上がりました。
この島は、オノコロ島といいます。
この2柱がオノコロ島に降り立つと、天の御柱という大きな柱を立ててそれぞれ柱を回り合い、出会ったところで「ああなんと、りっぱな男性だこと」、「ああなんと、美しい女性だろう」と呼び合い、二人で多くの島々を生みました。
2柱の神がこの時に生んだ島は国となります。
はじめに生んだ島が淡路島、つぎに四国、隠岐島、九州、壱岐、対島、佐渡島をつぎつぎと生み、最後に本州を生みました。
これが日本の国土のはじまりです。というのが、日本神話の世界観です。
国生み神話の舞台は阿波だった
国生み神話の説明が終わったところで、この【国生み神話の舞台は阿波徳島だった】というお話をしていきましょう。
まず国生み神話の話を聞いて1番最初に謎に思うのは、なぜこの順番に国を生んだのか?ということではないでしょうか?
日本の成り立ちが奈良ヤマトから始まったと考えるならば、国生みで奈良ヤマトがある本州が1番最後に生まれるというのは疑問が発生する点です。
その後のヤマト王権や天皇の統治の中心が畿内であったことを考えると、国生み神話で畿内が一番最初に生まれていても良いはずです。
阿波古事記研究会
国生み神話で生まれた四国の国別け
この国生み神話では、四国や九州については地勢が詳しく語られ国別けも行われているのに対し、本州については名前だけの登場になります。
国生み神話で生まれた国の詳細はこちらです。
淡路島
伊予二名島(これが四国)
隠伎の三子島
筑紫島(九州)
伊伎島(壱岐:長崎)
津島(対馬:長崎)
佐渡島
豊秋津島(畿内:本州)
このうちのは国別けもしっかりしてあり、現在の四国とほぼ一緒です。
そして、分けてある各国に祖神となる神様も存在します。
このうちのは国別けもしっかりしてあり、現在の四国とほぼ一緒です。
そして、分けてある各国に祖神となる神様も存在します。
四国の国別けはこの通り!
阿波(粟国):オオゲツヒメ
讃岐国:イヒヨリヒコ
伊予国:エヒメ
土佐国:タケヨリワケ
名前だけの登場が多い『古事記』の中で、国生み神話に書かれた国々の中でも何度も登場するのは阿波のみです。
このオオゲツヒメは、五穀の神、食糧の神として祀られます。
阿波は昔、飯の国と書いてイノクニと呼ばれていたそうです。
『古事記』に書かれたのは四国東部、をイの国,西部を予の国といっていた時代の呼び名です。
阿波の祖神
そしてこのには別名があり、その別名をといいます。
このオオゲツヒメとは、伊勢神宮の外宮に祀られている神様で、同じく伊勢神宮に祀られている天照大神に食事を提供する神です。
伊勢神宮は天皇家の高祖神である天照大神をまつる神社ですが、本当はを祀るためにできたのではないか?や天照大神よりの方が上位に祀られているなど噂されることを知っている方も多いのではないでしょうか?
『古事記』国生み神話で生まれた神の中で一番多く登場し、伊勢神宮にも祀られるが阿波の祖神であるというのは、日本神話の中で阿波が特別な存在であることを表しているのではないでしょうか?
オオゲツヒメについては、こちらの動画・こちらの記事をどうぞ。
出雲は阿波にある
そして次々と国生みをしていったイザナミですが、は火の神であるカグツキを生んだために陰部に火傷を負い亡くなってしまいます。
古事記では命は「出雲国と伯伎国(ははぎのくに)との堺との比婆山に葬りき」と書かれているのでイザナミは、亡くなると山に葬られたということがわかります。
従来であれば、『古事記』は大国主命のエピソードが満載なので「出雲国と伯伎国(ははぎのくに)との堺との比婆山に葬りき」の出雲国とは、出雲大社がある島根県のことだと思ってしまうのではないでしょうか?
先ほど紹介した国生み神話では島根県がある山陰地方は登場しません。
なので国生み神話の当時は島根県は別の文化圏地域であった可能性があります。
実際に今でも出雲国は島根ではなかったのではないか?や出雲大社に祀られているのは本当は大国主命ではないのではないか?などの説がいまだに言われています。
それでは『古事記』に書かれた出雲はどこにあたるのか?
先ほども紹介したように阿波の国は以前「イ(飯)の国」と呼ばれていたことが古事記や日本書紀の記述から確認することができます。

出雲とは、イの国の海岸部。
つまり阿波の海岸部をイツモ(伊津面)と呼んでいたそうなのです。
この説に当てはめると出雲は、今の徳島県の東部、阿南市や徳島市・鳴門市を含む地域です。
『古事記』に登場する出雲国は、阿波の東部の海岸地域だった可能性があるのです。
高天原は阿波にある
イザナギ・イザナミの神話のお話に戻りましょう。
イザナミが亡くなった後、イザナギはイザナミに会いに黄泉の国に行きますが「決して覗いてはいけない」と言われたにもかかわらず、覗いてしまいの朽ち果てている姿を見てしまいます。
見れたこと怒ったがを追いかけますが、必死に逃げては地上に逃げ帰り黄泉の国の入口を千引きの岩とされる大岩で塞ぎました。
そしてが黄泉の国の穢れを払うために、禊をします。
このが禊をしたときに生まれたのが、のちに高天原を統治することになる天照大神です。
徳島阿波で、が禊をしたと比定される場所は徳島県阿南市です。
カシワと天照大神

この徳島県阿南市のにあったとされる神社は賀志波比売神社です
神社の名前の由来ともなっている、賀志波比売とはどんな神様かご存じでしょうか?
賀志波比売とは、天照大神の幼名だといわれています
イザナギが禊をしたときに生まれた天照大神が、イザナギが禊をした場所である阿波の柏野に幼名で祀られているのです。
皇室の一大神事である大嘗祭で使われる食器には柏の葉が使われたり、神社で神様に拝むときに手のひらを打ちあわせて鳴らすことを「柏手を打つ」ということを考えると、何か関連しているとしか思えません。
天照大神の墓?
そして神話は続きます。
イザナギは天照大神のあまりの神威の強さに、「高天原を治める」ことを命じます。
日本書紀に「天照大御神は、天に送る」と書かれ「古事記」に「天照大御神は高天原を治め」と書かれていることからも、天照大神は生まれた後に高天原に送られたということになります。
では天照大神が送られたとされる高天原はどこなのか?
それはアマテラスの墓とされる場所があるがある剣山一帯ではないでしょうか?
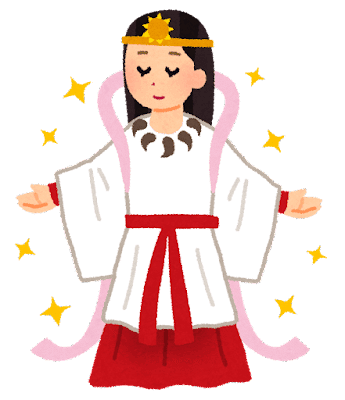
アマテラスの墓とは、天石門別八倉比売神社です。
天石門別八倉比売神社とは、背後の古墳をご神体として祀っている不思議な神社で祀られている神は、大日孁女命(オオヒルメノミコト)です
この大日孁女命(オオヒルメノミコト)は天照大神の別名だといわれています。
このとは邪馬台国の卑弥呼の墓とも言われていて、阿波の古代史では卑弥呼と天照大神を同一視しています。
延喜式神名帳と式内社

天石門別八倉比売神社のある剣山一帯は、ほかにも延喜式神名帳に記されている神社の中でも阿波にしかない神社がたくさん存在します。
延喜式神名帳とは、平安時代に編纂された古い神社や神祇祭祀について書かれた書物です。
この書物に書かれた神社というのは平安時代には確実に存在していたことがわかり、当時においても有力で由緒正しい神社であったと思われます。
延喜式神名帳に書かれた神社を「式内社」と呼びます。
神話の中でも早い段階でなくなってしまうを祀る式内社は1社しかなく、その1社は剣山一帯に存在します。
ほかにもが産んだ神を祭る神社など、関連する「式内社」は阿波にしかない神社が多いのです
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は、【高天原は阿波にあった!】というテーマで紹介しました。
阿波には、日本神話の初期の初期である国生み神話のエピソードに関係した場所がたくさんあります。
『古事記』は高天原と出雲の話がメインで描かれています。
もし高天原も出雲も徳島阿波にあったとなると、『古事記』の舞台は阿波徳島だったことになります。
日本神話や日本の成り立ちのすべてが徳島阿波だ!と言い切るには、まだまだ証明が足りないですが、偶然の一致では済まない古代史ロマンを感じるお話だったのではないでしょうか。
今回紹介した内容の情報元は、こちらです。
今後も阿波に隠されている古代史の謎について紹介していきますので、楽しみにしてください。
ばいばーい!
この記事は私が運営しているYouTubeチャンネル【きーの歴史本プレゼンチャンネル】の動画を、テキストにしたものです。
【きーの歴史本プレゼンチャンネル】はこちら💁♀️
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
