
久しぶりに認知症の母についての話・1
久しぶりに認知症の母について書きたいと思う。
最近、大変感心して読んだ精神科医、小澤勲さんの『認知症とは何か』という本と出会えたからでもある。
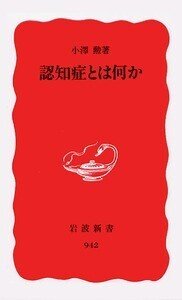
認知症者の心理面(情緒面)はその前段となる本、『痴呆を生きるということ』により多く割かれていて、本日の記載はどちらかといえば、後者の本の影響がよりダイレクトかもしれない。(本日の記事は続きを加えて書きたい)
おそらく、今の母の認知症は記憶障害(甚だしいのは短期記憶障害)に加え、見当識障害(時間、空間、人の認知がわからなくなる)がかなり出てきているので、認知症も中程度に入ってきていると思う。着衣着脱もだいぶ怪しくなったり、妄想がたりや、見えない人を相手に独りで話をしていたりすることも増えてきた。
特にいま、毎日の訴えとして、母が自分の両親や叔母がいま自宅にいるのか、いつ帰るのかという訴え、つまり亡くなった彼らが我が家に同居しているように思う訴えがある。(このことに関しては、小澤勲さんの『認知症とは何か』に「幻の同居人幻想」という言葉で紹介されていて、“あ、症状としてあるんだ“と大いに安心させてくれ、励まされた次第だ)
あるいは「明日からもうここには帰ってきませんから」と突然に宣言する。この帰宅願望は「夕暮れ症候群」というらしい。この点の自分の想像も、後日書きたい。
直近では小澤さんの本を読んだ上で、読む前から自分の推察のアプローチで概ね間違いはなかったんだなと安心というか、確信を得たのだが、一時は僕も母を相手に盛ん論理的に対応して、何度も激論になった。そこを少しだけ諦めることでお互いの関係が少し落ち着いたところが今現在、というところだ。(だが、時折蒸し返してしまうとは思う)。
それで、でも正直思うのは、老いた母に何か根源的な寂しさがあるのではないか、僕には埋められない固有の「喪失の感覚」があるように思えるのだ。
ただ、そこになぜか自分の夫、つまり僕の父親が全く出てこないのが不思議。以前は何とも不人情なものだな、やはり自分の夫との成人してからの家計維持生活は、両親や自分の姉妹や従兄弟と暮らしていた“娘時代“に比べて、安心の記憶からは遥か距離があるのか、と思っていた。しかし、実際そういう側面もあるのかも知れないが、実は「自分の夫も含めた」包括的な安心の感覚が母から失われつつあるのかも知れない。そしてそれこそが母の無意識にとっては決定的なものなのかも知れない。同居しているはずの「自分の両親」とは、実は言葉にできないけども「自分の夫」も含まれているかも知れないと最近憶測している。
僕の父親へ長く母は介護者としてその役目を果たしてきた。(ついでに言えば、自分の両親も介護していた。祖父母を引き取っていた母の姉夫婦は介護に自信を持てなかったので看護師だった母に依頼していたのだ)。
そうやって僕の父を気にかけ、介護することも実は母の依存の方法であったのかも知れない。いまやその対象も失い、ぼくみたいなものにも頼らないといけない。それは無意識のうちに情けなく、悔しく、「でも、やはり頼りたいのだよ」という両面感情があるのかも知れない。
僕には母の個的実存の深い喪失は埋めきれない。子にも距離は必要だ。その点では自分でもかなり意識してむきあっている。自分が共倒れしないためにも。でも、それでも母はいまぼくにとって一番大切な存在であるのは間違いない。
人は「世話をする」こと。逆に「世話になる」こと。その両面において、自分の中の喪失を埋める何かがあるのかも知れないと思う。
自分以外の誰か人がいてくれるというのは、実は我々にとって非常に根源的なことなのかもしれない。たとえ普通の意味でコミュニケーションが取れなくなっても、存在感そのものの、そのありかによって。
よろしければサポートお願いします。サポート費はクリエイターの活動費として活用させていただきます!
