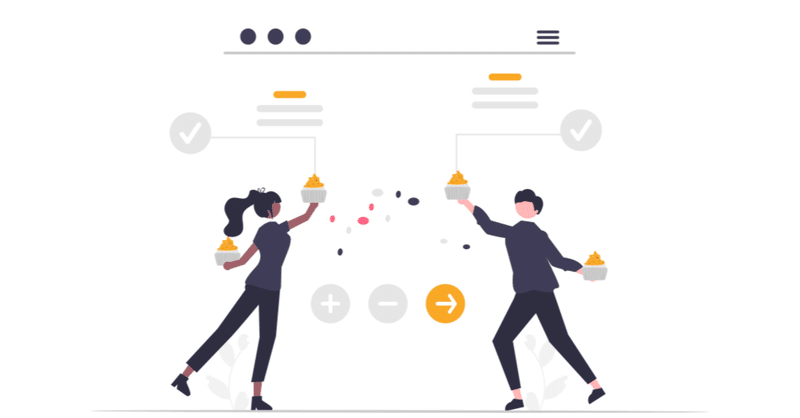
パフォーマンスマネジメント評価を導入するべき?グローバル企業が導入する最先端のマネジメント評価とは?
現在、欧米のグローバル企業を中心に世界中で広まっているマネジメント手法がパフォーマンスマネジメント評価です。
パフォーマンスマネジメント評価は、「従業員が主体性を持ちながら挑戦でき、やりがいの持てる職場を構築するマネジメント手法」としての評価が高まり、多くのグローバル企業で普及が進んでいます。
本記事ではパフォーマンスマネジメント評価の基礎的な知識からデメリット、導入時の注意点まで、実際に導入するときに知っておきたいポイントを分かりやすく解説しています。
パフォーマンスマネジメント評価の導入を検討している担当者の方や評価制度に迷っている方は、ぜひご参照ください。
パフォーマンスマネジメントとは?
パフォーマンスマネジメントとは、社員個人のパフォーマンスを高めるために、管理職や人事部が社員の目標・行動・改善のプロセスをサポートし、結果に結びつけるためのマネージメント手法です。
管理職は社員の行動や結果を評価する立場から、社員自らの行動や気付きを与える立場に変化していく必要があります。
従来の立場よりも一歩社員に近くなることによって、より社員の課題が明確化し、適切なフィードバックを届けることが可能になります。
社員個人も管理職や人事部がサポートしてくれる安心感から、迷いなく行動に移すことができるので、お互いにとってWINWINになるマネージメント手法といえます。
パフォーマンスマネジメントの評価制度を導入するメリットとは?

パフォーマンスマネジメントの評価制度を導入した企業はスピード感が早くなります。
現代は社会の変化のスピードが格段に早くなっているので、スピード感がない企業はかんたんに淘汰されてしまいます。
そういった意味において、パフォーマンスマネジメントの評価制度は現在の時代に合ったマネージメント手法といえます。
過去の成功手段が現在も成功手段であるとは限らないので、社員・管理職・人事部の複数の視点を持ったスピード感のある改善は大きな効果を期待できます。
時代の変化に柔軟に対応できるマネージメント手法は社内の風通しが良くなり、結果も出やすくなります。
また、社員としても、結果が出ることによってさらに自信が付き、より自主的に行動しやすくなります。
社員の帰属意識が芽生えた企業は強く、社員がまた別の社員に帰属意識を波及させてくれます。
こういったプラスの流れを生むことができることが、パフォーマンスマネジメントの評価制度の最大のメリットです。
パフォーマンスマネジメントの評価制度を導入するデメリットとは?
パフォーマンスマネジメントの評価制度を導入するのであれば、デメリットもしっかりと把握しておきたいところです。
デメリットは、下記の2つになります。
デメリット① 管理職が順応できない
1つ目のデメリットとして、従来の評価だけするマネジメント手法に慣れ過ぎてしまった管理職に起こる可能性があります。
パフォーマンスマネジメントはコーチングやフィードバックを頻繁におこないますが、コミュニケーションが苦手な管理職には向きません。
そのため、コーチングの管理マニュアルを作成したり、コーチング研修を実施したりと、管理職が適応しやすい環境作りも必要になってくるでしょう。
社員がいる以上、コミュニケーションが苦手なまま管理職になってしまったのは、企業のシステムエラーの一種なので、これを機に改善できるという発想が大切です。
デメリット② コストに対して効果が見合わない可能性がある
2つ目に、時間と労力というコストが大量にかかるというデメリットがあります。
パフォーマンスマネジメントは面談をする回数が多いため、管理職や人事部、社員の時間が奪われます。
面談中は実務作業は進まないので、時間というコストを投資していることになります。
しかし、面談をしたからといっても必ずいい結果が出るとは限らないので、充実した中身のある面談にしないとコストの無駄使いになってしまいます。
極力面談の時間を短く抑えるために、特にフィードバックする側は事前準備を徹底して社員に「何を気付いてほしいのか?」という部分は明確にしておく必要があります。
面談が中身のある内容になれば、信頼関係が深まり、大きな成果も獲得できるため、有効な投資にもなり得ます。
このようにデメリットはメリットと表裏一体なので、デメリットを把握することは非常に大切になってきます。
デメリットをメリットに変えられる企業が時代を生き抜くのは不変的な事実なので、導入する際は大きなポイントとなるでしょう。
混同されやすいパフォーマンスマネジメントとMBOの違いとは?
パフォーマンスマネジメントと混同されやすいマネジメント手法として、MBOがあります。
ここからはそんなMBOと比較して、具体的にどう違うのか解説していきます。
MBOとは目標管理制度のことで、1年に1回ほど目標に対して行動や結果はどうだったのか評価をおこなう人事制度です。
パフォーマンスマネジメントも同じようなステップを踏みますが、大きな違いは面談の回数です。
パフォーマンスマネジメントは回数を限定せずに面談をおこないますが、MBOは1年に1回ほどです。
以前は多くの企業でMBO制度が採用されていましたが、世の中の流れが緩やかな時代だったから運営できていたマネジメント手法です。
現代の変化が激しい時代において、MBOは時代にそぐわなくなってきています。
MBOのデメリットとして、半年か1年の評価をまとめておこなうため、評価者の時間と労力を膨大に使います。
また、フィードバックの具体性も低いため、社員の組織に対する不信感が芽生えてしまう可能性もあります。
現代においてはスピード感を持って柔軟に対応していかないと他社に大幅な遅れをとってしまいますので、MBOよりもパフォーマンスマネジメントに近年注目が集まっているのが納得できます。
パフォーマンスマネジメントの評価制度を導入する際のポイント
それではパフォーマンスマネジメントの評価制度を導入する際にどのようなポイントを抑えておくべきなのか、具体的に見ていきましょう。
主に「目標設定」「コーチング」「フィードバック」の3点が重要になってきます。
評価制度導入の際のポイント① 目標設定
目標設定では、企業の目標と個人の目標がつながっていることが非常に重要です。
管理者はまず企業の戦略や目標を把握し、チームや個人がどのような行動を取るべきなのか熟考する必要があります。
その上で、社員と話し合って個人の目標を決めるのです。
この時に社員に目標を押し付けるのではなく、目標を達成することでどのような状態になれるのかイメージさせ、自主性を促すことがポイントです。
評価制度導入の際のポイント② コーチング
コーチングをおこなう際は、管理者は聞き役に徹します。
社員の答えを導き出すように問いかけをおこないながらサポートすることによって、徐々に主体性が生まれてきます。
事前に社員の性格やパフォーマンス能力を把握しておけば、導くことが可能になってくるので、ここでも事前準備が重要になってきます。
評価制度導入の際のポイント③ フィードバック
フィードバックの目的は社員のランク付けではありません。
課題や解決策が明確化することによる社員の納得度、モチベーションアップが目的です。
課題や解決策が明確化しても社員が納得して行動に移さなければ何も意味がありません。
課題や解決策を明確化することは社員が迷いなく行動するための手段であって、目的ではありません。
社員一人ひとりが目標とプロセスをしっかりと理解し、自主性を持ってパフォーマンスを最大限に発揮できる環境を作ることが重要です。
パフォーマンスマネジメントにおいて、社員のモチベーションや能力を引き出すという点は最大のポイントなので、十分に配慮した上で導入していきましょう。
次の章では、実際にパフォーマンスマネジメントの評価制度を導入した企業の事例をご紹介していきます。
パフォーマンスマネジメント評価制度の導入事例①|スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックスコーヒーのスタッフは自主性を持って仕事をしていると一般的にも有名です。
それでは、スターバックスコーヒーでは、どのようにしてスタッフに自主性を持たせているのでしょうか。
スターバックスコーヒーでは4か月に1回面談がおこなわれます。
スタッフは4か月を振り返り、個人の短期目標とビジョンとをすり合わせます。
さらに、次の短期目標を設定した上で面談に臨むため、面談の質も必然と高くなります。
スタッフはやりがいや気づきに触れる回数が多くなるため、主体性も育まれ、パフォーマンスが向上するという良い循環が生まれています。
パフォーマンスマネジメント評価制度の導入事例②|アドビ株式会社

アドビは今までの評価制度を廃止し、Check-in制度を導入しました。
Check-in制度とは、3か月に1回管理者と社員がフィードバックし合う制度で、信頼関係の向上にもつながっています。
アドビはパフォーマンスマネジメントの評価制度を導入して以降、離職率が過去最低水準まで下がっています。
離職率を下げたい企業は導入すべきひとつの事例ですね。
パフォーマンスマネジメント評価制度の導入事例③|株式会社三栄建築設計

株式会社三栄建築設計では、従来の評価方法を廃止し、四半期ごとに面談をおこなう制度を導入しました。
管理者はコーチングに徹するようになったので、面談の質が向上し、社員のパフォーマンス向上につながっています。
従来おこなっていた五段階評価は一方的かつ、抽象的だったため、社員のパフォーマンス向上にはつながりずらかった点がありました。
パフォーマンスマネジメントの評価制度を導入することによって、具体的に改善された良い事例のひとつです。
それでは実際にパフォーマンスマネジメントを導入する際にはどのような点に注意すればいいのでしょうか。
ここからは、パフォーマンスマネジメント評価を導入する際の注意点を、具体的に解説していきます。
パフォーマンスマネジメント評価を導入する際の注意点 ①|会社の全体の考えを一致させておく
まずはじめに会社の方向性、目標を管理職だけでなく、人事部、社員にいたるまで一致させておくことが非常に大切です。
この段階でズレが生じてしまうと、個人の目標が達成しても会社としては違った方向に進んでしまったというエラーが生じてしまう可能性があります。
パフォーマンスマネジメントでは個人のパフォーマンスの向上にフォーカスするので、事前にしっかりと方向性を一致させておくことで、会社全体のパフォーマンス向上につながっていきます。
パフォーマンスマネジメント評価を導入する際の注意点 ②|管理職のスキルを向上させる
パフォーマンスマネジメントはコーチングの要素がとても重要になってくるので、管理職のコミュニケーションスキル向上は必須です。
具体的にリーダーやマネージャーの意識改革やコーチング研修をまず最初におこない、制度の土台を固めておくと、効果が最大限に見込めます。
社員のモチベーション向上につながるか、モチベーション低下につながるかを左右する重要な部分なので、しっかりと時間と労力を惜しまずにコストをかけておきましょう。
パフォーマンスマネジメント評価を導入する際の注意点 ③|効果のあるフィードバックをおこなう
パフォーマンスマネジメントを導入するとフィードバックをおこなう回数が多くなるので、質の高いフィードバックはとても重要になってきます。
まず大前提として、管理者と社員の日頃のコミュニケーションは必須です。
人に伝えるときに「誰が何を言うか」の「誰が」の部分が非常に大切で、コミュニケーションが取れていないと、そもそもまともにフィードバックを受け取ってもらえません。
人間関係が築けているという大前提があって初めて、社員のパフォーマンス向上につながる具体的なアドバイスが効果を発揮するのです。
フィードバックの際は目標が達成できたかどうかだけでなく、プロセスに対する評価もしっかりと社員に伝えていきましょう。
「必要とされている」「上司が自分のことを見てくれている」と社員が認識できたら、自然と自主的に行動するようになってきます。
より効果のあるフィードバックができるように、フィードバックの質に対してもこだわっていきましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
本記事ではパフォーマンスマネジメントの基礎知識から導入する際に知っておきたいポイントやデメリットについてもご説明してきました。
パフォーマンスマネジメントを正しく導入することによって、「会社の業績アップ」「社員の離職率の低下」につながります。
会社全体、管理職、人事部、社員すべてのパフォーマンス向上に役立ちますので、ぜひパフォーマンスマネジメントを導入し、より良い組織作りに活用してみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
・・・
ハイマネージャー
OKRや1on1、フィードバック、人事評価などハイブリッドワークのマネジメントに必要な機能が全て揃ったピープルマネジメント・プラットフォーム「HiManager」の提供、及びマネジメント・人事評価に関するコンサルティングを行っています。


