「相対主義」対「絶対主義」との対立=事実を置き去りにした哲学者たちが勝手に議論していること
相対主義も絶対主義も、極端な思考であると思います。古代ギリシアにおける議論で、相手を論破しようとするあまり、”売り言葉に買い言葉”的な流れで見解が極端になってしまったのでしょうか?
真理への確信が個人的・パーソナルなものであることは、共通の真理の否定にはなりません。
そのあたりのことについては、拙著
「本質」という倒錯:竹田現象学における「本質観取(本質直観)」とは実質的に何のことなのか
http://miya.aki.gs/miya/miya_report37.pdf
・・・で詳細に説明しています。(「私がいるから経験がある」のではなく「経験があるから私がいると思うことができる」~経験論への誤解に対する若干のコメント|カピ哲!の後半部分も参考になるかも)
私たちの真理への確信は、私たち自身の具体的経験によって確かめられるものです。そして、その確信を他者と共有できることもあれば、できないこともあります。そして共有できるような事象は「客観性」を有すると考えられることになります。
客観性を有する真理か否かは(客観性を有する真理があるのかどうかは)哲学者が決めることではありません。私たちの日常生活、科学研究、そういった生活の営みの中で、実際に現れている状況、それがまさに「答え」なのです。
見解が対立しているということは対立しているということ。同意できているのだとしたら同意できている、ということなのです。対立している人どうしでも、他の事柄については同意・共感できたりします。
もっとも、異なる考えの人たちがじっくり会話を続けることで共通の見解というものを見出すことができる可能性もないとは言えません。(しかしその場合の会話は、決して古代ギリシア風の議論、相手を論破するだけのテクニックではないことは確かです。)
哲学者たちが「〇〇主義」と勝手に名前をつけて議論したところで、ただの言葉の遊びにしかなりません。
※ ただ、一つの真理を目指している場合、複数の見解があることが(心情的に許せない場合でも事実として)理解できる場合、双方がありそれらはいったいどういう状況なのか、という議論はできるかもしれません。しかしそれらも哲学者に頼まなくても皆さん常識的に理解されているのではないでしょうか(事実と当為など)。哲学者たちはかえって議論を小難しくして混乱させているだけのように思えます。
長友敬一著「相対主義の変遷」『熊本学園大学 文学・言語学論集』第20巻第1号(2013年)1-46ページ
・・・で絶対主義・相対主義の歴史がまとめられていました。今回はとりあえず前半部分を見ていきます。
1.民族の文化が異なることは共通項が無いこととは違う
論文2~5ページにおいて、(古代ギリシアにおいて)民族ごとに異なる文化があることを相対主義の根拠としている様が説明されているのであるが・・・だからといって民族間の交流が不可能かと言われれば、おそらく交易もするだろうし、異民族間の友人関係も構築されることもあったのではなかろうか(断定はできないが)。
文化が違っても、お互いが交流することで、「他の民族の生活習慣もなかなか良いのではないか」と感じ取り入れたりすることもあるだろうし、文化というのは変化していく。共感できない場合もあれば共感できる場合もある。
2.”現れ”が個人的なものであることに関して
プロタゴラスの「人間は万物の尺度である」という主張について、ソクラテスは以下のように説明している(一部のみの引用であるが)。
おのおののものが何らかの様子で僕に現れている場合、そのものは僕にとってそのようなものとしてあり、また君に何かの様子で現れておるならば、それはまた別に君にとってそのようなものとしてあるというのではないか。
・・・個人個人の感覚から判断が導かれる=相対主義、というのは短絡的すぎる(もちろん長友氏自身の見解ではない。長友氏はただ説明されているだけである。)
ソクラテスはプロタゴラスのこの主張に対して反論を展開する。その主旨は、「各人にとってそのように現れているものは、そのように存在している」という主張と「各人にとってそのように現れているものは、虚偽の場合もありうる」ということが矛盾するために、プロタゴラスの主張は間違っている、ということである。ここでは主張の主体の変動も認められ、ソクラテスの反論が完全に正しいかどうかは議論の余地が残るが、ともかくもここから反̶相対主義の流れが哲学史上に現れ、絶対主義の考え方が哲学・倫理学史の主流になっていくのである。
・・・ソクラテスの詭弁である(長友氏も議論の余地が残ると述べられている)。この詭弁を見抜けない人のなんと多いことか。認識が”虚偽”だと分かるのも、別の”現れ”によるものなのである。
私たちの真理への確信は日々更新されている(更新されないものもある)。新たな真理も新たな経験、新たな”現れ”によって導き出だされるものなのである。
3.哲学者たちの主張の空虚さ
長友氏は哲学者たちの主張では何も解決されていないことを示されている。例えば次のように・・・
古代ギリシアでは、正義とは「各人に彼のものを与えること」だとされた時期があった。しかしこれは内容がない形式だけの言葉であり、絶対的な価値を定める正義の定義としては価値がない。
アリストテレスの「徳」の倫理学では、徳を「中庸」と規定している。これは徳を、過剰と不足の二つの不徳の中間とするものだった。善の問題は悪の問題とセットで答えられなければならない。しかし彼の中庸説での不徳つまり悪の存在は、彼の時代の伝統的道徳によって自明なものとして前提されており、悪の問題を解決しているのではないため、善や徳の問題も解決されていることにはならない。
カントが唱えた、義務を規定する「普遍化可能性の原理」、つまり「すべての人に適用されるように望むことができる規範に従って行われる行動は正しい行動である」は内容に欠けている。彼が提示している義務のいくつかの具体例は、結局は彼の時代の道徳や法に従ったものである。
4.「観察の理論負荷性」について
右の図も、人によっては、下から眺めたガラス箱、上から眺めたガラス箱、多面カットの宝石、凧の枠、平面上の単なる線の交差など、さまざまな物に見える、というより、その都度それとしてしか見えないだろう。つまりわれわれは、まず視覚的なパターンをつかんでその上に解釈をつなげるのではなく、見ると同時に解釈している、つまり解釈は見ること自体の中に初めから存在しており、「解釈することこそ見ること」なのである。左の図も、老婆にも見えれば若い女性にも見えるが、片方を見ているときはもう一方は見えなくなる。その時われわれは違った物を見ている・・・(後略)
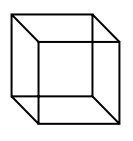

・・・例えば左の絵(図)を見て老婆の絵だと思ったとするならば、それは老婆の絵なのである。そうとしか思えない人たちが集まれば、それは老婆の絵なのだ。そこに「観察の理論負荷性」という考え方は生じえない。
しかしそこで「その絵は若い女性の絵だ」と発言する人が現れてきた場合、そこで初めて異なる見方があったのだと皆が知ることになるのだ。そしてそれまで老婆の絵だとしか考えていなかった人たちがその絵を見なおしてみると「そういえば若い女性にも見えるなぁ」と(おそらく大部分の人たちが)思うであろう。
観察の理論負荷性というのは、このように複数の見方、パースペクティブがありうるということが”発見”されて初めて成立するのである。つまり理論負荷性とは、事物の客観的見方が成立する過程で導き出されるものなのである。
そうなれば「老婆にも若い女性にも見える絵」という見方が共有されていく。(もっとも、上記の絵を描いた人はどちらにも見えるようにと思いながら描いたのであろうが)
繰返すが「理論負荷性」というものは、私たちが客観的事象を見出す過程において事後的に明らかになるものであって、(究極的に見れば)私たちの観察という行為の前提となるものではないのだ。
※ 観察の理論負荷性の議論における問題点については、拙著
理論があって経験があるのではなく、経験があって理論がある
~「観察の理論負荷性」の問題点
http://miya.aki.gs/miya/miya_report24.pdf
・・・でも説明していますので、参考にしていただければうれしいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
