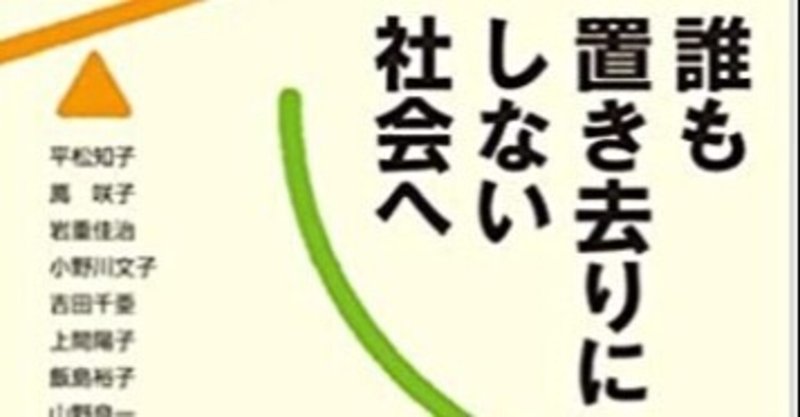
すぐそばにあるのに気づかない『誰も置き去りにしない社会へ』~読書感想文#24
現代は、近所づきあいも薄れ、家庭の内情は見えづらくなりました。
リサイクルショップなども増えたので、貧乏でもつぎはぎだらけの服を着ている人はおらず、外面からもその人が貧乏かどうかは分かりません。
日本における子どもの貧困率は高く、所得格差は拡大傾向にありますが、コロナは一層この傾向を押し進めることでしょう。それでも子どもたちは自分たちは貧困だとは言いません。なんとか隠そうとします。
この本は、貧困問題に取り組む人たちのインタビューを書籍化したものです。
何はともあれ目次をご覧ください。
これだけの内容を1冊で知ることができる、とても貴重な本です。
もっと深く知りたい内容があれば、本を出しているインタビュイーもいるので、その本にあたることができます。
1.保育現場にみる子どもの貧困と保育所の役割……平松知子
『貧困と保育 社会と福祉につなぎ、希望をつむぐ』かもがわ出版
の著者のインタビューは、保育から貧困を考え、見えづらい貧困を浮き彫りにします。保育園の頃から人生の辛い面ばかり見て育つこどもを垣間見ることができます。
2.学校給食から見える子どもの貧困……鴈咲子
給食費未納はモラルの問題なのか。
未納は保護者の責任感や規範意識が主な原因だとする役所の発表を検証もせずに報道する現実に待ったをかける著者のインタビュー。そこに隠れるのは、やはり子どもの貧困なのです。
3.若者の学びと成長を支える学費と奨学金制度を……岩重佳治
学費は上がり、正規雇用は減る変化の中、将来の収入が分からない中で借りざるを得ない奨学金制度の在り方について、弁護士である著者が疑問を投げかけています。
4.障害ある子どもとその家族の貧困を考える……小野川文子
『子どもの貧困ハンドブック』共著、かもがわ出版
北海道教育大学で肢体不自由児教育などを教える著者へのインタビュー。
子どもだけでの通園が認められず母子通園が課される親は、そのぶん働ける時間も減り、そんな条件で雇ってくれる先も制限される。それを「障害児がいるなら貧困はしょうがない」という見方をされる。それでも『頑張っている親』と『頑張れない親』との溝は、さらに断絶を深める……。少し想像すれば分かりそうなことではあっても、文字にし、誰にも分かるようにすることは大切です。
5.消されていく自主避難者……吉田千亜
原発事故で避難した母子の生活が困窮している.政府は,いわゆる「自主避難者」への住宅無償提供を2017年春に打ち切る.子どもを守りたい一心で避難した母親たちが,事故から5年経った今,何に不安を感じ,困り,苦しんでいるのか.事故後,避難した母子に寄り添い続ける著者が,克明に綴る.
子どもを守りたい、被曝させたくないという想いは「勝手」なのか。
「自主避難は間違っていない。これを伝えたい。(p.104)」という筆者へのインタビュー。
6.沖縄の夜の街の少女たちを追って……上間陽子
集団レイプ事件があっても、それを告発することで被害者が特定されてしまうため、誰もが黙っていた中、ある集団レイプ事件では被害者が自殺したことで記事になり明るみに出た。そして起こった被害者とその家族へのバッシング。
この沖縄における状況背景には、貧困や、基地の存在(暴力の容認)がある。
「この事件をきっかけにやはりきちんと実態を公表できるような調査をするしかないなと思うように(p.114)」なった著者へのインタビューです。
7.シングル女性の貧困、生きづらさ、働きづらさを追って……飯島裕子
『ルポ 若者ホームレス』という本も書いた筆者が、若者はホームレスになっても、女性は風俗とかあるから、ホームレスにならずに済むんじゃないかという見方への反論として書いたそうです。
そもそも、ホームレス状態で、外から見て女性ということが明らかだと危険です。その結果、女性ホームレスの存在は非常に見えづらく、なっています。(p.137)
8.教育偏重の子どもの貧困対策でいいのか……山野良一
子ども食堂や、無料の塾、それだけではなくもっと多様な生活への支援が必要ではないか。貧しい子どもは特別で、その子だけを救う(それも教育や就職に特化した)のではなく、社会全体の貧困の克服を目指すべきと訴えています。
9.貧困を乗り越える力をはぐくむ……萩野悦子
『孤立していく子どもたち』新日本出版社
『誰かボクに、食べものちょうだい』新日本出版社
日本の貧困が見えにくいのは、「貧困に陥っている人々が社会から孤立しているから(p.186)」という著者は、自宅に集まる息子の友人たちを通して、子どもの生きづらさに寄り添います。
10.貧困問題は解決に向かっているのか……中嶋哲彦
『子どもの貧困ハンドブック』共著、かもがわ出版
名古屋大学教授の著者が、豊富なデータから、現在の日本の貧困について総括的に説明しています。
貧困は居場所を奪い、自己を失う
最後に、飯島氏の言葉を紹介したいと思います。
彼女たちにとって、自分の願いを語るのは簡単なことではありません。いちばんやりたいことなど絶対に言えないように育っています。それに願いや思いを語ろうにもcapability(潜在能力)がグッと縮減されているなかで育っている。自分について語ってもいいと思える場所、なりたいものを自由に何度も言ってみることのできる場所を先行してつくらないと、子どもは自分の願いなど決して言わないのです。(p.131)
飯島氏が自身で取材した”彼女”は沖縄にいる女性ですが、ここで語られている彼女は決して沖縄だけにいるわけではないと感じました。
一つ条件が違えば、それは今の自分だったかもしれないし、今日すれ違った誰かかもしれません。
「船」を知らない人に「あそこに船がある」と言っても、その人には船が見えなかったといいます。
知らないものは目の前にあっても気づくことができません。
私も知らなかった。まずは、知ってほしい。
世界や自分自身をどのような言葉で認識するかで生き方が変わるなら、敬意を込めた敬語をお互いに使えば働きやすい職場ぐらい簡単にできるんじゃないか。そんな夢を追いかけています。
