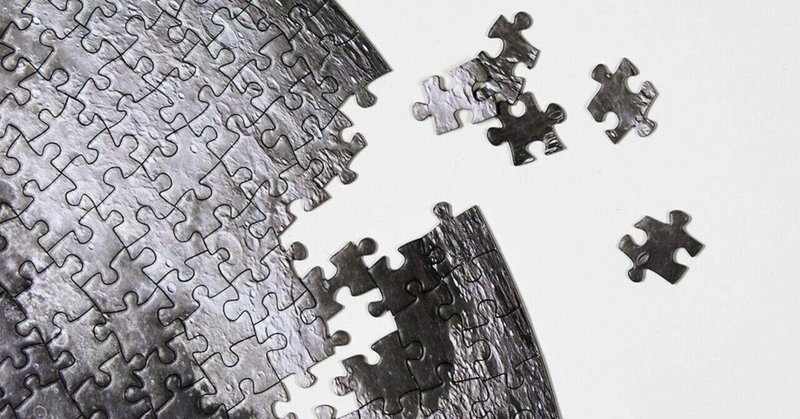
【読書メモ】中国哲学史/諸子百家から朱子学、陽明学まで
「中国(語)の経験を通じて、批判的に普遍に開かれていく哲学的な実践」
→哲学の普遍史VS地域的な思想史と言う枠組みを変形し、世界哲学に寄与する中国哲学、世界哲学史に寄与する中国哲学史を発明すること
→×中国における哲学
×中国的な哲学
大学の哲学研究に対する批判
→純粋な"哲学をすること"ではなく、ヘーゲルの「歴史」、カントの「普遍史」などの概念を念頭においた西洋哲学を解釈することを中心とした哲学学に終始してしまっている。その中でも解釈をクロノロジカルに並べた哲学史は哲学的ではなく歴史学の軍門に下っている。
→哲学は超歴史的な真理を探求するもの
歴史学自身において、歴史の概念やそれへのアプローチが批判的に見直されているのだとすれば、哲学と歴史の結合にもさらに別の可能性を見いだすことができるのではないか。それは新しい歴史概念に寄与する哲学という可能性である。もう少し述べるなら歴史学が前提としている諸概念を哲学史的に見直すことによって、グローバルヒストリー(世界史)としての歴史学の挑戦を支えるとともに、哲学におけるヨーロッパ中心主義を歴史学の力を借りることで、単なるその反対に陥らない道を見いだすことができるのではないかと言うことだ。
→グローバルヒストリー(世界史)が地域史の寄せ集めではないように、哲学者もまた諸地域の哲学史の寄せ集めではない
⚪︎「普遍化可能であること」「普遍化すること」の区別
フランスの哲学者/フランソワ・ジュリアン
「普遍化可能であること」
→あるパースペクティブ(観点)のもとに、比較可能なものを見出し、それらの同一性と差異を分析しながらより上位の審級との関係のもとに位置づけることに向かう。その場合、普遍は最上位の審級として可能性の極において登場する。
「普遍化すること」
→「普遍化する」という現在分詞のような形で普遍を考えることができるのであれば、普遍に向かう歩みはそれ自身が歴史の中で洗練されるプロセスということになる。
⭐︎哲学史は「普遍化すること」すなわち歴史の中で概念が批判的に洗練され、普遍に開かれることを前提としなければならない
中国哲学史の起源
孔子説/馮友蘭と老子説/胡適
→胡適はダーウィン=デューイ的な社会進化論、プラグマティズムによる影響を多分に受け、考古学的時系列の検証を無視してでも自説を擁護しようとしていた。なんとしても、老子を中国哲学史の起源に置くことで、儒教による起源の領有を阻み儒教ではない哲学としての中国思想の可能性を開こうとした。(WW2前の社会情勢の影響もある)
「中国哲学は、老子と孔子に至って初めて哲学というこの二文字を手にしたと言える。老子以前に思想がなかったのではなく、系統的な思想がなかったのである。(中国哲学の道筋/胡適)」
⭐︎哲学とは、系統的な思想である。ここで系統的と言うのは、体系性であり、系譜性である。老子の思想が哲学になり得たのは、それが系統としての歴史を自覚し、体系性を有した系統的な思想であり、そしてそれが内的道筋として継承されていくことになったからなのだ。
→中国哲学史の起源を見出せば、それで自動的に哲学が展開するわけではない。起源を自覚的に反復することが必要なのだ。そして、反復すべき起源をどう置くのかが哲学的に重要になってくる。
(胡適は主観的かつ独善的なポジショントークをしている感じがするけど、、、この営み自体が哲学である、ということなのかな?
⚪︎ドイツの哲学者カール・ヤスパースの『軸の時代』
→ユダヤ教、仏教、儒教といった世界宗教と古代ギリシアの哲学が、紀元前800年から前200年にかけて、ほぼ同じ時代に一斉に成立したことに着目し、これらの思想が世界の軸になったと考えるもの。ヤスパースは「軸の時代」と言う概念を用いて、人類には1つの起源と1つの目標があるはずだと考え、新しい世界史を構想しようとしたその背景には、第二次世界大戦とナチズムへの反省があった。つまり人間の極限的な蛮行をヨーロッパの近代的な理性が支えてしまった後に、いかにして、もう1度人間への信頼を取り戻すかを問うた。
孔子
⚪︎イエズス会士の孔子像
→イエズス会士たちが見てしまったのは、聖書に書かれているよりも古い歴史が中国にあり、ひょっとすると神なしで、地上の王国を倫理的政治的にうまく運営できるかもしれないと言う可能性であった。"哲学者"と評されることには宗教との距離感が込められてもいて、キリスト教の外部に立つ可能性が垣間見られていた。
「鳥は木を選ぶことができるが、木はどうして鳥を選ぶことができよう」
⭐︎『仁』
→神のような超越的な源泉にではなく、人間的なものに根ざしている。とりわけ感情的で相互的な次元に根ざしている。
→仁は、人を愛することである
→古代世界において(あるいは近代世界でも)意義の源泉を神やそれに類した超越に求めるというのは、1つの説得的な態度であったことだろう。しかし孔子はそれに対して否を言い、あくまでも人間と言う次元しかもより不安定な感情や相互性の次元に注目した。
※孔子の中には、超越への通路が残っていながら(祈りの問題)ヒューマニズムが想定するような理性的で、主体的な人間像とは異なる人間(感情的な相互的な人間)が想定されているので、ヒューマニズム(人間中心主義)と安直に重ね合わせるのは性急である。
「自己に打ち勝って礼に復帰することが仁である。1日でも自己に打ち勝って礼に復帰すれば、天下の人々はその人に帰服する。仁である事は自己によるもので、他人によることではない」
「礼でなければ見てはならず、礼でなければ聴いてはならず、礼でなければ言ってはならず、礼でなければ行動してはならない」
→仁は礼によって表現されなければ意味がない
⭐︎礼
→完璧にすべての状況に適合するような客観的で普遍的な法規範ではない。礼はその都度見直され変形され、状況への対応において適切であり続けなければならない。ここで挙げられている礼は単なる儀礼的で形式的な規範ではない。それはバラバラになりそうなこの世界を繋ぎ止める弱く、不安定な規範であって人間の感情の様式化に由来するものだ。
「礼は感情に由来する。それは範例的だとみなされた対応であり、次世代を訓練してその感情を様式化するのを助けるとも考えられている」ハーバード大学中国哲学者マイケル・ピュエット
◎仁を通じて人が人間的になるためには、感情と相互性の次元に深く立ち直さなければならないからこそ、礼という感情を様式化する規範に訴えようとしたのではないか
→礼は万古不易の規範ではなく、歴史的に変容する規範であるということ
⭐︎「正名」という概念
→名と実(実態、実質)が一致するという正しさ
ex.)君臣、父子の関係
「野哉、由也(やなるかな、ゆうや)」
⚪︎『荀子』の言語起源論
→古代中国で正名を哲学的に洗練した
→言葉(名)とその意味(宜/ぎ)、そして指示対象(実)の関係は恣意的であり、社会的な約束によって慣習化されて定まる
→別の仕方で名と宜そして実を結合させることが原理的に可能である以上、特定の正名を最終的な審級に据えることはできない。正名は常にすでに乱れる可能性がある。
→実際の名と実の関係を定めるのは、王による制名、すなわち名の制定だとイメージされている
⚪︎荀子の言語起源論は2つある
①権利上の言語起源論
→社会的約束によって名を定めるもの
②歴史的な言語起源論
→王による制命は、常にすでに歴史的なアレンジに過ぎないというもの
◎「荀子」は天と人とを分離し、人の領分で、その哲学(とりわけ性悪論)を展開していった。言語においても、同様に人を超えたものに言語を基礎づけるのではなく、あくまでも人の領分において約束であるとか、歴史的な反復であるとかに、言語の基礎づけを置こうとした。
孟子の性善説
⚪︎四端
①憐むという惻隠の心→仁の端(はじめ)
②恥ずかしいと思う羞悪の心→義の端
③他人に譲るという辞譲の心→礼の端
④正不正を判断する是非の心→智の端
→道徳はあらかじめ定められた素質としてしか自然には備わっていない。善は人間に本来備わっていても、それを可能にするかどうかは、私たち次第であるというのが孟子の性善説。道徳性の「端」もしくは糸口は、自然的な性向として、確かに私たちの中に生まれながらに備わっているが、それを拡充する(行いの隅々にまで広げる)のは私たちの努力にかかっている。
荀子の性悪説
秦漢帝国が成立する直前の古代中国における、いわば総合的な哲学者
⚪︎中心的な問いは、人間世界に規範をどのように成立させるか
→性と情を別のものとは考えず、人間を総体として捉えた場合、悪の根拠も善の根拠も人間にあると考えた。しかし、単純に孟子と対立したわけではなく、その人為の肯定は孟子とも通じていた。
「人の性は悪で、その善は偽(作為)である。」
「人の性に従い、人の情に従うと、必ず争奪が生じ、分理を乱し、暴に帰してしまうのだ。そこで師法による教化と礼儀の道が必要になる。そうして辞譲が生じ、文理に合し、治に帰する。以上から、人の性が悪であることは明らかであり、善は偽にある。」
→性そして情は天に由来する、人間を人間として可能にする条件であるが、その赴くままに従うと、秩序が乱れた暴力的な事態が必ず生じてしまう。したがって必要な事は性に反し情に悖ることであって、自然的なあり方に反し、その外に善の根拠を求めるべきである。
→人間は、その自然的なあり方のままでは壊れていく存在者であるから、自然を超えた次元を導入して、自然的なあり方を変化させ(化性)、それによって悪を抑え、善を実現しようと考えた。
⭐︎偽は性を変化させる作為である。荀子の場合、自然を変形する働きは、思慮する心が担っている。聖人は思慮を重ねて作為を行うが、それは具体的には礼儀や法規、さらには言語の制定として実現する。作為は社会的な実践でなければならない。
⭐︎「後王」という概念は荀子の発明で、その最大の特徴は歴史を導入したことにある。変更可能性を含みながら規範を基礎づけようとした。
※荀子は荘子の「物化」を乗り越えようとしたと見ることができる
荘子
『物化』
→あるものが他のものに変化するというだけでなく、そのものが作り上げていた世界が全く別の世界に変容するという事でもある。それは儒家が考える「教化」とは根本的に異なる。教化は小人が君子や聖人になるという啓蒙のプログラムであって、教えを通じて啓蒙されていない状態から啓蒙された状態に変化することだ。それは目的論的に方向づけられた変化であり、端的に言えば君主を目指す変化である。それに対して物化には定められた方向がない。
「胡蝶の夢」
→荘周が蝶になり、蝶が荘周になることが物化である。言い換えれば、自他の区別がなくなることではなく、自他が独立して存在しながらも、全く別の存在様態を有した、他なるものに変化することなのだ。それとともにその変化の背後に、それぞれ夢と目覚めという全く別々の世界が想定されている。荘子は、物化を通じて他なるものに変化するだけでなく、そのものが属している世界そのものが変容するという事態を見通していた。
→荀子が述べる化性(性を変化させる)が、人間の世界が作り上げる善に方向付けられているのに対し、荘子の物化はそれを超えて変化の自由度を究極にまで高めていると考えることもできる。荘子は倫理と反倫理の対立を超えて、今は非倫理の境地を目指した。
⭐︎能動性に転化することのない受動性に拘束されている。自己享受を通じたこの世界の肯定は、この世界が根本的に変容し、一種の開放空間となる可能性を創造するラディカルさを潜めている。
『礼』
→中国哲学における礼は、法と区別された美的な規範で、それは感情を様式化した範例的なものであって、世代から世代へと反復されていくものであった。
→法は外から規定する規範であり、刑罰という罰則を伴うのに対して、礼はその人の内からとりわけ感情を陶治(とうや)する規範である。罰則の代わりに、非礼や無礼というニュアンスからわかるように、美的な意味での格好悪さを突きつけられる。
「仁」
→端的に言えば「人によくすることによって、人間的になること」
→経済を含んだ人間の交通が盛んになった周の時代は、それまで考えられていた人間を超えた天から人へと言う垂直的な人間関係から、人間同士の水平的な人間関係へと社会的想像力が変化した時代であった。孔子が仁を主張するのは、こうした新しい状況であった。その上で礼を洗練し直そうとしたのである。
⚪︎孟子の「礼」
→孔子とはやや異なり、孟子は仁・義・智・礼・楽と言う5つの概念を体系化しようとしている。体系化は思考を整理してくれる反面、思考のダイナミズムや繊細さをしばしば損なうことがある。孔子と違って孟子の礼は、特定の他者に対して、何らかの形で定められた整え、飾られた態度ということになってしまう。
⚪︎荀子の「礼」(一つの到達点といえる)
→荀子の主張の重要なポイントは、天の領分から人の領分を切断することであり、天に訴えることなく人の領分において礼を基礎づけることにある。
→人間による妖怪(人妖)こそが、災厄の大きな原因となる。そしてそれを収めるには礼しかない。
「礼儀文理が情を養うものであることを熟知するべきである。」
「終始がともに立派であることに人道は尽きている。そこで君子は始めを敬い終わりを慎み、終始一の如しである。これが君子の道であり、礼儀の文である。」
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
孫子
→配置から生まれる力、すなわち勢を自分たちの側では最大化し、敵の側では最小化すること
※孫子の兵法は現代的な全体戦争とは異なり(目指すべきは絶滅ではない)、権力を適切に運用する政治に他ならない
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
政治哲学とユートピア
⚪︎老子
「万物は陰を負い、陽を抱いている。」
⭐︎水の政治哲学
→ 一としての王は道によって生じたものであり、万物の中に入り込んでいるために統治が保障される
→小国寡民という閉ざされたユートピア(ディストピア?)
⚪︎韓非子による法家的老子の解釈、注釈
→法という中心概念が、ここでは純粋に、そして端的に道という語によって示されている
「刑法は宇宙の秩序と協同している。それは自然の理法であり、社会に触れることで、刑罰の法律として具現化したのである。」
→中国古代のあらゆる形態の思想に共通する前提を韓非もまた継承しているということ。すなわち、自然の秩序と人間の秩序の連続性、さらには同一性という前提である。とはいえ、それを継承しながらも、韓非は人が天と合一するという道家の見方を転倒し、人間の秩序の求めに応じて天の秩序を裁断した。
⭐︎つまり道家も法家も、どちらも「自然の秩序と人間の秩序の連続性、さらには同一性」を前提としている点では同じ。荀子と老子の逆説的な結合こそが、法家を可能にした。
※荀子と老子の逆説的な結合
荀子=天に訴えることなく人の領分で統治する
老子=天に訴えて人を統治しない
法家=天に訴えて人の領分で統治する
⭐︎老子の実用的な利用(王権をいかに有効に利用するか)を韓非子は行ったと言って良い。そしてそれはそのまま帝国の論理につながっていく。
法家
→思想家(商鞅、申不害、慎到、韓非子)は必ずしも、自分たちを1つの思想潮流に属するとは考えていなかった
→思考の中心にあったのは、中央集権的な官僚機構、無制約な君主の権力、儒家が強調するような過去の権威や道徳的な価値の否定
→秦の焚書坑儒に繋がる
→「ニ柄(にへい)/韓非子」(2つのハンドル)と呼ばれるアメとムチの統治技法
董仲舒(とうちゅうじょ)の帝国哲学
『天人合一』
→新たな正統性を求めていた帝国としての漢に好都合な形而上学だった(前漢武帝などが尊重していた黄老思想では弱くなっていた)
→儒教の復活
⚪︎天が王を立てたのは民のためである。天人の相関関係において、政治的正統性が保障される。
→『天譴災異(てんけんさいい)』天は災異を下して統治者に警告を与え、聞き入れられなかった場合は王者を滅ぼす
※西洋の王権神授説とは質的に違う権力の型
→天によって皇帝権を基礎づけるという事は、同時に天によって皇帝権に制約をかけるという事
合理主義者/自然主義者(老荘思想的)王充による批判
「大人は風刺し、賢者は諫言するが、それが天の譴告なのだ。ところが譴告を災異に帰してしまうために、それが疑われるのである」
→天は無為である
→天は災異ではなく、聖賢という媒介者(瑞祥/ずいしょう)をおく
※王充は董仲舒ような天人相関、すなわち天と人との間に強い因果関係を設定する思想を批判したが、それは人の世の善悪の根拠を天に丸投げすることを避け、人が自ら善をなし、悪を退けるしかないと考えたから。だからこそ、王充は同時に天と人の関係を全く断ち切ることはせず、聖賢という特別な人間に天との間を媒介させていった。
漢帝国崩壊後の六朝期の玄学(深遠な学)
「玄のまた玄なるもの、衆妙の門」(老子第一章)
→「三玄」と呼ばれる『老子』『荘子』『易』というテキストに依拠しながら、本体である「玄」を探求する学
後漢末、宦官権力に反対する人々が「清議」すなわち清(清廉)なる士人による反対運動を組織したが弾圧される。そのため、多くの士人は政治から身を引き「清談」に耽るようになる。
→竹林の七賢
→彼らは儒教国家という国政を批判するために道家、道教的な思考に向かった。
王弼(おうひつ)の無の形而上学
→有の次元を超え、それを生み出し、基礎づけるような次元を王弼は無として提示した。それはもはやそれ以上遡ることのできない究極の根拠である。王弼は単に「無い」とか「存在しない」という無ではなく、究極の根拠という概念としての無を立ち上げた。このような意味での無に回帰できればすべての根拠を手に入れることができるために、それは有を全うすることになる。つまり万物がその本来的な性をあるがままに発揮する状態。すなわち「自然」が実現される。
→無為、そして不言が効果を及ぼしている世界は万物がそれぞれの用いられるべき場所にあり、利が実現された治の状態である。それはさらに一への集約として結論付けられる。
「言尽意・言不尽意論」(言は意を尽くすかどうか)
→一般的な言語活動では「言不尽意」を認めながらも、聖人の意という超越的な意を救うために、特権的な言語である象・卦(か)・辞(→易を構成している特権的な言語)を導入することで、その限りで「言尽意」と主張した
⚪︎王弼の議論
①意は言語(象と言)によって尽くされ、示される
②意を得れば言語は忘れられる
③意を得るためには言語は忘れられなければならない
「王弼の亜(次ぐもの)」と称された郭象(かくしょう)
「そもそも仁義は人の性である」
→これまで否定してきたはずの仁義に代表される儒家的な秩序がそのまま自然であると肯定した
→存在論において至高者ないし、形而上的な根源を一切排除した(本質主義)
有は「自生独化」あるいは「自化」するもの、すなわち自然であると考えた。有を無によらずに有それ自体において、絶対的に基礎づけようとしたのである。つまり有は有自らに基礎を置くもの、自己措定するものであると考えた。
→有が自己措定している以上、その在り方に外から作為的に介入することはできない。ということはつまり現状の肯定、あるいは自閉した議論になってしまっている。
⭐︎本質主義は本質に回収できない、人間の在りようには届かない。思考しなければならないのは、無為の政治や無・自然の本質主義の中では想像不可能な外部の現実である。その外部の現実を構成する重要な要素として、既に仏教は中国に浸透しつつあった。
仏教との対決[パラダイムシフト1]
『神滅不滅論争』
→仏教徒が「形(身体)」が滅んでも、「神(精神)」は滅ばないとして、身体と精神の二元論を主張したのに対して、儒者は身体と精神の一元論を唱え、形が滅べば、神もまた滅ぶ(形神相即)と批判した。その帰結は、形も滅ぶと神が滅ぶ、すなわち仏教の輪廻を支えるような魂などないことになる。
◎文の哲学
『詩経』『楚辞』そして辞賦(じふ)という分割線
→詩経という始まりから、楚辞による変化を経て辞賦に陥落するという文学史
韓愈の古文と道統
→後漢から魏晋南北朝、隋、唐にかけて隆盛した仏教を前に思想的強度を失っていった儒教が、再びその独自性を回復していく
→仏家や道家が主張する原理は、ダルマであれ、自然であれ、それ自体は人間にとって超越的な原理である。それは人間の行為を凌駕し、一般の人間であれば否定的な仕方でしか触れることのできないものであり、それに到達できるのは、仏や聖人という一部の超人間的な存在だけである。その超越的な原理は、無謬不壊の心理として一般の人間の前にも現れる。
儒家の側でそれに対抗できる原理は、天であった。しかし、韓愈は天と人との間に否定的な相関関係を見出していた。すなわち、天はすでに壊れており、そこから生じる人もまた壊れていると結論づけた。そうである以上、超越的な無謬不壊の心理とは異なる原理として、儒家の道を提示しなければならない。
⭐︎出発点からして壊れ、悪に溢れた人間の世界に、古という過去において、聖人が秩序を与えた
①「博愛」である仁
②「ふさわしい行い」である義
③「仁義に基づいて進む」ものとしての道
④「己に充足し外を恃まない」ものとしての徳
→先の王の道は仏家や道家が基づく超越的な道に比べて、原理としての内容に乏しい弱いものであるが、韓愈はこうした弱い原理こそが壊れた後の人間に相応しいと考えた。
⭐︎超越的な原理に対して、歴史的な原理(堯から孟軻へ)を置く。
→中国では仏教でも道家・道教でも儒家にしても、道学(道統の継承)の正当性、そして何が継承されるかではなく、継承することそのものが重要である。
「(古の聖賢の)意を師として、辞を師としない」
→自己発出に基づく独自性が古文の理念であるならば、模倣(ミメーシス)なき模倣の歴史(ミメーシスなきオリジナリティの回復)。
朱熹の朱子学
→韓愈を受けて仏教に本格的に挑戦し、中国においてはじめて内面の形而上学を確立した
→孟子を最大限に活用する
⚪︎身体的、物質的な「気」と天の理を共有する「性」
→自己啓蒙による悪の乗り越えを目指す
『格物致知』
→内面で完結する"誠意"が実現していることを保証するには、外の物の理を知り尽くせばよい。
→あくまで外部性にこだわった
王陽明の陽明学
→朱熹が格物致知においてこだわった外部性を消去し内部性に徹した
『知行合一』
→格物を通して外の物の理を捉えるのではなく、心を正しくすればそのうち理が明らかになるとして、知(致知)から、心に備わった一種の超越論的かつ経験的な知としての「良知」(直感的で実践と結びついた知)へと移行する。
→朱子学の思弁的な知を退け、直感的で実践的な知を据えることによって、社会に深く関わる実践において理を求めようとした
キリスト教徒の対決[パラダイムシフト2]
→イエズス会の戦略として、儒教や道教を批判するよりも、仏教を批判して、仏教の位置にキリスト教を置き換えようとした
◎西洋から見た中国
→「神なしでも世界は存在するかもしれない」という問い
18世紀後半カントは『啓蒙とはなにか』において「宗教を脱した成年状態」を啓蒙の到達点だと述べた
ライプニッツ(モナドロジーや可能世界論)やスピノザ(汎神論)を筆頭に影響を与えた
「われわれはすべての中国人が、地上幸福を得ようと渇望し、さらに神性も知らず来世も知らないことを注意した」ヴォルフ(ライプニッツの弟子)
→実践哲学、文化本質主義と評される今日の中国論にも通底している
...
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
