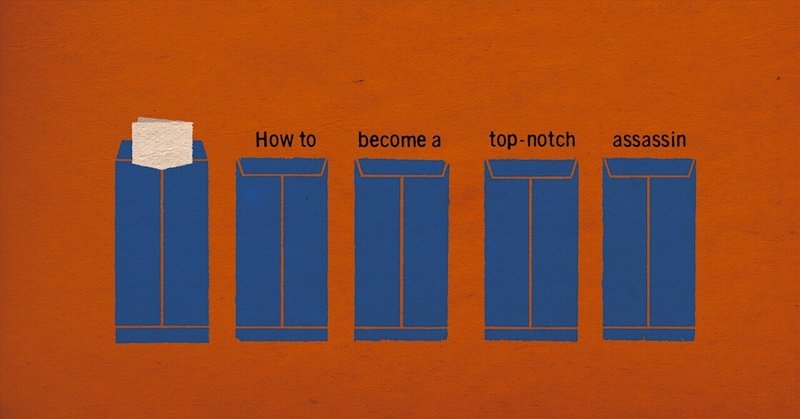
殺し屋の華麗なるレッスン
久しぶりに郵便受けを見にいこうと、バケツ片手にアパートの階段を降りた。郵政省の古い規格に則った赤い郵便受けで、開けると大量のチラシとダイレクトメールとポケットティッシュ付きの広告が足下に置いたバケツ目がけてどさどさと落下した。
アパートの敷地には建物と同じくらいの面積をもった庭があり、その隅に今どき珍しい焼却炉があった。焼却炉にはアパートの持ち主が近所の住民と協議を重ねた結果、屋根より高く伸ばすことで決着した立派な煙突がついていた。
わたしは焼却炉のそばに行って、バケツの中身を選り分けた。一度督促状を捨ててしまったことがあるので、いやでも慎重にならざるを得なかった。もちろんない場合のほうが多かったが、それでも全方位的に不要なものと、気分的には不要だが捨てるとのちのちろくなことにならないものとを見分けるのは骨の折れる仕事だった。
ひとつまみの良識をかろうじて保ちながらせっせと作業をつづけていると、青い洋形の封筒が出てきた。宛名や切手はなく、封もしていなかった。中をみると紙が一枚入っていて、「これは不こうの手紙です。同じ文でだれかに五まい出さないと、不こうになります」と拙い字で書いてあった。直筆できもちがこもっている分、督促状よりはましな気がしたけれど、迷うことなく不要に分けた。前世紀の古風な慣習がまだ残っていることにわたしは驚き、感心した。
ところがすぐにまた同じ青い封筒が出てきて、目を疑った。しばらく見つめてからすこし考え直し、この手紙のために新たな分別カテゴリを用意した。最終的に督促状は一枚もないことが判明したが、代わりに青い封筒は五枚を数えた。中身が同じであることは見なくてもわかった。わたしは不要であることがはっきりしたバケツの中身を焼却炉に放りこむと、空のバケツに不幸の手紙を入れて部屋に戻った。
入れた茶をすすりながら古い友人からの便りをひもとくように検分したところ、五枚の封筒のうち一枚の裏にボールペンでぐるぐると何かを消した跡があった。幾重にもからまり合ったパスタみたいな曲線の下には、差出人とおもわれる少年の名前と住所らしきものが記されていた。わりと近所から直接来たらしいこともあって、判読もできた。
露呈しているいくつかの粗忽さに敬意を表して、わたしは受け取った青い封筒に一言二言の返信をしたためて入れ、ポストに投函した。幸せが訪れますようにだったか、ケツでも食らえだったか、そんなようなことを親しみをこめて書いた。わたしとしてもちょっとしたいたずらのつもりだった。
返事はふたたび、今度は郵便できちんと届いた。「どうして返事がきたのかふしぎです」とあった。住所と名前が書いてあったからです、とわたしは書いて送った。そんな具合で、短いやりとりが行き来した。文通相手になるつもりはなかったけれど、向こうもどちらかというと首をかしげながら律儀に返してくる印象で、無碍にもできなかった。
何度目かの返信でわたしが何者であるかを知りたそうにしていたので、深く考えずに「殺し屋です」と返した。これがよくなかった。もともとの発端の意味を、もっとよく考えてみるべきだったとわたしは痛感した。少年は例の拙い字でこう書いて寄越したのだった。「二万円あったら引き受けてくれますか」
そんなわけでわたしたちはその週末、駅前のロータリーで初めて顔を合わせた。切実な金額と切実なリアクション、その他もろもろを考え合わせると、どう考えてもあのまま舌先三寸でやり過ごすよりは直接話したほうが手っ取り早くおもわれた。わたしは責任を持って殺し屋のままいくと決めた。
それまで名前でしか知らなかったイオリは、つまむとどこまでも伸びそうなもちもちした少年だった。Tシャツとデニムでトートバッグを大事そうに抱え、どこにでもいそうな小学生としては非の打ち所のない格好をしていた。そわそわと落ち着かない様子で、挙動だけなら誘拐犯に身代金を払いにきた男のようでもあった。彼はロータリーの花壇に腰かけ、わたしが買ってきたアイスバーをかじりながら、不安そうな面持ちでわたしを見上げた。
「まず最初に言っておくと」とわたしはアイスをくわえたまま言った。「不幸の手紙は五枚もいらない」
「でも」とイオリは目を伏せた。「五枚書かないと……」
「一人に五通じゃなくて、一通ずつ五人に出すんだよ」
「でも五枚って書いてあったから、それで」とイオリはうろたえた。「どうしよう」
「それからふたつ目」わたしは冷たく告げた。「仕事を引き受けることはできない」
えっという顔をして、イオリは膝上のトートバッグを引き寄せた。「でも……」
「どんなにイヤなやつでも百年たてばみんな死ぬ。待てばいいじゃないか。どうして殺す必要があるんだ?」
「そんなに待てない」
「どうして?」
「その前に僕がやられる」とイオリは首を振りながら言った。「そんな気がするんだ」
「先生はなんて言ってるんだ?」
「話したけど、でもだめだった」
「お父さんとかお母さんは?」
「お父さんはいない」
「お母さんは?」
「心配するから」
「心配してもらえばいい」
「でも……」
「でも?」
「僕どうしたらいいの?」
「わかったよ、じゃこうしよう」わたしはイオリの正面に回り、目線の高さまでしゃがみこんだ。「自分でやるんだ」
「自分でって、僕が?」
「君が殺し屋になるってことだよ」
「どうやって?」
「もちろん教える。一から全部」
「なれるの?僕でも?」
「さあね」とわたしは肩をすくめた。「まあ、五分五分ってところかな。とりあえず必要な道具を買いにいこう。持ってきた二万はその準備資金だ。行くぞ」
わたしたちはその足で駅前近くにある大型スーパーに向かった。エスカレーターで二階にある台所用品のコーナーを目指しながら、わたしはイオリに言った。「ここで凶器を買う」
「凶器って?」
「武器のことだよ」
「ピストルとかじゃないの?」
「ピストルに子供用はないんだ」
その点、包丁には子供用があった。ひよこ、狸、イグアナの三種類があり、マークはそれぞれ幼児用、低学年用、高学年用を表していた。わたしはイオリに学年をたずねた。
「三年生」
「じゃイグアナでいいな。次はエプロンだ」
「エプロンもいるの?」
「返り血を浴びたらつまらないだろ。三角巾も忘れるな」
潤沢な資金で支払いを済ませると、階下に降りて生鮮エリアを練り歩いた。標的をスマートに一発で仕留めるためには肉に精通している必要があること、それには絶え間ない鍛錬が求められるけれども、しかし頼まれてもいないのに無駄に誰かを始末するわけにはいかないこと、したがってその代替品に牛、豚、鶏その他の肉を使用すること、そして経験値を積みたかったらコストパフォーマンスも忽せにはできないこと等を懇々と説きながら、わたしは豚バラ肉のブロックをカートに入れた。それからタマネギ、人参、じゃがいもといったオーソドックスな野菜を順に選んだ。イオリがタマネギを手に訝しげな顔をしたので、相手が野菜みたいなやつだったらどうするんだと念のため釘を刺した。もちろんカレーのルーも忘れなかった。
わたしはイオリをアパートに連れ帰り、買ってきたエプロンと三角巾を身につけさせたうえで、肉の捌きかたを一から手ほどきした。椅子に立たせ、まな板に肉塊を置き、こうなるまでには幾千もの工程があると話した。これがどこの部位で、切り出すためにはまた別の包丁があり、その技術も一朝一夕で身につくものではなく、どんなに優れた刃であっても使いかた次第ですべてが台無しになると叩き込んだ。イオリの体をあちこちつついたりなぞったりしながら、解体されてまた新たな血肉になるまでの道のりがいかに長く、複雑で、感動的な一大叙事詩であるかを想像させた。手でふれ、指でさぐり、その厚みと重みを肌で知らしめた。何より一流の殺し屋とはすべからく一流の料理人であり、許可なく命を奪う以上は心からの感謝なくしては立ち行かないとくどいほど言い聞かせた。そしてその合間を縫いながら、美味いものは憂いに優るとサブリミナルにささやいた。
初めてふれる肉塊の存在感におそるおそるだったイオリもいつしか手つきに力がこもり、額に汗をにじませながら真剣な眼差しで肉との対話に取り組んでいた。イオリが指先を切って声を上げそうになると、わたしはあらかじめ用意していた絆創膏ですばやく処置を施した。「包丁なんだからそりゃ切れるし、切れたら痛い。今やってるのはそういうことだよ。肉にやさしくしろ!」
かくしてカレーは完成した。野菜の下ごしらえから炊飯まで、イオリはすべてひとりでやりきった。目を離さないようにと張りつめていたせいか、わたしは体中の力がどっと抜けるのを感じた。あとはきれいにたいらげるという最後の大仕事を残すばかりだった。
そこへインターホンが鳴り、ドアを二つ隔てた部屋に住む友人が入ってきた。病院勤務の薬剤師である友人は、土産にドラゴンフルーツを携えていた。わたしはイオリに友人を紹介した。
「イオリ、こちらドラゴン。毒にくわしいひとかどの人物で、殺し屋としての資質を見てもらうために招待したんだ。ドラゴン、こちらイオリ。殺し屋見習い」
「よろしく」と友人は手を差し出した。「ご招待ありがとう」
「こんにちは」とイオリは差し出された手をおずおずと握りながら言った。「これ何ですか?」
「フルーツだよ。見たことない?」
「初めてみた」
「きっと気に入るよ」
「どんな味?」
「どんな味?」友人はわたしのほうを向いて意見を求めた。「なんて言ったらいい?」
「人生みたいな味だね」とわたしは答えた。
ある種の門出を祝う遅めの午餐会は終始のどかに、和気藹々と進んだ。薬剤師はその道のエキスパートとしてハーブの効能を語り、イオリは初めて口にする果実の味わいに目を丸くし、どちらかといえば副産物だったカレーもまた、触媒として立派にその役目を果たした。
わたしはわたしで、あまり口から出まかせを言うものではないという尤もな教訓を得た。わざわざ心に留めるまでもないだけに、なおのこと身にしみた。できればとっとと無害な小市民に戻ってしまいたかったが、身分の詐称に伴う若干の支障はこの際いさぎよく受け入れることにした。
申し出に甘えてすっかりくつろいでいたわたしは、皿洗いに立つ二人の後ろ姿に目をやった。流れる水とかち合う皿の音に混じって「ミシュランで星取ってから言いな」とあしらう薬剤師の声が聞こえた。自分の前途を尋ねた不幸な殺し屋見習いがどんな顔をしていたのか、こちらからは窺うことができなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
