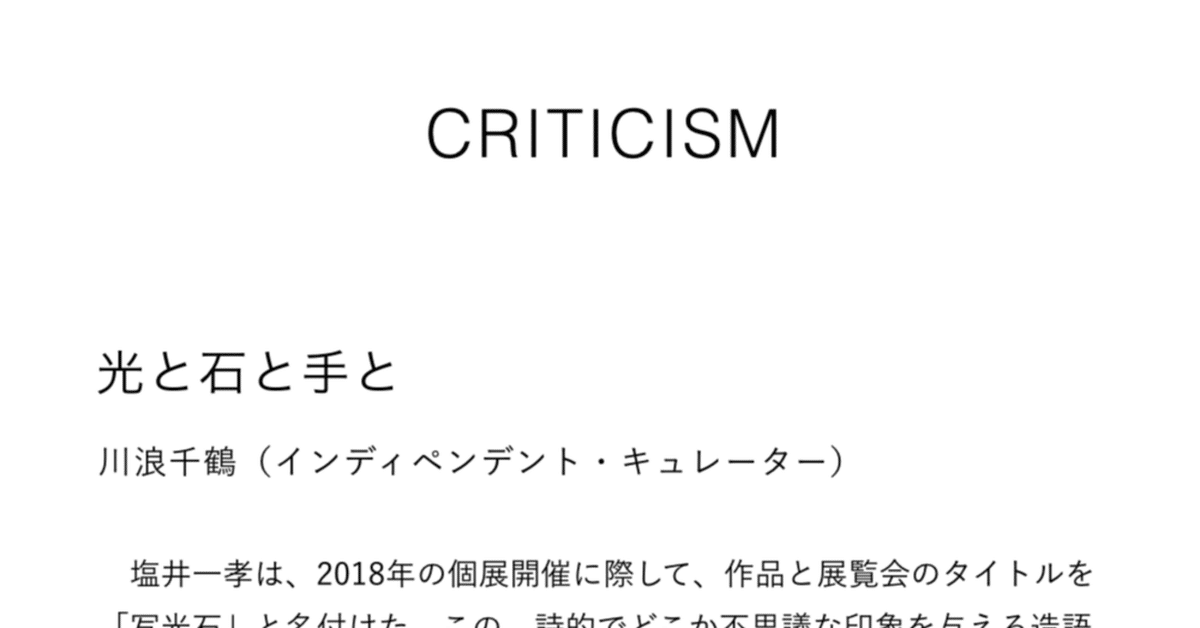
展覧会評:「光と石と手と」 川浪千鶴(インディペンデント・キュレーター)
インディペンデント・キュレーターの川浪千鶴さんにみぞえ画廊で開催した個展の展評を執筆いただきました。
僕の過去と未来、現在がぎゅっと凝縮された内容になっています。近年取り組んでいる《写光石》の制作過程やコンセプトにまつわる思想的な部分を詩的で洗練された文章で言語化していただき感謝感激です。個人的には恩師のお名前が登場しているのが胸熱ポイント。この世界の片隅で、鉄の時代を経て光の時代へ向かう小さなアーティストの大きな節目を記したテキストをご一読いただけますと幸いです。
川浪千鶴 |KAWANAMI Chizuru
インディペンデント・キュレーター。1957年生まれ、福岡市在住。早稲田大学第一文学部美術史学科卒業。1981年から2018年までの間に、福岡県立美術館学芸課長、高知県立美術館企画監兼学芸課長及び石元泰博フォトセンター長を務める。専門は日本の近現代美術史、美術館活動史。
主な展覧会企画には、「現代美術の展望‘94FUKUOKA 七つの対話」(1994)、「アートの現場・福岡 VOL.1〜23」(1998〜2008)、「菊畑茂久馬と〈物〉語るオブジェ」(2007)、「池田龍雄 アヴァンギャルドの軌跡」(2011)、「没後20年具体の画家 正延正俊」(2015)、「岡上淑子コラージュ展 はるかな旅」(2018)などがある。執筆活動のほか、大学講師や美術館評価委員等を務め、プロジェクト企画や審査等も手がける。
※個展の詳細はこちら
展覧会評
光と石と手と
川浪千鶴(インディペンデント・キュレーター)
塩井一孝は、2018年の個展開催に際して、作品と展覧会のタイトルを「写光石」と名付けた。この、詩的でどこか不思議な印象を与える造語は、以後作品の一貫した名称として使われ、今や塩井の代名詞となっている。作品だけでなく、彼の創作を支える基本概念や創作言語(スタイル)を象徴する言葉、写光石。「光」を「写し」た「石」と読み換え、制作工程を読み解きながら、その存在を探ってみよう。
まず用意するのは、思い出の風景写真。写真とは、目に「映った」反射光をカメラで「写し」撮ったものということができる。それを水溶性のインクを用いてプリンターで和紙に「移し」取る。次いで和紙に水を含ませながら、河原や海辺で集めてきた小石の表面全体にしっかり密着するように貼り付けたのちに乾燥させ、最後にクリアなウレタン塗料でコーティングして完成となる。
塩井は風景写真を「記憶の光」と呼ぶ。ある時、ある場所でふいに目に飛び込んできた風景の像(かたち)をとどめた写真には、確かに一瞬の光が記録されている。そして、人はその像の断片をかけがえのない記憶として無意識の内に心にも定着させている。
質感のある和紙に水溶性インクで印刷され、さらにそこに水が加えられることによって、色はかすれ滲み、溶け混じり合う。映り写され移し取られた風景は次第に輪郭を失っていく。私たちの心に残る記憶の多くは曖昧だ。隅々までクリアなイメージではなく、忘れられない雰囲気や気配をこのようにして写真から抽出することによって、写光石は「過去の光の出現」の現場となりうる。
写光石における「石」は、記憶の光を表面にとどめ、それを握りしめるための支持体や基盤ではあることに間違いはないが、同時に光の対比として重要な位置を占めている。
光の痕跡を人工的に蓄積したデータとしての写真と、膨大な時をかけて自然が生み出した硬質な物体としての石。儚さ(ヴァニタス)と永遠の対比は、古今東西の芸術で試みられてきたテーマだ。儚さは時の移ろいに結びついた観念だが、塩井は写光石を通じて、儚さと永遠を二項対立させるのではなく、その境界にとどまり続けることの重要性を示唆している。過去から未来へと流れ去るだけが時ではなく、今ここが常に新たで大切だとする考え方は、神道の「常若(とこわか)」の思想にも通じる。2022年に、285個もの「写光石」を配した大型のパネル作品が宗像大社に奉納されたことも腑に落ちる。
その一方で、写光石そのものに儚い、揺らぎの仕掛けがあえて施されていることがとても興味深い。写光石は完成されて終わりではない。目に見えないスピードで静かに生き物のように変わり続ける。年月を重ねた、あるいは屋外で長く陽の光を浴びた写光石は次第に色褪せ、白んでいく。環境による変化を受け続けた記憶の光は、最終的には存在の微かな痕跡だけになるかもしれない。
変容する自然に向き合う眼差しは、塩井が学生時代から長く扱ってきた鉄という素材からの影響が大きい。大学では鉄の彫刻家阿部守のもとで学び、環境造形やランドスケープに関心を寄せながら作品制作を行った。また修了後に鉄を扱う造形工房に勤務した経験も原点のひとつに数えられる。鉄を1200度近い炉で熱し叩き、高温の炎で溶断、溶接する作業を通じて、塩井は黒く重厚な鉄が、光輝きながら柔らかく美しく変化する、神秘的な様に何度も見惚れたという。鉄と身体の関係性は、光と身体のそれへとつながっていく。塩井は、鉄を通じて「自分の中にある自然」に気づき、「自然と自分の境界を探る」というテーマはそこから生まれたと語っている。
最後に、写光石を握る鑑賞者の「手」について補足したい。個展会場の白いテーブルの上の置かれた色とりどりの石たちには、どこか厳かな雰囲気とつい触れたくなる親密さが共存していた。手の上に石をひとつ置いてみてわかったことがある。私の掌(たなごころ)にすっぽり収まった写光石、それをみているのは目だけではなかった。小さな石の存在感を感じつつ、光の在処を遠く深く探っているのは、私の身体全体だったのだ。




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
