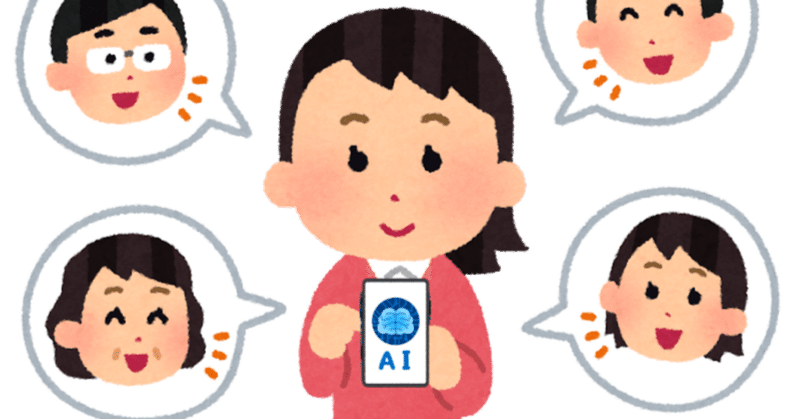
SNSの未来 - おせっかいなAIが心配
ソーシャル・ネットワーキング・サービス、略してSNSと呼ばれるサービスが普及してもうだいぶ経ったような気がしますが、時代を経るにつてその使われ方と課題も変化しているように思えます。
ソーシャル・ネットワーキング・サービス
遡れば、同じようなサービスはパソコン通信での掲示板から始まり、WEBサイト上の掲示板がその代わりを務め、そしてサービス名を冠したサイトであるとかアプリが使われるようになりました。スマホの普及に伴い「いつでもどこでも」サービスが利用できるようになり、ある意味で生活に無くてはならない情報源とコミュニケーションツールとなっています。そんなSNSもサービスごとの特徴があり、ひとりの人でもいくつものSNSに登録して使い分けるのが普通になっています(ひとりの人が同じSNSに複数のアカウントを登録して使い分けることすらあります)。
SNSのビジネスモデルは、利用時に表示される広告収入によるものが多く、利用者から見て料金のかかるサービスもあるとはいえ、その割合はあまり高くないようです。ですからサービスの内容を良く見れば、それは広告主にとって利益が出るようなものであり、そのためにサービスは利用者を増やしたり、より多くサービスをアクセスしてもらうような機能を提供しているのです。
よく知られよく使われるようなSNSが安泰かといえば、決してそんなに生易しいものではなく、常に新しいサービスが登場しては、それに対抗するためにも既存のサービスも機能を強化します。最近ではコロナ禍と在宅勤務の広がりを受けて、企業向けのサービスも普及しつつあり、仕事もプライベートもSNSでこなせる日々を過ごしている人も多くなっているのでしょう。
こんなSNSが、これからどう変化、進化していくのかは興味のある人も多いとは思いますが、それを考えるには、少しだけ過去を振り返ってみるのも悪くはないと思います。ちょうど10年前のレポートを見つけたのですが、今も人気のあるアメリカの主要サービス以外にも、国内のサービスがまだ頑張っていたのがわかります。
ソーシャルネットワークサービスの近未来構図2014
ここで挙げられている将来について振り返ると、カメラを搭載したスマホの普及による進化はそのとおりですが、それ以外については試みられたもののあまり広がらなかったものもあります。特に仮想空間とテレビに関しては、その投資の割にはかなり悲惨な結果になっているのではないでしょうか。
むしろこの10年の大きな変化は社会的な環境で、SNSを使って人が傷つけられたり、お金を失ったり、知られると不都合は情報が広まったりしてしまうことが多く起きたことです。根本的な理由は、SNSで情報を発信するために「どこの誰か」なのかをつまびらかにする必要が無いために、問題が起こってもその対処は発信された情報を削除するくらいしか出来ません。サービス事業者は発信元のアカウント情報を知ってはいるものの、それが何を担保しているのかと言うと、かなり怪しいものがあります。一般的には一番信用できるものはせいぜい電話番号で、それもある時点でその電話を受けることが出来ただけであることしか確認していないのが現実です。多くの国では電話番号を受け取る時に何らかの本人確認が行われますが、SNS事業者がそれを直接確認しているわけではありません。
さらに悪いことにはサービスの収入源である広告主に対しても、基本的には何らかの方法で存在が確認できて費用さえ振り込んでくれれば、あまりうるさいことは言いません。多くの場合、広告内容を事前に審査することはなく、その内容がサービス提供先のどこかで法律的に問題があったとしても、逐一問題視することすらありません。確かにグローバルに展開する多くの国や地域のすべてに対して問題があるのか無いのかの判断は困難だとは思いますが、その基準は曖昧で具体的な申し立てがあったとしても、その内容ではなく数で判断しているのではないかとしか思えません。根本的に自らの収入源に対して厳しい判断をするのは首を絞めることにしかならないので、サービス利用者が離れていかない程度の対応で構わないと判断しているフシがあります。
また、SNSが社会的インフラ的な地位を占めるに連れ、経済的な範囲に留まらず、政治に巻き込まれつつあります。サービス提供元の国や地域によっては、提供先の法律が及ばないものもあり、犯罪に使われたり軍事的な情報が漏洩したり、そして民主的地域の選挙にも影響が出るようになりました。こうなると法律を盾にとってサービスの規制が始まります。面白いのがいわゆる民主的な国ほど権力が分散しているので、この規制が実にマチマチで、そんなやり方をすればサービス提供側は逐一対処できないという言い訳をさせるためとして思えません。それに規制をしたところで、その効果をどのように担保できるのかといえば難しいところもあります。いわゆる地下に潜ってしまえば事実上、規制はできません。少なくともサービスとして規制しても実のところ意味はないのかもしれません。どんなサービスを利用していようとも、実際に問題が発生した部分を追い詰めないと、同じような問題は起こり続けるのでしょう。
そんなSNSにひとつの光が見えてきたのかもしれません。それは生成AIの登場です。生成AIは、実にいろいろな使い方が出来るもので、単に何かについて教えてもらうだけではなく、自分の書いた文章の誤りや不正確な部分を探してもらうとか、要約を作ることで意図が伝わる書き方になっているかも事前に確認することも出来ます。これを活用すれば情報を発信する際に、それが誤解なく伝わるか社会的に不適切な内容である可能性があると判断してくれるかもしれません。既に社会的に誰でも知る必要がないと思われている例えば爆弾の作り方を生成AIに尋ねても、シレッと無視して答えてくれません。
この技術が使いやすくなれば、うっかり不適切な情報を発信することを防ぐことも出来ますし、誤解を与えそうな表現を適切に修正してくれることも期待できます。また1か0ではなく程度問題で判断できるのがAIなので、一定の範囲を超えればそもそも発信を許さず、それ以下であっても発信前に警告を与え、それを理解した上でしか発信を許さなければ、サービス提供側としては十分な対策をしたと胸を張るでしょう。生成AIの都合の良いところは判断の根拠をあまり細かく説明できないところで、対策に漏れがあったとしても責任を取りにくいところがあります。これはサービス提供側にとっては非常にやりやすく、これが理由で導入されるケースが増えてくるのではないかと邪推しています。
そうなると何が起こるかなのですが、上っ面の表現ばかりがチェックされ、日常的な不満を投稿するような人にとっては、いつもチェックに引っかかり投稿することを拒否され、家族の写真を上げれば個人情報的に問題があると警告されたり、南国リゾートで撮った写真を友人と共有しようとすれば「不適切な画像です」と拒否されて結局メールで送る羽目になるとかが起こり、SNSで見られる情報は一見、大人しくなるかもしれませんが、同時につまらないものとなってしまう公算も大きいです。利用者の方も面倒になって「あれとこれについて書いて」とAIに指示した内容を投稿するようになるでしょうしね。炎上をAIにとめてもらうなんて、ちょっと不思議な世界が待っているのかもしれません。
ヘッダ画像は、以下のものを組み合わせて作りました。
https://www.irasutoya.com/2014/10/sns.html
https://www.irasutoya.com/2024/04/ai.html
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
