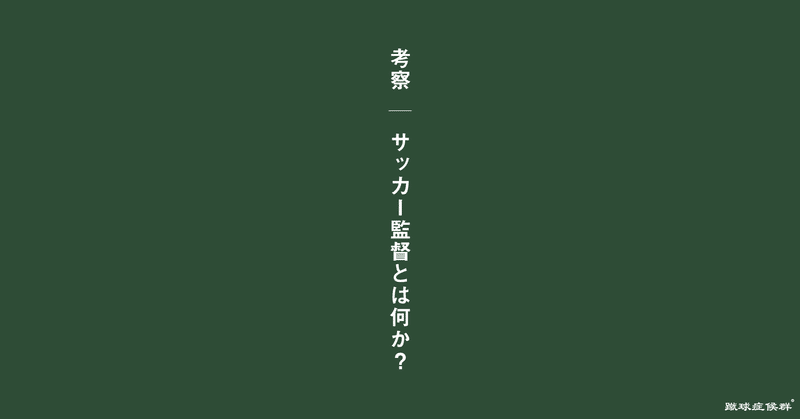
サッカー監督とは何か——。
監督(かんとく)とは、多くの事柄や人々・組織など見張ったり、指図をすることで取り締ることである。転じて、それらを行う人や組織のこともいう——。wikipediaより
映画監督、現場監督、舞台監督、野球監督 etc.と、世の中ではある組織や集団において、先頭に立って他者をまとめ、動かす人や行為のことを「監督」と呼ぶ。これを書いている私は「サッカー監督」という言葉を使って自らを説明するが、さてそれは、例えば映画監督や野球監督と同じものなのであろうか。
サッカーの世界では、国や人によってサッカー監督のことを「マネージャー」や「ヘッドコーチ」と呼ぶことがある。私がいるアルゼンチンでは、サッカー監督のことを『Director Técnico』と呼び、つまりテクニカル・ディレクターであるが、ここでは言葉の意味を整理することを目的としていない。
サッカー監督、もしくはヘッドコーチ、あるいはテクニカル・ディレクターとは、何をする人で、何として存在するべきで、どのような能力が必要なのか。言われてみれば、私は自分を説明するひとつの概念として「サッカー監督」という言葉を用いてはいるが、頭の中に浮遊している要素を改めて文字に変換したことはない。ここで一度、整理しておきたいと思う。
・・・
要素:
1.ミクロというよりマクロである
2.対話というより演説である
3.スペシャリストというよりゼネラリストである
4.知識というより人格である
5.インストラクターというよりプレイヤーである
6.一面性というより二面性である
7.サイエンティストというよりアーティストである
1.ミクロというよりマクロである
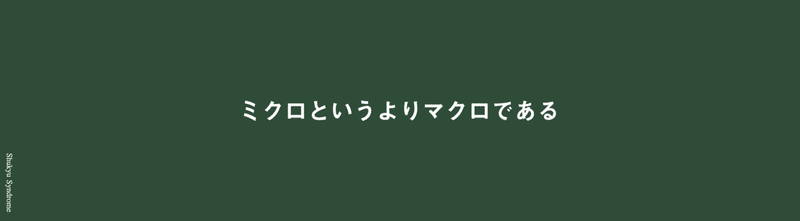
『顕微鏡を用いてしか見ることが出来ないような細かい事象』を観察するのがコーチであり、『首を左右に振っても見渡すことが出来ないような大きな事象』を観察するのがサッカー監督(以下監督)である。その点で、監督というのはミクロ視点以上にマクロ視点で物事を理解する必要があると、私は考えている。『細かな美しさに敏感でなければならないのがコーチ』であり、『大きな醜さに敏感でなければならないのが監督』である。両者が両立していなければ、良い作品を作り出すことは出来ない。大抵細部に注視している時、人は全体の醜さに鈍感になるのだ。
2.対話というより演説である
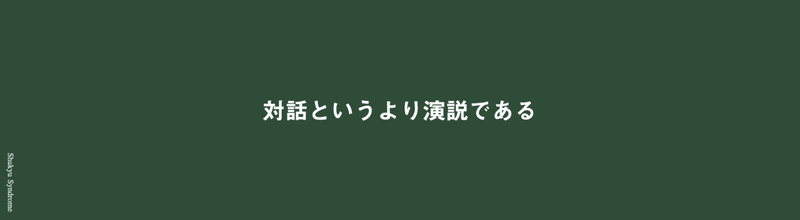
サッカー監督に最も重要な能力は何かと言われたら、私は迷わず「スピーチ」と答える。昨今テクノロジーの発展が顕著だが、私の理想像はいつだって「身体1つ」で選手を動かすことが出来る監督だ。
言うまでもなく、選手やスタッフ、その他取り巻く人々との対話を通してしか見えてこないものがあるが、対話で大きな組織を急速に動かすことは難しい。サッカーには、急速に、猛烈に人間を動かさなければならない場面がある。あくまでサッカーにおける対話とは、演説の準備であって、その点コーチは対話力に秀でている必要があるが、監督が演説力に秀でていなければ、組織は荒れた大海原を進んでいくことは出来ないだろう。
3.スペシャリストというよりゼネラリストである
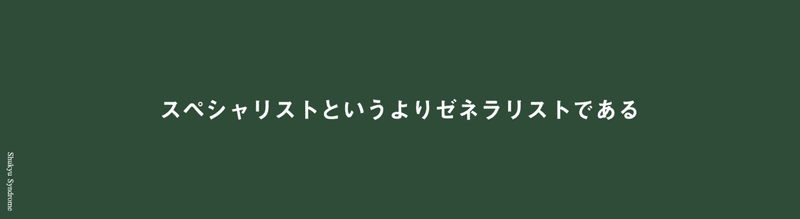
サッカー監督とは、極めて狭い範囲の専門的知識をもつこと以上に、分野・領域を跨いだ広い範囲の知見を持つべきである。誤解を恐れずに言えば、1のことを10知っている人間よりも、10のことを1知っている人間の方が、あらゆる視点・角度で物事に取り組むことができ、必ず複雑性と持続性を持って問題が発生するサッカーというゲームにおいて、またはサッカーチームという組織において、それこそが先頭に立つものが持つべき能力であると言える。
同時に、サッカーのチームにおいてスペシャリストは数人必要だが、ゼネラリストは1人であるべきだ。
4.知識というより人格である
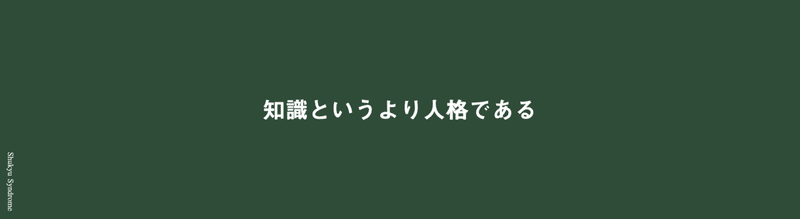
他のスポーツ競技に関してはこれに限らないかもしれないが、サッカーにおけるリーダーは、人格者であり、また何らかの点でカリスマ性がなければならない。
上で言及したように、サッカーには、急速に、猛烈に人間を動かさなければならない場面が多いからであり、「この人の為なら」とプレイヤーやスタッフが思えない限り、それはなし得ない。人間は事実では動かない。誰に言われるかで、動くのだ。
人生において、望まない限り「人の手本」として生きる必要はないが、サッカー監督は必ず、人々の手本にならなければならない。
5.インストラクターというよりプレイヤーである
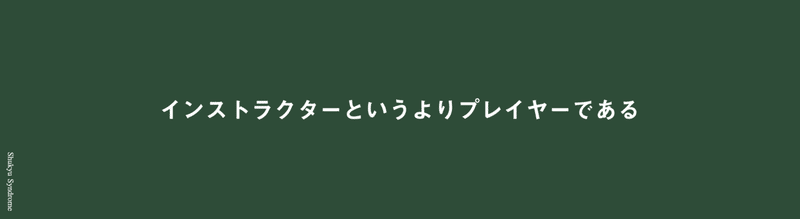
11人の選手の他に、何らかの方法を用いてゲームに直接影響を与えることが出来る(権利が与えられている)のは、サポーターと監督だけである。
サッカー監督とは、選手がゲーム中に解決することができない数々の問題を、リアルタイムで改善していくことが許されているプレイヤーである。ピッチに立つプレイヤーとの違いは、ボールを触れるか、触れないかのみであり、両者は解決できる問題の種類が異なる。選手のタスクを変更する、システムを変化させる(事前の準備が必要)、叫ぶ、態度で示す、立つ座る、表情を変える、そういった全てのことがゲームに影響を与え得る可能性があることを、理解しなければならない。
6.一面性というより二面性である
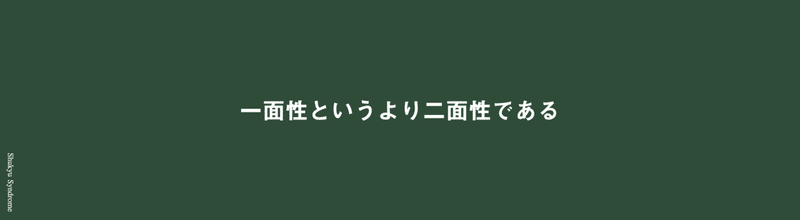
サッカー監督の人格には、二面性がなければならない。温厚と冷酷、弛緩と緊張、早と遅、冷静と興奮などの「差」を用いて、組織に緊張感をもたらす必要がある。ただし、その「基準」には明確な物差しがなければならず、またそれをプレイヤーやスタッフが「把握」している必要がある。
人格に一貫性を持ちつつ、二面性を持つこと。一面性しか持ち合わせていないリーダーには基準がなく、複雑性と持続性を持った問題に迅速に対処することはできない。
いつも笑顔の人間は、問題が多発する世界では信用されないのだ。
7.サイエンティストというよりアーティストである
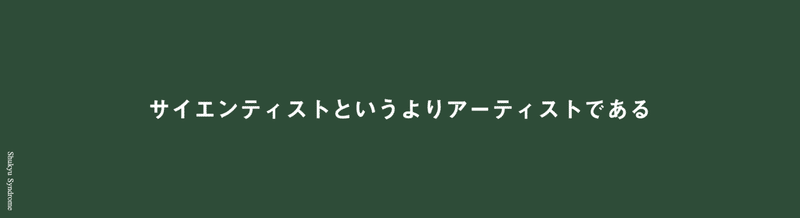
両者を完全に分けることはできないが、サッカー監督とは「創造」であり「観察」ではないという点で、アーティストであると言える。
サッカー監督がアーティストなのであれば、サッカーとはアートである。現代アートに重要なのは「コンセプト」であり、「何を創るか」より「なぜ創るか」こそがアートに価値をもたらしている。
アーティストとは表現者であり、表現者である限りは「何を表現したいのか?なぜそれを表現したいのか?」という確固たるテーマと、それを表現する決意を持つべきであり、そのためにサッカー監督は、“自ら”サッカーを思考しなければならない。コーチは必ずしもそうではないが、サッカー監督は知識を他者から吸収すること以上に、己から何かを創造する意識を強くもたなければならない。
ピッチに立つプレイヤーとは、それを共に表現する同志であり、また監督が立ち入ることの出来ない領域で表現行為をする、表現者である。どちらか一方が欠けてしまえば、良い作品を創ることは叶わない。
よってサッカーとは芸術であり、表現である。
・・・
私は「サッカー監督」という職業が持つ可能性を、縦にも横にも広げていきたいと考えている。映画監督のそれと同じように、アーティストであり、クリエイティブであり、そして作品を生み出す者として、これからも分野や領域を跨いで活動をしていきたい。これまで日本人がもってきた「サッカー監督」のイメージを変えることとはつまり、サッカーの可能性を広げることだと思っている。サッカーの歴史を動かしてきたのは、いつだって偉大な監督たちだった。
それでもなお、私という人間の中心には「ゲームに勝つ」という最大の標的があり、そのためにピッチに立つわけであるが、それはきっと、私という人間の深くに備わっている根本的な「欲求」なのかもしれないと、最近は考えている。
河内 一馬(Kazuma Kawauchi)
1992年生まれ(27歳)東京都出身。サッカー監督。アルゼンチン在住。サッカーを"非"科学的視点から思考する『芸術としてのサッカー論』筆者。監督養成学校在籍中(南米サッカー協会 Aライセンス保持)。NPO法人 love.fútbol Japan 理事。2021年より鎌倉インターナショナルFCの監督 兼 CBO(Chief Branding Officer)に就任予定。
いただいたサポートは、本を買ったり、サッカーを学ぶための費用として大切に使わせて頂きます。応援よろしくお願いします。

