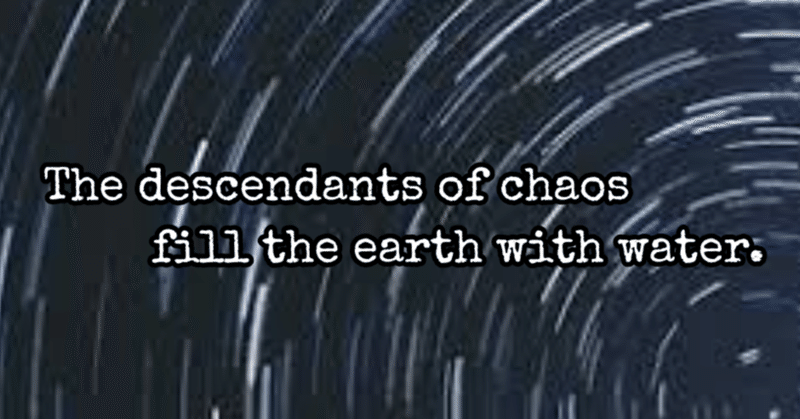
混沌の落胤は水とともに地に満ちて(6)
抹香と紫煙が漂っていた。
次に目に写るのは、白と黒。明と暗、ハレとケガレ、生と死──。
鈍色の服を纏う葬列と、死者を弔うための、意味不明な発音のらせん。
襖の格子に分かたれた目映い光は、目の前の景色の色を簒奪しているかのごとく、誰も彼もが陽炎のようにあやふやで、自分達に投げ掛けられる哀れみも残響の彼方へと消えてゆく。
震えた吐息。『狩人』は隣に座した弟を見る。感情は鉛のように重く──氷のように凍てついて、ただただ疲労のみが表情に表れていた。
触れるのを一瞬躊躇って──結局、不安を紛らわせるように肩に手を置く。
互いに視線を合わせぬまま、『狩人』は決意した。たった独りの家族を守ろうと。
それが果たせぬ約束とは知らぬまま。
賃貸住宅の1室。新品の家具の匂いと、すこしの酒と惣菜の香り。
暖色の家具と白い穢れなき壁紙、艶やかなフローリングに肌触りのよい絨毯は、侵されざる聖域のようだった。
義妹となる、かよわいお嬢さんとの水仕事。酔いつぶれて眠る弟を揶揄しながら、なぜ弟と一緒になろうとしたのかを聞いた。
まるで鈴の音がなるような、上擦って跳ねるような声音。熱を帯びて赤くなる頬。言葉を重ねる度に輝きを増してゆく瞳。
皿を洗う手に触れる水は冷たく、体の芯は熱を帯びて暖かくなり、良い心持ちになる。
互いに弟の思い出を語り合い、『狩人』は義妹となるであろうこの女性を弟と共に守り抜くと決意した。
その決意が無駄になるとわからぬまま。
繰り返し見るのはあのハロウィンの日。震えるスマホ。当たり障りのないやりとり。
「渋谷に行く」という呪いの言葉。
頭では「行くな」と叫んでも、喉に鉛を詰められたかのように声にならず、勝手に動く指はどうでもいい返事を入力する。
テレビに映る渋谷。阿鼻叫喚。乱れた画面。砂嵐のような走査線のヴェールの向こうに透けて見える、落ちてくる空に潰されて四散する弟と義妹。
肉が散る。骨が砕ける。臓物が溢れて、空を舞う目玉が見咎めてくる。
守るんじゃなかったのか。
そしてスマホが震える。
弟からのLINEがくる。
返事をする。
テレビを見る。
阿鼻叫喚。
四散する弟と義妹。
飛び散るカラダ。
責めるような視線。
そしてスマホが震える。
弟からのLINEがくる。
返事をする。
テレビを見る。
阿鼻叫喚。
四散する弟と義妹。
飛び散るカラダ。
責めるような視線。
そして──。
□□□□□■■
胸のつかえを吐き出すように勢いよく呼吸し、潮と黴に侵された空気と匂いを『狩人』は取り込んだ。
荒い呼吸が収まると同時にぼやけた視界が明確になり、暗い夜空に明滅する星々と、金色に光る白痴の眼がこちらを見つめていた。
崩壊したビルの屋上。わずかな燃料と薪で燃える橙色の焚き火の側で、『狩人』と少女は睡眠を取っていた。そして、少女は魘されていた『狩人』を、介抱するわけでもなく、ただ見ていた。
「うなされていたよ」
少女の視界を塞ぐ触手がぬるりと狩人を指した。臓腑を絞り上げたように滲む脂汗をてのひらで拭い、『狩人』は息をついた。
「──いろいろ、あってな」
「いろいろ」
意思を伴わぬ復唱。『狩人』は視線を落とした。
「弟夫婦を、捜しているんだ」
「渋谷にいたの?」
「ああ……」
繰り返し見る悪夢で鬱いだ心を紛らわせるように、『狩人』は少女へと話しかけた。
渋谷ハロウィンの惨劇の後、職を辞して全てを捨てて渋谷で弟夫婦を捜していたこと。
そこで別の『狩人』と出会い、自身も『狩人』となったこと。
『狩人』の修練を詰み、漸く二日前、渋谷へ戻ってきたこと──。
「必ず、必ず見つけてやる……」
「生きてると思う……?」
腹のそこから何かがせりあがる感覚を錯覚し、少女の問いかけに揶揄も悪意もないことを受け止め、数拍ののちに『狩人』はつぶやいた。
「……生きている、と思いたい」
傍らのカンテラに灯る青い炎が、動揺を表すように揺らめいた。
そして、何かを示すように激しく揺らめく。
『獣』か──と、『狩人』は剣を抜き、臨戦の体勢をとる。
朽ちた都市の構造物から構造物へ、跳躍し迫る気配。『獣』より重く鋭く、無駄のない機動。そして闇に灯るわずかな灯りが、その輪郭を映し出した。
古びた皮の外套、体に沿うような革鎧が浮かびあがらせるしなやかで肉厚な体躯、帽子の隙間から流れる絹のような髪。背負うのは槍斧、腰にはいくつかの剣。
「──アンタか」
『狩人』はカンテラを掲げる。現れた『女狩人』もカンテラを掲げた。青い炎ふたつが互いを舐め合うように炎を交わらせる。
「具合がよろしくないようだね」
「問題はない」
『女狩人』は『狩人』の言葉にさしたる感情も見せず、淡い赤の瞳で少女を見た。少女は警戒も怯えもなく、ただ新しい狩人の闖入を見詰めていた。
「アンタ、錦糸町の担当だろう。なぜ渋谷に?」
「錦糸町のは片付いたよ。直に他の『狩人』も渋谷に来る」
「──それほどか」
『狩人』と『女狩人』は渋谷の中心──瓦礫と汚水の繭の内側で微睡む『あの存在』を見詰めた。わずかな継ぎ目から、生物の残滓が蠢いては隠れた。
「師匠連の見立てじゃ、あと5日──ってトコロだね」
「……降臨すると?」
「代々木あたりの『魔狩りの騎士』も渋谷に集まりつつある。『魔狩りの騎士長』もだ」
『狩人』は肌がささくれ立つ感覚を覚えた。──騎士長。『魔狩りの騎士』を統括する人物にして、聖ランスロット修道会の秘蹟により、数世紀の時を生き続ける魔人。
かつてアメリカの寒村に於いて、『子孫送り』に罹った村人ごと『あの存在』を焼き払った無情の騎士。あれが態々出張ってきたことが、今回の事態の深刻さを物語っていた。
「──家族は?」
「まだ見つかっていない」
「今は『狩り』に集中しとくれな。私も永い間『狩人』をやって来たが、降臨間近のを見るのは初めてだ」
『狩人』は押し黙る。
渋谷の一角、深い闇が落とされたそこが煌々と緑色に輝いた。わずかに焼け落ちる匂いが潮の悪臭と混じり、『狩人』らの鼻腔を刺激する。そして肌で、ルーン魔術が機動されたことを感じ取っていた。
「……『魔狩りの騎士』共か」
「そういや、あすこにぁ"獣溜まり"が出来てたね。あすこだけじゃない、渋谷のあちこちに"獣溜まり"が出来上がってたよ」
三人は彼方の闇を照らす、毒々しい緑の色彩を眺めていた。その刹那──。
「!」
『狩人』と『女狩人』が得物を振り抜くと同時に、少女へ『獣』のあぎとが迫っていた。
【つづく】
アナタのサポート行為により、和刃は健全な生活を送れます。
