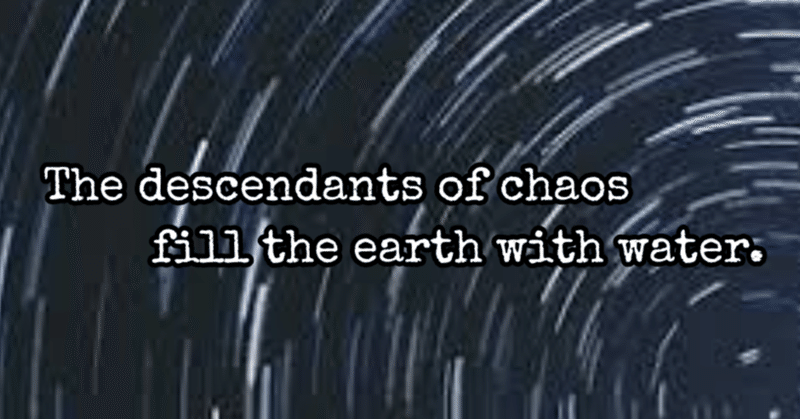
混沌の落胤は水とともに地に満ちて(8)
『獣溜まり』に囚われた『子孫送り』が子供を為している。
それを知った『狩人』が、仮の拠点である廃ビルを飛び出して1日が経過した。屋上では、『子孫送り』の少女と『女狩人』が、渋谷区中心部にある汚水と瓦礫の繭を見ながら、近隣のコンビニで拝借してきた粉末ポタージュを飲んでいた。
板金が凹み、底が焦げた風情のあるカップには白濁したとろみのある液体と、緑のうきみと極小のクルトンが泳いでいる。湯気が曇天へ立ち上るなか、少女は唇をすぼめながらポタージュを一口嚥下する。
強い塩気と舌を焼くような熱さ、香ばしい玉ねぎの風味が味蕾にまとわり、鼻へ抜けてゆく。食道から胃へ、液体が落ちる感覚を味わって尚、少女に目立った反応はない。
「帰って、こないね」
「ああ」
少女の言葉にポタージュを飲みながら相づちを打つ『女狩人』。本来ならば、このような食事は摂取する必要は無い。『獣』に近しい『狩人』や『子孫送り』は、三大欲求から解放されている。
──が、『獣』へ堕ちぬための分水嶺として、生存のための行為ではなく、人を保つための儀式として食事や睡眠を行う術を『狩人』たちは身につけている。
人を保つため──。だからこそ『女狩人』は、緊急の事態にありながらも個人の目的のために奔走している『狩人』を見逃している。
恐らくは、彼にとって望まざる結果に終わるだろうと予感しながらも。
風が枯れ葉を巻き上げる。冠水した渋谷の風はより冷気を含ませて、廃墟に隠れ住む人々の身を苛む。襤褸を纏う少女も、呆けた表情のまま身をすくませた。
『女狩人』は外套を広げ、少女へ近寄るよう促す。少女は雛鳥のように、なんの警戒心もなく、彼女の外套へくるまった。
「冷えてきたね」
「さむい」
「冬に入ると、もっと冷えるよ。──今年の冬を迎えられたら……のハナシだけど」
そして、何かを告げるように『女狩人』の目に青白い紋様が光った。
□□□■■■■
派手に汚水を巻き上げて、『狩人』は小休止すら惜しんで渋谷の廃墟を疾駆する。崩れて断裂した道路を飛び越し、追突し百足のごとく曲がりくねった廃車群を渡り、地面に突き刺さる大型バスの窓の隙間を通り抜け、倒壊し、中で通路が繋がったビル群の、崩壊しかかった回廊を抜けて、なお走る。
渋谷の各所にできた『獣溜まり』を巡って、中に囚われた『子孫送り』の中に、もしかしたら、弟夫婦がいるかもしれない。
もしかしたら、まだ生きているかもしれない。生きていてほしい。
切なる願いは『狩人』の体をめぐる血液を暖め、燃料と化して歩を進ませる。途中で見た、『魔狩りの騎士』たちに焼き尽くされた『獣溜まり』跡が焦燥感を刺激し、過剰に分泌された脳内物質が肉体を突き動かし、呼気とともに気化したエンドルフィンが大気へ散ってゆく。
とにかく早く、すべての『獣溜まり』を見て、弟夫婦がいたならば助ける。今度こそ、今度こそ──。
苔むしたアスファルトを蹴り、跳躍を以て廃墟を飛ぶ『狩人』。
そして、彼方に『魔狩りの騎士』たちが、一つの『獣溜まり』を燃やさんとしているところを見た。
密度を増した筋肉から放つ、剣の抜き付けは騎士の一人を袈裟懸けに引き裂き、鎧の破片と肉と骨とを、水垢で黒く変色するアスファルトへとぶちまけた。
しかし、騎士は死ぬこと敵わず、ビクビクと顕になった内蔵や肉をうねらせ、収縮させ傷を癒してゆく。融解し結合する肉の異臭が漂い、音が響く。
一人の騎士が、『狩人』の首目掛けて横薙ぎに剣を振るう。『狩人』は振り抜いた剣を、鎬を叩きつけるように振り上げた。互いの得物がぶつかり合い、雑音を奏で火花を散らす。
後ろからもう一人の騎士が背中を突き刺さんと肉薄する。『狩人』は剣の軌道を変えて、騎士の刃目掛け打ち下ろす。
刃同士がかち合い、刃先は水面へと落ちて刺突が食い止められる。汚水の飛沫が互いの服にかかる。
三人とひとり──『魔狩りの騎士』らは四方から刃の軌跡を『狩人』へ浴びせんとし、『狩人』は、剣舞を以て凶刃をいなし、あるいは弾き、まるで加速する剣閃が球体に見えるほどの丁々発止を凌いでいた。
互いに人知を越えた斬り結び。剣の打ち合う音は尋常ではなく、途切れることなく廃墟に響き渡る。金属同士を打ち鳴らす音は間隔が狭まり、雨垂れが屋根を穿つが如く、止まぬ残響となって『狩人』と騎士らを包み込む。
乱れ飛び交う凶刃に曝されながらも、『狩人』の剣は限界を超えて加速し、力も増してゆく。肉体が自壊と再生を繰り返し、より強靭さを伴い、剣舞は暴風のように、荒々しく肉体ごと打ち合う剣を薙ぎ払わんと、ますます激しく律動していた。
『獣』らを相手取りながら、昼夜山野を駆け回ることのできる『魔狩りの騎士』らであっても、天災のように勢いを増して衰えるようすのない剣戟に対応出来なくなり、無理矢理に着いていこうとするが──。
『狩人』の斬り払いが、騎士らの剣を、まるで花を手折るかのように、いとも容易く叩き折っていた。
そして分断された剣の間を、刹那の間より素早く、銀の軌跡が空気抵抗すら置き去りにして煌めく。遅れて風鳴りが響き、切断された空気が円形に吹き荒れる。
その空気に圧されて、音を置き去りにした斬撃で別たれた騎士らの上半身が汚水へと落ちた。ぬるりとした苔と水垢と、鮮血が混じり合う。
己の消耗すら気にせず、『狩人』はよろよろと『獣溜まり』へと歩を進める。弟夫婦が囚われていると信じて。そして──生きているという、あきれるほどに儚い希望にすがって。
眼前に『魔狩りの騎士』たちが、ルーンの炎をたぎらせて、行く手を阻む。翠の炎は束になり、まるで『獣溜まり』が火鉢に見えるような密度。
『狩人』の視界が揺らぐ。もはや疲労か、騎士の大群が掲げる炎が産み出した陽炎か、わからなかった。
怒り、悲しみ、焦りが呼気とともに滲みだし、震える喉から叫びが迸る。人を逸脱し、獣に片足を突っ込んだ、空気を震わせる咆哮。肉体の、細胞一つ一つが鳴動し、筋肉は屹立し、増した筋力でアスファルトを踏み砕く。
踏み込み。アスファルトが砕けて、派手に水柱を立て、自らの身体で押し出した空気が炎を揺らした。空圧で身動きが取れない騎士たちへ、刃を振るう。
□□■■■■■
曇天に夜の帳がかかり、そしてわずかな光芒が雲を裂いて夜の終わりを告げるころ。
『獣溜まり』の内側は、派手に散らばる肉片に、滴る鮮血、砕けてひしゃげた、鎧の体裁を成さぬ屑鉄、叩き折られて僅かに炎の残滓を残す剣の残骸で満たされた。
屍の中で、『狩人』が蠢いた。外套も肉体も切り刻まれて、折れた剣の切先が身体中に突き刺さり、両足は骨が露出するほどに、筋肉が引き裂かれていた。
それでも、筋繊維は虫の触角のようにうねうねと蠢き、少しずつ、だが確と結びつきはじめ、肉体を修復していった。
肉体の再生を待たず、『狩人』は這って進む。背中の一部が膨張と収縮を繰り返し、剣の破片を吐き出す。
うめきだけがむなしく廃墟に響き渡る。
汚水を被りながら、あるいは呑みながら、『狩人』は這って進む。まるで手負いの獣のように。
そして──。
『狩人』と地面を、巨大な槍が縫い止めた。
乾いた音と、喀血。そして『狩人』の身体を翠の炎が包み込む。肉が焼けて、縮み、激痛が駆け巡る。弱々しい悲鳴が上がる。
狩人の側に騎士が降り立った。豪奢な装飾。
『魔狩りの騎士長』だった。
「忌々しい、『獣』もどきめ」
吐き捨てるような、嫌悪。火達磨になる『狩人』は、しかしまだ死ねなかった。未だに熱傷を凌駕する再生と、気迫が命を繋ぎ止めていた。
「お前たちは、『獣溜まり』で産み出されるアレの恐ろしさを知らない。人と寸分違わぬ姿をしながら、人とは認識できぬおぞましきモノ。忌まわしき、"混沌"の落胤だ」
騎士長は槍の柄を掴み、『強化』のルーンを起動させる。炎は勢いを増して、『狩人』の体内へと入り込む。
臓器や気道が焼かれ、機能不全によるさまざまな苦しみや窒息にもがき苦しむ『狩人』は、それでも、死ねなかった。
「……首を落とせば、生きてはおれまい」
のたうつ『狩人』に嫌悪を募らせながら、騎士長は槍を肉体から引き抜いた。傷口から炎が吹き上がり、瞬く間に血を蒸発させていく。全身の血液が沸騰する憂き目に遭いながら、やはり、『狩人』は死ねなかった。
槍の穂先が煌めき、凶刃が首へ迫る。
刹那──。
弩から放たれた矢が、槍柄へと刺さる。
そして、『獣溜まり』の外周から次々と、草臥れた外套を纏う者たちが次々と飛来してくる。皆一様に、革の鎧と帽子を纏い、剣や槍、斧などを構え、腰に蒼い炎が揺らめく歪なカンテラを提げていた。彼らは、『狩人』を守る盾のように立ちはだかる。
『狩人』の師匠連である。
「貴様ら……」
『魔狩りの騎士長』は槍を天へ翳す。その背後に隊列を組む、『魔狩りの騎士』。一矢乱れぬ行軍は、具足の擦れ合う音を寸分の狂いなく響かせる。
騎士らは剣で襖を作り上げ、剣先を師匠連へと向ける。
にらみ合う、『騎士』と『狩人』。
互いに向けられた切先は鈍く光り、空気の震えが微かに剣を鳴らす。互いの殺気が、凪いだ水面を揺らしはじめる。
「──あと、二日だ」
師匠連の一人が口を開く。
「あと二日で、あの繭が孵る」
全員の脳裏に、渋谷の中心に佇む、汚水と瓦礫の繭に揺蕩う『あの存在』が過る。
「そうだ。だから『獣溜まり』も、『子孫送り』も『狩人』も、『旧支配者』も全て葬る。この世界に人を脅かす存在はいらない」
「この体たらくでか?」
師匠連が首を巡らせる。血で赤く染まる水面には、大量の騎士の死骸。鎧から歯ぎしりの音を響かせる『魔狩りの騎士長』。
「──提案だ」
「……休戦して、まず『旧支配者』に合同で当たろうと言うのではあるまいな」
「他に手があるか?」
師匠連の殺気は粘度を増して、騎士らを包み込もうとする。騎士らの身体が強ばった。
「貴公らの主張を通そうが、我らの主張を通そうが、世界が終わってしまったらどうにもならんだろうが」
「……」
「おれたちは『あの存在』が身動ぎすれば消えてしまうような、泡沫の泡に過ぎん。影ですらない。あらゆる神話で語られた終わりが、いま現実として、あそこに在るんだ」
□□■■■■■
騎士長と師匠連が睨み合うなか──。
肉体が炭化しながらも、『狩人』は再生し、肉と肉が互いに癒着しようと、虫のようにうぞうぞと蠢くなか、汚水を這っていた。
世界の終わり──。そんなことばを背中に叩きつけられながら、『狩人』は必死に、『獣溜まり』の外壁、粘液が硬化し、『獣』や『子孫送り』が塗り固められた其処へ急ぐ。
世界の終わりなどどうでもいい。
弟に、義妹──。助けてやらねばならない。
『獣』が『子孫送り』の少女を喰わずに連れ去ったとき、わずかな希望があった。弟夫婦も、もしかしたら生かされているのではないか──と。万が一、『子孫送り』にもならず……万が一、この外壁に囚われて……。
気力を燃料とし、外壁にすがり、身体を起こす。
そして、見つけた。
それは、あまりにも簡単に。
拍子抜けするほど、あっさりと。
硬化した、琥珀のような外壁を隔てて。
「 」
弟と、義妹の顔が、まるで眠りについたように穏やかで──。
振り上げた拳を外壁へ叩きつける。血飛沫、砕けた骨の破片、肉。千切れた爪が顔に刺さる。
外壁を砕かんと、再生すら追い付かないままに拳をぶつける。喉が震えて、脳がゆだるほどの熱さを感じているが、あげたはずの叫びは聞こえない。
痛みすら置き去りにして、ひたすらに拳を叩きつける。血飛沫や肉体の損壊により、壁が汚く染まってゆく。
まるで永遠のような、一瞬のような──。
肉や骨や、血のヘドロがへばりついた外壁に亀裂が生じて、砕けてゆく。
固まりきらない粘液に抱かれ、弟夫婦が『狩人』にもたれかかる。
顔"は"無事だった。
身体は、あらゆる生物や昆虫の特色が混じり合い、生物の様相を呈して居なかった。人とも、動物とも、虫とも呼べる姿ではなかった。
義妹のかすれた唇からは、わずかな呼気すら感じられなかった。いつからこうなのかは、最早わからないが──彼女は手遅れだった。
弟は、僅かに目を開いた。その眼球に、『狩人』の表情が映る。か細い呼吸、言葉にならない言葉が、消え入りそうな灯火のように瞬く。
人ならざる弟の手が、動いた。彼と彼女の間──まるで二人が覆い被さり、守るように包んでいたのは、『何か』。
手と足、胴と頭。人間と寸分違わぬ特徴を備えながら、人間と認識できぬ赤子。
『狩人』の、甥か、姪か。
弟は、『狩人』を見た。喘ぐような仕草をして──息を吐いて、そして、二度と呼吸しなくなった。
声にならない末期の言葉、読み取れない眼差し、何者か理解できない、二人の遺したもの。
『狩人』は三人を包み込むように抱いた。
胸のうちに凍りついたような、弟夫婦の思い出、色褪せてゆくそれが結露し、胸から溢れて、視界を、脳を埋め尽くして──。
守ると決めたはずなのに。
助けると誓ったはずなのに。
両肩に冷たくなる質量を、胸に温かく鼓動する質量を感じて、『狩人』は、兄は、どうにもできなかったモノを、吐き出すように叫んだ。
喉が裂けんばかりに咆哮したはずなのに、自分の声が、全く聞こえないように感じた。
【つづく】
アナタのサポート行為により、和刃は健全な生活を送れます。
