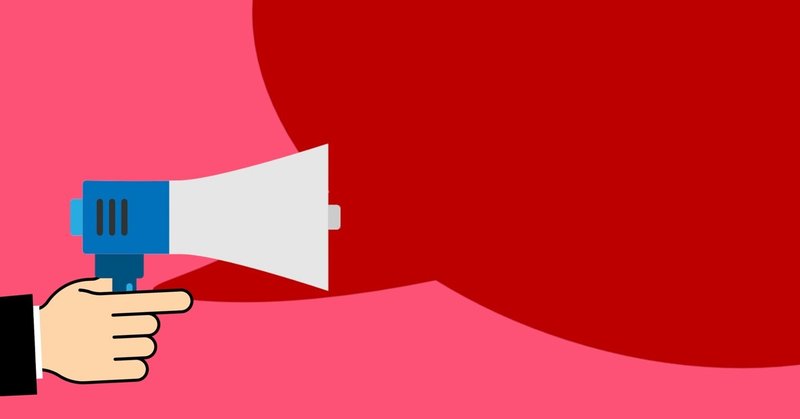
権利から考える子どもアドボカシー〜子どもアドボカシー基礎講座4日目
2月から受講開始した子どもアドボカシー基礎講座(主催:子どもアドボカシーセンター広島)の講義も4日目。今回も受講記録を書いてみました。
1コマ目<障害児・乳幼児のアドボカシー>
講師:堀正嗣
熊本学園大学、著書「子どもアドボケイト養成講座」
◆障害の捉え方の変化=医学モデルから社会モデルへ
医学モデル
障害=インペアメント=損傷・しょうがい
身体的・知的・精神的な機能障害=個人の問題
社会モデル
ディスアビリティ=障害
社会のとの間の障害物によって、その能力を発揮する機会を奪われた状態=社会側の問題(=排除)
障害の捉え方が医学モデルから社会モデルへ変化
=問題は社会との関係性の中にある
=障害は(個人の体にあるのではなく)社会の側にある
◆障害者の権利=障害者権利条約(2006採択・2014批准)
第7条「障害児の権利」
1) 他の児童との平等を基礎として
2) 児童の最善の利益
3) 意見表明権+障害と年齢に適した支援
忘れてはならないこと=「障害者である前に人間/子どもだ」
◆乳幼児の権利とは
国連子どもの権利委員会一般的意見7号
子どもの権利条約…
2条:差別の禁止(乳幼児=全ての権利の保有者)
3条:子どもの最善の利益
6条:生命・生存及び発達に対する権利
12条:意見表明権(最も幼い子どもでさえ)
◆非指示型アドボカシー
非指示型アドボカシー=子どもの言葉による明確な指示を受けずに行うアドボカシー=人間中心アプローチ(ヒューマンファースト)
障害児・乳幼児のアドボカシー=人間アプローチ+最善の利益アプローチ
注)最善の利益アプローチはアドボカシーではない、との指摘も。
(1コマ目を終えての感想)
障害児・者であろうと、乳幼児であろうと、相手が言葉を話せても話せなくても、「対人間」であること、人間同士として尊重し興味を持ち、耳と心を傾けることが突破口なのだなと感じた。相手への興味が一番大事で重要。

2コマ目<経験者・当事者が求めるアドボカシー>
講師:川瀬信一
一般社団法人子どもの声からはじめよう代表理事
里親家庭、児童自立支援施設、児童養護施設を経験
◆川瀬さん自身の経験
児童相談所に保護された後
「里親さんがいい?それとも施設がいい?」
=自分で選んだという思いが失敗も前向きに歩ませてくれた
◆なぜ声を上げることは難しいのか?
・親の離婚以前のことを教えてもらえない
・里親の相談をしたら出て行けと言われないかな?
・いじめアンケートに書いたけど何も変わらなかった
・担当の児童福祉司がいるけど毎年交代する…
・親のことを相談したら、親にバレて怒鳴られた
・職員さんが忙しそうで意見を言って迷惑をかけたくない
忘れないようにしたいこと①
=感情や思考が抑圧された経験は深刻な影響を及ぼす
=諦め・孤立感・孤独感・自己責任の重圧
◆子どもアドボカシーの原則6
子どもの参加
「私たち抜きで私たちのことを決めないで」
=アドボカシー活動が子どもにとってより魅力的で効果的なものにするために
忘れないようにしたいこと②
相手のことを理解したつもりになってはいけない
理解するために耳を傾け続ける
忘れないようにしたいこと③
ケアをする側、受ける側双方に権利が尊重されている時、良いケアが生まれる
(2コマ目を終えての感想)
「理解できた」という思いは目眩しになること、理解し続けることこそが子どもの願いや思いに最も近づくことができることを忘れないようにしたい。達成感?とは程遠いところにある活動がアドボカシーかもしれない…謙虚に進みたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
