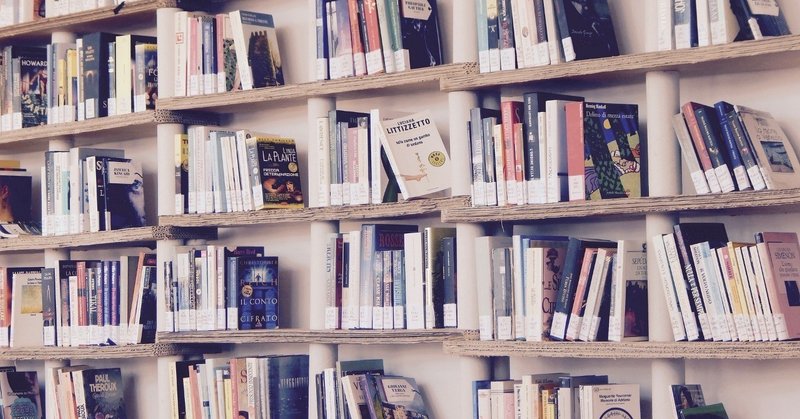
読んだ記事3つで振り返る9月。抑うつと英語とインターネット
私が9月から新たに始めたことが、3つある。
①気になった記事はひとりslackに投げておく(後で読む)
②1週間に1冊「じぶん課題図書」を決めて読む
③週に1つ、英語の記事を読む
①の「ひとりslack」はこれまでにもTwitterなどで見かけた方法だったが、実践はしていなかった。けれど9月の頭に「先週見かけた記事、読みたかったのにどこだー?何だったー?」状態になり、すごく後悔したのと、すごく「もったいない!」と身に染みたので始めてみた。
1ヶ月やってみた感想。
・「今読まなきゃ」という焦りから解放された。
・「いつでも読める」と「忘れない」が両立されて気持ちが良い
・いつでも読めるので後回しにすることも多い(反省)
・ちょっと内容がきつい記事などは、呼吸を整えて読めるので精神安定
・先月自分が考えたことが記事の選択からほんのり見えて面白い
②の「自分課題図書」は、月半ばから始めた。しかし、始めた週は読めたけれど、次の週以降は体調がみごとに低空飛行したので読めなかったという失態。でも選書もあるのかもしれないので、分析しつつ、実行していきたい。
③の「英語記事を読む」も月半ばから。ニュースを日本語でばかり仕入れているので、多言語でも知りたくて、というのはカッコイイ目当て(でもこれもほんとう)。一番は英語の勉強。読めば読めるものだ。「楽しい!」が一番の感想。続けていきたい。
では、読んだ記事の紹介を。

記事①:鈴木悠平さん「適応障害になって2ヶ月。「弱った」自分を前提に仕事と生活を編み直す」
私「も」というのはちょっと気が引けるのだけれど、私も8月のお盆の後から急激に体調を悪くしている。もともと双極性障害を持っていて、おそらくは気温低下による季節性うつの始まりだと見ているのだけど、いつもの年よりも安定するのに時間がかかりすぎている。
つらい。
こうなった時、自分の状態をオープンにするのはすごく難しいこと。私はとにかく抱え込んでしまいがち。そして飽和状態になって、周りに迷惑をかける。オープンにすることで助けてもらえることもあるのに、こんな自分が情けなくて悔しくて隠しておきたいと私は思ってしまう。
悠平さんのすごいところは、オープンにするだけでなくて、自分の取扱説明書を細やかに提示して、周囲との協力体制を「必要な分、充分量を」構築していること。できること、できないこと、負担になること、かかる負担の強さまで提示している。
これなら周りは助けやすいだろうなあと思う。つらいよー助けてよーばかり言っていても(いや、この表明も大切ではあるのだけど)、助け方がわからないことはよくある。そして、助けてもらえない。これはもったいない。
このつらい期間に、自己分析を怠らないのは、大切なことだけれどとても困難なことでもあるはず。「諦めることは停滞ではない」という言葉は、諦めることが大嫌いな私にとても明るく響いた。「編み直す」もすてきだ。
つらい時こそ、自己分析と説明書作成をしていこう。

記事②:The New York Times「U.S. Marine’s Son Wins Okinawa Election on Promise to Oppose Military Base」
私はTwitterで、自民党、公明党、希望の党、立憲民主党、共産党をフォローしている。だから、翁長さんが亡くなってからのタイムラインは沖縄だらけ。もともと沖縄の県知事選挙は世界地図を描き替えるほどの影響があると考えていたのもあり、毎日ひとりで盛り上がっていた。
政治に興味を持つのは楽しい。思い通りになることなんて本当に少ないけれど、私はあの「力が動いて周囲を変形させていく過程」が好き。どう変わっていこうとその変化を観察するのが好き。もちろん、変わっていってほしい方向もあるのだけれど。
さて、この記事、とにかく「読み終えること」を主題に読んだので、わからない単語は結構飛ばしている。それでも記事の大きな流れは読めたし、わからない単語の意味も大方掴んだ。辞書は読み終わってから引けばいい。読みながら引いてはだめ。
今後はnoteに感想を書ける程度に自信を持って読み終われることを目標にしたい。

記事③:辻大介さん「最新調査で判明、インターネットはこうして社会を「分断」する」
私が常々感じていたことがそのまま記事になっている!という感触で読んだ。よく「SNSなんて心の汚いひとの巣窟だ」なんて言われるけれど、私のTwitterタイムラインはほんとうに暖かい。励まされる言葉ばかり並んでいる。
この違いはなんだ?
辻さんはインターネットを使う時間が長いほど、排外主義とアンチ排外主義の分断が進むと書いている。ひたすらに敵を増やすひとと、ひたすらに受容へ進むひとに分かれるというのだ。
どうせ社会が変わっていくのなら、受容がいいな。違いを受け入れ、強さを丸め、弱さを開き、それぞれができることで助け合える社会。
我が家の子どもたちは上から中3、中2、小6。揃って不登校になった時点で夫と2人腹をくくって子ども用のノートパソコンを増やし、Wi-Fiの容量を上げて、インターネットも自由に使えるようにした。
だから、我が家の子どもたちはかなりの長時間、インターネットの海で遊んでいる。その子どもたちを日々見ていて感じる不安の原因が、この記事できれいに解剖された、と私は思った。
子どもたちにこの記事の話をして、どうすればいいか?考えた予防策が以下↓
・心がチクッとしたら、どうしてかな?と立ち止まって考える
・いつも「そうは思わないひと」の考え方を想像する
・「自分とは違う」にいつも手を伸ばそうとしておくこと
・たまには「大して好きじゃないこと」にも興味を持ってみる

10月も始まって1週間。読みたい記事も本も読んで、後悔しない1ヶ月にしていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
