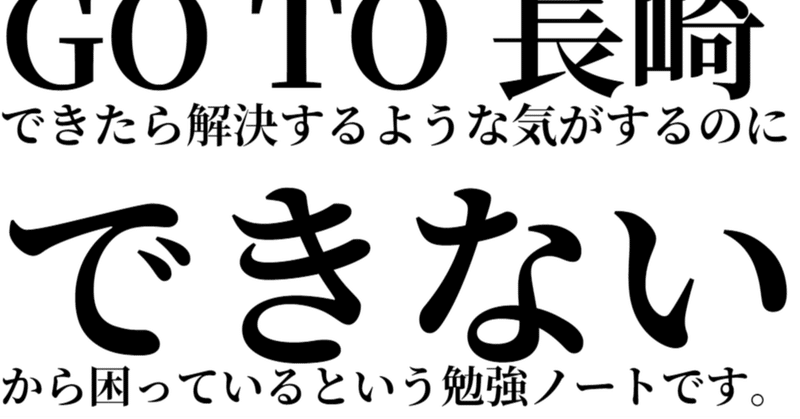
長崎遊郭の特殊性『価格帯別』
長崎遊郭は先にあった丸山町に、あとからつくられた寄合町のふたつの町で構成されています。
古地図や長崎を描いた絵から、埋立地(新地ともいいますかね)が増えるまえから山あいに丸山町らしきものが見えるので、長崎では「やま」「宿」と呼ばれていたそうです。
※以下、表記簡略化して「長崎遊郭」に表記統一します。
長崎遊郭の特殊性/個性はいくつかあるのですが、なかでも
・鎖国政策下に唯一異国人を受け入れる「幕府公許の遊郭」地であったこと
・揚代の支払いが「砂糖」を使った例がみられること(年末にまとめて換金したようです)
・これはソースが微妙なんですが、ほかの公許遊郭で夜間営業、つまり泊まりが許可されていないときにも泊まりがあったので「宿(やど)」と呼ばれていたこと(揚屋まで赴いていくのではなく、自前の店舗内でお客をとるから説もある)
・唐人屋敷や出島に徒歩/駕籠/舟をつかって出向いていくので、いわゆる「お歯黒溝と大門に囲まれた籠の鳥」ではなかったこと(借金でしばられたりという面で見れば籠の鳥ですが)
以上は今までも書いてきたような気がするのですが、いま引っかかっているのがコレ。
・ひとつの店に揚代が別の複数の遊女が同居している営業形態ではなく、遊女の格(揚代)ごとに店がわかれていたこと
どういうことかというと、
すこし江戸時代の遊郭に興味があるかたなら「吉原細見」をご存知かとおもうのですが、あれに掲載されている店は、ひとつの店に格や揚代の違う複数の遊女が混在して所属となっています。
対して、長崎遊郭の細見的なものは「長崎土産」になりますが、おおざっぱに分けるとひとつの店には同じ格や揚代の遊女しか所属していません。
上から遊女の格は「太夫」、張見世をする「みせ」、最下級の「なみ」。それぞれ「太夫屋」、「みせ屋」、「なみ屋」(のちに、なみ屋の名前は消滅)と揚代/価格帯別にわかれているのです。
客先(揚屋)に遊女を派遣するデリバリー方式は大阪もやっているのですが、長崎はより現代の風俗店に近い営業形態なのです。もとから価格帯別に分かれているので、登楼する客層がはっきり分かれているのも現代的ですね。
この営業形態は「博多と長崎だけ」と書いてある本のなかでも(丸山遊女と唐紅毛人 (前編) )、同時代の博多遊郭での営業形態はどのようであったか触れられていないので探している最中です。タスケテ……
長崎遊郭は店のなかで「唐人行」と「紅毛行」にわかれるのですが、揚代が高いのは「紅毛人が客の場合の紅毛行遊女」です。日本人と唐人は揚代が同じだったそうなので、遊女としての格が最下級でも紅毛行遊女がいちばん稼いでいる状況が生まれてしまう場合、例えば吉原遊郭での「その店でいちばん稼ぐお職女郎」だから偉い。みたいなことはあったのか個人的に気になっています笑。
丸山遊女と唐紅毛人 のボリュームがすごくて読みきれていないので、しばらくこういう覚書みたいな記事が続くと思います。
つぎは長崎絵のはなしとか書きたいです!!
いただいたお金は本の購入代金に替えさせて頂きます。
